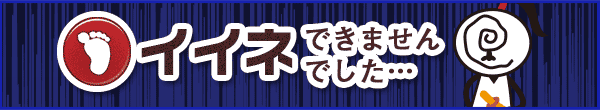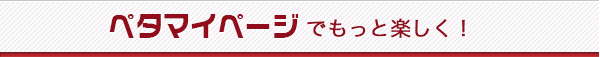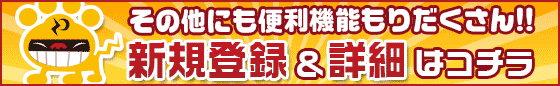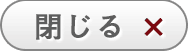カオス帝国〜リターンズ
-
スレッド一覧
- 雑談!! (241)
- たった一言!! (814)
- つぶやき!! (459)
- 生駒ちゃん (851)
- 画像!! (451)
- 芸能スレッド (1013)
- 名言!!!!!!!!!! (985)
- イマジン〜想像力育成講座〜 (256)
- 面白画像(≧▽≦) (884)
- MUSIC♪♪♪ (654)
- ヌコスレ(=^ェ^=) (688)
- 事件,事故!!( ; ゜Д゜) (471)
- 修造松岡!! (103)
- 俗にいうオカルト系(;゜∀゜) (299)
- (50)
- 豆知識 (677)
- つまるところこの人は美しい (307)
- 世 (112)
- JRA (1448)
- The パチ!!!!!!〜懐かしの〜 (457)
- 飲み食い市場(´・c_・`) (385)
- (140)
- サイエンス (202)
- 映画!!DVD!!ドラマ等々!! (157)
- AVタイトル‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- 復活!いい話スレ(ToT) (37)
- (80)
- つまるところこの人は美しい 本編 (33)
- (654)
- フラグ成立!!(^_^)/‾‾ (39)
- 笑 (392)
-
厚労省、薬用せっけんの実態調査へ 米での販売禁止受け
米食品医薬品局(FDA)が抗菌作用のあるトリクロサンなど19種類の成分を含むせっけんの販売を禁止する声明を出したことを受け、厚生労働省は国内で流通している「薬用せっけん」の実態調査に乗り出す。菅義偉官房長官は7日午後の記者会見で「日本においても同様の成分を含む商品の確認を早急に実施し、とるべき措置について検討を行っていく」と述べた。
FDAは今月2日、「通常のせっけんと水で洗うより抗菌効果があるという科学的な根拠がなく、長期的な安全性も検証されていない」などとして、トリクロサンやトリクロカルバンなどを含むせっけんの販売禁止を発表した。一部の米企業はすでにこうした成分の使用を中止しているという。
厚労省によると、国内でもトリクロサンを含む「薬用せっけん」が広く流通している。同省は今後、根拠となる研究報告などFDAの措置に関する情報を確認し、国内の対象品の種類や範囲を調査する。その結果を踏まえ、審議会で必要な措置について検討していく。(黒田壮吉) -
悪性の顔面腫瘍で個体数が大幅に減少したタスマニアデビルは、非常に急速な遺伝子進化を通して絶滅の危機から立ち直りつつあるとみられるとの驚くべき研究結果が30日、発表された。
オーストラリアのタスマニア(Tasmania)島にのみ生息する、イヌほどの大きさの夜行性の肉食有袋類で絶滅危惧種に指定されているタスマニアデビルについて、20年前に顔面腫瘍が発生した前後の294個体のゲノム(全遺伝情報)を詳細に比較した結果、ほんの4〜6世代の間に、7個の遺伝子に種全体に及ぶ適応進化が起きていることが明らかになった。7個のうちの5個は、哺乳類の免疫力とがんへの抵抗力に関連する遺伝子だ。
英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に掲載された研究論文の共同執筆者で、米ワシントン州立大学(Washington State University)のアンドリュー・ストーファー(Andrew Storfer)氏はAFPの取材に「タスマニアデビルは進化している」と語る。「特筆すべきことに、この進化は極めて急速だった」
環境や病気などの要因に対応した有益で持続する遺伝形質の獲得による生物種内の進化のプロセスは、長い時間をかけてゆっくり進行すると一般に考えられている。そのため研究チームは、種を救う可能性のある変化がまさに自分たちの目の前で起きているのを見て「うれしい驚き」を感じたという。
タスマニアデビルの顔面に増殖する奇妙な腫瘍に科学者らが最初に気づいたのは1996年のことだった。
■悪魔のような疾病
大半の悪性腫瘍とは異なり、この顔面腫瘍は伝染性で、互いのかみつき行為によって拡散していることが間もなく明らかになった。
このデビル顔面腫瘍性疾患(DFTD)を発症した個体は多くの場合、腫瘍の増殖によって餌をとることができなくなり、餓死する。
ストーファー氏は電話会見で「この病気の致死率は100%に近い。タスマニア島全体の95%に広まり、既知の個体群のほぼすべてに感染し、タスマニアデビルの個体数を全体で約80%減少させた」と述べた。
個体数はかつて25万匹を超えるほどだったが、現在野生の状態で残っている個体はわずか数千匹にすぎないと考えられている。
種の絶滅も予測されたタスマニアデビルがいまだに現存しているのはなぜかを解明するため、ストーファー氏らの研究チームは研究に着手し、20年以上にわたって収集された数千に及ぶ組織サンプルの遺伝子データを分析した。
論文の共同執筆者で米アイダホ大学(University of Idaho)のポール・ホーエンローエ(Paul Hohenlohe)氏によると、タスマニアデビルが「著しく急速に進化している」ことをこのデータは示しているという。「この疾患が最初に現れたのが1996年なので、わずか20年間というのは、特に哺乳類にとってはことのほか急速だ」
今回観察された遺伝子の変化が、実際にタスマニアデビルのDFTDに対する抵抗力を高めているかどうかについては、科学者らはまだ確証を得ていない。今回の研究で得られた情報はタスマニアデビルの飼育者らが予防的に作用する遺伝子変異を持つ個体を生産するために利用できる可能性もある。
「全体的に見て、今回観察されたタスマニアデビルの進化応答は、この動物の持続的な生存が期待できることを示唆している」と、論文の執筆者らは結論付けた。【翻訳編集】 -
深宇宙からの「強い信号」検知 地球外文明発見の期待高まる
【AFP=時事】地球外生命体が存在する証拠を求めて宇宙観測を続けるロシアの電波望遠鏡が、「強い信号」を検知したことが明らかになり、科学者らの関心を集めている。
信号探知のニュースは、深宇宙探査研究に関する情報を発信するウェブサイト「ケンタウリ・ドリームス(Centauri Dreams)」の運営者ポール・ギルスター(Paul Gilster)氏が27日、イタリア人天文学者のクラウディオ・マッコーネ(Claudio Maccone)氏によるプレゼンテーションの内容として伝えた。
同氏は、「これが地球外文明の仕業だと主張している者はいないが、さらに調査する意義があることは間違いない」と話している。
この信号は地球から約95光年離れた恒星「HD164595」の方向から届いたとされる。この星は少なくとも1つの惑星を持つことが知られており、惑星の数はもっと多い可能性もある。
ロシアのゼレンチュクスカヤ(Zelenchukskaya)にある電波望遠鏡「RATAN-600」によるこの観測結果は今になって公になったものの、実際に検知されたのは昨年のことだったという。
専門家らはこの信号について、その意味や、発信元の正確な位置を解明するにはまだ相当の時間がかかるとみている。
それでもギルスター氏は、「あまりに刺激的な信号だったため、RATAN-600の研究者らはこの目標の常時監視を呼び掛けている」と書いている。
この発見は、来月27日にメキシコ・グアダラハラ(Guadalajara)で開催される第67回国際宇宙会議(IAC)で議題として採り上げられる予定だ。
ギルスター氏によると、信号を検出した研究チームは、ロシアの天文学者ニコライ・カルダシェフ(Nikolai Kardashev)氏が提唱した宇宙文明の進歩度を示す尺度を用い、この信号が等方性ビーコンからのものだった場合、地球文明よりもはるかに進歩した「タイプ2」の文明でなければありえない強さだと説明している。
一方、もし太陽系だけに向けて送られた狭い信号であれば、地球文明の能力により近い「タイプ1」の文明でも出せる強さだという。【翻訳編集】 AFPBB News -
脳梗塞は「生活習慣病」ではなく「性格習慣病」!?
<「読学」のススメ>『脳が壊れた』(鈴木 大介 著)
脳卒中は日本人の死因第4位
脳梗塞という病気について、どのくらいのことをご存知だろうか? 身内や身近な人の中に発症した人、あるいは自身が罹った経験のある人もいるかもしれない。私事で恐縮だが、筆者も実父をこの病気で亡くしている。
脳梗塞は、簡単に言えば脳の血管がつまることで生じる疾患で、脳卒中(脳血管疾患)の一種。脳卒中は2010年まで日本人の死因第3位(厚生労働省調査。2011年から3位は肺炎となり4位に)で、今でも保険会社では三大疾病の一つに数えている。その脳卒中の約60%を占めるのが脳梗塞だ。
脳梗塞が恐ろしいのは、ある日突然発症することと、命が助かっても後遺症として脳機能障害が残る確率がきわめて高いことだ。
『最貧困女子』(幻冬舎新書)などの著作で知られるルポライターの鈴木大介さんが自身の脳梗塞の闘病経験を綴った『脳が壊れた』(新潮新書)には、後遺症による感覚や行動の不自由さがリアルに表現されている。そして発病をきっかけにした心と「生き方」の変化が感動的に描かれるドキュメンタリーだ。
鈴木さんはフリーランスとして超多忙な生活を送っていたある日、左手指が痺れて動かなくなる。それからしばらくたった朝、原稿を書くためにパソコンの音声入力(片手が動けなくなったため導入していた)を使おうとした時に、「しゃべれない」ことに気づく。
呂律が回らず、視界が歪む。歩行はできたため、すぐに脳神経外科を受診、緊急入院することに。41歳だった。
幸い命に別条はなかったが、鈴木さんは高次脳機能障害者としてリハビリテーションに励むことになる。
<病院のトイレの個室に突然見知らぬ老紳士が出現>
鈴木さんは右脳に障害を負ったため、「左側」の認識が困難になった。病院のトイレの個室に突然見知らぬ老紳士が出現する。これは左側にその老紳士がいたのに、顔を左に向けるまでその存在をまったく認識できなかったということだ。
また、真正面にいる相手と話す時にも、顔が横に向いてしまう。さらに、右側にいる人に注意が向くと、凝視してしまい、目が離せなくなる。
リハビリ中であっても、歩行に支障はなく、見た目は「普通」に見える。だが、本人にしてみれば、以前できたことで「できなくなったこと」が山ほどある。鈴木さんは、できないことが「他者にわかってもらえない」経験が何より辛かったという。
こうした「他者との関係」が、本書を貫く重要なキーワードといえそうだ。
「人との接し方」「関係のつくり方」を振り返る
41歳で“脳が壊れた”ルポライターが「異世界の経験」から学んだこと
脳梗塞は、いわゆる生活習慣病の一つであり、不規則な生活、飲酒・喫煙、ストレスなどが発症の原因となるとされている。鈴木さんの場合、フリーランスであったものの、自己を律し、比較的節制した生活を送っていたようだ。県の無料健康相談で高血圧が指摘された後は、その時に指導された減塩食生活を続けてきた。
ではなぜ発症したのだろう? 鈴木さんはそれまでの自分を振り返り、これは「生活習慣病」ではなく「性格習慣病」ではないかと思い至る。「生活」ではなく、鈴木さん自身の「性格」に問題があったということだ。
41歳という若さで脳梗塞に倒れた理由を、鈴木さんは「自業自得」と結論づける。そして、自らの性格や行動傾向を「背負い込み体質」「妥協下手」「マイルール狂」「ワーカホリック」「吝嗇(ケチ)」「善意の押し付け」と列記。どれも「自己中心的」という言葉に集約できそうな短所ばかりだ。
とくに大きかったのが、妻の千春さんとの関係。家事全般に「マイルール」を決め、テキパキと自分でやってしまうのは、夫の大介さんの方だった。注意散漫な傾向がある千春さんがグズグズしていると、家事を取り上げ、自分でやってしまう。
そしてイライラする。たくさんの仕事を背負い込んだ上に、(自分が奥さんから取り上げた)家事の負担が重なり、余計にストレスを溜めていく。高血圧の原因ともなり、しまいには脳梗塞発症に至った。
鈴木さんは、先に列記した自らの性格のうち、最大の欠点が「善意の押し付け」ではないかという。「妻のため」と思ってやってきたことが、実は「相手が望んでいること」ではなく、「僕がそうしたほうが良いと思っていること」にすぎなかった。
一方の千春さんは、相手が「してほしいと思っていること」を察して行動するタイプだ。夫婦仲がとくに悪かったわけではないが、(大介さんが原因の)二人の歪んだ関係が、彼自身の健康を損ねていったということだ。
脳科学の世界的権威であるマイケル・S・ガザニガは、著書『〈わたし〉はどこにあるのか』(紀伊国屋書店)の中で、他者の脳との相互作用の重要性を強調している。研究者は脳の機能を単体で見がちだが、実際には脳と脳が交流することで、単体にはない機能が発揮できる。
逆に、もし他者の脳と一切触れ合うことがないとすると、脳内のインタープリター(自己認識や意思を生むプロセス)が暴走し、「独りよがり」の意思決定しかできなくなる。他者との関係は、脳の機能にも重要な影響を及ぼすということだろう。
鈴木さんは、その後大きく回復したものの、緊急入院から7カ月たった今でも、注意欠陥、パニック、話しづらさといった障害が残っているそうだ。
だが、それまでの間に、自らの性格、そして妻の千春さんや実親との関係を反省し、改善を図ってきた。そして「人の縁」の大切さを、身にしみて感じるようになった。
もちろん、鈴木さんの言う「性格習慣病」が脳梗塞の原因として医学的に証明されたわけではない。また、彼が列記した性格や行動傾向があるからといって脳梗塞を発症するわけでもない。
だが、心身の健康を保つ上で、生活習慣と一緒に自分の「人との接し方」「関係のつくり方」を振り返ってみることは決してマイナスにはならないはずだ。 -
年を重ねていくうちに、食べ物や音楽、ファッションなどの好みが大きく変化することがある。だが、「異性」だけは、昔から同じような人ばかりを好きになっているような気が…。「好みの異性のタイプ」は加齢とともに変化することがあるのだろうか? そこで、脳科学の観点から、『脳科学的に正しい恋愛脳の作り方』などの著書がある黒川伊保子さんに、好みのタイプは変わることがあるのか聞いてみた。
「脳科学的な結論から言うと、異性の好みは意図的には変えられません。しかし、年齢を重ねるごとにだんだんと妥協ができるようになるのです」(黒川さん、以下同)
黒川さんによると、「好みのタイプ」とはズバリ「生物として生殖する相性がいい相手」。動物の脳は無意識の領域で、見た目、声、感触、匂いなどから、異性のタイプを認識しており、とくに体臭から感じ取れる「HLA」という遺伝子からは、「ウィルスに強い」「寒さに強い」といった資質を知ることができるという。遺伝子レベルで相性がいい異性を感じ取っている以上、好みのタイプが一定になるのは当然。脳科学的には、好みのタイプは産まれた時から決まっているわけだ。
しかし、この生来定められた「運命」も、年齢を重ねていくことで緩和される傾向にあるとのこと。
「好みのタイプを決める取捨選択の精度は、若いころほど厳しいもの。年を取るごとに“ストライクゾーン”は広がり、30代ごろからは相性以外にも、人間性でパートナーを選ぶことができるようになります」
男性の場合は「なるべく多くの子孫を残す」という生物としての戦略上、色々なタイプの女性と恋ができるような仕組みになっている。そのため、相手から「好き」と言われれば釣られるように好きになったり、ときには「いい人だなぁ」と思ったりするだけで結婚ができるケースも考えられるのだとか。
反対に女性は、相性が悪い相手を簡単に受け入れるわけにいかないため、俗に「フェロモンセンサー」とも呼ばれる、HLA遺伝子の匂いを嗅ぎ取る「鋤鼻器官(ヤコブソン器官)」と、その情報を受け取る脳の感覚野の機能が男性に比べると高め。センサーの感度のピークは25歳とされており、その精度は1000人の中からたった1人を選ぶ程度という厳しさだ。
しかし、黒川さんの元に寄せられた2000件超の恋愛相談のデータを分析すると、30歳を過ぎてもマッチングしない女性には急激に「妥協」の傾向が現われるという。
この傾向について、「『このままでは一生相手が見つからないかも!』と焦った脳が、戦略を変えてセンサーの感度を鈍化させているのでは」と黒川さんは推測。とくにアラフォーの女性はセンサーの感度が弱まるのか、妥協の傾向が他の年代と比較して顕著になり、激しい恋には落ちなくとも、人間性の良さだけで結婚できる確率が高まるのだという。
では、いつも同じタイプの人を好きになって失敗してしまうという人は好みのタイプが変えられない以上、情熱的な恋愛はあきらめて妥協できる年齢になるのを待つべきなのか…と思いきや、「恋愛は何度失敗してもめげないでください!」と、黒川さんから男性に対して力強い励ましのお言葉が。
「男性よりも女性の方が異性選びのハードルが高く、いわゆる“ストライクゾーン”の幅に男女差がある時点で、男性が女性にアタックするのは狭き門を突破する必要があるということ。哺乳類のオスがフラれるのは、スペックが劣っているからというわけではなく、生殖システム上、想定内といえます。男性には、99回失敗しても1回成功すればよし! くらいのタフさを持って、好きなタイプの女性に何度でも惚れたらいいと思いますよ」
お互いのセンサーが「合格」を出し、好みのタイプ同士の男女が付き合えれば、カップルとしての相性はきっと抜群なはず。脳が自分にピッタリの相手を探してくれているもの…と納得して、何度でも好みのタイプの異性に恋しちゃいましょう! -
北極海などに生息するニシオンデンザメは最高で約400年生き、最も長生きする脊椎動物かもしれない――そんな研究成果を、コペンハーゲン大学などが8月11日に発表した。雌の個体だと成熟するまでに約150年かかるという。
ニシオンデンザメは北極海などの水深100〜1200メートルに生息。体長は最大約5メートルほどだが、成長スピードが遅く年間1センチほどしか大きくならないため、長生きする魚と考えられていた。だが、サメは軟骨しか持たず、硬骨魚類と違って骨に成長の跡が残りにくいため、従来の手法では年齢を正確に知ることは難しかった。
研究チームは、サメの目の水晶体が一生変化しないことから、年齢を導き出せると考えた。漁船の網に誤ってかかった28匹から水晶体を取り出し、含まれる放射性炭素を基に年齢を推定したところ、うち1匹が392歳だと分かった。これより長生きの動物は、500年生きるアイスランド貝しか発見されていないため、脊椎動物の中ではニシオンデンザメが最も寿命が長い可能性があるという。
研究成果は、米科学誌「Science」に8月12日付で掲載された。
-
人工知能が病名突き止め=国内初、白血病患者の治療貢献―東大医科研
2016年08月07日
東京大医科学研究所が臨床研究を進める医学論文2000万件以上を学習した人工知能(AI)が、医師の診断では分からなかった白血病患者の病名を突き止め、治療方法を変えた結果、容体が回復していたことが分かった。同研究所は「AIが患者の容体改善に貢献したのは国内初とみられる」としている。
同研究所によると、使われたのは米IBMが開発し、2011年にクイズ番組で人間のチャンピオンを破り有名になったAIシステム「ワトソン」。人間の言葉を理解し、膨大な情報から解決策を導き出す能力があり、がん研究に関する2000万件以上の医学論文と約1500万件の抗がん剤情報を学習させ、診断や治療に役立てる研究を進めている。
60代の女性患者は昨年1月、医師から「急性骨髄性白血病」と診断され、同研究所付属病院に入院。抗がん剤治療などを続けていたが、体の免疫機能を担う白血球の数が回復せず、感染症で40度の高熱を出すなど生命の危険もあった。
同研究所が病名が異なる可能性もあるとして、女性の約1500カ所の遺伝子変異のデータをワトソンに分析させたところ、わずか10分で原因となる部分を特定し、有効な抗がん剤も提案。「二次性白血病」であることが判明し、治療方法を変えたところ、容体が回復に向かった。
女性は同年9月に退院し、通院治療で経過観察を続けている。ワトソンの分析が診断や治療に役立った患者は約50人いるが、容体が改善したのは初めてという。
研究を行った井元清哉教授は「がんの医学論文だけで毎年数十万件出ており、専門医の知識による診断には限界がある。実用化には時間がかかるが、将来的にはAIを使うのが当たり前になるだろう」と指摘している。
東京大医科学研究所が臨床研究を進める医学論文2000万件以上を学習した人工知能(AI)が、医師の診断では分からなかった白血病患者の病名を突き止め、治療方法を変えた結果、容体が回復していたことが分かった。同研究所は「AIが患者の容体改善に貢献したのは国内初とみられる」としている。
同研究所によると、使われたのは米IBMが開発し、2011年にクイズ番組で人間のチャンピオンを破り有名になったAIシステム「ワトソン」。人間の言葉を理解し、膨大な情報から解決策を導き出す能力があり、がん研究に関する2000万件以上の医学論文と約1500万件の抗がん剤情報を学習させ、診断や治療に役立てる研究を進めている。
60代の女性患者は昨年1月、医師から「急性骨髄性白血病」と診断され、同研究所付属病院に入院。抗がん剤治療などを続けていたが、体の免疫機能を担う白血球の数が回復せず、感染症で40度の高熱を出すなど生命の危険もあった。
同研究所が病名が異なる可能性もあるとして、女性の約1500カ所の遺伝子変異のデータをワトソンに分析させたところ、わずか10分で原因となる部分を特定し、有効な抗がん剤も提案。「二次性白血病」であることが判明し、治療方法を変えたところ、容体が回復に向かった。
女性は同年9月に退院し、通院治療で経過観察を続けている。ワトソンの分析が診断や治療に役立った患者は約50人いるが、容体が改善したのは初めてという。
研究を行った井元清哉教授は「がんの医学論文だけで毎年数十万件出ており、専門医の知識による診断には限界がある。実用化には時間がかかるが、将来的にはAIを使うのが当たり前になるだろう」と指摘している。 -
実はキケン!「寝たきり」を生み出す「薬・手術」がこんなにあった 考え直したほうがいい
降圧剤を飲んだら脳梗塞に 胃酸過多の薬で骨粗鬆症
脳動脈瘤の手術で植物状態 椎間板ヘルニアの手術で歩けなくなった ほか
不整脈のワーファリンは危険
都内に住む30代女性が語る。
「父は数年前から高血圧になり、医者から処方された降圧剤を真面目に飲み続けました。血圧が下がり、最初は喜んでいた父ですが、少しずつ様子が変わっていきました。以前の父は休日はいつも仕事仲間とのゴルフだったのに、段々と自室にこもり一人で過ごすことが多くなったのです。
そして半年前、急に脳梗塞を患い寝たきりに。私たちの生活は一変しました。母は介護疲れで精神的にも肉体的にも限界です。私自身も仕事で手一杯の上、家でも介護のサポートなどで疲弊し、休まる暇がありません」
ミカルディスなどの日本で主に処方されているARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)と呼ばれる降圧剤は、副作用が弱いからと安易に処方している医者が多い。患者も安心しきって複数の降圧剤を並行して服用している場合もあるが、こうした甘い認識が冒頭のように「寝たきり」を招き、患者本人やその家族を悲劇に巻き込みかねない。
事実、血圧を下げすぎるのは危険だ。東海大学名誉教授の大櫛陽一氏もこう警鐘を鳴らす。
「過度な低血圧は危険です。血圧が低いということは、血液を送り出す力が弱いということです。脳に血液がうまくまわらなくなると、めまいや貧血になる恐れがあります。さらには血流が乱れることにより血栓ができ、脳梗塞を引き起こす可能性も高まります」
脳梗塞の症状には高次脳機能障害や手足、顔半分の麻痺がある。こうした脳梗塞などの「脳血管疾患」を患ってしまい、寝たきりになるケースは実に多い。厚生労働省の調査によると寝たきり患者の3割以上が脳血管疾患が原因であり、最も多いことがわかっている。
脳梗塞と同じく脳血管疾患である脳出血もまた、寝たきりの原因となりうる。新潟大学名誉教授の岡田正彦氏が指摘する。
「不整脈がある人によく処方されるのがワーファリンです。この薬は、副作用として脳出血が起こるというデータがあります。特に高齢者は脳出血や消化管出血で重症になる方がすごく多い。私にとっては処方したくない薬の筆頭ですね」
ネキシウムやタケプロンなどの胃酸過多や逆流性食道炎の治療に使われるPPIと呼ばれる胃薬にも、寝たきりのリスクが潜んでいる。
「PPIは胃酸を抑える薬ですが、確かに効きます。胃酸過多や逆流性食道炎の患者さんにこれを出すと収まるのです。
ところが、長く飲み続けるとどうなるかということが外国で調査されていて、1年以上飲み続けると骨粗鬆症が進行して、骨折する確率が上がることがわかっている。4年飲み続けると5割を超える患者の骨が弱くなるというデータがあり、予想外の副作用がある薬なのです。
一時的に(1‾2ヵ月)飲むならともかく、これを安全と信じて何年も飲み続けている人がとても多いのです。その人たちは、骨粗鬆症が進行していることを知らない」(前出の岡田氏)
骨粗鬆症は骨密度の低下、または骨質の劣化により骨強度が低下し、骨折しやすくなる状態を招く。くしゃみや咳をしただけで肋骨を骨折、ということもありうるのだ。特に高齢者であれば、骨折によって入院を強いられ、ベッドに釘付けにされる時間が増えれば増えるほど、身体機能が低下し、寝たきりのリスクが増える。
クレストールで呼吸困難に
写真:現代ビジネス
クレストールなどスタチン系の薬は高脂血症の患者に処方され、脳血管障害のリスクを抑制する効果を持つが、横紋筋融解症という副作用がある。これは、筋肉の一部が溶けだし、筋肉痛や手足のしびれを引き起こす。前出の大櫛氏はこう言う。
「横紋筋融解症により、運動筋が溶け、呼吸困難になり、寝たきりになることもあります」
糖尿病薬にも注意が必要だ。代表的な糖尿病薬にはアマリール、ダオニールなどのSU剤やジャヌビア、エクアなどのDPP‐4阻害薬がある。これらはインスリンの分泌を促進させる効果があり、広く処方されているものの、副作用として血糖値が正常の範囲を超えて下がり過ぎてしまうことがある。
その結果、神経細胞に障害が発生し、認知機能を低下させることすらある。認知症は終末期になると脳萎縮が進行して、話が通じなくなり、食事も思うようにとれず、やがて寝たきりになる。
薬だけではない。手術の失敗や術後の合併症で寝たきりになる人も決して珍しくはない。50代の会社員男性が言う。
「昨年、母に脳動脈瘤が見つかりました。未破裂で小さなものだったため、手術を受けさせるか少し迷いましたが、医者からはくも膜下出血を防ぐため、瘤が小さくても予防手術をしたほうがよいと勧められ、手術を受けました。結果、神経を損傷してしまい、上手くいきませんでした。
現在は意識が戻らず、私たちの言葉も理解できなくなり、身体機能も麻痺して植物状態になってしまいました。元気だった母がこんな姿になってしまい、信じられないし信じたくもありません」
脳動脈瘤の手術で患部以外の正常な血管や神経に触れてしまった場合、損傷具合によっては脳に重度の後遺症を残してしまう危険性がある。確かに脳動脈瘤にはくも膜下出血の恐れがあるが、そのすべてが破裂するわけではなく、大きさや形、瘤ができた場所で治療方法も異なる。そのため、手術をせずに経過観察が推奨されることもある。後遺症で寝たきりになるリスクを考えると、手術を受けるかどうかの判断は慎重にすべきだろう。
椎間板ヘルニアなど、腰痛の手術も寝たきりのリスクを伴う。医師でジャーナリストの富家孝氏はこう語る。
「私はヘルニアによる腰痛に長年、悩まされてきました。痛くて歩くのもままならない状態でしたが手術はしませんでした。腰の手術は成功率が低く、症状がさらに悪化する恐れがあるからです」
ヘルニアの手術は位置や症状に合わせて方法が異なり、危険度も違う。
「特にラブ法と呼ばれる背中を大きく切開し、肉眼で見ながら神経の圧迫を取り除く手術は神経を傷つけてしまう可能性があり、寝たきりになる危険が見過ごせません」(整形外科医)
あのときあの薬を飲まなければ、あの手術を受けなければ寝たきりにならなかったかもしれない。そう後悔しないために、もう一度そのリスクについて、立ち止まってよく考えるべきだろう。
-
薬剤耐性のまん延と闘うための新薬開発に取り組む生物学者らが、抗生物質を予想外の場所で発見した──人の鼻だ。研究結果が27日発表された。
研究チームの発表によると、この抗生物質として有望な化合物は、鼻の中に生息する細菌によって生成され、病気を引き起こすスーパーバグ(抗生物質が効かない細菌)を殺傷する能力を持つという。
研究論文の共同執筆者で、独テュービンゲン大学(University of Tubingen)のアンドレアス・ペシェル(Andreas Peschel)氏は「人に関連する細菌が、実効のある抗生物質を生成することが明らかになるとは、まったくの予想外だった」と述べ、「さらに大規模なふるい分け調査計画がすでに開始されており、この発生源から発見される抗生物質がさらに多数存在すると確信している」と続けた。
抗生物質化合物は通常、土壌中に生息する細菌から採取される。
ペシェル氏と研究チームは、黄色ブドウ球菌が鼻腔内に常在する人は全体の3割で、7割の人には存在しないのはなぜかについて調査していた。黄色ブドウ球菌は、重症の細菌感染症の最も多い原因の一つで、実際にこれによって多くの人が命を落としている。この細菌の菌株の一種は、抗生物質に対する耐性を獲得している。
研究チームは、これとは別のブドウ球菌属の細菌で、体の中でも特に鼻の中に多くみられる「スタフィロコッカス・ルグドゥネンシス(S.lugdunensis)」が、黄色ブドウ球菌と闘う抗生物質を生成することを発見した。この化合物は「ルグドゥニン(Lugdunin)」と命名された。
研究チームの報告によると、マウスを用いた実験では、この新発見の抗生物質による皮膚感染菌の除去または改善がみられたという。有害な副作用は確認されなかった。
ペシェル氏は、英科学誌ネイチャー(Nature)への論文掲載に先立ち開かれた記者会見で、これらの結果は「極めて予想外の、心躍る発見であり、抗生物質の開発を新たに構想する上で非常に役立つ可能性があると考えている」と述べた。
人体には1000種以上の細菌類がいるため、発見を待つばかりの抗生物質産生菌がさらに多数存在している可能性が高い。そのため、研究チームは「ヒト細菌叢(そう)を、新たな抗生物質の供給源とみなすべきた」と結論付けている。 -
米疾病対策センター(CDC)は15日、中南米などで流行中のジカウイルス感染症(ジカ熱)について、性交渉で女性から男性に感染した例を初めて確認したと発表した。これまで性交渉での感染は、男性からしか確認されていなかった。
CDCによると、ジカ熱の流行地域から米ニューヨークに帰国した女性が、その日にパートナーの男性とコンドームなしで性交渉をした。女性は翌日に発熱などを訴え、男性も1週間後に同様の症状を訴えて、いずれもジカ熱と診断された。男性は最近、ジカ熱の流行地域に行ったことはなく、蚊に刺された覚えもなかったという。
CDCは、流行地域から帰国した男性に性交渉の際にはコンドームを使うことを勧めていたが、女性からも感染する可能性があると注意を呼びかけている。 -
南極のオゾンホール縮小確認、世界初の発見!
南半球のオゾンホールを30年にわたって観察してきた科学者たちが、ついに南極のオゾンホール(オゾン層の穴)が縮小していることを確認した。
オゾンホールの大きさは気象や火山活動の影響を受けて毎年変化するため、回復の傾向を見てとるのは難しい。科学者たちは、オゾン層は2000年前後から比較的安定していて、徐々に回復する傾向にあると考えていたが、2015年10月にはオゾンホールの大きさが過去最大になってしまった。
そんな中で、米マサチューセッツ工科大学(MIT)の大気化学・気候科学教授のスーザン・ソロモン氏が率いる研究チームが、オゾン層の回復を示す複数のデータを『サイエンス』誌に発表した。MIT、米国立大気研究センター、リーズ大学の研究者からなるソロモン氏の研究チームがオゾン層回復の厳密な証拠を初めてつかんだかたちだ。
米カリフォルニア大学アーバイン校の化学者マリオ・モリーナ氏とシャーウッド・ローランド氏が『ネイチャー』誌に論文を発表し、フロンガスがオゾン層への脅威になることを警告したのは1974年のことだった。フロンは当時、スプレー用のガスや冷蔵庫の冷媒として広く利用され、大気中に急速に蓄積されていた。
地上で使われたフロンが大気中を上昇して成層圏に達すると、強烈な紫外線により分解されて塩素原子が生じる。塩素原子はいずれ大気に吸収されるが、大気が塩素を吸収する能力には限りがあるため、残った塩素原子が大量のオゾンを破壊してしまうというのが論文の結論だ。モリーナ氏とローランド氏は、この画期的な研究により1995年にノーベル化学賞を受賞した。
両氏の仮説は化学産業界から激しい攻撃を受けたが、11年後の1985年に英国の科学者チームが南極上空のオゾンホールを実際に確認したことにより、その正しさが裏付けられた。成層圏のオゾン層は、太陽からの有害な紫外線を吸収して地上の生態系を保護している。オゾン層が失われると地上に届く紫外線が増え、ヒトや動物の皮膚がんが増加する可能性がある。
ある大きさ以上になる時期に注目
オゾン層の破壊が意識されるようになった1980年代、大気中のオゾン濃度は急激に低下していった。1987年にモントリオール議定書が採択され、フロンの製造と使用が強力に規制されるようになると、オゾン濃度の急激な低下はなくなったが、濃度は低いままだった。
現在も南極上空には毎年オゾンホールができている。南極の冬である8月にオゾンホールはできはじめ、その大きさは10月にピークに達する。2015年の例もあり、10月の大きさはばらつきが大きいため、ソロモン氏のチームは、気球と人工衛星で測定した9月のデータを、オゾン層の状態を計算する統計的シミュレーションの結果と比較した。
すると近年は、オゾンホールの面積が1200万平方キロメートルを超える時期が遅くなっていることが明らかになった。これはオゾンホールの成長を示す強力な指標であり、つまり、オゾンホールが縮小していることを示している。研究チームは、オゾンホールは以前より400万平方キロメートル以上も小さくなったと考えている。オゾンホールの深さも、以前より浅くなっている。
「重要なのは、オゾン層に穴があきはじめる時期が遅くなったという事実です」とソロモン氏。「オゾンホールが形成される時期が遅くなり、穴自体も小さく、浅くなってきているのです。独立に行われた観測のすべてがオゾン層の回復を示唆していて、それ以外の説明をするのは困難です」
研究チームは、実際に観測された結果が気候モデルによる予測とも一致し、オゾンホール縮小の半分以上が大気中の塩素成分の減少による可能性も示した。
カリフォルニア大学アーバイン校の化学教授ドナルド・ブレイク氏によると、今回の研究は、南極のオゾン層の研究としてはこれまでで最も徹底したものであるという。
なお、ソロモン氏は、2015年のオゾンホールが異例の大きさになった主な原因は、同年4月にチリでカルブコ火山が噴火したことにあると考えている。火山の噴火により大気中に微粒子が撒き散らされたせいで、極域における成層圏の雲の数が増え、この雲の表面で大気中の塩素原子が活性化してオゾン層を破壊したという。
大きな環境問題にも希望はある
今回の発見は、オゾン層の回復が、期待されていたスケジュールにのってきたことを意味している。ブレイク氏の説明のとおり、オゾン層を破壊するガスが減少してきたのだ。
ソロモン氏もブレイク氏も、オゾン層の回復のペースは遅く、完全な回復は今世紀半ばになるだろうと予想している。フロンの製造は1990年代に終わっているが、その寿命は50〜100年と長いため、1970〜80年代にできた不安定な形の塩素がいまだに大気中に残っているからだ。
オゾン層の回復は、世界中の科学者、技術者、外交官による数十年間の努力の成果だ。
「大きな環境問題に挑むことを恐れるべきではないと教えてくれた、歴史的快挙です」とソロモン氏は言う。
ブレイク氏も心から喜んでいる。「私たちの期待したとおりの成果があったことが、厳密に証明されたのです。シェリー(シャーウッド・ローランド氏の愛称)が生きていて、この論文を読むことができたら、どんなにか喜んだことでしょう」 -
交尾の最中や後に、雌のカマキリが雄を捕食する「性的共食い」の習性をめぐり、雄がその死後も、子孫のための栄養となって役立っていることを視覚的に確認したとする研究論文が29日、発表された。
英学術専門誌「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B)」に発表された研究論文の共同執筆者で、米ニューヨーク州立大学フレドニア校(State University of New York at Fredonia)のウィリアム・ブラウン(William Brown)氏は、「性的共食いは、子孫への雄の投資を増強するものだ」と話す。
ブラウン氏と豪マッコーリー大学(Macquarie University)のキャサリン・バリー(Katherine Barry)氏は、追跡可能な放射性アミノ酸を投与したコオロギを複数の雄のカマキリに食べさせ、その後、雌のカマキリと交尾させた。
雄の半数は、交尾後に放置して雌に捕食させ、残る半数は、交尾後に雌から離した。
科学者らは、放射性の追跡物質が共食いする雌の体内を通って、卵にたどり着くのを確認。その大部分は雌によって吸収されず、卵へと届けられていた。
AFPの取材に答えたブラウン氏によると、生んだ卵の数にも違いがみられ、パートナーを捕食した雌の方が、捕食しなかった個体と比較してその数が多かったという。
研究論文によると、自然界では、雄のカマキリが交尾の際に雌によって捕食される確率は約13〜28%だという。【翻訳編集】 AFPBB News -
1億年近く前に生きた原始的な鳥の翼が、琥珀に閉じ込められた非常に保存の良い状態で見つかった。羽毛の重なり方、模様、色、配列など、現在の鳥類にそっくりの形態が、当時の鳥類にもすでに備わっていたことがわかる。
科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」の6月28日号に論文が掲載された。白亜紀末期に絶滅した鳥類の系統、エナンティオルニス類のものである可能性が最も高いという。ナショナル ジオグラフィック協会もこの研究を支援している。
「我を忘れるほどの発見」
恐竜の多くが羽毛に覆われていたという事実は1990年代から一般に浸透してきた。一方、当時の鳥の羽毛に関する手がかりは、これまでのところ、炭化・圧縮された化石に残る羽毛の痕跡や、琥珀の中で化石化した個々の羽毛くらいしかなかった。
羽の痕跡からその並びがわかることもあるが、たいてい細部までは保存されていなかったし、色に関する情報が残っていることもまれだった。他方、琥珀に封入された1枚切りの羽毛では、その持ち主である動物までたどり着くことができなかった。
今回、新たに見つかった翼のサンプルは2つ。それぞれ重さ1.6グラムと8.51グラムしかないが、骨の構造や羽毛群、軟部組織を備えている。論文の共著者で中国地質大学のリダ・シン氏によれば、動物の本体から抜け落ちたのではない羽毛が研究されるのは白亜紀のものとしては初めてという。
「琥珀内の羽毛を調べていて一番問題なのは、わずかな断片だったり、体から離れたものだったりして、どんな動物に生えていたのかが永遠にわからないことです」と語るのは、共著者の1人であり、カナダのロイヤルサスカチュワン博物館で無脊椎動物の古生物学を担当する学芸員、ライアン・マッケラー氏だ。「これほどのサンプルが見つかることはまずありません。我を忘れるほどの発見です」
現代の鳥類に近い姿
X線マイクロCTによる分析で、2つのサンプルは骨の大きさと成長段階からいずれも幼鳥と判明。羽毛の特徴や骨の構造も類似していることから、同一の種に属する可能性がある。
どちらのサンプルも、皮膚、筋肉、かぎ爪、羽軸が確認でき、風切羽(かざきりばね)や雨覆羽(あまおおいばね)が並んでいるのも見て取れる。いずれも、配置や微小構造が現代の鳥類に近い。
裸眼では羽毛は黒く見えるが、顕微鏡分析では風切羽はおおむね濃い茶色、雨覆羽はやや薄い茶色から銀色、白色の帯まで色の幅があることがわかった。
紛争地帯から豊富な化石
今回の琥珀は、ミャンマーで手に入れたものだ。同国で産出する化石入りの琥珀は、ほとんどが北部のカチン州、フーコン渓谷から出ている。この渓谷は現在、カチン独立軍(KIA)の支配下にあり、50年以上にわたって州との間で断続的に紛争が続いている。
そのため、ミャンマー産琥珀の採掘や売却はほとんど野放しの状態で、大部分が中国の消費者に渡り、宝石として、あるいは装飾を施した彫刻として珍重される。
シン氏ら調査チームが今回の研究に使ったサンプルも、カチン州の州都ミッチーナーにある有名な琥珀市場で収集したものだった。
「ミャンマー産琥珀の魅力は、多様な白亜紀の動植物が含まれていること」と、アメリカ自然史博物館の学芸員、デイビッド・グリマルディ氏は言う。「ミャンマー産琥珀のうち約7割は何も入っていませんが、残りの3割に驚異的な生物多様性を見ることができます。これほどの多様性は、全く予想していないものでした」
科学者には宝物、消費者には不純物
ミャンマー産琥珀の多くは宝飾品や彫刻に使われるため、封じ込められた虫や植物は不純物とみなされ、研磨の段階で一部または全部が壊されることがある。しかし、羽毛が残っていた場合は珍重され、それを生かしたカッティングと研磨が施される。
シン氏らのチームは、今回の羽毛サンプル2つのうち小さい方を「天使」と名付けた。ジュエリーデザイナーが、この琥珀から作ったペンダントに「天使の羽」という名前を付けようと考えていたからだ。研究者たちが化石を分析した際、翼の表面が琥珀の表面に出た状態で端が切れていたことから、もともと初期鳥類の全身が琥珀に閉じ込められていた可能性もある。
体のごく一部だったとしても、マイクロCTの分析で浮かび上がった姿にシン氏の胸は高鳴った。「1枚きりの羽ではなく、1億年近く前の翼に付いていた複数の羽が、その骨構造とともに観察できたのです」と、シン氏は振り返る。
シン氏は、「間違いなく天使です」と誇らしげに締めくくった。 -
公益財団法人「日本骨髄バンク」(東京都)に登録して造血幹細胞移植を待つ白血病などの難病患者のうち、昨年末までの5年間で1655人が移植を受けられず、待機中に死亡していたことが、同バンクへの取材で分かった。他に病状の悪化で286人が登録を取り消したことも判明。手続きなどで登録から移植までに時間がかかることが一因とみて、同バンクは待機日数短縮の検討を始めた。【須田桃子】
正常な血液を作れない白血病などの患者が血縁関係のない他人から移植を受けるには、バンク登録の必要がある。同バンクによると、2010年からの5年間に新たに登録した患者は1万1042人。このうち、死亡や病状悪化に加え、血縁者からの移植や他の治療法である臍帯血(さいたいけつ)移植、化学療法への変更などで計3648人がバンクによる移植を受けず、翌年末までに登録を取り消した。待機日数が長いため治療方法を変えた人もいるという。
待機日数は2003年に約175日(全登録患者の中央値)で、手続き改善の試みにもかかわらず、15年にも147日と約5カ月かかった。このため、移植を待つ医療現場からも短縮を求める声があったという。造血幹細胞を提供するドナーの登録者は約46万人おり、患者の約96%には移植に適したドナー登録者が見つかるが、ドナー側の仕事の都合や健康状態、家族の同意、転居先不明などから、移植に至るのは約5割にとどまるという。
このため、同バンクは、家族や第三者立ち会いの下で従来は別の日にしていたドナーの最終同意書作成の手続きを、骨髄採取のための健診直前に行うことで、患者の待機日数をさらに1カ月弱短縮する対策を検討している。ドナーにとっても通う回数が減り、負担軽減が見込まれる。
同バンクの担当者は「患者にベストのタイミングで移植してもらうため、手続きの簡略化を検討中だ。年内にも試行的に始めたい」と話している。
◇日本骨髄バンク
白血病や再生不良性貧血など血液難病の患者に対し、健康な非血縁者からの造血幹細胞移植を仲介する組織。日本赤十字社や国、地方自治体の協力で運営されている。今年4月末時点の患者登録者数は3284人、提供するドナー登録者数は45万9365人。1992年の開始以来の移植実績は1万9397件。 -
【保存版】実はキケンだった!医者に言われても受けてはいけない手術
この痛みから早く逃れたいと思っている時、医者から「良くなるには手術するしかない」と言われ、信じてしまう。でもよくよく考えてください。その手術は本当に必要ですか。
受けてはいけない手術の一覧表はコチラ!
尿が上手く排出できなくなる、一日に何回もトイレにいきたくなる頻尿などの症状が出る前立腺肥大症。55歳以上の男性のうち5人に1人が罹患しているとも言われ、一昔前は、手術で切るしか治らないと言われていた。だが、それはもはや古い話だ。
泌尿器科を持つ楠医院(東京・板橋区)の板倉宏尚院長が言う。
「前立腺肥大症という同じ病名がついていたとしても、各々の年齢も違えば、体つきも違いますし、症状も違います。その人にあった治療が必要になってきます。当然、すべての人に手術が必要というわけではありません。重度でなければ、薬で十分治療することができます。
もちろん、手術にはリスクがあります。手術による出血や、おしっこの通り道に細菌が入り感染症を引き起こすこともある。また、前立腺は生殖器でもありますから、逆行性射精障害やEDになってしまうこともある」
さらに医師であり医療ジャーナリストの富家孝氏は、こんな危険性もあると指摘する。
「前立腺肥大の場合、医師は前立腺がんかどうかを調べたがるので、細胞を採取して調べる生検をすすめます。生検では、十数ヵ所、前立腺に針を刺して細胞を採るのですが、これが危険なのです。
出血しやすい上、尿が出にくくなって腎不全を起こす可能性がある。現に、私の知人も前立腺肥大で生検を受けた後、腎不全になり高熱にうなされ死を覚悟したそうです」
腰の手術は成功率が低い
医者にすすめられるまま手術を受けたら、さらに症状が悪化することがある――その最たる例が腰痛だ。
前出の富家氏が語る。
「私は長年、脊柱管狭窄症と椎間板ヘルニアによる腰痛に悩まされてきました。痛くて歩くのもままならない状態でしたが、手術はしたくなかったので放置してきました。なぜなら腰の手術は成功率が低く、症状がさらに悪化する恐れがあり、再手術する人が多いと聞いていたからです。
ある病院の整形外科医は、『良くなりたかったら手術をするしかないですよ』とすすめてきましたが……」
60歳以上で、腰痛に苦しんでいる人は、日本全国にごまんといる。だが、治療のため腰の手術を受けた人からは「手術しなければよかった」、「手術前よりも痛みがひどくなった」という声が多く上がっている。富家氏が続ける。
「今は腰を伸ばすマッケンジー体操や関節の動きをよくするAKA-博田法といったマッサージをすることで、痛みを緩和しています。医者の言う通りに手術をせずに本当によかった。私の知人は脊柱管狭窄症のため、一時5メートルも歩けませんでした。でも手術はせず10年間、ストレッチなどの保存療法を行っていたところ、不思議なことに痛みへの意識がなくなり、79歳の今は毎日元気に歩き回っていますよ」
医療ジャーナリストの田辺功氏も「ほとんどの腰痛は、手術では治らない」と断言する。
「腰痛持ちの人がMRIやX線写真を撮ると、異常が見つかる場合が多く、医者は手術をしたがるのですが、実は腰痛の原因の8割は『不明』と言われているように、腰を手術したからといって必ずしも治るわけではない。姿勢やバランスなどに加え、精神的なものまで原因は多岐にわたっている。だから患者は、整形外科で手術してもらっても効果を感じられず、整骨院やカイロプラクティックに殺到するわけです」
原因が分からないのにもかかわらず、なぜ医者はメスを入れたがるのか。
「彼らは彼らなりに先人たちからそう教えられてきたので、どの医師も手術をすることが正しいと信じ込んでいるのです。もちろん前提として『手術は儲かるから』という理由もある。でもそんな理由で手術をされたら患者はたまったもんじゃないですよね」(田辺氏)
腰痛同様に、年齢とともに増えてくるのが変形性膝関節症、いわゆる「膝痛」だ。病院に行くと、「手術をすればあっという間に痛みが消えますよ」、「楽になりたいなら手術しかない」などと甘い言葉をささやく医者がいるが、実はここにも「落とし穴」が待ち受けている。
人工関節のリスク
整形外科医の寺尾友宏氏が言う。
「膝の手術は人工関節を入れるのが主ですが、医者として正直な感想を言わせてもらうと、人工関節にしなくてもいいのに、わざわざ手術を受けている人が多い。人工関節は人間の体と違って、自ら修復する機能はありません。手術後は摩耗していくだけ。一度人工関節にすると、後戻りはできず、もし違和感や痛みが出ても、一生それを抱えて生きなければならないリスクがあります。
人工関節は、金属とプラスチックで出来ていますが、金属と生体との境目は常にトラブルの元でもあります。4‾5年経ったら緩んできてしまい、痛みが出るんです。歩くことも嫌になり、最終的には車椅子生活になってしまう人もいます」
変形性膝関節症は、痛み止めを飲む、湿布を貼る、ヒアルロン酸注射を打つなど、治療の選択肢が少ない。そうなると、医者も「痛くて我慢できないなら手術しましょうか」という話に、飛躍してしまう。
「高額療養費制度を使えば10万円ほどで済んでしまうので、『だったら手術しようか』と思いがちですが、先ほども述べたように、将来的にリスクがあることを理解していない人がほとんどです。
人工関節は最後の最後の手段であり、その前に、機能回復をするためのリハビリを徹底的にやれば、痛みが引く可能性はあります。でも、今の医療制度では、電気を当てたりすることくらいしか日常的にはしてくれない。リハビリは儲からないので、医者としてはやらせたくないのです」(寺尾氏)
だが、近年は手術やリハビリ以外の画期的な治療法が開発されつつあるという。
「ここ最近は、『軟骨細胞シート』と呼ばれる、自分の細胞を取り出し、培養して膝に注入する治療法が注目されています。関節のメカニズムを活性化してくれて、膝の自然治癒力を増幅し、症状を緩和してくれるのです。この方法は、リスクもなく60代以上の方でも十分効果を発揮します」(寺尾氏)
五十肩は手術では治らない
40代‾50代に多い、関節リウマチ。この病気もやはり「人工関節の手術はやめたほうがいい」という。医療経済ジャーナリストの室井一辰氏が言う。
「人工膝関節を入れると、静脈血栓塞栓症(足にできた血栓がもとで肺の血管が詰まる)になるリスクが高まります。そのため、抗血栓薬を一生、飲み続けなければならず、若い人にとってはかなり負担になるでしょう」
腕が上がらなくなる五十肩(肩関節周囲炎)は辛い。だが、いくら痛いといっても、医者がすすめるままに手術をするのはこれも危ない。
「五十肩もそもそもの原因が分かっていない病気です。関節鏡で骨を削る手術をするのですが、根本的な治療にはなりません。五十肩も肩だけでなく、首やその周りの筋肉など様々な要因が複雑に絡み合って痛みが出ているので、一部を手術しても効果が薄いのです。
特に60歳以上の方は、わざわざ体に負担のかかる手術より、ストレッチや半身浴をして温めるなど、保存療法のほうが良いでしょう」(前出の室井氏)
物を食べる時に顎が痛くなったり、口が閉じられなくなったりする症状が出る顎関節症は、手術が必要なのか。
「手術で顎関節症が治ったというエビデンス(効果があることを示す証拠)は一つもありません。体全体のバランスがずれている場合が多く、手術で噛み合わせを治したとしても、完治は難しい。それだったら、痛みが出ない程度に顎の体操をしたりして、うまく付き合っていくほうがいいでしょう」(前出の室井氏)
女性の中には、足の親指が曲がり歩くたびに痛みを伴う、外反母趾に悩む人も多い。「靴を履くたびに、脳天まで響くような痛みがある」、「出かけるのが憂鬱に感じる」と、医者に言われるまま「楽になるなら」と手術をする人がいるが、より悪化するケースは後を絶たない。
白内障手術で失明の危険性も
外反母趾・浮き指研究家で接骨院を営む、笠原巖氏は「手術をする前に、もう一度よく考えてほしい」と語る。
「手術を考えている人の多くは痛みで苦しんでいます。とはいえ、変形はわずかにもかかわらず、痛みのために手術をしてしまい、かえって後遺症に苦しんでいる人も多い。『痛い時は曲がる時』であり、炎症を起こしている時期こそテーピングなどで固定する保存的療法を行うと、痛みはなくなります。痛みが止まってから手術を考えても遅くはありません」
眼のレンズにあたる水晶体が白く濁り、ものが二重にぼやけて見えるようになる白内障。著書に『緑内障・黄斑変性症・糖尿病網膜症を自分で治す方法』などがある、日本綜合医学会理事長で回生眼科の山口康三院長は、白内障の手術に対して、こう警鐘を鳴らす。
「著しく生活に支障が出る場合を除き、基本的に手術は避けるべきです。リスクとして、もっとも考えられるのが、水晶体を取り除き、人工レンズを入れる時に、レンズを支える水晶体の後ろの膜が破れ、眼球の中の硝子体が流れ出してしまうこと。最悪、失明することもあります。
腰や膝の場合は補助器具がありますが、眼はもし失敗したら取り返しがつかない。その認識が薄い患者さんがいますが、安易な気持ちで手術をするのはやめたほうがいい」
白内障より手術の危険度が高いのが緑内障だ。
「緑内障手術はそもそも眼圧を下げるためであって、欠けた視野が回復するわけではありません。緑内障は、眼球の眼圧が高まり視神経を圧迫することで視野障害が起こると考えられていますが、日本人の緑内障患者の7割程度は正常眼圧です。
それでも医者として傍観するわけにはいかず、少しでも回復する可能性があれば、細菌が侵入して失明するリスクがあったとしても、手術をすすめてくる場合があるので、しっかり自分で判断してください」
さらに山口院長は「緑内障や白内障を治すのにもっとも効果的な方法は、手術ではなく食事療法や生活習慣を改めることだ」と言う。
「たとえば白内障で言えば、水晶体の濁りを引き起こす最大の原因は活性酸素です。本来は水晶体の中に含まれるビタミンCにそれを消去する働きがありますが、そのビタミンCが不足すると、活性酸素が大量に生じて視力が悪くなる。食生活、生活習慣を変えなければ、たとえ手術で視力が回復したとしても根本的な解決にはなりません」
身体がボロボロになる
日本人の3人に1人は悩んでいるといわれている痔も、手術しないほうがいい病気だ。
「特にイボ痔は切らないと治らないと思っている人がいるかもしれませんが、今は薬で十分治せます。ALTAと呼ばれる注射療法という選択肢もある。痔核を切り取る手術と違って痛みを感じない部分に注射するため、患者の身体的・精神的な負担が軽減される。また、入院期間も短縮でき、社会生活への早期復帰も可能です」(医学ジャーナリストの松井宏夫氏)
女性を深く悩ませる子宮筋腫。医者から手術をすすめられたが、手術をせずに完治したというケースもある。埼玉県在住の佐藤智子さん(仮名・42歳)の話。
「子宮筋腫が大きくなって握り拳ぐらいの大きさの筋腫が二つ、小さめの筋腫が三つできました。不正出血や生理痛に悩まされ、医者から『手術で子宮を全摘するよう』すすめられましたが、体にメスを入れるのが嫌で……。しかも専門書を読むと、子宮を全摘すると、ホルモンバランスが崩れ、更年期障害になる可能性があると知ったんです」
佐藤さんは、自分で全摘手術以外の治療を探し、子宮動脈塞栓術(UAE)という方法を選んだ。
「子宮筋腫は子宮動脈からの血液を栄養にして大きくなります。そこで子宮動脈に塞栓物質を詰め込んで、子宮筋腫に栄養が行かないようにして、筋腫を小さくするのです。
この治療法は保険が効きませんが、数日の入院で済むし、全摘手術に比べると体の負担はほとんどない。子宮筋腫の大きさは1年後に半分ぐらいに縮小。その後、年を経るごとに小さくなり、わずか数mm程度の大きさになりました。症状もなくなったので、いまは病院にも通っていません」
子宮の病気は非常にデリケートだが、月経痛や排便通の症状が出る子宮内膜症も手術の必要はないと、医療ジャーナリストの増田美加氏は語る。
「手術をしたからといってその後、子宮内膜症が一生発症しないということはありません。手術後、最初の1‾2年は問題なくても、再発するケースが多い。すぐに妊娠・出産を考えていない場合は、体に負担をかけて手術するよりも、基本的には低用量ピルなどのホルモン剤でコントロールしていくのが一番望ましいですね」
その手術は本当に必要か?
尿漏れなど過活動膀胱に悩まされている人も多い。女性の場合は、更年期以降、特に閉経したあとに骨盤底筋群が緩むことが原因で起こる。
「かつては開腹をして、膀胱頸部の両脇と骨盤筋膜の腱弓を縫い縮め、固定する手術が行われていましたが、近年では、TFS手術といって、メスを使わずに、腟内から針を刺してテープ薬剤を移植して子宮や膀胱の筋膜や靭帯を補強するので、1時間半程度で終わり、日帰りが可能です。
自由診療のため、行える医師や施設は限られていますが、開腹手術をすすめられたら、他の病院を当たってみてもいいかもしれません」(増田氏)
腰痛、膝痛、内臓疾患……自分が弱っているとつい医者のことを崇め「楽になれるなら……」と手術に飛びついてしまう人がいるが、ちょっと待ってほしい。医療ジャーナリストの伊藤隼也氏はこう言う。
「日本人は不思議なもので、車や趣味にはこだわる人が多いのに、自分の身体のことになると、どうも他人に任せてしまうところがあります。
頭に置いておいてほしいのは、身体にメスを入れれば、何かしら弊害が出るということです。手術は常に、リスクと等価交換の関係にあるのです。
特に高齢者の場合、ある1ヵ所を手術で治しても、他の部分は古くなっているわけですから、むしろ全体のバランスが崩れ悪化することもある。自分の身体に対して、最終的に責任を持てるのは自分しかいないのです」
「その手術は本当に必要か?」と思ったら、セカンドオピニオンなど、複数の医者に意見を聞き、自分で判断することが求められている。 -
【AFP=時事】インド西部に生息するカエルの一種、ボンベイナイトフロッグ(学名:Nyctibatrachus humayuni)は、両生類7000種の中で他に類を見ない交尾姿勢(体位)を好むとの研究結果が14日、発表された。これまで確認されているカエルの交尾姿勢としては7例目となるという。
「背面またぎ」と命名されたこの新たな交尾姿勢は、それがどんなによじれて曲芸的なものであろうとも、精子と卵子を受精させるための方法にたどり着く性選択の進化の事例研究の一つだ。
インド・デリー大学(University of Delhi)のサティアバマ・ダス・ビジュ(Sathyabhama Das Biju)教授率いる研究チームは、研究対象のこの小型カエルの交尾現場を確認するために、インド西部マハラシュトラ(Maharashtra)州ハンバーリ(Humbarli)村近くの密林で40日間、夜間の張り込みを行なった。
前後の文脈からボンベイナイトフロッグの風変わりな行動についての説明文だけを抜き出すと、それはまるで、1970年代の性愛指南書からの抜粋のようだ。
論文では「雄は、雌には抱きつかずに、葉や枝、木をつかんだり、その上に前脚をついたりして、雌の背中の上にまたがる」と交尾が始まる際の状況が描写されている。
雌は、2匹がいる葉の上に卵を放出して受精に備えるが、ここからの行動は、一般的な交尾とはかなり様相が異なる。
研究チームは、科学誌「PeerJ」に発表した研究論文の中で「雄は、雌の背中の上に射精する。精子はその後、雌の背中から後ろ脚を伝って流れ落ち、卵に到達。受精となる」と説明している。
この間、ボンベイナイトフロッグの雄と雌の間には数ミリの隙間が保たれ、ほとんどの場合、お互いに決して触れ合うことはない──強いて言うならカエル版「タントラセックス」のようなものだろう。
この儀式的な交尾の最終段階で、雄は慎重に脇へ退き、頬を膨らませて卵に覆いかぶさる。
これは、未来のカエルたちをヘビから守るための行動かもしれない。研究チームによると、カエルの卵をヘビが食べることも今回初めて確認されたという。
ヘビに食べられることを免れた卵は、最終的に葉から落ちて、下を流れる小川でオタマジャクシになる。
ビジュ氏は声明を発表し、「他に類を見ない繁殖行動」であることを指摘しながら、「これは、無尾目両生類の進化生態学と習性を理解する上で基礎となる発見だ」とカエルの学術的な分類名を用いて述べた。
しかし、ボンベイナイトフロッグの独自性は、これだけではなかった。
通常、交尾相手を引き寄せるために鳴くのは雄だが、この種では雌も、こうした鳴き声を発する。これが進化の上でどのような目的を果たす可能性があるかについては、まだ科学的に解明されていない。【翻訳編集】 AFPBB News -
「体内受精」の性行為、3億8500万年前に始まった 研究
(パリ/フランス)
それは、われわれが知っているような「愛」ではなかったかもしれないが、性行為の技術は約3億8500万年前に既に発達していた──板皮(ばんぴ)類と呼ばれる骨板に覆われた魚類の化石を調査したオーストラリア・フリンダース大学(Flinders University)などの進化論科学者チームが、19日の英科学誌ネイチャー(Nature)に研究論文を発表した。
研究チームが調べたのは、板皮類の一種「ミクロブラキウス・ディキ(Microbrachius dicki)」の化石。体長約8センチのこのミクロブラキウスは、現在の英スコットランド、エストニア、中国にあたる地域に生息していた。スコットランドでは1888年に最初の化石標本が発見された。
最も原始的な有顎(ゆうがく)動物である板皮類については、これまで知られている中で最古の脊椎動物であり、人間の祖先とも考えられている。今回の研究を通じ、生命史におけるさらなる名誉を得ることになった。
論文によると、ミクロブラキウスは、体内受精をするために交尾を行ったと考えられる最初の生物種だという。
ミクロブラキウスの雄は、クラスパー(交接器)と呼ばれるL字型の硬い生殖突起を持ち、これを用いて雌の体内に精子を送り込んでいた。この生殖方法は、水中に放卵する方法に比べてより効率的と論文は指摘している。
雌は小さな一対の骨を発達させており、この骨を用いて、交尾するのに適切な位置に雄の生殖器を固定していたという。
フリンダース大学のジョン・ロング教授(古生物学)は「ミクロブラキウスは『小さな突起』を意味するが、科学者らは数百年の間、この骨質の一対の突起が実際に何のためにあるのかという謎に頭を悩ませてきた」と語る。
「われわれは今回、この大きな謎に答えを出した。これらの突起は交尾のために存在するもので、雄の交接器を雌の生殖器部内の適切な位置に固定させるものだ」
体内受精はこれまで、脊椎動物の進化史上ではかなり後期に発生したと考えられていた。
頭部と胴体を分厚い骨板で覆われた板皮類は約7000万年の間、世界の海、川、湖を支配していたが、約3億6000万年前に、謎の大量絶滅で全滅してしまった。
板皮類は、現在の爬虫(はちゅう)類、鳥類、人間を含む哺乳類などでみられる顎、歯、一対の手足などの特徴を後世に伝えたとされる。
今回の研究が正しければ、ミクロブラキウスの「交接器」は数億年かけて進化し「男性器」になったということが考えられる。
ミクロブラキウスの交尾技術の解明は2013年、ロング教授がエストニアのタリン工科大学の所蔵品の中にある化石に偶然目をとめたことがきっかけになったという。(c)AFP -
4月16日午前1時25分に熊本県で発生したマグニチュード7.3の大地震。熊本県で震度6強、大分県も最大震度6弱を観測した。その後、震源から北東にある阿蘇地方や東の大分県で地震が相次ぎ、震源が東へ移動していると指摘する専門家もいる。
M7.3の「本震」は、14日の「前震」があった断層帯と、その北の断層帯の交差地点北側で発生。午前3時55分に熊本・阿蘇でM5.8、午前7時11分には大分県でM5.3の地震が発生した。
気象庁の気象庁の青木元・地震津波監視課長は16日午前の記者会見で「広域的に続けて地震が発生したケースは近代観測が始まって以降は思い浮かばない」(毎日新聞)。
NHKの報道によると、京都大学防災研究所の西村卓也准教授は、熊本県で起きたマグニチュード7.3の大地震に誘発されて、各地で地震が起きていると分析。
朝日新聞の報道によると、「震源はじわじわと東に移動している」(川崎一朗・京都大名誉教授)、「地震活動が南へ拡大する可能性も忘れてはいけない。注意が必要だ」(遠田晋次・東北大教授)、「長期的には南海トラフ巨大地震に影響を与える可能性があるかもしれない」(平原和朗・京都大教授)という指摘がある。
14日 午後9時26分:震源地 熊本県熊本地方 -
理化学研究所の研究チームが2004〜12年に合成に成功し、日本に初めて命名権が与えられた原子番号113番の新元素について、化学者の国際組織「国際純正・応用化学連合(IUPAC)」は8日、名称案がニホニウム(nihonium)、元素記号案が「Nh」と発表した。
IUPACはインターネットを通じて世界から意見を募った上で、来年夏にも正式決定する。日本由来の元素名が確定すれば、欧米を中心に発展した近代科学史上で初の快挙となり、世界中の化学の教科書に「ニホニウム」の名称が掲載されることになる。
ニホニウムは日本(nihon)と、元素名の末尾につける「ium」を組み合わせたもの。113番元素の命名権を持つ理研仁科加速器研究センター(埼玉県和光市)の森田浩介グループディレクター(59)(九州大教授)らが提案し、IUPACが審査していた。 -
科学というより数式だが…
〈問題〉
ある細菌をビンの中に入れると1秒ごとに倍に増えていく。今、この細菌が増え続け1分39秒で容器がいっぱいになったとする。では、この細菌が容器の半分を満たしたのは何分何秒の時点か。
本問の原案は、実は数十年前に中学受験を控えた受験生のお父様から尋ねられたものだった。答えは、1秒間にこの細菌は2倍に増殖するのだから、この細菌が1分39秒で容器をいっぱいにするのならば、その1秒前の1分38秒に容器の半分に増加しているというものである。なかなかトンチの効いた問題だ。
この記事を読まれた多くの読者の方は、普通に面白がってくれたようだった。ところが、である。記事を出した後、この問題に関して2人の方から私のサイトに連絡があった。「物言い」がついたのだ。
1人は関西方面の大学の教員の方、もう1人は東大の医学部の在学生だった。質問の内容はほぼ同じで、おおむね次の通りだ。
〈連絡内容〉
東洋経済オンラインの記事を読みました。この問題は算数の出題としてはいいかもしれませんが、現実的ではありません。
もし仮に、この細菌を長径が2μm(マイクロメートル)、短径を1μm、高さを1μmの直方体とすると、その体積は2μ㎥になります。この細菌が1個の状態から1分39秒の間分裂し続けると、22μ㎥×2の99乗という値になりますが、これはとてつもない大きさです。単位をk㎥に直して考えても1200 k㎥を超える値で、一般的なビンのような容器のイメージからはほど遠くなります。
優秀な子どもさんなら、「1Lぐらいのビンなら、より短い時間ですぐにいっぱいになってしまうのになあ……」と思うはずです。
■ 直感力・数値感覚が一般人と違う?
いやあ、これにはたまげた。細菌の体積をどう見積もるかにも左右されるが、確かに細かく分析し計算をすると、テーブルの上に置けるビンのような感覚とは程遠い大きさになる。東京ドームの体積が124万㎥(0.00124k㎥)、また体積ではないが、東京都23区の面積が621k㎡だから、1200 k㎥を超える空間はなかなかイメージできないほどの大きさだ。 -