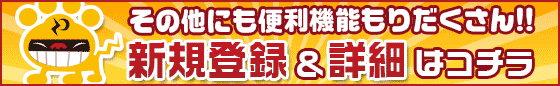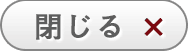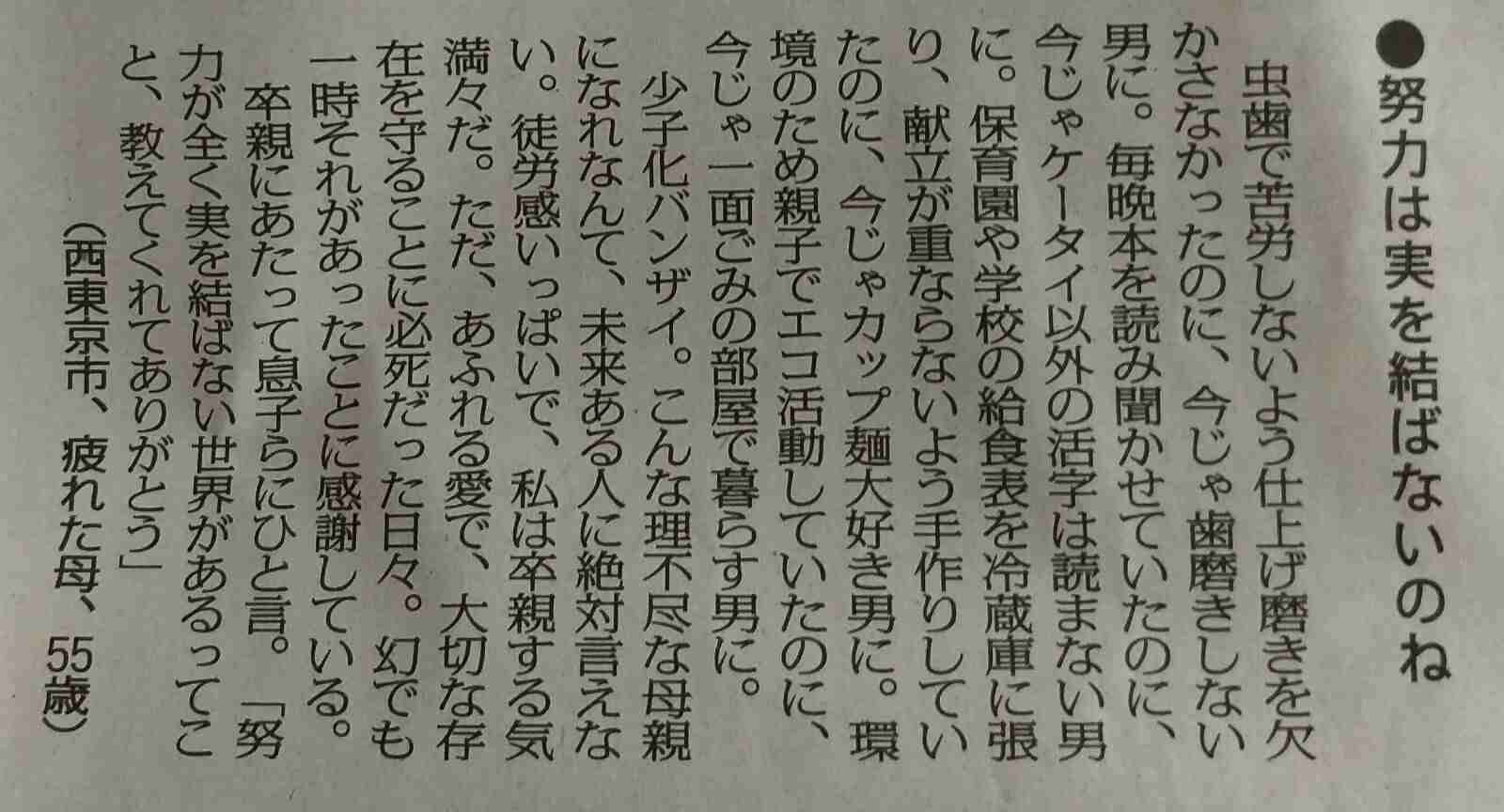�J�I�X�鍑�`���^�[���Y
-
�X���b�h�ꗗ
- �G�k!! (241)
- �������ꌾ!! (814)
- �Ԃ₫!! (459)
- ������ (851)
- �摜!! (451)
- �|�\�X���b�h (1013)
- ����!!!!!!!!!! (985)
- �C�}�W���`�z���͈琬�u���` (256)
- �ʔ��摜(������) (884)
- MUSIC���� (654)
- �k�R�X��(=^�F^=) (688)
- �����C����!!( ; �K�D�K) (471)
- �C������!! (103)
- ���ɂ����I�J���g�n(�G�K�́K) (299)
- (50)
- ���m�� (677)
- �܂�Ƃ��낱�̐l�͔����� (307)
- �� (112)
- JRA (1448)
- The �p�`!!!!!!�`�������́` (457)
- ���ݐH���s��(�L�Ec_�E`) (385)
- (140)
- �T�C�G���X (202)
- �f��!!DVD!!�h���}���X!! (157)
- AV�^�C�g��‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- �����I�����b�X��(ToT) (37)
- (80)
- �܂�Ƃ��낱�̐l�͔����� �{�� (33)
- (654)
- �t���O����!!(^_^)/~~ (39)
- �� (392)
...

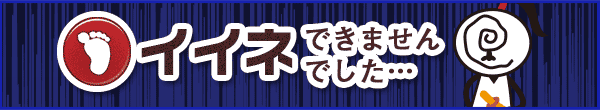
���C�C�l�I�͊e�J�L�R�~�ɑ��A1��̂ݎt���܂��B
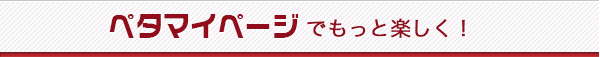
���}�C�y�[�W�ł́A�������u�C�C�l�I�v�������J�L�R�~��ۑ����A�����Ƃ��Č��鎖���ł��܂��B
-
����������Ă���ϑz����
1.�����C��NETFLIX�����Ă��鎞�ɁA�ǂ����̕ώ��҂��E�F�u�J�����Ƀn�b�L���O�����Ă��ē������̎����𓐎B����鋰�|�B
2.�������ɒ����ԍ����Ă�����ɗ����オ��Ƃ��A�����̎q�{�����Ȃ̈�ʂɒe���U�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������|�B
3.�d�ԓ��Ń_�T���Ȃ��Ă���Ƃ��ɒN�ɂ�������Ȃ��悤�ɉ��ʂ������鋰�|�B
4.�E���R�L���g�C���ɓ���A���������������ďo�Ă����̂ɁA����Ⴂ�ɓ����g�C���ɓ������l�ɁA���Ȃ������̃N�\�L���E���R�������ƌ������鋰�|�B
5.�F�N�₩�Ȍ��g�����č��G�����d�Ԃɏ���Ă���Ƃ��A����đO�ɂ�낯�A�����V���c�𒅂��j���ɂԂ���A�ނ̔w���ɃL�X�}�[�N�����Ă��܂������A���̒j���͂���ɋC�Â����ɋA��A�Ȃɕ��C�����Ɛӂ߂��Ă��܂��A2�l�̌���������j�]�����Ă��܂��Ƃ������|�B
6.�V�����[���Ȃ̂ɕςȉ������āA���ɂ��N���������Ă��āA�f��ł悭����悤�ɎE����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������|�B
7.�����̎��Ɏ����̓����ɋC�����A���̐l���������̓����ɋC�����̂ł͂Ƃ������|�B�݂�Ȃ����̐����̓����Ɋ��Â��Ă���Ƃ������|�B
8.���̓����A���Ȃ��̑�������L�����āA���Ȃ��͂������f�G�Ȑl�Ȃ̂ɑ����L���Ȃ�Ďc�O�ˁA�ƉA�Ō����Ă��邱�ƂɋC���������̂́A���Ȃ��̃p�[�g�i�[�͗�V���������Č����Ȃ��������ƂɋC�Â��Ȃ������ƒm�鋰�|�B
9.�Ƃ��o�āA�����Ԍ�ɋΖ���ʼnƂƂ͈Ⴄ�Ɩ��̉��ɍs���ď��߂āu���������Ă���V���c�����S�ɃV�[�X���[���������Ɓv�ɋC�Â����|�B
10.�˕��ɂ������A���K���ی����ɂȂ�Ƃ������|�B
11. �I�[�����Z�b�N�X�����Ă����Ă���Ƃ��ɁA�������˂��ˑR�h������A�����肩�܂킸�f���U�炷�Ƃ������|�B
12. �V�����^���|��������O�ɌÂ��^���|�����o���Y��A���̌���܂��o���Y��āA3�̃^���|�����̓��ɂ���A��������x�����x���̂Ƀ^���|�����M���E�M���E�ɋl�ߍ��܂��܂ŌJ��Ԃ��A�Ƃ������|�B
13.�Z�N�V�[�Ȏʐ^���B��A�����̃X�}�z�̐ݒ��ς��Ă������ƂɋC�����Ȃ��܂B�e�������ׂĂ̎ʐ^�������I��Facebook�ɓ��e���Ă��܂��Ƃ������|�B
14.�r�̃��_�т��������̂́A�����Ȃ��Ƃ���ɑ�ʂ̒��c�������������߁A�r�̗��Ƀ����_���ɒ������_�у]�[�����ł��Ă��邱�Ƃ���C�����Ȃ��Ƃ������|�B
15.�O�ł������������Ă���ƁA�A�����A�\�R�ɔ����オ���Ă���Ƃ������|�B
16.�C�ʼnj���ł���ƓˑR�������n�܂�A�Q�����T���̌Q������т��Ă��܂��Ƃ������|�B
17.���y���Ȃ���d�Ԃɏ���Ă��ēˑR�A����܂ł����ƋC�����Ȃ��܂܉̂ɍ��킹�ĉ̂��Ă���������Ȃ��Ƃ������|�B
18.��\�N�Ԃ������g�p�������Ă������̕ێ��܂��A���ɓŐ����������킶��Ƃ��Ȃ���I��ł���Ƃ������|�B
19.�N���ɃA�\�R���r�߂Ă�����Ă����������b�N�X���Ă���Ƃ��Ɍ���Ă��Ȃ�����Ă��܂����|�B
20.���邢�́A�I�[�K�Y���̎h�����������ăE���R��R�炵�Ă��܂����|�B -
�j�����猩�������̗��z�̑̌^���āH
�����̖\���\�H�̃c�P�Ƃ��đ̏d�̑������C�ɂȂ鎞���ł���B���ɏ����ɂƂ��đ̌^�͔Y�݂̎�B��ɑ����Ȃ���I�@�Ǝv���Ă�������������낤�B�������A�{���ɑ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��낤���H
�u�����āIgoo�v�ɂ́A��������u�j���������ɋ��߂闝�z�̑̌^���Ăǂꂭ�炢�ł����H�v�Ƃ������₪���Ă����B����҂���̐g����163cm�ŁA�X���[�T�C�Y���o�X�g85cm�A�E�G�X�g63cm�A�q�b�v91cm�A�̏d��50�s�Ƃ̂��ƂŁA����قǑ����Ă���悤�Ȑ��l�ɂ͎v���Ȃ��̂����A����ɑ��ďW�܂������Љ�悤�B
�������������͕W���̌^�̕��������Ƃ����ӌ�������
�u�������ۂ������ł����A�j�����D�ނ̂͂������ۂ������ł���I�v�igagagagagagagav����j
�u���z�̑̌^�Ƃ����̂͌l�������ɑ������̂œ���ł���ˁB�����ڂŔ��f����Ȃ�ׂ߂̐l���D���Ȑl�������C�����܂����A�ꏏ�ɂ������̂́A�����ۂ������n���Ǝv���܂��B����җl�̑̌^�͔��Ƀ��e��̌^���Ǝv���܂��v�idekaguma����j
�u�j���͏������t���̗ǂ����炢�̑̌^���D�݂܂��ˁB���f���̂悤�ɑ����Ă���̂͂����܂ŋ��߂��Ă��܂���v�izacoin����j
�ƁA�ނ��돭���ۂ�����肵�Ă��邮�炢�̕������͓I���Ƃ���ӌ��������ڂɂ����B�ɒ[�ɑ�����������g������A�e�ߊ�����������̂�������Ȃ��B���ʁA�����������������������̂ł́H�@�Ƃ����ӌ����������B
�u���߂�̌^�͐l���ꂼ��ł�������߂��ł��ˁB�����������ǂ��ł��傤�B�����ł킩���Ă��Ċ��w�E���ꂽ�Ȃ�s�����܂��傤�v�ionihei55����j
�u�E�G�X�g�͏����i�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B���z�́A���������ۂ������ł��ˁv�irain773����j
�������Ă݂�Ȃ̈ӌ��𑍍����Ă݂�ƁA����҂���̑̌^�͏��������E�G�X�g���ۂ������C���Ƃ������ƂɂȂ肻�������A���ɋC�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����ӌ����قƂ�ǂ������B
�u�j���͏������v���Ă���قǑ����Ă���q���D���Ȑl�͏��Ȃ��Ǝv���܂���B��͂�W���̌^���P�Ԃ��Ǝv���܂��v�itetsuoakira����j
�Ƃ����ӌ��ɑ�\�����悤�ɁA�j���͂�����Ƒ������̌^�̏��������߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B�f�[�g�����Ă��ĐH�ו��ɋC����������́A�ꏏ�ɔ����������ɂ��т�H�ׂĂ���鑊��̕����D�����͂����B
���������ɁA�Ƃ͂������N���ێ����邽�߂ɂ����������H�߂��ɋC�����Ȃ���A���邭�y���������Ă��������Ɩ��͓I�ȏ����ɂȂ��͂��I -
�u���p�U�̂Lj��v���h�[�s���O�w��H�@������F�ɂ��f�}���L����
�@1��1�����h�[�s���O�Ɋւ���֎~�\���ۊ���ύX�ƂȂ�A�X�|�[�c�I��́u��V�v���܂ނ̂Lj��̕��p���ł��Ȃ��Ȃ�܂����B�Ƃ��낪�A�u��V�v����؊܂܂Ȃ��u���p�U�̂Lj��v���h�[�s���O�w�肳�ꂽ�Ƃ���f�}���g�U���ł��B
�@���{�싅����h�[�s���O�R���g���[���ψ���͍�N�i2016�N�j12��28���A1��1�����V���Ƀh�[�s���O�����Ɏw�肳���֎~�����Ɋւ��Ē��ӊ��N�̂��߂̏�M���s���܂����B����ɂ��ƁA�u�q�Q�i�~���v���܂܂��u��V�v����̂̂Lj��͎g�p�֎~�ɁB�Ƃ��낪���̏������āA�u���p�U�̂Lj��v�ɓ�V���܂܂��Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����l��SNS�ɓ��e�B����͏u���ԂɍL����A���܂Ƃ߃u���O�Ȃǂł��L��������鎖�ԂɁB
�@�q�P゙�i�~���͓�V�ȊO�ł̓R゙�V����(�����)�A�t゙�V(���q)�A �T�C�V��(�אh)�A�`���E�V゙(���q)�ɂ��܂܂�܂����A�u���p�U�̂Lj��v�̐����ɂ����͂ǂ�������Ă��܂���B
�@���p�U�͂˂Ƃ�ڂ̎�ނɑ��A�u���p�U�̂Lj��v�ɂ̓q�Q�i�~���͈�؊܂܂�Ă��Ȃ����߃h�[�s���O�ɂ͓����炸�A�܂��A�u���p�U���̔�����̂Lj����i�Ƀq�Q�i�~�����܂ނ��̂�1���Ȃ��v�ƃR�����g���Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�u��c���v�̓G�t�F�h�����i�����j�Ƃ����֎~�������܂ނ��߁A�ȑO����I��̕��p�͕s�ƂȂ��Ă��܂����B
�y�NjL1�z13��15��
�@���p�U�������Ɂg�u�q�Q�i�~���v�͈�؊܂܂�Ă��Ȃ��h�Ƃ��郊���[�X���o���܂����B
�y�NjL2�z17��06��
�@�����L�����Łu���p�U���̔����鐻�i�Ƀq�Q�i�~�����܂ނ��̂�1���Ȃ��v�ƋL�ڂ��Ă��܂������A���p�U����u�w���p�U���[�@���J�v�Z���x�ɂ����܂܂�Ă������Ƃ����������v�ƘA�������������߁A�\�����C�����܂����B
-
�g�����v�����2017�N�����J���F�x�����ׂ�7�̃g�s�b�N�X
�đ哝�̑I�Ńg�����v���������Ă���Ƃ������́A���a�}�́A�S��1640���l�����b�����Õی����x���A�����I�ɖ����̂Ȃ��őP�̕��@�Ŕp�~�ɒǂ��������ƁA�n�����d�˂Ă���B�R�������ϐ��̋��͉��A�h�炮���@�A�f�Ր푈�A�����ĊO��ʂł̐푈�B�l�X�Ȗ�������Ȃ���A��X��2017�N���}�����̂��B
�哝�̑I�����̃I�o�}�哝�̍Ō�̃C���^�����[�F�g�����v�̏����A���ꂩ��̎���
2016�N�͎U�X��1�N�������B�����ׂ��X�s�[�h�Œn�����g�����i��ł���B����܂łɖ�50���l�����𗎂Ƃ����V���A�̓���͌������𑝂��Ă���B�S�Ăŕp������e�������͎��܂邱�ƂȂ��A2016�N��12��29���܂ł�1��4748�l���]���ƂȂ����B�����čL�������ꂽ�X�^�[�������������ŖS���Ȃ����B�܂�������Ƃ��哝�̂ɏA�C���邱�Ƃ��Ȃ��悤�l����ꂽ�͂��̗�����`�I���J�j�Y�����A���̒j�̏������Ă��܂����B
��X�ɂƂ��ėǂ��j���[�X�́A2016�N���I������A�Ƃ������Ƃ��B
�����Ĉ����j���[�X�ƌ����A2017�N�������ƌ��ȔN�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ��B
��ǓI�Șb�ł͂Ȃ����A�A�����J�̐l�X���҂���x�����ׂ��j���[�X�������Ă݂悤�B
1.�����Ƃ̖f�Ր푈
�哝�̑I���Ԓ��A�h�i���h�E�g�����v�͒�������̗A���i��45���̊ł�������Ǝ咣���Ă����B�����A���a�}�̑哝�̌��̍��𑈂��Ă����e�b�h�E�N���[�Y�́A�A�����J�̏���҂��A���ň����グ�ɂ���āA�����㏸�ŋꂵ�ނ��ƂɂȂ�Ǝw�E���Ă����B�ň����グ�̋��������̂܂��s����A�̔����i649�h����iPhone7�́A2017�N��941�h���ɒl�オ�肷��B�����Ă���́A�������V�F�A��7�����߂�g�ѓd�b�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��B�G�A�R���i�������V�F�A8���j����C�i�������V�F�A6���j�܂ŁA��������̂����������B
2.�����Ƃ̊O��ʂł̐푈
�Ռ��̏������琔�T�Ԍ�A�g�����v�����哝�̂́A��p����p���������瓖�I���j���d�b�����B���̓d�b��k�ɒ������͓��h�����B�Ē��Ԃɂ����ẮA��p��Ɨ����Ƃ��ĔF�߂Ȃ��Ƃ����̂��A����܂Œ����ԕۂ���Ă����F���������B�����`������̎����哝�̂́A������W�[���Ӗ��������Ȃ��˔��I�ȏo�����W�Ƃ��Ď��������i���̂Ƃ���A�N�V�f���g�ł͂Ȃ��j�A�\�����ʂ��Ƃ������Ƃ͌����A�Ē��Ԃ̐푈���N���蓾��Ƃ�����Ƃ��S�z����ʂ�̂��Ƃ��N���Ă���̂��B2016�N�Ăɔ��\���ꂽ�����h��������116�y�[�W�ɂ킽��_���ɂ��ƁA�Ē��o���͐搧�U����U���Ă���A��F�ɂ���Ă����炳��鋺�Ђ��A����I�Ȏ����̘A���������N�����\��������Ƃ����B
3.�h�炮���@
�ێ�w�͉������ׂāA���@�Ɋ�Â�������������Ǝ��̂�����̂����A��n�߂ɘA�M���{�x�o�̏�����K�肵�A�ō��ٔ����ƘA�M�c��c���̔C���𐧌�����Ƃ����C���Ă���Ă����x���A�Z�`���[���Y�A��f���B�b�h�̃R�[�N�Z��̂悤�ɁA���@�����̕K�v��i����ێ�w������B�������A���@���C��������@��2�����Ȃ��B���@��3����2���K�v�ƔF�߂��ꍇ�A��������3����2�̏B�̗��@���i�܂�34�B�j�����������ꍇ�ɁA�����Ɍ��������@��c�����W�����B����1���ɂ�33�̏B�c������a�}�������邱�ƂɂȂ�B����܂�28�̏B���A���@��c�̏��W��₤���c���������B2017�N�ɂ̓��@�[�W�j�A�B�ƃj���[�W���[�W�[�B�őI�����s����B���_��́A���@�C���̔��c����]���鋤�a�}���K�v�Ƃ���[�������邱�ƂɂȂ�B
4.�̎��R�ɑ���V���ȋ���
�哝�̑I�̑S���Ԃ�ʂ��A�g�����v�w�c�́A�s���ȓ��e�������ǂ̃u���b�N���X�g����葱���A�w�肳�ꂽ�����ǂ̋L�҂��g�����v�w�c�̃C�x���g������ߏo�����B�Q���������ꂽ�L�҂͎d��̒��ɓ�����A����̏ォ��A�������̓g�����v���炯��������ꂽ���̎x���҂�������l�|�A�������͈Њd���ꂽ�B�����哝�̎�ȕ⍲���A���C���X�E�v���[�o�X���Ɋւ��郋�[���𑁋}���W�����W����Ɣ��\�������A�W�҂ɋْ����������B
�����Ď�ވȏ�ɐS�z�Ȃ��Ƃ�����B�I�����Ԓ��A�g�����v�͗T���Ȏ��͎҂������ƊȒP�ɕ@�ւ�i������悤�ɁA���_�����@���u��������v�Ƌ����Ă����B�܂�Ȃ��ٔ��𗧂đ����ɋN�����A�����Ɏ��Ƃ��g�債�Ă����j���[�X�z�M��Ђ�g�D�I�ɒׂ����@�ɂ��ăA�h�o�C�X���~�����̂��Ƃ�����A2016�N�̔N���ɃI�����C�����f�B�A���Gawker Media�i�S�[�J�[�E���f�B�A�j��j�Y�����邽�߂Ɏ����𓊓������A�����ڍs�`�[���̈���A�s�[�^�[�E�V�[���ɕ����Ηǂ��B�g�����v�͂�����^�C�~���O�ŁA���̉e���͂��ێ����邽�߂ɁA�V�[�����ō��قɑ��荞�ނ��Ƃ��ł���B�g�����v����������Ɖ\����Ă��邪�A2�l�͂����ے肵�Ă���B
2016�N�A��C���̓�_���Y�f�iCO2�j�Z�x���A�e�B�b�s���O�|�C���g�i�ՊE�_�j�Ƃ�����400ppm�����B
5.�C��ϓ��̉e������w�[����
2016�N10���A��C���̓�_���Y�f�iCO2�j�Z�x���A400ppm�����B������e�B�b�s���O�|�C���g�i�ՊE�_�j���B���̐��l����Ɖ��g���̉����Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ȃ�ƁA�Ȋw�҂��i�������Ă����傫�ȓ]���_���B��̏����A�X�єj��A�C�ʂ̏㏸�A�C�����̏㏸�A�\���J�̌����A�ߋ��ɗ�̂Ȃ����a�̔����A�푈�̖u���Ȃǂ̖�肪�����炳���Ƃ����B
6.�R�������ϐ��̕ω�
�p�j���[�E�T�C�G���e�B�X�g���iNew Scientist�j�̘_���ɂ��ƁA2017�N�͍R�������̗}����p�Ɋւ��A�傫�ȓ]���_�ƂȂ�Ƃ����B�܂�A�H�����A�A�����ۈ������A�x���Ȃǂ������Ŏ��S����l���o�Ă���Ƃ������Ƃ��B
7.�I�o�}�P�A�i��Ô�S�K�����@�j�̓P�p
�R�������̌��E�������Ă��鎞�ɁA�A�M�c��ƁA���������z���C�g�n�E�X���肷�鋤�a�}���́A�S�Ă�1640���l�̎҂������Õی����x���A�����I�ɖ����̂Ȃ��őP�̕��@�Ŕp�~�ɒǂ��������ƁA�n�����d�˂Ă���B���a�}�͂��ꂾ���ɂƂǂ܂炸�i���a�}���������߂�A�M�c����j�A�č��Ƒ��v��A���iPPFA�j�ɑ���o���ł��������ɓ���Ă���B�S�Ă�240���l����ÃT�[�r�X���Ă���v���O�������B
8.�j�푈
���E���j�Ɋւ��Ďv�����ʂ��킫�܂���܂ŁA�č��͊j�\�͂�啝�ɋ����E�g�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
-
�V�����̘b��ŏ��a���܂ꂪ�����@�u�����̊ԂɌ����ł��Ȃ��\���v�u�������C�_�[�������I���v
�@���{���A�V�c�É��̏��ʂ̊�]�������A����31�N�i2019�N�j1��1���ɍc���q�l�̓V�c���ʂ��s�������Ō����ɓ��������Ƃ�����Ă��܂��B
�����a���܂�u�����̊ԂɌ����ł��Ȃ��\���c�c�v
�@�V�c�É��̏��ʂɂ������ẮA�c���q�l�̓V�c���ʂ���сu�V�����v�̒a�����Ӗ����܂��B�V�c�É��͑���30�N��ߖڂɏ��ʂ���]����A���肷��Ε���31�N1��1�����V�����̃X�^�[�g�ƂȂ錩���݂ł����A�V�����̒a���ɂ�菺�a���܂�̐l�B����͎v���v���̐����l�b�g�ɏグ���Ă��܂����B
�E��艻�Έ��������̂�
�E���܂ŏ��a���܂�ƕ������ɍ����i��������Ă������ǁA����ɂ͂��ǂ肻��
�E���a���܂�ŕ����̊ԂɌ����ł��Ȃ��\���c�c
�E�������܂������������������鎞��ɂȂ�̂�
�E�������C�_�[�V���[�Y�������I��肩�@���a���C�_�[����̃t�@���Ƃ��Ă͊��S�[��
�@���˂Ă�菺�a���܂�́A�l�^�I�ɕ������܂�̐l�B����u�������E���v�������ꂽ��A�܂�ŌÂ����̂̂悤�Ɉ����Ă�������������܂��B���̂��߁A�����ɂ��u���O����l�̂��Ə��Ă�ꍇ����Ȃ����v�Ƃ������͋C�����a���܂�̊ԂɕY���A�����Ɂu�Â����̓x�v������ɐi�����Łu���a���܂ꊴ�o�̖����E�吳���܂�ɂȂ邾���v�Ƃ�����C���Y���Ă��܂����B
���Ƃ͂������a��64�N�܂ł���������ˁI
�@�Ƃ͂����Ă�������30�N�A�����a��64�N�܂łƔ{�ȏ�B�ł������قǏ��a���܂�S�����S���u�������E���v�����Ă���Ƃ�����ł͂���܂���B���a64�N�ł��蕽�����N�ƂȂ�1989�N���܂�̐l�Ȃ�A2017�N��28�B�܂��܂��s�b�`�s�`�̃����O�ȕ��ނɓ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�ŋ߂ł͏��a64�N��1�T�Ԃ����Ȃ��������߂��u���̏��a64�N�I�v�u�Ռ�!���a�ɂ�64�N���������I�v�Ȃǂƃl�b�g�œs�s�`���I�Ɉ����A����ɏ��a���܂������ΏۂƂ��邱�Ƃ��u���a��v�ƕ\�����邱�Ƃ܂ł��邻���ł����c�c�B�܂��A�C�͎����悤���Ǝv���܂��B�C�x�߂�������܂��B�i�����ځj
-
�̗͂��Ȃ��B���Ղ������Ȃ��B���N�H�i�ɂ����ɐH�����B�|�\�l�̖��O���킩�炸�A�A���A�\���A�R���̘A���B�́A�ꂪ�����Ă������Ƃ́A���������̎��̕�̔N��ɋ߂Â����Ƃ��A���g�ɂ��݂Ă�[���킩��܂����B
�a�a�r�ɂ��A�N������ď��߂Ă킩�������Ƃ̐��X�����Ă��܂��B�݂Ȃ���ɂ͓��Ă͂܂邱�Ƃ�����܂����H
�����C�Ȃ��������K���X�B�f�������������������I
�C�����͎Ⴂ���ƕς��Ȃ��̂ł��B����ǁA�ӂƑ��K���X�ɉf���������̎p�ɃM���b�Ƃ����I�@�����A�I�o�T���ɂȂ����̂ˁc�c�ƒɊ��B
�w�����A������Ȃ̂ɁA�����ł��킩���Ă�̂Ɋw���̎��̋C�����ł���B���`���낵���B
�ӂƁA�o��ŃK���X�ɂ����������ɋ����āA�V�����ȂƁB
�l�Ԗ{���ɗ��Ă��ˁx
�w�C�����͕ς���ĂȂ����ǁA���ۂ͂����̂�����ȂȂƁA�O�o��̑��ɂ��鎩���̎p�ŒɊ�����B
���e���̋��Ȃ�ċ��|�ł����Ȃ��x
�������ʂ�A���g�ɐ��݂�g�̕�
�̂͂ǂ�ȂɓO�邵�Ă����C�������̂ɁA��������܂����̗͂���Ȃ��B���h����̂����ނ������Ղ��N�P�ʂłȂ��Ȃ������Ȃ��B�g�̂Ɋւ��Ă����ɂ�������̂��邠�邪���܂����B
�w�Q�������̗͂��s���s���ɂȂ�܂����B�N���T���Ă��������x
�w�N���Ă���̑�ꐺ���u���[�A��ꂽ�B�v�B
�o�C�o�C���đ傫���r��U��Ə�r���r�b�N�����邭�炢�h���B
���������Ĕ������Ƃ������ǁA�������������Ĕ�������n�Q��Ǝv�����|�x
�w30�����Ă���A�肪�������ăX�[�p�[�̃r�j�[���܂��{���ɊJ���Ȃ��Ȃ����B
�������Ƀc�o������͂��Ȃ����ǁA�����Ⴄ�l�̋C�������킩���Ă��܂��������̂���x
�w�C�͂łǂ��ɂ��Ȃ����Ȃ��ƌ�����x
�w���K���l�p���Ȃ��Ă���B���Ă������ɂȂ�x
�w�`�B
���[�O���g�B
���āB
�}�k�J�n�j�[�B
�̂ɗǂ��炵���ƕ����Ƃ����ɐH�����x
�w�m��Ȃ������ɃA�U���ł��Ă�x
�w�ЂƂ茾���ł����x
�w�i���̂Ȃ����ł܂����x
�w�N�����ɂ�Ċ����ɏ��ĂȂ��ƒm�炳�ꂽ�x
�w�����������ł�B���̍��ɂ͖߂�Ȃ��x
�w���̖у����O�́A�������B���������h���D��x
�w�������߂Ɋ����ƂقƂ���o�o�A���x
�w���N�̕���������Ȃ��Ȃ�B
�Ȃ̂ň������������V�[�Y�����Ƃɔ����ւ���x
���܂��܂�����I�@�L����
�����̂��ꂳ��Ɂu����I�@�������̂��̐l���A�������Ă����Ȃ̂�v�Ȃǂƌ����A����Ղ�Ղ����肵�����Ƃ�����܂����B���ꂪ����䂪�g�ɍ~�肩����Ƃ́c�c�B���Ɍ|�\�l�̖��O��h���}�̃^�C�g�����{���ɏo�Ă��Ȃ���ł��I
�w�|�\�l�̖��O���o�Ă��Ȃ��B�̂̓X���X���������̂ɁB��͕����Ԃ̂ɂˁ`�x
�w�u���̔ԑg�A���̃h���}�ɏo�Ă��A���̏��D�͒N�������H�v�ƕ����ă{�P���n�܂����Ɗ�����x
�w�|�\�E�̎Ⴂ�q���݁[��ȓ����Ɍ�����B
�W���j�[�Y��AKB�A�T�؍�Ȃ�ĒN���N�����A���������킩��Ȃ��x
�w�D���ȃA�[�e�B�X�g��o�D����A���D����̖��O����͂킩��̂ɖ��O���o�Ă����u����A����I�@���̂Ȃ��̃h���}�ɏo�Ă��l�I�v�Ƃ��A�u���̃o���h���̂��Ă����̋ȁI�v�ȁ[��̃q���g�ɂ��Ȃ炸�������悤���Ȃ��Ƃ��x
�w�|�\�l�����킢��������x
�w���̂��g�ɂ��݂�x
�Ⴂ���ɂ͑S���킩��Ȃ������A�����Ȃ��ƁB�N�X�u���[�A���̎��̕�͂���Ȋ����������Ȃ��v�Ǝ������邱�Ƃ������Ă��܂��B�ł��A�����Ȃ��Ō��C�ɖ��邭�߂������I�@�������悤�B -
5�l��1�l�u��N�̓��o�C�v�@����Q�ɉ��P�ʂ̑��Q���c
�l�̗��j�̂Ȃ��ł��u��N�v�́A���̂�a�C�A�ƒ����Љ�I���ɂ����čЂ����N����₷�������Ƃ��Ċ��ݐT�܂�Ă���B
��������Ɋ��ɑ��݂��Ă����Ƃ���邱�̕��K���A���M���Ɗ�����l�����邾�낤�B
����ő����̐_�Е��t�����̔N���ƂɁu����v��u����v�F������{���Ă���A�������M���Ă���l���B
����萔���u��N���o�������v
����ׂ��ҏW���ł͑S��20��`60��̒j��1365����ΏۂɁu��N�̈З͂����������Ƃ����邩�H�v���������{�B
���̌��ʁA��5�l�ɂЂƂ肪�uYES�v�Ɖ��錋�ʂɁB
2017�N�ɖ{����}����l�́A�j���������N��25�A42�A61�A������19�A33�A37�B�i�ߔN�͏���61�˂��j�����ʂŖ�N�Ƃ���ꍇ������j
�����܂ʼnȊw�I�����Ɋ�Â������K�ł͂Ȃ����A��萔�A��N���}�����ۂɕs�^�������Ă���悤���B
�����P�ʂ̑����ɋ�...�����킸���
�ҏW���ł́A���N�O�Ɂu��N�З́v���o�������Ƃ��������ɘb�����B
�u33�̑��Ƃ���鎞���ɁA�Ƒ��Ԃő�����肪�����B����Ɏd����̃g���u���A����Q��3�A���̃p���`��H�炢�܂����B
���Ӑ悪�|�Y���ĕs�n��͔�炸�ɍς��ǁA���P�ʂ̔��グ���Ȃ��Ȃ�����A���ɓ����p�\�R���ƌ��������܂��...�B
������Ȃ�������ӂ��ĉ߂��������Ȃ������ł��ˁB��N���������邩�͂��ꂼ�ꂾ�Ǝv���܂����A���͈�ԃV���h�������Əd�Ȃ����̂ňЗ͂������܂����v
�Г������ʂ��苭������邪�A�u��N�v�͐l���̐ߖڂ�������ʉߋV��ł���u�Ȃ�U��Ԃ���̖͂��ɗ��N��ɒB�����v�ƍl�����������Ƃ����B
�l���̃T�C�N���͐l���ꂼ��B���ꂩ��}����l�͎Q�l�ɂ��Ăق����B
���݂ɉ����n���̗l�Ȗ�N�p�����corz -
�u���@�v�܂łP�N�҂��I�H�g�ʂ�����ݕa�@�h�|�u��p�v�u�����v������P�A�A���ԉ���Ă��č�������l��
�@�u�q���̍����炸���ƈꏏ�v�u��Ȑl�����������v�Ȃǎv������̂���ʂ�����݂́A�܂��Ɂu�Ƒ��v���̂��́B�������A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA������ŁA�j���āA�{���{���ɂȂ��āc�B�N���[�j���O�X�ւ��肢����̂��������A�u�Ȃ�ƂȂ��s���c�v�Ǝv���Ă���l�������B�����ŁA�ʂ�����݂��g���m�h�Ƃ��Ăł͂Ȃ��g���ҁh�Ƃ��Ď����u�ʂ�����ݕa�@�v���o��B���@�\�����݂��E�����Ă���A���݂P�N�҂��̏�Ԃ��Ƃ����B�i���R�݂ǂ�j
���Ȃ��̖Ȃ̓���ς��@���������K���̍Đ����I�H
�@���{�L���s�ɂ���u�ʂ�������N�@�l���ӂ��Ӊ�@�ʂ�����ݕa�@�v��K�ꂽ�B�ʂ�ɖʂ����傫�ȑ�����́A��������̂ʂ�����݂��ʂ�l�߂Ă���B�a�@�̑ҍ��X�y�[�X�ɂ͎��Â��I���A�g���C�ɂȂ������ҁh�炪�֎q�ɕ���ł����B�܂�ŁA�A���S�҂��ɂ��Ă���悤���B
�@���@����މ@�܂ł́A���a�@�̃z�[���y�[�W�́A�i�P�j�u�\�����݃y�[�W�v�Ɋ��҂̎�ށE�T�C�Y�E�����܂��ȏǏ�ȂǁA�K�v�������L���i�Q�j���Ԃ�������A��f�[�Ɛ�p�̗\��y�[�W�����[���ňē�����A���@����\��i�R�j���@�i���@���Ԃ͊�{�I�ɂW�`�Q�O�������A�Ǐ�ɂ�蒷���ɂȂ�ꍇ���j�i�S�j�������Â��I���މ@�ց|�Ƃ�������ɂȂ��Ă���B
�@�X�^���_�[�h�ȓ��@��p�͂W��~����i�ʂ�����݂̃T�C�Y�ɂ���ĈقȂ�j�B���Ȃ��̌Â��Ȃ̓���ւ���A�畆�����ꂢ�ɗD�����Ƃ������e���B�ӂ��ӂ��̃x�b�h�ŐQ�āA�g�h�N�^�[�h�̐f�@��g�i�[�X�h�̊ŕa�Ȃǎ�����P�A������B
�@�I�v�V�����i�lj������j�ŁA���⌊�����̖D���A��A���A�K���Ȃǂ̂��Ȃ����A�h�J�i�����イ�j�ɂ��Đ��A�A�сB�܂��A��ʁE�g�̂̂䂪�����⑫�̂��ڂ݁A�@�A���Ȃǂ̍Đ��B��A���A�K���Ȃǂ̌����Đ��ȂǁA�u�\�Ȍ���Ή��ł���c�v�Ɠ��a�@���^�c����x�����݂�����������B
�ʂ�����ݔ̔�����q�̐��Ŏn�߂��u�a�@�v
�@�U�N�O�A�ʂ�����݂̔̔����n�߂��B�ʂ�����݂��w�������q�炩��A�u���ꂢ�ɂ��Ă�����������ǁA�厖�Ɉ����Ă���邩�s���v��u�N���[�j���O�X�ɗa����ƁA��₵���v�������Ă����Ȃ�������v�Ȃǂ̔Y�݂̑��k�������Ă����B�x������́A�u���q���܂ɂƂ��Ăʂ�����݂͉Ƒ����̂��́B�ʂ�����݂̕a�@�Ȃ�Έ��S���Ă��炦��v�ƍl���A���烁���e�i���X�𐿂��������Ƃɂ����B
�@����ł͂Ȃ��u�����C�v�A�C���ł͂Ȃ��u��p�v�c�B�����܂Ń��m�ł͂Ȃ��u���ҁv�Ƃ��Ď����Ԑ��͓O�ꂵ�Ă���B��f�[�A�f�@�A��p�A�G�X�e�܂ŁA�l�Ԃ⓮���a�@���Ȃ���̑Ή������ł͂Ȃ��A�u���@���Ă���ԁA�ʂ�����݂��S�z�B���g�����݂����v�Ƃ����l�̂��߂̑Ή����l�����B
�@���@���̎ʐ^��������Ƒ���p�̃y�[�W�����A�����łǂ�ȕ��ɓ��@�����𑗂��Ă��邩�̊m�F��A�i�[�X�֎��ÂɊւ��Ă̎�����ł���B�u���@���̊��҂��܂��A���A���҂��Ƒ������S���Ă��������܂��v�Ɩx������B�܂��A�މ@���ɂ́A���@���̂ʂ�����݂��B�e�����ʐ^���������b�c���n�����B
�u�ʂ�����݂͉Ƒ��v�C�����Ɋ��Y��
�@�ʂ�����ݕa�@�́A�����Q�U�N�W���ɃX�^�[�g�����B�����͂P���ɂP�`�Q���̖₢���킹���������������A��N�R���Ƀl�b�g�j���[�X�Ŏ��グ���A�S��������@�\�����݂��E�������B�u������̕�������Ȃɑ��������Ǝ������Ă��܂��v�Ɩx������B�u���Ԃ�����Ă��āA�悩�����v�Ɠd�b���ō������ꂽ���Ƃ����邻�����B�u�h�N�^�[��x�b�h���Ɍ��肪����̂Łc�B���҂������Đ\����Ȃ��ł��v
�@�ʂ�����݂̉Ƒ��i������j�̑w�͕��L���B�q���������̂��Ǝv������v�w��J�b�v�����͂��߁A�R�O�`�S�O�Α�̃r�W�l�X�}���i�E�[�}���j�������Ƃ����B�u�C�O�o���ɂ��K���A��čs���Ƃ����j������������Ⴂ�܂����B�w���������̂Ȃ����݁A�����̂��́x�Ƃ������������ƂĂ�������ł��v�Ɩx������B
����ɏ[�������P�A��ڎw���ĕ�����
�@���݁A����̐����ł���悤�Ɍ������Ă���Ƃ����B�ʂ�����݂̔���p�ɊJ�����ꂽ�I���W�i���̃V�����v�[�Ȃǂł₳�������J�ɐB���Ȃ��ɋl�߂�Ȃ͓��{���̍��i���̂��̂��g�p����B�x������́u�����Ƃ����Ƃ����f�ނ�T���āA�[�����Ȃ���ΊJ�����܂��I�v�Ɩڂ��P������B
�@�S���ł������Ȃ��ʂ�����ݕa�@�B�u�i�����Ƃ��āj�����Ƃ���ɖڂ������˂Ƃ����܂����A����Ȃ��Ƃ��l�������Ƃ���܂���ł����B�����ł��菕���ł���Ƃ����v���Ŏn�߂܂����v�Ɩx������B
�@�����̂ʂ��邮�݂Ɉ��������l�́A�u�����ւ��v�Ƃ����T�O�͂Ȃ��B�l�̋C�����Ɋ��Y���u�ʂ�����ݕa�@�v�̑��݂͑傫���B -
�u���l��3���ŖO����A�u�X��3���Ŋ����v�B�c�悭�������̌��t�A�܂���l�ƕt���������茋�������肷��̂������ł͂Ȃ��I�@�Ƃ����Ӗ��炵���B���ʂɍl����A���l�ƕt����������O����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł́A�Ǝv���Ă��܂����A���̌��t�̐^�ӂ͂ǂ��ɂ���̂��낤���H
�܂��́A�Ɛg��20�`30��j����Ј�200�l�i���l���������Ƃ�����j��ΏۂƂ����A���P�[�g�������s�����I�iR25���ׁ^���́F�A�C���T�[�`�j
�q���l�ƌ����Ă��鏗���ƕt�����������Ƃ�����H�r
�E�͂��@80�l
�E�������@120�l
�q�u���l�v�Ƃ̌��ۊ��Ԃ́A���̐l�Ɣ�ׂĒ��������H�@�Z�������H�r
���O��Łu�͂��v�Ɠ��������̂݉�
�E���������i�����t����������j�@40�l
�E�Z�������@40�l
�u�O���v������Ȃ���l�Ƃ̌��ۊ��Ԃ͒Z���Ȃ�͂��ł́c�Ǝv������A���ʂ͂��ꂢ�ɂ܂��Ղ��B���l�Ƃ̌��ۂ��u���������v�Ƃ����l����́u�����������������v�i25�j�A�u�����ڂ͖��ł͂Ȃ��v�i29�j�ƁA�r�W���A���̗ǂ������́A�t�������̒����ɊW���Ȃ��Ƃ����ӌ�����ꂽ�B����A���l�Ƃ̌��ۂ��u�Z�������v�Ɠ������l����́u�S�z���Ƃ������Ĕ�ꂽ����v�i39�j�A�u�{�l�����l���Ǝ��o���Ă���̂ŁA�i�s�����Ȃǁj����ē�����O�i�Ȋ����j�����ɋ��������v�i34�j�Ƃ����ӌ��������ꂽ�B
�ł́A�Ȃ��u���l��3���ŖO����A�u�X��3���Ŋ����v�ƌ�����悤�ɂȂ����̂��H�@�j���̗����ςɏڂ����A�����Ɂw�u���C�Ƃ͌ߑO4���̐ԐM���v�ł���B�x����������Ƃ̂�����B���́A�u�j���o���̎v�f�������Đ��܂ꂽ�s�s�`���Ȃ̂ł́v�ƌ�����B
�u�ЂƂ́A���l�𗎂Ƃ��Ȃ������j�̌�����ł��傤�B�A���P�[�g���ʂ����Ă��A�w���l�ɖO���ĕʂꂽ�x�Ȃ�Đl�͂��܂���B����A�w���l����Ȃ��������L�߂��x��������Ǝv���܂��B�w�l�ނ́A�j�������l�ɌQ�����Č��������Ƃ��A�����������h�����Ƃ��邱�Ƃɂ���Č��ꂪ���B�����x�ƍl���Ă��铮���w�҂�����قǁA���Â��珗�����m�̈�˒[��c�I�ȃl�b�g���[�N�͂����������B���̂Ȃ�����w���l�͂ǂ����O��������߂Ă����Ȃ����x�Ƃ����A�j���Ɍ������\���L�߂�ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
�l�ނ̐i���ɂ��W���Ă���!?�@���R���Ŕ��l�ɂ���C������Ă���j�����N�B���l����Ȃ���������̃`�[���U���ɑ��ẮA���ꂮ����^�U���悭�m���߂悤�B -
�y��ɂ̃��|�z���ܑS���́u���E�}���V�����v�ŋN���Ă��邱�Ɓ@�����ƏZ���̘V���ŃX������
�����������ώ��̂��c
�@�������E�����s������BJR�̔����w����k��10���قǂ̗��ʂ�ɖʂ����A�z40�N����A�}���V�����B
�@�N�G����������D�F�̕ǂƁA�h����������ĉ��������Ă���̂����ʂ��ɂ����}���V�������̃v���[�g�������A�ꌩ�A�ǂ��ɂł�����悤�ȌÂт������Ɍ�����B�����A�����́A�u�X�������}���V�����v�Ƃ��đS���I�ɗL���ɂȂ����������B
�@�ߗׂ̕s���Y����舵���Ǝ҂������B
�@�u���āA���̃}���V�����͒����̉ƒ낪�������邲�����ʂ̕����ł����B���ꂪ�A�n�グ���ƏZ���̑Η�����A�������т̉ߔ����s�݂ƂȂ�A���ʓI�ɊǗ��g���̋@�\����Ⴢ��Ă��܂����B
�@���p���̓d�C��̎x�������~�܂��āA�G���x�[�^�[�͓����Ȃ��Ȃ�A����̒����^���N�ւ̐��̋�������~�B���Z���s�\�ɂȂ�܂����B
�@�����̏Z�����o�Ă����Ă��܂��A���Q�҂�s�R�҂̂��܂��ƂȂ�A�r��ɍr�ꂽ�B�s�R�ɂ��Ђ��������đS�Ă����������ۏł��̂܂ܕ��u����Ă�����A�����������ώ��̂��������ꂽ��ƁA�����L��l�ł����B
�@�o�ϓI�Ȏ���ŏo�Ă������Ƃ̂ł��Ȃ���������̏Z���ׂ͈��p���Ȃ��A�����ȋ�J�����ꂽ�Ǝv���܂��v
�@���܂ł����A�O�ǂ͓h�蒼����Ă��邪�A���Ă͈�ʂ��y���L�̗��������炯�������B�����ɏ悶�Ė\�͒c�����������������Ƃ��������̃h�A�ɂ́A���C�����̒e�������܂��c��B
�@���݂́A�S�Z�˂̔����قǂɏZ��������Ƃ͂����A����ɂ͍����S�~���U�����A�ǂ̂Ƃ���ǂ���ɂ́A�܂��V���ȗ��������Ȃ���Ă���\�\�B
�@�ɂ킩�ɂ͐M�����������i�B�����A����A���������Ǘ��s�S�ɂ��u�X�������}���V�����v���A���{�S���ŋ}������\���������B
�@�w���E�}���V�����x�Ȃǂ̒���������A�x�m�ʑ����̕ĎR�G�����������B
�@�u�}���V�����ɂ�2�́w�V���x������܂��B�����ƁA���Z��(�����̎�����)�̍���ł��B���̘V���̉ߒ��ŁA������݉����}���ɐi�݁A�ێ��Ǘ��⌚�đւ��Ή�������Ȃ��Ă����B
�@�������ĊǗ��s�S�̏�ԂɂȂ��������}���V�����������炩�w���E�}���V�����x�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B
�@���{�ɕ����}���V�������o�ꂵ���̂́A'50�N��̏I��荠�ŁA���x�������ɂ͂���ɑ��������B�������������̃}���V�����́A���݁A�z�N����50�N����60�N���}���Ă��܂��B
�@�Ǘ��g�������݂��Ȃ��Ƃ���������A����������I�ȊǗ�����s���Ȃ��Ȃ�A������Ƃ���ɕs����o�Ă���B�w���܂ɂ��|�����x�Ƃ����قǂ̗�́A�s���ł͂܂�����܂��A����20�N�łǂ�ǂ��Ă����ł��傤�v
�Ǘ��g�������R����
�@���݁A�S���̃}���V�����̂����A���ю�̔N�60�Έȏ�̂��͖̂�5�����߁A�}���V�����Z���̍���͋}���ɐi�s���Ă���B
�@�Z���̍�����i�ނƁA�ǂ��Ȃ�̂��B���̃��f���P�[�X���A�����E�V�h��̍��c�n��w����k��15�����x�̂Ƃ���ɂ����K�͂ȓs�cB�c�n���B
�@�����́A���ː���2300�˂̂���65�Έȏ�̏Z�l���ߔ������߂�B�s���A�P�g�ł̓�����60�Έȏ�Ɛ������Ă��邱�Ƃ�����ɔ��Ԃ����������Ƃ�����A��s��́u�W�̂ĎR�v�Ɲ�������҂��炢��B
�@�G���x�[�^�[�̂Ȃ�5�K���Ă̓��ɏZ�ށA70��̒j���������B
�@�u�͎̂q���������ς��������ǁA���܂͂����N������B�������N�Œm�荇�������ŏ\���l���S���Ȃ����B�Ȃ��ɂ́A�����̒��œ|��āA����2�T�Ԉȏ�o���Ă��甭�����ꂽ�l�������B
�@�c�n�S�̂��ƌǓƎ��̘b�͂�������イ�����܂��B�F�ǂ�������̂��������āA�a�@�ɍs���ȊO�͉ƂɈ����������Ă���B������̖������Ȃ�肪���Ȃ��A����5�N��������A�^�c�����藧���Ȃ��Ȃ�܂���v
�@����B�c�n�́A�����܂œs�c�ł��邽�߁A�ݔ��̈ێ��Ǘ��͓s���S���Ă���̂ŁA���Ɏ�����g�D�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��A���̊��͈ێ�����邩������Ȃ��B
�@�����A���ԃ}���V�����̏ꍇ�A���l�ɏZ���̍�����i�݁A�Ǘ��g���̋@�\���ʂ�����Ȃ��Ȃ�A���͂�N���ʓ|�����Ă���Ȃ��Ȃ�B
�@�V�����}���V�����̖��ɏڂ����A���茒�N������w�������̏��{�������������B
�@�u�ȑO���́A����̂���s���̑����n�悩��A��w�̂������Q�n������s�̋ߕӂ܂łɌ���250���̃}���V�������A���N�����Ă���݂Ԃ��ɒ������܂����B
�@���ʁA����1���A25���̃}���V�������Z���̍���ɂ��Ǘ��g���̋@�\��~��A�Ǘ���ϗ��s���ɂ��C�U�s�\�Ȃǂ́w�Ǘ��s�S�x�Ɋׂ��Ă����̂ł��B
�@�������琔�N���o���A���̐��͂����Ƒ����Ă���͂��B�������������g���������͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ����猩�߂����ꂪ���ł����A�����������ł̊Ǘ��s�S�̃}���V�����̑����X�s�[�h�́A�z����y���ɒ�������̂�����B
�@�������ۂɕ����Ē������������ł��A��ʌ��̏���s��V���s�A�F�J�s�A��錧�̎��s�ȂǂŁA�Ǘ��s�S�}���V�����̑������ڗ����Ă��܂��v
�����Ȃ�L��������
�@�����ƏZ�l��2�̘V���B���̐i�s���Ƃ�킯�����Ȃ̂��A'81�N��6���ȑO�Ɍ��݂��ꂽ���ϐk�}���V����(�z35�N�ȏ�)�ƁA���̂���ɑO�A'71�N�ȑO�Ɍ��Ă�ꂽ���X�ϐk�}���V����(�z45�N�ȏ�)���B
�@���{�S���ŁA���ϐk�͖�106���ˁA���X�ϐk�͖�18�����������Ă���A���҂����킹�����́A�������ɓ����A�_�ސ�A���A��t�A���ɁA��ʁA���m�Ƒ����B
�@���̂��������ɂ́A���ϐk��36���ˁA���X�ϐk��7���ˌ����B���y�[�W�̕\������Ε�����ʂ�A���c�J���a�J��A�`��A�V�h��ȂǁA�l�C�Z��n�Ƃ����n��ɑ����B
�@�s���ɖڂ��ڂ��A�����j���[�^�E���ɑ�\������K�͒c�n������鑽���s�┪���q�s�A���c�s�ɑ����c��B
�@���̏Ɋ�@�����o���������s�́A���N3���u�ǎ��ȃ}���V�����X�g�b�N�̌`�����i�v��v������B�}���V�����Ɗe�Ǘ��c�̂�o�^�����A�s�̑��ŘV�����̏�c�����鎎�݂��͂��߂��B
�@�s�́A8���ȏ�̃}���V�����̓o�^��ڕW�Ɍf���邪�A�O�o�̕ĎR���́A���̌��ʂɉ��^�I���B
�@�u���������A���������d�g�݂ɂ����ɔ������ēo�^�ł��鎞�_�ŁA����Ȃ�ɊǗ����s���͂��Ă���Ȃ�ł��B���Ȃ̂́A�Ǘ��g�����@�\���Ă��Ȃ��}���V�����B���������Ƃ���́A��Ԃ�������̂�������A�o�^���Ȃ��̂��ڂɌ����Ă���B
�@���邢�́A���������g�����Ȃ��}���V�����̏ꍇ�A���������v��̑��݂��̂��̂��Z�����c���ł��Ȃ��B�V���������̑����͔������Ȃ����ۂȂ̂ŁA�s���͑��ӁA�}���V������̖̂��ɖ{�������Č��������K�v�ɔ�����ł��傤�v
�@�V���������}���V�����̕s���v����̂́A���Y�}���V�����̏Z�����������ł͂Ȃ��B
�@�u�C�U�����낻���ɂȂ��Ă����}���V�����̊O�ǃR���N���[�g���{���b�Ɣ�����āA�����ɗ��������Ȃ�Ă������̂́A�S���e�n�Ŗ����̂悤�ɋN�����Ă��܂��B���Ԃ��̂��Ȃ��厖�̂����N���Ă����������Ȃ��v(�O�o�E���{��)
�@����'09�N�ɂ́A���ꌧ�Y�Y�s�̏Z��X�ɂ���z35�N(����)�̘V�����}���V�����ŁA������15���[�g���̘L�����������鎖�̂��N���Ă���B����5���Ƃ������ԑт��������߁A�����l�͂��Ȃ��������A���~���ɂȂ����y�����Ԃ̓y�V�����R�ɂԂ�A��S���ɂȂ鋰����������B
�@������A�Ǘ��g����������Ƌ@�\���A����I�Ȍ�����ۑS���s���Ă���A���O�ɑ�̑łĂ����̂������B
�@���������Ǘ��g���̋@�\�s�S�ɉ����āA�O���l�̒��ݗ��p�ґ������u�X�������v�ɔ��Ԃ�������P�[�X������B
�@�_�ސ쌧���l�s����E�֓��B�Ŋ��̎s�c�n���S�̉w����k��5���قǂ̍D���n�ɁAC�}���V����������B���ӂɂ̓R���r�j�G���X�X�g�A���K�̓X�[�p�[������֗��ȏꏊ�B
�@�����}���V�������ї������тɂۂ�ƘȂށA�����O�ǂ��A���₵�����͋C�������B�ǂɂ͂Ђъ��ꂪ�ڗ����A�o���R�j�[�̎肷��̂܂��̃R���N���[�g�͕���A���肷�肪�O��Đl���]�����Ă����������Ȃ���Ԃ��B
�@���̃}���V�����͒z40�N���x��9�K���ĂŁA���ː���40��ƋK�͂����������Ƃ�����A�n�傪����Ǘ������Ă������A5�N�O�A�n�傪�S���Ȃ����̂��@�ɁA����C�Ɉ��������B
�@�ꎺ�����L���Ă���70��̏����Z�����Q���B
�@�u�����̘V�������i��ł���̂ɁA�C�U�̎藧�Ă��Ȃ������B���������ŋN���鐅�R��Ȃǂɑς����Ȃ��Ȃ�A�Z���L�u�ł���ĂĊǗ��g���𗧂��グ�܂����v
�@�����ŏՌ��̎��������o����B�n�傪���O�ɒ������Ă����Ǘ�����g�����݁A�c����0�ɂȂ��Ă����̂��B
�@����ĂďC�U��ϗ������W�ߏo�������̂́A�\�z�O�̏o��͍���̏Z�l�����ɂׂ͉��d���A�u���Ԃɑؔ[�҂��������B�Ȃ��Ȃ��ςݗ��Ă��i�܂�������܂˂������ɁA�����ɑ傫�Ȏx������������x���̕s�����A�}���V�����̂��������ŋN����͂��߂��B
�@�u�܂Ƃ��ȃ}���V�����Ȃ�N�ɐ���͍s���鋋�r���̍�����ł��Ȃ������̂ŁA��������イ�����l�܂�悤�ɂȂ�܂����B����ɂ�����̐��|�����Ă��炸�A�����������K�v�Ȃ̂ł����A���̔�p�����Ȃ������v(�O�o�E�����Z��)
�n���̂悤�Ȉ��L
�@��������ɁA���ݏZ���������o���A�I�[�i�[���L�҂��������Ȃ�Ƃ����悤�Ǝ���I�Ȃ��Ȃ������ƂŁA�����l�̋��Z�҂��ꋓ�ɑ����������B
�@�u�ނ�́A�����Ŏg�������ʂɔr�����ɗ����Ď̂Ă��ł��B���Ƃ��ƃT�r��S�~�ŋl�܂�C���̂Ƃ���ɖ��𗬂����ނ���A�r���ǂ̒��Ōł܂��Ă��܂��B��������Ȃ��̂Ő��͂��납�A������܂Ƃ��ɂł��Ȃ��B
�@�g���������R�c�����ɍs���Ă��A�w���������x�ƊJ�������A�b�������ɂ���Ȃ�Ȃ��B���̂����������l�܂��āA�������t�����A�����C��Ɉ���悤�ɂȂ����B���L�Ȃ�Ă���Ȃ��B
�@�����n���ł��B�d�����Ȃ�����A�f���C��}���Ȃ���A�N�̂��̂����킩��ʉ����C���ł������Ă̓S�~�܂ɂ��߂Ď̂Ăɍs���B���̍ɂȂ��ĂȂɂ����Ă���낤�ƁA�܂��o�܂����B
�@���ǏC�����Ă��炤���߂ɁA�Ǝ҂��ĂԂ��Ƃ����܂����̂ł����A���N�̘V�����ŁA�w��ɔj�����郊�X�N�����邩��x�Ƃ����ĂقƂ�ǂ̂Ƃ���ɒf���Ă��܂��A�r���ɕ��܂����v(�O�o�E�����Z��)
�@���̃}���V�����͔S�苭�������o�āA���ꂩ��悤�₭�C�U�̑����ݏo���Ƃ����B�����A��ގ������傤�ǔz�ǂɂЂт�����A�K�X�R�ꂪ�����B�Z�������̔Y�݂͐s���Ȃ��B
�@���������A�Ǘ��s�S�̘V�����}���V�����̋~�ϋƖ��ɓ���������Ƃ��o�Ă��Ă���B
�@���̂ЂƂA���l�T�����[�̗����G��\�������B
�@�u�����́A20�N�قǑO���炱�������Ɩ��Ɏ��g��ł��܂������A�Ǘ��s�S�����̐��͔N��ǂ����Ƃɑ����Ă��܂��B���n���ǂ�������v�A�ȂǂƂ����l���͂܂������̌��z�B
�@���܂̂܂܂ł́A���L�҂̑������S���Ȃ�C�U�̎������ꂸ�A����������Ȃ��}���V���������ɓ��ɑ����čs���B���⎩���̂���̂���ɂ��Ă��A�c��Ȃ�����������B��̂ǂ������炢���̂��c�c�v
�@�O�o�̕ĎR����������B
�@�u���ǁA�}���V�����͎��������̂��̂Ȃ̂ŁA���l�������Ă���邱�Ƃ����҂��Ă͂����܂���B�s�����x������Ƃ����Ă��A�o���邱�Ƃ͌�����B���̏Z�l�ɔC������ɂ���̂ł͂Ȃ��A������������Ǘ��g���̏�c���������������B
�@�}���V�����p���ĘV�l�z�[���Ȃǂɓ������邱�Ƃ��l���Ă��A���Y���l�������Ȃ����߂ɐϋɓI�ɊǗ��g���Ɋ֗^���邱�Ƃ��A�Ђ��Ă̓X��������h�������ł��v
�@�u���E�}���V�����v�̌����́A�����đ��l���ł͂Ȃ��B -
���{�̉ߏd�J���̕����͂悤�₭�I������̂�
���{�̉ߏd�J���̕����͂悤�₭�I������̂�
�ߏd�J���������ŘJ���҂����𗎂Ƃ����Ƃ́A���{�ł͒��N�̖��ƂȂ��Ă���A�ukaroshi�i�ߘJ���j�v�Ƃ������t��������B
���{�Ɗ�ƒc�̂͑�̂ЂƂƂ��āA�J���҂������̎��Ԃ����������ł����߂���悤�A����1��A�������ԂɑގЂ�����g�݂𐄐i���Ă���B
�u�v���~�A���t���C�f�[�v�ƌĂ�闈�N2������̐V���x�ł́A�����̍ŏI���j���͌ߌ�3����ގЎ��Ԃɂ���B
�L���㗝�X�ő��̓d�ʂŁA��100���Ԉȏ�̎c�Ƃ����Ă��������V���Ј����ߘJ���E���������A�V���x�̓������㉟�������B
�����Ј��̎��E���āA�d�ʂ́A�����J���ǂ���J����@�ᔽ�e�^�ŏ��ޑ�������A����ɂ͎В������C��\���B���������߂���[�����O���A���{�Љ�S�̂ɍL�܂����B
�������A�ߘJ���Ɋ֘A�������S�Ⴊ���N2000������Ȃ��ŁA�����͂̂Ȃ��u�v���~�A���t���C�f�[�v���x���A�l�X�̍l������傫���ς���Ƃ݂͂��Ă��Ȃ��B�ǂ̒��x�̉�Ђ���������̂����A������Ȃ����B
���{�͉ߋ��ɂ��L���x�ɂ̎擾�𐄐i������g�݂�i�߂����A�傫�Ȍ��ʂ͂Ȃ������B�����J���Ȃɂ��ƁA���{�̉�Ј��̗L�x�������͖�5���B
���{�̌��x���͍��N1�������A���v16���ɂȂ����B�����I�ɋx�ɂ���点��̂��A���x���̖ړI�̂ЂƂɂȂ��Ă���B
���{�̓t���b�N�X�^�C�����x�̐��i�����Ă���B���{�E�����ċG���Ԃɐ����ԁA�n�ƂƑގЂ̎��Ԃ𑁂߂鐧�x�ɉ����A�I�t�B�X��[��ɂ͏��������܂ōs�����B�d�ʂł��[��̏��������Ă���B
�J���ґ��ł��A�������͎c�Ƃ����Ȃ��ƌ��߂鎩��I�ȓ���������B�\�[�V�������f�B�A�Ő錾���āA�ق��̐l�������悤�Ɏc�Ƃ��Ȃ��悤�Ăт�����l��������B
�������A�����Ԃ̎c�Ƃ͗ǂ����Ƃł���͂����Ƃ����l����ς��鏕���ɂ͂Ȃ������A�J�����Ԃ̒Z�k���̂��̂ɂ͑傫���Ȃ����Ă��Ȃ��B
�Ɨ��s���@�l�̘J�������E���C�@�\�ɂ��ƁA2014�N�ɂ͘J���҂�22���O�オ�T49���Ԉȏ�c�Ƃ��Ă����B�������v�̊؍�35�����͒Ⴂ���A�č���16�����͍����������B
�Ȃ��ς��ׂ��Ȃ̂��H�@
�����ԘJ���̐����́A���{���ƒc�̂ɂƂ��Ă������b�g������B
���{�o�ς�20�N�ȏ�ɂ킽���Ē���𑱂��Ă���B������Ɉ������Ă���̂́A����x�o�̎コ����ɒႢ�o�������B�ǂ����1���̑����̎��Ԃ��d���ɔ�₳��Ă���̂�������B
�����ԓ����Ă����l�����邽�߂ɉ�Ђ��������Z�p�ɓ��������A���Y���ƌ������̌���ɂ����e�����y��ł���B
��ꐶ���o�ό������̃`�[�t�G�R�m�~�X�g�A�i�_���A����BBC�̎�ނɑ��A�v���~�A���t���C�f�[�̑ΏۂƂȂ�J���҂��S���A�ߌ�3���ɑގЂ���A1����{���邲�ƂɁA�l������ő�1240���~�����グ����ʂ��o��A�ƌ�����B
�������i�_���́A�v���~�A���t���C�f�[���ǂ̒��x�Z�����邩�͒N�������炸�A�S������������\�����Ⴂ�Ƃ��w�E����B���̂��߁A���ۂ̌o�ό��ʂ͐��v���������Ə������\��������B
������Ȃ���Ƃ�J���҂�����Ƃ���A�Ȃ��Ȃ̂��B�擪����Ďn�߂�̂͑�ςȂ̂��A�Ƃ͌�����B
��ƂɂƂ��Ă̓R�X�g�͑�����B�����ē��{�̘J���҂́A�����葁���ގЂ��邱�Ƃɍ߈�����������B
�i�_���́A���{�̘J���҂͓����ɖ��f�������Ȃ����S�z����A�Ǝw�E�B�`�[���œ����Ă���ӎ����������炾�Ɛ�������B
�����̓��{�̏��K�͊�ƂɂƂ��āA�J�����Ԃ̒Z�k�͓��ɍ���B�����ł����R�X�g�팸�ɋ�S���鏬�K�͎��Ƃ̏ꍇ�A�����͉Ƒ��o�c�̂��߁A���������������ԂɑގЂ���͓̂���B
�i�_���́A�v���~�A���t���C�f�[�����s�����Ƃ��Ă��A���̖��ߍ��킹���ق��̓��ɂ�����A�ʂ̎d��������悤�ɂȂ�A���x�̖ړI�͎�����Ƙb���B
�v���~�A���t���C�f�[�̊��U����߂�o�ώY�ƏȂ̐��k�O���o�Y���́A�v���~�A���t���C�f�[�̌ߌ�3���ȍ~�͗\������Ȃ��Ɛ錾���Ă��邪�A���Ȃł�����������̂��͕s�����B
�^�O�͑������̂́A1�J����1���Ƃ��������₩�Ȉ�����B���{���Ƃ̌㉟�������邱�Ƃ���A�V���x���Z�����A�ŏI�I�ɂ͐E��̕����ɍ��{�I�ȕω��������炷�̂ł͂Ȃ����Ƃ������҂�����B
���i�h�́A���X�g������e��X�܁A���s��ЂȂǂɂƂ��Ă��r�W�l�X�`�����X�ɂȂ�Ƃ��Ă���A��ЂɂƂ��Ă��]�ƈ��̎��R���Ԃ𑝂₷���_������̂��������Ƃ��Ă���B
�������A�[�����������J���K����ς���̂͂Ȃ��Ȃ�����B����܂ł̑����̎��g�݂͎��s�ɏI����Ă���B�������A����Ȃ���A���{�l�̉�Ђɑ��钉���S���ቺ������X�����A����̎��g�݂��㉟�����邩������Ȃ��B
�I�g�ٗp�ɂ���Ĉ�̉�Ђɔ���t�����Ă����e����ƈ���āA���X�g����������O�ɂȂ�������ɐ�����Ⴂ����ɂƂ��ẮA���ɂ͋��j���ɑ����ގЂ��������ɍs���@���̂��A���[�N���C�t�o�����X��ۂ��߂̔w���̈ꉟ���ɂȂ�̂�������Ȃ��B -
�N���̑�z�ƊE�̓u���b�N�H
�u12���ɓ����āA3�L���������܂����v�B��s���̃��}�g�^�A�ɋ߂�A����́A����10�N�ȏ�̃x�e�����Z�[���X�h���C�o�[�B�̏d������̂́A�����Ԃ̓��̘J���ɉ����A���H�̎��Ԃ����Ȃ����߂��B
�u�ו��������āA�܂Ƃ܂����x�e�����܂���B12���́A���Ε�A�N���X�}�X�A��������1�N�ň�ԖZ�����B��7���������11�����炢�܂œ����Ă��܂��v
�����I�Ȏ��ԊO�J���́u�ߘJ�����C���v�ƌĂ�錎80���ԑO��B�u�l�����łȂ��A�唼������Ȋ����œ����Ă����ł��v
���l�b�g�V���b�s���O�Ńh���C�o�[�敾
�l�b�g�V���b�s���O�̊g��ŁA��z�ւ̗��p�������Ă���B���y��ʏȂɂ��ƁA2015�N�x�̑�z�ւ�37��4493���B����10�N�ԂŖ�8���i��27.3%�j�����������B
�V���b�v���Ǝ҂Ƃ��ẮAAmazon���Ƒ����Ă���B�C���v���X�̒����ɂ��ƁA2015�N��Amazon�̔��㍂��9300���~�B2�ʂ̃��h�o�V�J������790���~������A10�{�ȏゾ�B�y�V�ɂ��ẮA�y�V�u�b�N�X�Ȃǂ̒��̂��Ώۂ̂��߁A5�ʁi550���~�j�B�y�V�s����܂߂����ʑ��z�ł͓��{�g�b�v�N���X�Ƃ����B
�K�R�AAmazon�̔z�B�������}�g�̎�舵������������B���Ђ�2015�N�x�́u��}�ցv��舵��������17��3126�����BAmazon�̔z�B�J�n����3�N�ŁA���悻2��4000�����i��16.4%�j�L�т��B
�{���A�ו����������Ƃ́A�h���C�o�[�ɂƂ��ă}�C�i�X����ł͂Ȃ��B���}�g�ł͔z�������ɉ������u�Ɩ��C���Z���e�B�u�v�����邩�炾�B�������A��}�ւ�1��20�~�قǁB���ɗ]����50�^��ł��A1000�~������Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��B
�u�Z�����ɔ䂵�āA�������オ�������o�͂���܂���v�BA����͑i����B���ʂƂ��āA����ɂ�Amazon�ɑ��镉�S�����������Ă���Ƃ����B
���I���Ȃ��u�Ĕz�B�v�A�R���r�j�z���́u�I�A�V�X�v
A����̏ꍇ�A1���ɉ^�ԉו���150�قǁB12����200�ȏ�̓����������Ƃ����B���̂����A2�`3����Amazon���B�uAmazon�������悤�ɂȂ��āA�{���ɂ���ǂ��Ȃ�܂����v
A����͒��A�z�B���n�߂�ƁA�܂��}���V�����Ɍ������B�u��z�{�b�N�X���Ă���ł���B���������ς��ɂȂ����Ⴄ����A���ЂƋ����ɂȂ��ł��v
�{�b�N�X��_���̂́u�Ĕz�B�v�������Ȃ����炾�B�����Ȃ̒����i2014�N�j�ɂ��ƁA��z�ւ̍Ĕz�B����19.6%�B�Ĕz�B1��ڂł���4%���c��B�u�݂�ȋA��Ă���Ĕz�B�̓d�b�������Ă���B�������̎d���͂��܂ł����Ă��I���Ȃ���ł��B���}�g�̎��Ԏw��͌ߌ�9���܂łł����A���̌���z�B�𑱂��Ă��܂��v�iA����j
��z�{�b�N�X���g���������R�́A�ق��ɂ�����B�s�S���œ���B����i40��j�́A�u�^���[�}���V�����͑�z�Ǝ҂ɂƂ��āA�ʓ|�ȃ��[���������v�ƌ��B�Ǘ��l�����Ԃ̗��p�֎~��A�ꌬ�ꌬ�C���^�[�z���ŋ����Ƃ�悤�����邱�Ƃ������������B��z�{�b�N�X���g����A���̂킸��킵�������������B
�uAmazon�́A�����Ɖו����܂Ƃ߂Ĕ������Ă��ꂽ��ȂƎv���܂��B���ꂩ��A���������͕̂����ő����Ă��炦��ƁA�s�݂ł��X�֎ɓ������̂ł��肪�����ł��v�iB����j
�Ĕz�B�ɔY�܂�����z�h���C�o�[�ɂƂ��āA�I�A�V�X�Ƃ�������̂��u�R���r�j�v���B���N�A���}�g��ގЂ������h���C�o�[��C����i30��j�́A�u�R���r�j�͂܂Ƃ܂����ʂ��m���Ɏ���Ă���邩��A�{���ɂ��肪���������ł��v�ƌ��B
�������A�R���r�j�X���̕]���͖F�����Ȃ��悤���BC����͂���������B�u�m�荇���̓X������́A�w����ȃT�[�r�X�Ȃ��Ȃ�����̂Ɂx�Ƙb���Ă��܂����ˁB�o�b�N���[�h�������ς��ɂȂ邵�A�n���Ɏ��Ԃ������邩��w�x�߂Ȃ��x���āv
���Ɩ������ŃJ�o�[�}����u����̓p���N��ԁv
Amazon�̔z���͂��Ƃ��ƍ���}�ւ������Ă����B�Ƃ��낪�A�^���̒l�グ�������P�ށB����ւ��ŁA���}�g��2013�N����Q�������B���݁AAmazon�̔z���̓��}�g�𒆐S�ɁA���{�X�ւ�u�f���o���[�v���o�C�_�v�ƌĂ�钆����ƂȂǂ������Ă���B
���삪�P�ނ���悤�ȉ^���ł����}�g������������̂́A����Ƃ̃r�W�l�X���f���̈Ⴂ���傫���B����̑�z�ւ̑����́A�������Ǝ҂ɑ�����ē͂��Ă�����Ă���B����ɑ��A���}�g�͂قڎ��Ѓh���C�o�[�œ͂��邱�Ƃ��ł���B�z�B�������グ��A���v���o��B
�������A�ژ_���ɔ����āA����̓p���N���O���Ƃ����B�O�q��A����͎��̂悤�ɏ،�����B�u����1�N�Ŏ���̃h���C�o�[��10�l���炢��߂܂����B�������̐l�ɂ��肢���ė����ł��邯�ǁA�Ј����̂͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B���̊Ԃ��A�̌����Ђ̎q��1���A�g���b�N�̏���Ȃɏ悹���Ƃ���A�w�d�����Q������������x�ƌ����Ă�߂Ă��܂��܂����v
���u���������v�����߂�����
A����͂������q�ׂ�B�uAmazon�ɂ��Č����A��Ёi���}�g�j�������d��������ė��āA����ɉ����t���Ă���Ƃ������o�ł��B���������w���������x�͌������Ǝv���܂��B�ŋ߂́A�Ă␅�ȂǏd�����̂��l�b�g�ʔ́B����҂̕����w��������Ԓ��x���Ǝv���Ă��炦�Ȃ��ł��傤���c�v
�����������Ȃ̂�Amazon�����ł͂Ȃ��B�}���ɃV�F�A��L���Ă��郈�h�o�V�J�����Ȃǂ��������B�쑺������2016�N�ɔ��\�����u�������Ɋւ���A���P�[�g�����v�ɂ��ƁA�u�l�b�g�V���b�v��I�ԍۂ̕K�{�����v�́A�u�������������Ɓv����70���ŁA�u���i�̈����v������1�ʂ������B���������̔w�i�ɂ́A����҂̋����v�]������B
�u�K���ȑ���������������A�������オ�邵�A�l��������Ǝv���̂ł����c�B�_�b�V���{�^�����o�āA���ꂩ��Amazon��l�b�g�ʔ̗̂��p�͂����Ƒ����܂���ˁB���̘J���ł�����A���̂܂܂ł́A���Ɖ��N�̂������A�܂������悪�����܂���v
���u�J�����Ԃ̍팸�v���������ăT�[�r�X�c�Ƃ�
���}�g�͍��N8���A���l�s�ɂ���x�X���J����ē�����̐������������B��莋���ꂽ�̂́A�i1�j�x�e���Ԃ��@��ʂ�擾�ł��Ă��Ȃ����ƁA�i2�j���ԊO�J���ɑ���������x�����Ă��Ȃ����ƁB
�J��ɋ����i�������h���C�o�[�ɂ��ƁA�J�����Ԃ�Z�k���邽�߂̎��g�݂��A�������ăT�[�r�X�c�Ƃݏo���Ă����������B
���}�g�̘J���g���́A��ЂƂ̋���ŘJ�����Ԃ̏�������߂Ă���A����͔N�X�Z�k����Ă���B�������A�Ɩ��ʂ͑��������B�T�[�r�X�c�Ƃ��Ȃ��ƁA�d�������Ȃ���Ԃ������Ƃ����B
���}�g�̎Ј��h���C�o�[��5�N�O�����4000�l�����āA���悻6���l�B�������A�ו��̑����ɒǂ����Ă���Ƃ͌����������B�P���v�Z�����A���̊ԁA�Ј��h���C�o�[1�l������̑�}�ւ̌������N3000���ȏ㑝���Ă��邩�炾�B
��Ђ��Ɩ��̌�������ڎw���A�ߔN�͒n��̎�w��2�`3���Ԃ����p�[�g�Ј��Ƃ��Čق��u�`�[���W�z�v�Ƃ������@�ɗ͂����Ă���B�h���C�o�[�Ɠ��悳���āA�q��܂ʼnו���͂�������̂��B
���ЍL��́u�J���W��^�̎Y�ƂȂ̂ŁA�l�肪��Ƃ����F���͓��R����܂��B�h���C�o�[�̑������܂߂āA����������Ă��܂��v�Ƙb���B
�����[�U�[�͂ǂ����ׂ��Ȃ̂��H
12��24���ߑO�A�L�ґ�̃C���^�[�z���������B�����̑O�ɂ����̂́A���}�g�^�A�̒��N�Z�[���X�h���C�o�[�B�l�b�g�̎����Œ����������i��͂��Ă��ꂽ�̂��B
�T�C�������Ȃ���A���鋰��q�˂Ă݂�B�u��͂�A�N���X�}�X�͑�ςł����H�v�B�j���͋���œ������B�u�L���p����������Ă܂��ˁB����Amazon�͑��߂��B�d�������ǂ����Ȃ��ł���v�B�����ʂ̃T�C�g�Ŕ��������̂́A���߂����C�������肪�c�����B
�ߏ��̉c�Ə����̂����ƁA�召���܂��܂Ȓi�{�[�������������ς܂�Ă����B�Q���������o���肷��X�^�b�t�B�u����̃T���^�N���[�X�v�͖Z�����B������������\�\�B
���N�̓N���X�}�X���Ԓ��ɁA����}�ւɑ�K�͂Ȓx�z���������A�傫�Șb��ɂȂ����B�l�b�g�ʔ̂Ő����͔���I�ɕ֗��ɂȂ������A�^�Ԃ̂́u�l�v���B��z�ւ̑����ɁA�ƊE���ς����Ȃ��Ȃ��ė��Ă���B
�Ƃ͂����AAmazon���͂��߁A�l�b�g�ʔ̂֗̕������藣�����Ƃ͓���BA����ɐq�˂Ă݂��B�u���p�҂Ƃ��čŒ���ł��邱�Ƃ͂Ȃ�ł��傤���v�B�Ԃ��ė��������́A���̂悤�Ȃ��̂������B
�u�l���w���p�ҁx�Ȃ�ŁA����܂�̂����Ȃ��Ƃ͌����܂���c�B���Ԏw�肵�āA���̎��ԕK���Ƃɂ��Ă����A���ꂾ���ł������ԈႢ�܂��v
-
�@"�l���_���ɂ���\�t�@"�Ƃ��Ęb����W�ߐl�C�������Ă��閳��Ǖi�́u�̂Ƀt�B�b�g����\�t�@�v���A2017�N�̐�������Œl���������B
�@�u�̂Ƀt�B�b�g����\�t�@�v�́A���̔����q�r�[�Y�ɂ���Ď��R�ɕό`����Ɠ��̍���S�n�������ŁA2005�N�ɔ����B2013�N�ɂ́A�����b�N�X���߂��邱�Ƃ���l�b�g���"�l���_���ɂ���\�t�@"�Ɩ��t�����ASNS�Ȃǂ�ʂ��čL�܂����B���̌���q�b�g�𑱂��A2016�N�̖���Ǖi�l�b�g�X�g�A�̐����G�݃J�e�S���[�ł́A����グ���N��1�ʂ������Ƃ����B
�@2017�N�̏����肩��1��3���܂ŁA�ʏ�͐ō���1��2,600�~�́u�̂Ƀt�B�b�g����\�t�@�E�{�́v��2,017�~�����B�z�����������ɂȂ�B
���x�F�A������~����(���) -
���l���f�������l���f���̍L���ʐ^�����S�Č��c�ޏ����`���������� �g�^�̑��l���h �Ƃ́H
���͐̂��������ƁA���l�����F�߂��鎞��ƂȂ�܂����B����ł��A�e���r�A�G���A�X�p�A�����ăC���^�[�l�b�g�A������ꏊ�Ŗڂɂ���t�@�b�V�����L���ɋN�p����Ă���̂́A�܂��܂����l���f���������c�c�B
���A�t���J�E���x���A���a���o�g�Ō��݂̓��T���[���X�ݏZ�̍��l���f���A�f�f�[�E�n���[�h����ɂ��v���W�F�N�g�u�u���b�N�E�~���[�v�́A�S�ɐ��܂ꂽ����Ȏv�������������Ŏn�܂����̂������ł��B
�y�����|�[�Y�A�����\�}�ŎB�e�z
�u�u���b�N�E�~���[�v�v���W�F�N�g�ł́A�n���[�h���g����ʑ̂ƂȂ��āA���l���f�����t�B�[�`���[���ꂽ�L���ƑS�������|�[�Y�A�\�}�̎ʐ^���B�e�B�o�����r����悤�Ȃ������ŁA���g�̃E�F�u�T�C�g�uSecret of DD�v��C���X�^�O�����Ō��J���Ă��܂��B
�y�����ʂ��o�l�Ɂz
�C�O�T�C�g�uELLE.com�v�̃C���^�r���[�ŁA���f���̃L�����A���X�^�[�g������18�̍����獕�l�Ƃ��������ŋ��₳�ꂽ���Ƃ����X�������A�ƌ�����n���[�h����B
����ȋ�X�����̌������z�̂��ƂƂȂ��Ă���Ƃ����u�u���b�N�E�~���[�v�́A�t�H�g�O���t�@�[�Ńf�U�C�i�[�ł���p�[�g�i�[�A���t�@�G���E�f�B�b�N���[�^�[����Ƃ̋����v���W�F�N�g�ł��B
�u���͗c�����A�Ȃ��O�b�`��V���l���A���C�E���B�g���Ȃǂ̑��u�����h�̍L���ɂ͍��l���f�����N�p����Ȃ��̂��A�s�v�c�Ɏv���Ă��܂����v
�u���l���f�����������邱�Ƃ͂���܂����A���������B��������Ԃ�͂��������ł��v
�x�@�ɖ\�s�����Ȃǃ}�C�i�X�ȑ��ʂ̓N���[�Y�A�b�v�����̂ɁA�X������ʂł͂������������Ƃ͂��܂�Ȃ��B���l�Ɋւ���l�K�e�B�u�ȗv�f������ڂɂ�����Ԃ����܂�ɂ����������̂��ƁA�n���[�h����͎��g�̃E�F�u�T�C�g�Ō���Ă��܂��B
���l�A���l�A�A�W�A�l�A���e���n�̐l�X�B���ׂĂ̐l��͓���������˂Ȃ�Ȃ��B�u���l���|�W�e�B�u�ȑ��ʂւƈ����߂������v�Ƃ��������M�O�������ĎB�e���ꂽ�ʐ^�̐��X�́A�K���ł��B
������B�N�g���A�E�V�[�N���b�g�̃V���[�ō��l���f���̃W���X�~���E�g�D�[�N�X���t�@���^�W�[�u����g�ɂ��邱�Ƃ��ł���B��̃��f���ɑI��܂������A���������V�[���𐢊E�̂�����Ƃ���Ō�����悤�ɂȂ��Ăق����ƁA�n���[�h����B
�^�̈Ӗ��ł̑��l���Ƃ͂Ȃɂ��[���l����������v���W�F�N�g���A���ЂƂ������ɂȂ��Ă݂Ă��������B -
�h�~�m�E�s�U��12��25���A�ꕔ�X�܂Ŕ������Ă����z�B�x������ѓX���n���̒x���ɂ��āA�����T�C�g�ŎӍ߂��܂����B�N���X�}�X�C�u�ɒ������E���������Ƃ���A���\�ԂɃs�U���Ă����X���ł͑卬���ɁB�C���^�[�l�b�g��ł́u19���̎�肪�A�������23�����A�Ƃɒ�������0���c�c0���Ƀs�U��H���ƁH�v�ȂǁA�p�j�b�N�̗l�q��`���鐺������������܂����B
�y�摜�z24��19�����납��u�h�~�m�E�s�U�v�֘A�c�C�[�g���}��
�@�h�~�m�E�s�U�̍��G�Ԃ��`����c�C�[�g�������n�߂��̂�24��19�����납��B�u�҂���2���ԁA�܂��ł��ĂȂ��v�u2�T�Ԉȏ�O����\�Ă����̂ɃL�����Z�����Ă����v�ȂǁA���ł����������̂́u��莞�ԂɂȂ��Ă��s�U���Ă��Ă��Ȃ��v�Ƃ������̂ł����B�܂��A�҂����ꂽ�q����́u�ӂ�����Ȃ�I�v�u�N���X�}�X�p�[�e�B�[�ł��Ȃ����낤���I�v�Ƃ������{����A�ԋ���v�����鐺���������Ă����Ƃ̂��ƁB
�@���ɂ̓A���o�C�g�X���������o���Ă��܂����A�x�@���o�����Ă���Ƃ�����������A�X���E�q���Ƃ��ɑ卬���̂��Ȃ��ɂ��������Ƃ����������܂��B�x�����Ԃ͓X�܂ɂ���ĈقȂ�悤�ł����A�����邩����ł�1�`2���Ԓx�ꂪ�����A���ɂ͖`���̃c�C�[�g�̂悤�ɁA4���Ԕ��҂�����Ă悤�₭������Ƃ��������݂��܂����B
�@�܂��A�c�C�[�g�̒��ɂ́u�T�[�o�������炵�����l�тŃs�U5����������v�Ƃ���������A�N���X�}�X�C�u�ɂ�钍���E���ɉ����A�T�[�o�_�E�����d�Ȃ������Ƃł܂��܂������������\��������܂��B�܂��A�\��̎��_�Ŗ��炩�ɓX���̏����\�͂��Ă���̂��������Ă����ɂ�������炸�A�Ȃ����̂܂ܗ\����t���Ă��܂����̂��\�\�ƁA�\��V�X�e�����̂̐v�̊Â����w�E���鐺������܂����B
�@��̓I�ɂǂ̓X�܂Œx�����������Ă����̂���A�T�[�o�_�E���̏ڍׂȂǂɂ��Ă͕s���B�h�~�m�E�s�U����т��q�l���k�Z���^�[�ɂ��d�b���Ȃ��炸�A�ڍׂ��m�F���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B
�@�h�~�m�E�s�U�̓T�C�g�Ŏ��̂悤�ɎӍ߂��Ă��܂��B�u���̌��ʂ�[�����Ȃ��āA������悢�T�[�r�X��ł���悤�ɁA�X�^�b�t�ꓯ�Ŏ��g��ł܂���܂��B���̂��т͑�ϐ\�������܂���ł����v�i�Ӎߕ����j�B
-
���N���u�����c�Ɓv�̔�Q�������@�u��������2��3000�~�v�u�ޏ��Ȃ���X'mas�P�[�L�����w���v
�m���}�B���̂��߁A�Ј���A���o�C�g���s�v�ȏ��i�킳���u�����c�Ɓv�B�u���b�N��Ƃ�u���b�N�o�C�g�����ƂȂ�A�N�X�ӎ��͉��܂���邪�A����ł��Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂����Ԃ炵���B�N���X�}�X�����T���ɍT���A�l�b�g��ł͍��N���u�����c�Ɓv�ɂ܂��ߖ��������Ă����B
�u����Ȃ������炨�����Ȃ�Ă�߂�����v
���̎����A���N�b��ɂȂ�̂��N���X�}�X�P�[�L�ɂ܂�鎩���c�Ƃ��B�c�C�b�^�[��ł́A12�����{����R���r�j��X�[�p�[�Ȃǂ̃o�C�g��ŃP�[�L��\����ꂽ�A�Ƃ����������X�Əo�Ă���B
�u�o�C�g��ŋ����I�ɃN���X�}�X�P�[�L���킳�ꂽ�B�ޏ����Ȃ��̂ɔ����Ӗ��Ȃ��ł���ww�v �u�R���r�j�Ńo�C�g���Ă�킪�����I�ɃC�x���g�n�̕��i�����ƃN���X�}�X�P�[�L�Ƃ�)���킳�����Č����Ă���ǁA�R���r�j�o�C�g���Ăق�ƌo�c�҂������ȁv
���ɂ��A���N�̐����p�̂������̗\����������ꂽ�Ƃ����l���B
�u�Ȃ�ł�������2��3000�~������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂�H�Ј��͋����Ŕ��킹��Ƃ��Ӗ��킩��Ȃ����A����Ȃ������炨�����Ȃ�Ď��߂�����v
�����J���Ȃ�2015�N�Ɏ��{���������ł́A�R���r�j�Ńo�C�g����w����11.6�����u���i��T�[�r�X�̔����������v���ꂽ�v�Ɖ��Ă���B�w���̃A���o�C�g�ł���A10�l��1�l���u�����c�Ɓv���o�����Ă���Ƃ������ʂɂȂ����B�Ј����w���ȊO�̃A���o�C�^�[���܂߂�Ƃ��Ȃ�̊����̐l���u�����c�Ɓv�����v����Ă���\��������B
���������u�����c�Ɓv�́A�@���Ɉᔽ����ꍇ������B�u���v�߁v�Ƃ��āA3�N�ȉ��̒����ɏ������\��������Ƃ����B�܂��A�������珤�i�����V�������邱�Ƃ��J����@24���Ɉᔽ����\��������A�����l�Ƃ��Ă͐E��Ŏ����c�Ƃ�v������Ă������ɉL�ۂ݂ɂ��Ȃ����Ƃ��̗v�̂悤���B
�w���Ȃ�u�e�ɑ��k���܂��v�ƌ����̂��L��
��s���N���j�I���ɂ��ƁA�u�����c�Ɓv�ɂ܂�鑊�k�͈�N��ʂ��Ċ��邪�A���̎����ɂ̓N���X�}�X�P�[�L�₨�����A�N���ɂ��Ă̑��k��������Ƃ����B
�u�N���X�}�X�P�[�L�₨�����̏ꍇ�������ł����A���ɂ��A�X�Lj����A�N������炳�ꂽ�Ƃ������������܂��B��ʂɔ���������N���������V���b�v��`�P�b�g�V���b�v�ɓ]�����邽�߁A���������V���b�v�ɂ͂�������̔N����т܂��v
���������u�����c�Ɓv��������ꂻ���ɂȂ�����ǂ���������̂��B��s���N���j�I���̒S���҂́A�u�f�邱�Ƃ��ł��Ȃ���A�Ƃ肠�������̏�ł͕Ԏ������Ȃ��悤�Ɂv�ƒ��ӂ𑣂��B
�u���ƒf�����ꂪ��Ԃ����ł��B����������ꍇ�ɂ́A���̏�ŕԎ������Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B�w������ƍl�������Ă��������x�Ƃ����ĕԎ���扄���ɂ�����A�w���ł���w�e�ɑ��k���܂��x�ƌ������肵�ĞB���ɂ��Ă����܂��傤�v
�L�^���c���Ă������Ƃ�����BIC���R�[�_�[�Ř^���ł���悢���A���ꂪ�ł��Ȃ������ꍇ�����̓��̂����Ƀ���������Ă����ƌ�Ŗ𗧂Ƃ����B
���͂╗�����ƂȂ����u�����c�Ɓv���A�Ȃ��Ȃ���͂���̂��낤���B -
�@��ăE���O�A�C����A�O�哝�̂̃z�Z�E���q�J�����߂ē��{�ɂ���ė����͍̂��N�S���̂��Ƃ������B�P�T�Ԃ̑؍ݒ��A��������̉���������A�����̊w���Ƃ��G�ꂠ�������q�J����B�A����́A���{����{�l�ɂ��ăX�s�[�`�̂Ȃ��ŐG���@��������Ƃ����B�u���n�v���т��N�l�����Ƃ̖ڂɁA���{�̉����A�ǂ��f�����̂��B���ꂩ�琢�E�́A�ǂ��ς��̂��B���t�ɑ����A�X���ɍĂсA��s�����e�r�f�I�Ƀ��q�J����ɉ�ɍs�����B
�����{�b�g�͏�������Ȃ�
�@�\�\���{�K��̂P�J���O�A���q�J����͎��̎�ނɁA�u���{�̂��܂��A�悭�m�肽���B���{�ŋN���Ă��邱�Ƃ̂Ȃ��ɁA������m��肪���肪����悤�Ɏv���v�Ƙb���Ă��܂����B���ہA���{��K�˂Ă݂ĉ��������Ă�����̂�����܂������B
�@�u�ЂƂS�z�Ȃ��Ƃ�����B�Ƃ����̂́A���{�͋Z�p���ƂĂ����B�������ŁA���������ӂɂ͘J�������̈���������������B��������{�͌o�Ϗ�̕K�v����A�����Ƌ������邽�߂ɁA���{�b�g�̎d���𑝂₳�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�Z�p�����{�����邩��A����̓��{�b�g���O�����Ă����ŏ��̍��ɂȂ��Ă����̂��낤�B�����A����ɔ����āA���ꂩ����{�ł͗l�X�ȎЉ��肪�\�ʉ����Ă��邾�낤�B�����ꐢ�E�̂ǂ̐�i���������邱�ƂɂȂ�A�Ő�[�̖�肾�B�m���ɁA���{�b�g�͑f���炵����B�ł��A����͂��Ȃ�����v
�@�\�\���{�ł͓��s����������̐l���琺���������Ă��܂����B���{�̐l�X�ɂ��āA�ǂ�Ȉ�ۂ������܂������B
�@�u�ƂĂ��e�ŁA�D�����āA��V�����������B������ۂɎc�����̂��A���{�l�̋Εׂ����B���E�ň�ԁA�Εׂȍ����̓h�C�c�l���ƁA����܂Ŏv���Ă������A���̊ԈႢ�������B���{�l�����E�ꂾ�ˁB���Ƃ��A���X�g�����ɓ�������A�X�����݂�ȋ��тȂ��瓭���Ă������v
�@�\�\�ǂ�����ۂɎc�����X������܂������B
�@�u���s���B�f���炵���Ǝv�����B���{�͂��̕����A���̗��j�������Ă͂����Ȃ��v
�@�u�����A���s�Ŕ��܂����z�e���ŁA�w���{�l�̓C�J��Ă���I�x�Ǝv�킸����ł��܂����邪����B�g�C���ɓ�������A�֊�̂ӂ�������ɊJ����������肷�����B����Ȃ��Ƃ̂��߂ɒm�b���i��Ȃ�āA�܂��Ɏ��{��`�̋����}�j�A�̎d�Ƃ��ˁB�d�����u���V�����ċ������B�Ȃ�ŁA����Ȃ��̂��K�v�ȂH�@�����̎�����Ė����ςޘb���낤�B���ʂȂ��ƂɁA�Ƃ��ꂷ���Ă���悤�Ɏv�����ˁB����ɁA���܂�ɂ��ߓx�ȕ֗����́A�l�Ԃ��キ����Ǝv���v
�@�u�ƂĂ������A�Ǝ��̗��j�ƕ������������Ȃ̂ɁA�Ȃ��A�������܂Ő��m�������̂��낤�B�ߗނɂ��Ă��A�����ɂ��Ă��B�L���̃��f�������m�n���������B������ʂŐ��m�I�Ȃ��̂��̂����Ă��܂����悤�Ɍ������B���̂Ȃ��ɂ́A�������̂����邪�A�悭�Ȃ����̂�����B���{�ɂ͓Ǝ��́A�ƂĂ���������Ă��āA�e��ȂƂ���̂Ȃ��A���m������ۂǑ@�ׂȕ���������̂ɁB���̗��j���A���܂̓��{�̂ǂ��ɐ����Ă���낤���ƁA���^��Ɏv�����Ƃ��������v
���L���ȍ��قǍK���ɂ��ĐS�z����
�@�\�\�Q�O�P�T�N�ɑ哝�̂�ނ��Ă���K�ꂽ���ŁA�l�X�̔����͓��{�Ɠ����ł������B
�@�u�ޔC��ɍs�����̂̓g���R�A�h�C�c�A�p���A�C�^���A�A�X�y�C���A�u���W���A���L�V�R�A�č����B�s������Ŏ��͂悭��w��K���B�N�V���Ă͂��邪�A�Ȃ�����҂����Ƃ́A���܂������v
�@�u�����ŋC���������A�ǂ��ɍs���Ă��A�����̐l���K���ɂ��čl���n�߂Ă���B���{�����ł͂Ȃ��B�ǂ��̍��������Ȃ�v
�@�u�L���ȍ��ł������قǁA�K���ɂ��čl���A�S�z���n�߂Ă���B��Ăł́A�������͂܂��V���[�E�B���h�[�̑O�ɓ˂������āA�w�����A�������i���Ȃ��x���ĊԔ����ʂ����Ă��邯��ǁA���łɂ�������̃��m�������Ă��鍑�X�ł́A���������ĎԂ��ւ��邱�ƂȂɂ́A���͂�O�����l���o�n�߂Ă���悤���v
�@�\�\�l�X���K���ɂ��čl���A�S�z���n�߂Ă���̂́A�Ȃ��ł��傤���B
�@�u�����炭�A���������͍K���ł͂Ȃ��A�l���������ɉ߂������Ă��܂��Ă���A�Ɗ����Ă��邩�炾�Ǝv���B�̂̌Â����E�ł́A�@���Ɉ��炬��������l�������B������������������ł́A�M�S���Ȃ��Ȃ�������v
�@�\�\�u���E�K���x�����L���O�v���ƁA���{�͂T�R�ʂ������ł��B
�@�u�����͔ƍ߂͏��Ȃ����A���E�������B����͓��{�Љ���܂�ɂ������Љ���炾�낤�B�K���Ɏd�����������ŁA�����Ɛ����邽�߂̎��Ԃ��c���Ă��Ȃ�����B�Ƒ���q�ǂ�������F�l�����Ƃ̎��Ԃ��]���ɂ��Ă��邩��A���낤�B�����߂��Ȃ�v
�@�u���������������Ԃ����炵�A���������Ƒ���F�l�Ɖ߂������Ԃ𑝂₵����ǂ����낤�B���܂�ɂ��d���ɒǂ��Ă���悤�Ɍ����邩��B�l���͈�x����ŁA�����ɉ߂������Ă��܂���v -
���x�́u���傤���g���O�ŋ��������j�v���l�b�g�ʼn���@�����Ɓu�B�e�҂���肵�A�x�@�ɒʕ�E���k���Ă��܂��v
�@�����Ƃōg���傤���p�̃g���O���g���ċ����������A���̗l�q�z�M���Ă���Twitter���[�U�[�����サ�A�l�b�g�Řb��ɂȂ��Ă��܂��B�����Ƃɂ��A���Ɍx�@�ɂ͑��k���Ă���A���݂͌x�@���̔��f��҂��Ă���Ƃ̂��ƁB
�@���̔z�M���s��ꂽ�̂�12��10���B�z�M�ł͒j�����g���傤���p�̃g���O���g���ċ�����������������A�g���O��H�ׂ����̊�ɓ��ꂽ�܂܋�����H�ׂ��肵�Ă���l�q���ʂ��Ă��܂����B�܂����H��ɂ͒j�����e��ɏ悹�Ă���悤�ȗl�q���ʂ��Ă���A�l�b�g�ł͂���ɑ��u�s�q�����v�Ȃǂ̔ᔻ������������B������Ă����Ƃ�13���A�����T�C�g�Łu���łɎB�e�҂���肵�A���x�@�ɒʕ�E���k���Ă���܂��v�u���q�l�ɂ͂��S�z�E�����f�����������邱�Ƃ��A�[�����l�ѐ\���グ�܂��v�Ƃ̎Ӎ߁E���m�点���f�ڂ��Ă��܂��B
�@�����Ƃ̍L��S���҂ɖ₢���킹���Ƃ���A���Б�������ɂ��Ĕc�������̂�11�����_�ŁA���̋q����̃��[���ʕ�Ŕ��o�����Ƃ̂��ƁB����̓��e�ɂ��Ċ��z���ƁA�u�s�q���ȑΉ����Ǝv���܂����B������̔�Q�Ƃ������A���q�l���s���Ɏv���Ă��邱�Ƃɂ��Ĉ⊶�Ɏv���܂��v�ƃR�����g���܂����B
�@�j���͂��̌�Twitter�ŁA����̔z�M�ɂ��āu�����f���������������X�ɂ͐S��肨�l�ѐ\���グ��Ƌ��ɋ݂𐳂�����̑Ή������Ă������Ǝv���܂��v�ƎӍ߁B�z�M���e�ɂ��ẮA�u��������30���̑��H���ŃL���O�����i�����j���[�j�����H����v�Ƃ�����悾�����Ɛ������܂����B�����A�g���O��e��ɏ悹�Ă������Ƃɂ��Ă͔F�߂Ă�����̂́A�g���O�ŋ����������������Ƃ̎w�E�ɂ��ẮA�����܂Łu�������悤�Ɍ����������v�Ɛ����B�܂��A�e��ɏ悹���悤�Ɍ������̂��u�悹���ӂ�v�ł������Ɣے肵�Ă��܂��B -
�u�����p�v���P�n����ɂ��Č��������ӊ��N�@���P�n�}���V�����Ŏʐ^�B�e��Z���X�y�[�X�̐N���Ȃ�
�@TBS�n��ŕ������̃h���}�u������͒p�������ɗ��v�̌����T�C�g��12��17���A���P�n�̏���ɂ��Ē��ӊ��N���܂����B
�h���}�͖����ŏI����I���܂������A�����T�C�g�ɂ��ƁA�h���}�̃��P�n�ł���}���V�������t�@�����K��āA�ʐ^���B�e������A�Z���X�y�[�X�ɓ���ȂǁA���f�ȈČ����m�F����Ă���Ƃ̂��ƁB�u�������݂��������������P�n�́A�h���}�Ŏg�p����Ă͂��܂����A��ʂ̕����������鋏�Z�n�ł��B���̂悤�ȍs�ׂ͂��T�����������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��v�ƒ��ӂ��Ă��܂��B
�@�܂��A���h���}�̋r�{��S�����Ă���r�{�ƁE��؈��I�q��������g��Twitter�ŁA�u�ߗׂɖ��f��������ʂ悤���肢���܂��v�ƃc�C�[�g���܂����B
�@���̂悤�Ȃ�����u���n����v�Ɋւ���g���u���́A2016�N�ɑ�q�b�g�����f��u�N�̖��́B�v�ł��N���Ă���A9���Ɍ����T�C�g���u�ߗׂ̕��X��葛���⑁���[��̖K��Ɋւ�����𑽐����������܂����v�Ƃ̒��ӂ��f�ځB�ߓx����s������у}�i�[��S�|����悤�Ăъ|���Ă��܂����B -