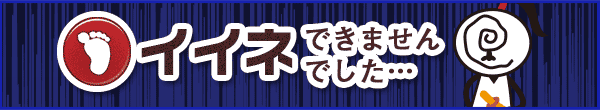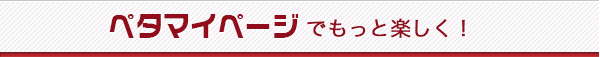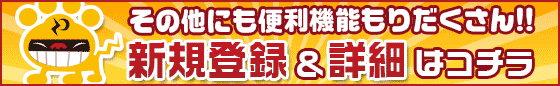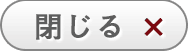カオス帝国〜リターンズ
-
スレッド一覧
- 雑談!! (241)
- たった一言!! (814)
- つぶやき!! (459)
- 生駒ちゃん (851)
- 画像!! (451)
- 芸能スレッド (1013)
- 名言!!!!!!!!!! (985)
- イマジン〜想像力育成講座〜 (256)
- 面白画像(≧▽≦) (884)
- MUSIC♪♪♪ (654)
- ヌコスレ(=^ェ^=) (688)
- 事件,事故!!( ; ゜Д゜) (471)
- 修造松岡!! (103)
- 俗にいうオカルト系(;゜∀゜) (299)
- (50)
- 豆知識 (677)
- つまるところこの人は美しい (307)
- 世 (112)
- JRA (1448)
- The パチ!!!!!!〜懐かしの〜 (457)
- 飲み食い市場(´・c_・`) (385)
- (140)
- サイエンス (202)
- 映画!!DVD!!ドラマ等々!! (157)
- AVタイトル‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- 復活!いい話スレ(ToT) (37)
- (80)
- つまるところこの人は美しい 本編 (33)
- (654)
- フラグ成立!!(^_^)/~~ (39)
- 笑 (392)
-
火星に液体の水がある可能性が高まった――。9月末、アメリカ航空宇宙局(NASA)がこう発表しました。これを裏付ける証拠が見つかったというのです。そうなると、「火星にも生命はいるのか」という期待が沸いてきます。
ここでは、火星にNASAの発表通りに「液体の水」が存在したと仮定して、どんな生物がいるのか、地球にいる生物を参考に探っていきたいと思います。魚やカニみたいな生物がいたらいいなと期待する一方、発見されたとしても微生物のような小さな生物だろうと思われる方が多いのではないでしょうか。どのような生物ならば火星にも生存できそうか、地球の生物を参考に想像してみましょう。
ここからは、地球と火星の水の違いが、どのように生物に影響を与えるのか、水の塩分濃度と酸性かアルカリ性か、という水質の2点に注目していきます。
はじめは塩分濃度についてです。塩分濃度が高い環境は多くの生物にとって過酷な環境です。
多くの生物は体の中に水を蓄えて生きているという話をしました。自分の体液よりも塩分濃度が高い塩水で過ごすと、体液中の水が出ていってしまうため、生きていけません。キュウリを塩もみして、キュウリの水分を出すことができますが、これと同じです。私たち哺乳類は、皮膚のバリア機能が優れているので、すぐに水分を失うようなことはありませんが、バリア機能が未発達の生物だったらひとたまりもありません。
続いて、酸性・アルカリ性に注目すると、強酸性・強アルカリ性といった極端な環境下では、生物の膜や殻などが破壊されてしまうためやはり生きていけません。私達の普段の生活でも、酸性やアルカリ性の強い薬品を扱う際は、手袋を着けます。もし、皮膚に薬品がかかってしまったときは急いで水で洗い流す、ということをして皮膚の破壊を防いでいます。
しかし、地球には、過酷な環境で生きている生物がいます。どのような生物がいるか、その一部を紹介したいと思います。
まずは、塩分濃度が高い環境で生きている生物「アルテミア」です。アルテミアはアメリカのグレートソルト湖をはじめとした、20%以上もの高い塩分濃度でも生きることができます。
また、卵は完全に乾燥しない物質を含んでいるため、乾燥した状態に置かれても10年以上耐えることができます。高い塩分濃度のみならず、乾燥という悪条件の中でも耐えられるため、絶滅することなく今まで生き延びることができたと言われています。
続いて、極端な酸性・アルカリ性に強い生物です。北海道の噴気孔で発見された「ピクロフィルス」という細菌はpH0.7という驚異的な酸性環境下でも生きることができます。人間ならば、皮膚が焼けただれてしまうくらいの酸性度です。
[画像]イデユコゴメ(ウィキペディアより引用)
他にも、温泉に生息する「イデユコゴメ」という紅藻の一種はpH0.24まで生育可能であるという報告があります。強固な細胞壁を持つ上、その外側にガラス成分である珪酸を沈着することで溶けずにいられるのです。
一方、アルカリ性に強い生物として挙げられるものは、「アルカリフィルス・トランスバーレンシス」という、南アフリカの地下3200mから採取された細菌です。pHが8.5〜12.5という非常に過酷なアルカリ性の環境下で発見されています。
火星にいるとしたら……?
[画像]昔の火星のイメージ図(NASA/GSFC)
これまでの火星の調査や研究によって、火星も地球と同じように様々な気候変動を経験しており、昔は火星にも海があったと考えられるようになりました。具体的には、約40億年前〜35億年前の火星には大量の水が地表と地下に存在していたと考えられており、その火星の水は10億年程度の時間を経て、アルカリ性の状態から、現在のような酸性の状態へと変化したと推定されています。このようなことをふまえ、火星は過去のある時期に、今よりももっと生命に適した環境があったと考えられているのです。
そして、このような生物に適した環境下でいくつかの生命が生まれたとすれば、それらを完全に絶滅させることは難しいといわれています。地球の過酷な環境でも生きている生物がいることはこれまで紹介してきた通りです。いまこの瞬間にも、火星の液体の水という過酷な環境で生きている生物の存在を期待し、どんな生物が火星にいるかを想像しながら、気長にその発見を待っていただけたらと思います。 -
地球は46億年前に誕生したといわれています。そして生命は約40億年前に生まれ、わたしたちホモ・サピエンスの種が初めて現れたのは、およそ20万年前。地球の長い歴史を1年に置き換えた場合、人類は12月31日午後11時半過ぎにようやく出現したと例えられるほど、わたしたち人間の歩みは実は、とても短いものです。
人類出現まで、地球はどのように環境を変え、生き物はどのように進化してきたのか―。古生物学者の池尻武仁博士(米国アラバマ自然史博物館客員研究員・アラバマ大地質科学部講師)が、世界の最新化石研究について報告します。
----------
2016年8月31日付けの学術雑誌NATUREに「世界最古」とされる生物化石の研究が発表された。
> (http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7621/full/nature19355.html)
グリーンランド南東部の37億年前と推定される地層から見つかった今回の化石は、非常に斬新で興味深い発見といえる。
> (発掘現場の風景:https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160831172441.htm)
37億年前。長い地球の歴史において、どれくらい古い地質年代にあたるのか、想像がつくだろか?地球の誕生は約46億年前と推定されている。多細胞生物(=動物)の最古の化石が約6億年前。最古の脊椎動物は5億年前頃。恐竜がはじめて現れたのが約2億3千万年前で、(2016年10月現在)知られている限り最古の人類は280万年前だ。
それまでに見つかった最古とされる生物化石は、約35−36億年前の地層からのものだった。バクテリアの仲間で単細胞生物の個体の化石だ。顕微鏡でなんとか観察・識別できるサイズの生物だ。今回の発見はそれよりも1−2億年は古いことになる。
「世界最古の生物化石」に関する研究発表は専門の学術雑誌などで時々目にする。しかし、こうした生物グループにおいて、化石標本にもとづくはっきりとした正体の確認・判定はなかなか簡単ではない。まずその性質が単細胞生物という点による。骨や歯のような化石としてよりと保存されやすい硬質の体の部位は見あたらない(ほぼ水分とタンパク質系の物質からなる)。実際岩石などから派生した「ただの鉱物の粒ではないか?」「火山灰ではないのか?」こうしたクレームや疑念の目が他の研究者から常に向けられる運命にある。
そして多細胞生物のものと比べバクテリア類の細胞のサイズは極端に小さい。バクテリアの細胞はわずか0.0005−0.005mm(0.5−5.0μm)ほどだ。(ちなみに人間の体細胞は種類によって1−2ミリにもなる。)こうした条件を顧みれば、何十億年以上の長い時を経て、化石として保存および発見されること自体、奇跡的な出来事だと分かるだろう。
さて、今回の発見が多くの古生物学者(化石研究者)や太古地球環境における地質学者達から(少しばかりの驚きとともに)強い興味をもって迎えられているのは、まず単にバクテリアの個体化石ではなく「ストロマトライト」として判定されている点にあるようだ。ストロマトライトとは、主にシアノバクテリア(いわゆる藍藻類)の幾つかの種によって形成されたと考えられる構造物をさす。この生物グループは基本的に緑色をした光合成を行う多数の細菌類で、ネンジュモなど寒天状の食材(中華料理の髪菜など)もこのグループに分類されている。
一部のシアノバクテリアは、興味深いことに多くの個体が密集し土砂などを利用して大きな家のような構造物をつくる(建てる)。ちなみにストロマトライト(英名:Stromatolite)とはギリシャ語のstroma+lithosから派生し、直訳すると「マットレス状、層状の石」という意味で、文字通りこの建造物を端的に表している。(これほどふさわしい生物グループの名前もなかなか見あたらないといえばおおげさだろうか。)私を含む多くの古生物研究者にとって、無数にある化石グループや種などの名前を覚える際、その語源やオリジナルの意味をチェックすることは非常に重要だ。
イメージ2:アラバマ州カンブリア紀の地層(約5億年前)で筆者が見つけたストロマトライトの化石。独特の幾重ものライン構造が見られる
こうした構造物(ストロマトライト)の存在は、1960年代の発見以来、オーストラリアの一部の海岸沿い(シャーク湾など)やカナダ西部の淡水湖など、非常に限られた地域において、現生種のものが直接観察することができる。サッカーボール大程のものが遠浅の温暖な海や湖の沿岸に、かなり広範囲に何千何万と群がっている。ちょっとしたさんご礁のような独特の趣でなかなかの壮観だ。
現生のストロマトライトは(植物のように)光合成を行うため、年間を通し強い太陽光が降り注ぐ場所でしか生息できない。このストロマトライトだが波が激しく打ち寄せたり風雨の強い場所では、なかなかその構造物を維持できないようだ。温暖で静かな環境を好むライフスタイルは、太古の昔から引き継がれてきたものと考えられている。
このストロマトライトの構造はかなり独特だ。何重にもライン状の層がみられる(年間1−2ミリほど厚さで層が積み重なるようだ)。そして、この独特の構造物は化石として非常によく見つかる。その構造状、比較的簡単にその判定を下せるので、見間違うことも少ない。(今回発見された化石も1−4cmくらいで積み重なった層が確認されている。)
化石記録におけるストロマトライトの存在は、25億年前から5億年前頃(原生代初期から顕生代初期)の地層から非常に多数、世界各地において知られている。実際私も、ここ北米アラバマ州の約5億年前(カンブリアン紀)の地層で、非常に多数の化石が見つかる場所を知っている(イメージ2参照)。しかし生物の歴史上、25億年より古い時代の地層からはあまり知られていない。
生物がバクテリアの仲間として初めてこの惑星に誕生したのが、(現生バクテリアのDNAなどのデータによって)約40億年前と推定されている。そのすぐ後、37億年前頃に、太古の生物ははたしてどのようにしてストロマトライトのような、一見壮大でしゃれた見かけの建造物をつくる技術を進化上、手に入れたのだろうか?「シンプルから複雑なものへの変遷」とういマクロ進化の流れに反してはいないだろうか? 一古生物研究者の戯れ言として聞き流しておいて頂けたら幸いだ。 -
【AFP=時事】西南極(West Antarctica)にある巨大氷河では、7年間で最大500メートルの厚さの氷が失われ、科学者らの予想を超える急速なペースで氷河が減少しているとの研究結果が25日、発表された。
米航空宇宙局(NASA)による上空からの調査で収集されたデータに基づく研究論文によると、南極のアムンゼン海(Amundsen Sea)に注ぐスミス氷河(Smith Glacier)は、2002〜2009年の期間に年間最大70メートル薄くなったという。
論文の主執筆者で、NASAジェット推進研究所(JPL)の研究者アラ・カゼンダール(Ala Khazendar)氏は「1種類の測定器だけで収集されたデータを使っていたら、目にしている結果を信用しようとは思わなかっただろう。それほど、薄化の度合いが大きかった」と述べた。
氷の厚さを測定するアイスレーダーと、レーザー高度測量の両方で同じ結果が得られたと、カゼンダール氏は英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に掲載された論文で報告している。
スミス氷河では、2009年以降も氷塊の消失が続いたが、そのペースはわずかに減速したと、カゼンダール氏はAFPの取材に語った。
より精度の低い測定技術を用いたこれまでの研究では、スミス氷河から延びる2つの棚氷は、同期間に年間約12メートル薄くなったと推算されていた。
この研究結果は、温度が上昇した海水が南極の氷河の底部、特に氷河が海と接触する「接地線」付近を以前より速いペースで浸食していることを示す新たな証拠だと、カゼンダール氏は語った。
「南極大陸の一部では、主に降水量の増加で氷の量は増えているかもしれないが、同大陸全体でみた場合、氷の量は大きく減少している」、「この氷河系は均衡が崩れており、氷が解けるペースは氷河流による補充を上回っている」と、カゼンダール氏は話した。【翻訳編集】 AFPBB News -
恐竜以外にも、いろいろ面白い生き物がいたんですね。
約1億年前の琥珀の中から、今は存在しない種の寄生バチが発見されました。羽がなく、飛ぶ代わりにバッタのように跳ねていたとか。
Aptenoperissus burmanicusと名付けられたこの寄生バチは、非常に良い保存状態で琥珀に閉じ込められているのを、白亜紀の化石が豊富な鉱床として知られるミャンマーのフーコン渓谷で発見されました。バッタのたくましい後肢を持つという科学者やゴキブリの分厚い腹部を持つという科学者もいる、あまりに特異な見た目だったため、これがハチであるかどうかについての議論には長い時間が費やされました。
結局、オレゴン州立大学の生物学者George Poinar氏は、この変わった形の生物はスズメバチやミツバチ、アリなどからなる昆虫目である膜翅目の一種だと判断しました。同氏はphys.orgで「その顔はほとんどスズメバチのように見える」とし、この生物が既存の分類の「どこにも当てはまらなかった」ため、Aptenoperissidaeという新たな科を作ったことも語っています。
Cretaceous Researchに執筆した内容によれば、Poinar氏と同僚たちはこの寄生バチをメスと断定したとか。長い脚を使って地中に穴を掘り、他の昆虫のさなぎの中に卵を産み付けたのだろうと推測しています。被害を受ける昆虫が防御しようとすれば、おそらくA. burmanicusは跳躍力のある脚を使って飛び出して、鋭利でギザギザな毒針で攻撃したのでしょう。研究者たちいわく、羽は邪魔になったのだろうとのこと。
Aptenoperissus burmanicusは既に絶滅していますが、もしこんなおっかない捕食者が白亜紀末の大量絶滅を生き延び、現在も生息していたとしたら…。生態系は大きく変わっていたかもしれません。 -
欧州発の火星探査機「スキアパレッリ」、着陸直前に通信途絶える
火星に起こる砂嵐の解明めざす
欧州とロシアの宇宙機関が火星へ送り込んだ着陸機が、表面への着陸に失敗した可能性がある。
火星の大気などを調査する周回機「トレース・ガス・オービター」は、10月19日、無事に火星の軌道に入ったと当局が発表していた。しかしその後、着陸機「スキアパレッリ」が火星着陸まであと1分のところで通信が途絶え、欧州宇宙機関(ESA)は無事着陸したことを示す信号を確認できていないという。
心配されるのは、2003年に着陸失敗に終わった、同じESAの着陸機「ビーグル2」の再現だ。現在当局は、他の火星周回機を含む複数の情報源からデータを集めて検証し、「スキアパレッリ」の状態を確認する作業を進めている。
失敗したとすれば、大きな痛手になる。着陸機「スキアパレッリ」は、ESAとロシアの宇宙機関ロスコスモスが共同で行うエクソマーズ(ExoMars)計画の一部だ。スキアパレッリの主な任務は、降下・着陸技術のテストだった。ESAとロスコスモスは、2021年に火星に送り込む予定の探査車でこの技術を使おうと計画しているためだ。
スキアパレッリが着陸に失敗した場合、技術的な試験に次ぐ第2のミッションも果たせなくなる。火星の砂嵐の調査だ。
NASAゴダード宇宙飛行センターの惑星科学者、マイケル・スミス氏は、「塵の粒子は非常に小さいので、どんなところにも入り込みます」と話す。「火星探査車の写真を見れば分かりますが、いずれも汚れています。ソーラーパネルも塵で覆われますが、探査車が稼働を続けるためには最低限の電力が必要です」
しかも、砂嵐は電場を作り出す。このような地球以外で起こる旋風が通信を妨げたり、電子機器を故障させたりする可能性があるのか見極めるため、科学者たちはこうしたエネルギーの測定に強い関心を抱いている。
厄介な砂嵐
火星の季節は地球上のそれとは異なる。火星の自転軸の傾きは地球よりわずかに大きく、軌道はずっと長いためだ。火星の1年間では、太陽までの距離は約2億600万キロから2億4784キロまで変化する。
ダストデビルとも呼ばれる小規模な塵旋風は1年を通じて起きているが、広範囲にわたる嵐は、火星が太陽に最も近づき、受けるエネルギーが40%増えるときに発生する。このエネルギーの大半を受け取るのが、火星の南半球だ。
強い太陽光が地表に降り注ぐと、地表近くの空気が暖められて上昇する。風が吹き始めて砂粒を巻き上げ、千分の数ミリという非常に細かい塵の粒子が空中に舞い上がる。
NASAジェット推進研究所の惑星科学者、ジェームズ・シャーリー氏は、「軽くてふわふわした細かな塵の粒子が一度大気中に浮き上がると、なかなか降りてきません」と話す。
火星の大気は薄く、地球の海面上に比べると1%ほどしかないため、塵を大量に含んだ風はそれほど強い威力になるわけではない。スミス氏は、映画「オデッセイ」で宇宙飛行士のマーク・ワトニーが砂嵐に襲われ、火星に取り残されるはめになったのに触れて、「ロケットを吹き飛ばしたり、アンテナやなんかが宇宙飛行士に刺さったりするようなことにはならないでしょう」と話す。
それでも、風速は時速数十キロにもなり得るため、視界を妨げたり、あるいは機器の故障につながったりするかもしれない。「動き回る機械には、必ず接合箇所があります」とスミス氏。「それらをすき間なく密着させておかないと、機器の中に塵が入り込んでしまいます。そのような状態は望ましくありません」
塵が鏡やレンズを覆い、科学機器をだめにしてしまうこともある。2007年の嵐では、探査車「スピリット」と「オポチュニティ」の熱赤外線分光器が壊れ、地表の組成分析を行う機器の一部が取れてしまった。
最も懸念されるのは、塵がソーラーパネルを覆ってしまうことだろう。スミス氏によると、2007年の砂嵐に遭った「スピリット」と「オポチュニティ」は、稼働し続けるために太陽光で発電するヒーターが必要だったため、活動も短期間に設定されていた。いずれも砂嵐の中を持ちこたえたが、「今も稼働中のオポチュニティが再び同様の砂嵐に襲われれば、老朽化もあって大きなダメージになるでしょう」とスミス氏は言う。
間もなく嵐が発生か
火星では時折、局地的な砂嵐がいくつも合わさり、全球的な現象になる。「火星全体の風の吹き方は、地球によく似ています。ジェット気流と、大規模な流れのパターンです」とシャーリー氏。「大抵の場合、砂嵐は温度が上がる夏に南半球で始まります。塵が十分な高さまで持ち上げられると、風の流れに乗って別の地域に運ばれます」
仮に複数の砂嵐が起これば、塵による煙霧は赤道を超えて広がり、北半球に入り込む。そして、遂には火星全体を包み込むまでになり得る。
だが、このような全球規模の砂嵐は毎年起こるわけではないため、科学者たちはパターンを見つけ出そうと苦心している。1924年以降に9回発生しており、直近の5回は1977年、1982年、1994年、2001年、2007年だった。
これについて、シャーリー氏は天体力学に基づいた有力な説を出している。軌道上を周回する火星の運動量は他の惑星から影響を受けており、その影響の大きさは一定の周期で変動する。
この点を考慮し、シャーリー氏は砂嵐シーズンの初めに火星の運動量が増加していると、全球規模の砂嵐が起こる傾向にあることを突き止めた。この説が正しければ、火星では今後数週間から数カ月以内に、全球を覆う砂嵐が起こることになる。
「砂嵐が今日から始まっても全く驚きません」とシャーリー氏。
科学者たちの熱い期待
スキアパレッリが安全にかつ無傷で着陸できていれば、その後は火星での2〜8日間を気象観測に費やす。スキアパレッリは、砂嵐が生み出す電場を計測するための特殊な機器を積んでいることから、この段階では砂嵐も歓迎すべき客と言える。着陸機の動力源は内蔵電池なので、ソーラーパネルが塵で覆われるのを心配する必要はない。
砂嵐で電気現象が起こることは従来から知られていたものの、火星では1990年代後半のパスファインダー計画で初めて観測された。科学者たちは、砂嵐の季節ではないのに火星の大気中に大量の塵が含まれていることを発見。間もなく判明した「犯人」は、ダストデビルと呼ばれる塵旋風だった。
NASAゴダード宇宙飛行センターの物理学者ウィリアム・ファレル氏は、「明らかなのは、特に塵旋風の一番下で粒子がかき回されているということです」と話す。「小さな粒子は負の電荷を、重い粒子は正の電荷を帯びる傾向にあるということが分かりました」
火山の噴煙口の中と同様に、塵旋風の中では負の電荷を帯びた小さな粒子が垂直方向の風によって高く吹き上げられる。一方、正の電荷を帯びた粒子は低い高度にとどまる。「塵旋風の内部で、実際に大規模な電場を作り出せます」と、ファレル氏は話す。
ファレル氏によれば、火星で起こる大きな砂嵐の中でも電場は生じているかもしれないが、他の条件によって緩和されている可能性があるという。
地球上であれば、雷雲の中に電荷が蓄積され、限界を超えると放電が起きる。だが研究室でのシミュレーションでは、火星のように大気が薄い場合、過剰な帯電が起こりにくいとファレル氏は話す。
この現象を研究する機器を火星に送ろうと、ファレル氏は他の科学者たちと共に15年もロビー活動を続けてきたという。それだけに、エクソマーズの着陸機は、世界の火星研究者たちの関心を一層かき立てている。
「この問題の解明にスキアパレッリがいくらかでも貢献するよう、心から応援しています」とファレル氏は話している。 -
マウスのiPS細胞(人工多能性幹細胞)から体外で卵子を作ることに、世界で初めて成功したと、林克彦・九州大教授(生殖生物学)らの研究チームが発表した。
この卵子から健康なマウスが生まれることも確認したという。英科学誌ネイチャーに18日、論文が掲載される。
林教授は2012年、京都大の斎藤通紀教授らと、マウスのiPS細胞から卵子や精子のもとになる始原生殖細胞を作製、成体のマウスの卵巣に移植し、卵子を作ることに成功している。今回は卵巣への移植を経ずに、全工程を体外で実現した。
この手法を使えば、卵子が出来る過程を詳しく観察できるため、不妊症の原因解明や治療法の開発につながる可能性もある。一方で、生命の誕生につながる卵子を容易に作製できるようになると、生命倫理上の問題が浮上しそうだ。 -
エジプトのギザの大ピラミッド(Great Pyramid of Giza)」に、これまで知られていなかった2つの「空洞」が存在する可能性があることが、ラジオグラフィ(X線撮影)を用いたスキャン調査で判明した。ピラミッドの謎解明を目指すプロジェクト「スキャンピラミッド(Scan Pyramids)」の科学者らが15日、明らかにした。
これに先立ちエジプト考古省は13日、クフ王(King Khufu)の命により約4500年前に建てられたギザの大ピラミッドで「2つの異質な点」を発見したと発表。その機能や性質、大きさなどを特定するには、さらなる調査が必要だとしていた。
高さ146メートルのギザの大ピラミッドは、古代エジプト第4王朝のスネフル王(King Snefru)の息子であるクフ王にちなんで「クフ王のピラミッド」と呼ばれ、世界の七不思議の一つに数えられている。
「スキャンピラミッド」の科学者らは声明のなかで、ラジオグラフィと3次元再構築技術を用いた調査で大ピラミッドの北壁の裏に隠れた「空間」が存在することを確認したと発表。大ピラミッドの内部に通じる通路を少なくとも一つ形成しているとみられるという。さらに、北東の側面にも「空洞」を発見したという。【翻訳編集】 AFPBB News -
44歳の英国人男性が、新しい治療法によってHIV(ヒト免疫不全ウイルス)が完全に消滅した世界初の人物になるかもしれない──現在、この男性を含め50人のHIV感染者が、「潜伏感染状態」にある細胞も対象とする新たな治療法の臨床試験を受けている。
臨床試験を行っているのは、英国のオックスフォード大学(University of Oxford)、ケンブリッジ大学(University of Cambridge)、インペリアル・カレッジ・ロンドン(Imperial College London)、ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ(UCL)、ロンドン大学キングスカレッジ(King's College London)の研究者ら。
英紙サンデー・タイムズ(Sunday Times)の取材に応じた研究者らによれば、今のところ、この男性の血液中にHIVは一切検出されず、この状態が続けば、初のHIV完全消滅症例ということになる。
英国立衛生研究所臨床研究部門(National Institute for Health Research Office for Clinical Research Infrastructure)の担当責任者、マーク・サミュエルズ(Mark Samuels)氏は、「HIV完全消滅を目指した初の本格的な試みの一つだ」として、「私たちはHIVを消滅させる真の可能性を探っている。これは大きな挑戦であり、まだ始まったばかりだが、目覚ましい成果が出ている」と語っている。
HIVがT細胞のDNAに侵入すると、T細胞の免疫機能が破壊されて病気に対して無反応になるだけではなく、ウイルス自体も増殖するため、HIV感染症の治療は非常に厄介だ。
現在一般的なのは抗レトロウイルス療法だが、この治療法では活性化しているT細胞には効いても、潜伏感染状態にあるT細胞は見つけることができない。
一方、新たな治療法は2段階で作用する。まずワクチンがHIVに感染した細胞を体に認識させて排除する役目を果たし、次に、「ボリノスタット(Vorinostat)」と呼ばれる新薬で潜伏感染状態にあるT細胞を活性化させ、免疫システムに検知できるようにする。
英国のHIV感染者は10万人以上と言われているが、そのうちの約17%が感染に気づいていないとされる。世界の感染者数は3700万人だ。
これまでにHIV感染症が完治した人間は世界で1人だけ。生まれつきHIV耐性を持つドナーから2008年に幹細胞移植を受けたティモシー・ブラウン(Timothy Brown)さんだ。【翻訳編集】AFPBB News
「テレグラフ」とは:
1855年に創刊された「デイリー・テレグラフ」は英国を代表する朝刊紙で、1994年にはそのオンライン版「テレグラフ」を立ち上げました。
「UK Consumer Website of the Year」、「Digital Publisher of the Year」、「National Newspaper of the Year」、「Columnist of the Year」など、多くの受賞歴があります。 -
永遠の命は「かなわぬ夢」か、米研究
AFP=時事 10月6日 10時16分 AFPBB News
【AFP=時事】人の寿命の「上限」を発見したとする研究論文が5日、発表された。この研究結果を受け、記録史上最も長生きした人物の122歳という金字塔には、誰も挑戦しようとすらしなくなるかもしれない。
米アルバート・アインシュタイン医科大学(Albert Einstein College of Medicine)の研究チームは、世界40か国以上の人口統計データを詳細に調べ、長年続いた最高寿命の上昇が1990年代に、すでにその終点に「到達」していたことを突き止めた。
最高寿命の上昇は、1997年頃に横ばい状態に達した。1997年は、フランス人女性ジャンヌ・カルマン(Jeanne Calment)さんが前人未到の122歳と164日で亡くなった年だ。
論文の共同執筆者で、アルバート・アインシュタイン医科大のブランドン・ミルホランド(Brandon Milholland)氏は、AFPの取材に「それ以降は、世界最年長者が115歳前後という傾向が続いている」と説明した。
こうした傾向は、医療、栄養、生活などの状態の向上を受け、平均寿命が伸び続けているなかでのものだ。
言い換えれば、最近は老齢期まで生きる人が増えているが、群を抜いて長寿命の人は、以前ほどの高齢には達していなかったということになる。
ミルホランド氏は、「このような(傾向)が当面の間、変わらず続くことが予測される」と指摘する。
そして「もう少し(115歳より)長生きする人がいるかもしれないが、今後どの年においても、世界の誰かが125歳まで生きる確率は、1万分の1に満たないと考えられる」としながら、「過去数十年間における医学の進歩は、平均寿命と生活の質(クオリティ・オブ・ライフ、QOL)を上昇させたかもしれないが、最高寿命を伸ばすことには寄与していない」と続けた。
■自然の限界
「寿命」は、個体が生存する期間がどのくらいかを表すのに用いられる用語で、「最高寿命」は、ある生物種に属する最も長命の個体が到達する年齢を指す。
他方で、「平均寿命」は、ある年齢層の人々が持つと見込まれる余命の平均値で、社会福祉の尺度となる。研究チームによると、平均寿命は19世紀以降、全世界でほぼ連続的に上昇しているという。
人間の最高寿命もまた、1970年代から上昇を続けていたが、現在は頭打ちの様相を呈している。
これは、「不老の泉」を見つけたいという一部の人々の希望をよそに、人の寿命に生物学的な限界がある可能性を示すものだ。研究チームは「人間の最高寿命は限定されており、自然の制約を受けるものであることを、今回の結果は強く示唆している」と論文に記している。
ミルホランド氏は、「それでもなお、不老長寿を追い求める人々は、今回の研究で明らかになった寿命の上限を超える、何らかの『未発見の技術』の登場への希望にすがりつくだろう」と予想する。そして「今回の研究はそうした人々のために役立つことをした。(われわれは)既存の医学の進歩が、最高寿命に影響を及ぼさないことを明らかにしたのだから」と付け加えた。
その上で、「従来型の医学の進歩に期待を寄せるのであれば、それは激しい失望に変わるであろう」とも指摘している。【翻訳編集】 AFPBB News -
2016年10月3日(月)英国の研究チームが、血液中からのHIVウイルス完全除去に成功したというニュースが報道されました。
研究内容としては、HIV感染症の新しい治療法を治験として行い、50人の患者のうち1人の身体からHIVウイルスの消滅が確認されたということです。
今回の大発見によって今後世界にどのような影響を与えるのでしょうか。医師に解説をしていただきました。
HIVウイルスとは
HIVウイルスは、日本では俗にエイズウイルスなどと呼ばれることもあるもので、私たちの身体の免疫に非常に大切な役目を持つTリンパ球やマクロファージなどに感染し、身体の免疫機能を著しく低下させてしまう状況をつくりだしてしまうものです。
このウイルスに感染し、AIDS(後天性免疫不全症候群)を発症してしまうと、通常はかからない菌やウイルスなどに日和見感染してしまう恐れがあります。
従来の治療「抗レトロウイルス療法」
治療法
何種類かの抗レトロウイルス薬を組み合わせることによって、HIVウイルスの体内での増殖を抑制する治療法。
欠点
HIVに感染後、潜伏している細胞に対しては効果が乏しい。
今回研究された新しい治療法
今回研究チームよって、効果が確認された今回の新しい治療法は、以下の2つの段階により構成されます。
1:まずワクチンを使用
まず、HIV感染患者さんにワクチンを使用して、体内にあるHIVに感染した細胞を取り除く。
2:新たに開発された「Vorinostat」と呼ばれる薬を使用
HIVに感染しているT細胞の機能を活性化し、患者さんの身体に本来備わっている免疫機能を賦活させることによって、HIVを攻撃し消滅を図る。
今回の発見が、今後世界や日本にどのような影響を与えるか
非常に大きな発見であり、今までは抗レトロウイルス薬でHIVの増殖を抑え、AIDSの発症を防ぐことが唯一の治療法であったHIV感染症を、とうとう根本から治せる治療法ができたかもしれないというところに非常に期待が持てますね。
患者さんは日本でも、それ以外の国でも数多くいらっしゃいますので、この治療法の有効性がより多くの患者さんで証明され、一般的にHIV感染症の治癒が期待できるようになれば、非常に大きな影響を与えるのではないでしょうか。
医師からのアドバイス
今までたくさんの方を苦しめてきたHIV感染症が、とうとう治癒する時代が来るかもしれないというとても希望の持てるニュースですね。
一日も早く、安全な形でこのような治療法が実用化されるといいですね。 -
日本列島の南側には深さ4000メートルの深い溝が横たわっています。これが南海トラフです。その南海トラフでこれまで想定されていなかったある動きが、名古屋大学の調査で初めて観測されたのです。この調査によって、巨大というより超巨大津波の恐れが高まっていることがわかりました。
名古屋大学の田所敬一准教授らの研究グループは2013年から3年間、和歌山県新宮市の約100キロの沖合いの海底の動きを調べてきました。その結果ー
「トラフ軸(海溝軸)の近くにも歪みをためていそうだ、陸に向かって押されてそうだ、ということがわかってきた」(名古屋大学大学院・地震火山研究センター 田所敬一准教授)
「トラフ軸」とは一般的には「海溝軸」と呼ばれていますが、フィリピン海プレートが陸側のプレートに沈み込む境界付近のことです。そこに歪みが溜まると、何が起きるのでしょうか。
静岡県の駿河湾から九州の東まで続く南海トラフの周辺では、100年から150年の周期で、M7あるいは8クラスの巨大地震が繰り返されてきました。巨大津波は駿河湾が震源の東海地震、その西の、三重県沖までを震源とする東南海地震、そして四国沖までを震源とする南海地震の、3つの地震が単独あるいは連動して起きたときに発生すると考えられてきました。
しかし・・・5年前の東日本大震災がその考え方を一変させました。どうしてあれほどまでの巨大津波が発生したのか?地震後、研究者らが調査したところ、従来、想定していなかった場所、「海溝軸」の周辺で地震が起きていたことがわかったのです。東日本大震災では想定されていた震源域に加え、海溝軸周辺でも地震が起きたことで、津波がさらに大きくなったのです。なぜ、海溝軸が動くと超巨大津波になるのか?
海のプレートが陸のプレートにちょうど入り込む「海溝軸」は、従来の想定された地震の震源域よりも浅い場所です。つまり海面に近い「海溝軸」の周辺が跳ね上がれば、短時間で大きな津波を引き起こすのです。東日本大震災では、この海溝軸周辺も跳ね上がり超巨大津波を発生させました。
南海トラフで同じことが起きる恐れはないのか。名古屋大学の田所准教授らは、深さ約3500メートルの海溝軸周辺の3箇所に観測機器を設置。海上の船から音波を出して海底の動きを監視してきました。その結果、南海トラフでも海溝軸周辺にひずみを溜めていることがわかったのです。
「南海トラフに非常に近くに場所、西北西に年間4センチくらい動いていることがわかった。この紀伊半島沖でプレート境界の近くが歪みをためているというのがわかったのは初めて」(名古屋大学大学院・地震火山研究センター 田所敬一准教授)
つまり次の南海トラフの地震でも、海溝軸で地震が起き、東日本大震災と同じような超巨大津波を引き起こす恐れがあることになります。田所准教授らはこの調査結果を来月開かれる日本地震学会で発表するとともに今後、さらに観測点を増やし、調査を続けることにしています。
そしていま、その巨大津波による被害軽減をめざして「ある技術」が注目を集めています。それは天気予報などで雨の粒を観測するレーダーの応用です。
津波防災を研究する関西大学の高橋智幸教授が目をつけたのが、すでに実用化されている「海洋レーダー」というもので、海岸に設置したアンテナから海面に向かって電波を発射し、波に反射した電波を受信して波の形などを観測します。現在、海洋レーダーは海流の観測をはじめ、海面にたまったゴミを発見し、船で回収することなどに使われていて全国各地に設置されています。この「海洋レーダー」が東日本大震災の津波を捉えていました。
「一般的に使われているレーダーは、ひとつの地点で5,60キロから200キロまで測ることができる。レーダーを1基いれるだけで相当広い範囲が測れる」(関西大学社会安全学部・高橋智幸教授)
現在、気象庁による津波観測はGPS津波計によるもので、海上に設置した装置が襲来する津波をひとつのポイントだけで観測します。しかし、レーダーでは何十キロにもわたり津波を面でとらえることができ、速さや高さもわかることから、海岸部の市町村に詳しい被害予測を伝えられるようになります。
超巨大津波の可能性が高まった次の南海トラフ地震。一方で、「津波レーダー」など新たなツールが活用できることが明らかになってきました。被害を軽減させる方策がますます重要になっています。 -
地球上の酸素量が減少し続けていることが、プリンストン大学のダニエル・ストルパー(Daniel Stolper)教授の研究により明らかになった。教授はグリーンランドや南極の氷に含まれる気泡を調査し、その結果をサイエンス誌に発表した。
氷の中の気泡を調べることで、古生代からの大気組成の変化を調べるとこができる。教授によると、過去80万年で大気中の酸素量は0.7%減少し、現在も減り続けているという。これは、海面と海抜100メートルの酸素量の差に匹敵し、幸いにも生物に深刻な影響を及ぼすレベルではないという。
酸素量は、地球全体のシステムが複雑に影響して変化するため、100万年近くもの間一貫して減少し続ける理由を特定することは極めて困難だ。今のところ科学者たちは2つの仮説を立てている。
なぜ酸素レベルは減少し続けるのか
一つは、岩石の侵食を原因とする説だ。鉄製品が酸素と結合して錆びるように、岩石も酸素と反応して風化し、その結果として大気中の酸素量が減少したというのだ。特に黄鉄鉱や有機炭素は多くの酸素を取り込む性質がある。
そうだとすると、世界規模で岩石の侵食が急速に進展した要因は何なのだろうか。科学者たちは、過去数百万年で氷期と間氷期が繰り返され、気温の急激な上下に伴って大陸を覆う氷のシートが増えたり減ったりして山々が侵食されたと考えている。地球の気温は今後も上昇を続け、2050年と2100年には過去数百万年で未曽有の高水準になることが予測されている。
もう一つの説は、PETM(Paleocene-Eocene Thermal Maximum)と呼ばれる、5,600万年前の地球温暖化の後に長く続いた寒冷化を原因とするものだ。海水温度が下がったことで酸素の溶解度が高まり、大気中の酸素量が徐々に減少したことが考えられる。コカ・コーラは温度が高くなるほど炭酸が早く抜け、冷蔵庫で保存すると長持ちするように、気体は液体の温度が低いほど溶解しやすい性質を持つ。
いずれの説の場合も、他に生物の多様化や火山活動の活発化など、様々な地球規模の変化が影響する。このため、科学者たちは膨大な量の地球科学データを読み解きながら、酸素が減少し続けるメカニズムの解明に挑み続けているのだ。 -
熊本大大学院生命科学研究部の尾池雄一教授(分子医学)の研究グループは、心筋細胞から過剰に分泌されたたんぱく質の一種が心不全を発症させることを発見した。心不全の新たな治療法の開発につながる可能性があり28日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ電子版に掲載された。
問題のたんぱく質は「アンジオポエチン様タンパク質2」。本来は組織の正常な働きを助ける作用があるが、心筋細胞内で過剰に分泌されると、細胞のカルシウム濃度の調節やエネルギーを生成する力を弱める。その結果、心筋の収縮低下を招き、心不全を引き起こすという。また、高血圧や加齢が過剰分泌の一因となることも突き止めた。
研究グループは、このたんぱく質の生成を抑えるウイルスを投与して、マウスの心不全進行を抑える実験にも成功。尾池教授は「将来は人への応用を考えている。3〜5年以内に臨床試験に入りたい」と語った。 -
地球上で最も耐性が高い生物と言われる極小の生物クマムシに特有のタンパク質が、X線による損傷から人間のDNAを保護する働きを持つとする驚くべき研究論文が20日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に発表された。
「Dsup(Damage suppressor 「ダメージを抑制するもの」の意)」と命名されたこの新発見のタンパク質とともに培養したヒト細胞は、放射線を照射された際に受ける損傷が通常の細胞の半分に抑えられた。
論文の主執筆者で今回の実験を設計した東京大学(University of Tokyo)の生物学者の橋本拓磨(Takuma Hashimoto)氏は本当に驚いたと語る。
橋本氏はAFPの取材に対し、クマムシ由来のタンパク質Dsupについて特筆すべき点は1個の遺伝子でヒト培養細胞の放射線耐性を向上させられることだと述べた。
科学者らは長年、クマムシの持つ強靱(きょうじん)な生存能力に魅了されてきた。
砂粒ほどの大きさのクマムシは、まるで映画『スター・トレック(Star Trek)』の続編から飛び出してきたような姿をしている。
防護服に似た体で、目はないように見え、クマのようなかぎ爪が付いた8本のずんぐりとした脚と、掃除機のノズルのような口器を持つ。大半はコケや地衣類を食べるが、他のクマムシを捕食するものもいる。
注目すべきことにこの原始的な動物は、自然界に存在するどんな環境より過酷な環境にも耐えることができる。やけどするほど高温の液体に浸されることや、絶対零度に近い超低温で凍らされることにも耐性を示すのだ。
■X線を遮る
さらにクマムシは苛烈な宇宙空間にも動じないようだ。
2007年、クマムシ数千匹を人工衛星に乗せ、真空の状態で生命を奪う恐れもある宇宙放射線に直接さらし、地球に持ち帰る実験が行われた。地球に戻ったクマムシはその多くが生存していたばかりか、一部の雌は後に卵を産んで健康な子孫を誕生させた。
極限状態で生き延びるためクマムシは乾眠と言われる状態になることができる。この状態では極小の体の中にあるほぼすべての液体が失われ、代謝のペースが通常の1万分の1に減速する。これをクマムシがどのようにして行っているのか、科学者らはまだ解明できていない。
大半の研究は、クマムシが損傷を受けたDNAを修復するための高度な能力を持っていると結論付けている。数十年続く場合もある極度の脱水状態から脱する際には特にDNAの修復が必要となる。
橋本氏と研究チームはヒト細胞を用いた実験で、クマムシの持つDsupタンパク質はX線による損傷からもDNAを守るある種の物理的な防御物として機能する可能性があることを明らかにした。
2015年、クマムシの一種のゲノム(全遺伝情報)を解読した別の研究チームがクマムシのDNA全体の約6分の1近くが異種の植物や動物から遺伝子の「水平伝播」によって獲得されたものだったと発表し、これがクマムシの耐性が並外れて高い理由だとする仮説を示した。
これについては、異種の動植物の遺伝子の割合が高かったのはサンプルが汚染されていたからではないかとの指摘がなされた。橋本氏の研究結果もこの指摘が正しかったことを示唆している。
橋本氏の研究チームは今回、クマムシの中で最も耐性が高いと考えられているヨコヅナクマムシのゲノムを100倍の精度で解読、外来遺伝子の割合が1.2%にすぎないことを発見した。
この結果は遺伝子の水平伝播が耐性の主な要因ではないことを示唆していると橋本氏は述べている。【翻訳編集】 AFPBB News -
トイレに行ったら…赤い!?「血尿」が出た時、どんな検査をする?
血尿には重大な病気が潜んでいる可能性があり、疑いがある場合には検査が必要です。見た目で尿の色が赤くなくても、顕微鏡を使った検査で血尿とわかることがあります。また、見た目が赤くても検査の結果、血尿ではない場合もあるのです。検査はすべて痛いわけではありません。以前は痛かった内視鏡検査でも、最近ではなるべく痛みを感じないよう工夫されています。ここでは、血尿の検査の流れや、泌尿器科と腎臓内科での精密検査について詳しくみていきます。
■病院で行なわれる血尿の精密検査の流れ
学校・職場などの集団健診で血尿の検査に使われているのは、赤血球中のヘモグロビンに反応する性質の試験紙です。この試験紙はヘモグロビンに似た物質にも反応するので、集団健診での尿潜血陽性には血尿ではない疑陽性が含まれていることがあります。疑陽性を除外するために、顕微鏡による尿珍渣が行なわれます。
尿珍渣試験紙による尿検査で尿の異常が見つかった場合、顕微鏡での尿珍渣(尿沈渣)で尿中の細胞成分や細菌を調べます。世界的に、尿の中に見られる赤血球数が20個/μL以上、尿珍渣(尿沈渣)は5個/HPF以上(※)と認められる症状が血尿の基準とされています。
※尿珍渣5個/HPFとは、顕微鏡で400倍に拡大した1視野につき、5個以上の沈殿物が見られるという意味です。
目で見て赤くても血尿ではなく、実は薬物による場合や濃縮尿の場合もあります。赤い尿が出るミオグロビン尿、ヘモグロビン尿が尿珍渣で除外されます。
泌尿器科での検査の流れ一般的に尿珍渣(尿沈渣)の後は、超音波検査、尿細胞診を行ないます。その次がCT検査や造影剤を使った尿路造影検査です。膀胱に腫瘍が疑われる場合は、尿道から内視鏡を入れる内視鏡検査で、膀胱内を観察します。以前は内視鏡を入れるときにかなり痛みがありましたが、最近は細くて柔らかいものを使うことが多く、尿道にゼリーのような麻酔剤を入れて行ないます。膀胱内の腫瘍切除も尿道から内視鏡を入れて行ないます。
腎臓内科での検査の流れ24時間の尿を溜め蓄尿検査を行ない、1日の蛋白尿の量と尿の成分を調べます。クレアチニンがどれくらい腎臓で排泄されているかで腎機能の状態がわかります。超音波検査や腹部CTなどで、腎臓の状態と腫瘍や結石などの有無を調べます。慢性的な蛋白尿や血尿があったり、腎機能の異常が見つかった場合は、腎臓の安全な部位から腎組織の一部を採取する、腎生検を行ないます。腎生検は全身麻酔で行なう場合もあります。
■原因がわからない血尿には経過観察
精密検査の結果が血尿の基準に当てはまる場合でも、原因が特定できるのは検査を受けた方の30%ほどといわれています。そのうちの2〜3%の方に悪性腫瘍が見つかりますが、原因がわからない場合もあります。泌尿器や腎臓に異常がない方には、経過観察が行なわれます。3〜6か月ごとに尿検査・超音波検査を受けながら3年間様子を見て、問題がなければ経過観察を終えるのが一般的な対応です。
血尿や血尿に似た症状にはさまざまな原因や病気が考えられます。子供に比べ成人では、年齢が高くなるほど血尿の症状から多くの病気が発見されるといわれています。健康診断で複数回尿潜血陽性反応が出て気になるようであれば、一度泌尿器科で診察をしてもらうとよいでしょう。また、一度でも血尿の症状を確認したら、早めの受診をおすすめします。 -
ジャンクDNA、それはあっても意味がない無駄なDNA。いや、無駄というか、機能が特定されていないDNA領域のこと。ジャンクDNAなんて面白いネーミングだなぁと思っていましたが、DNA側からしたら失礼な話かもしれません。研究が進み、ジャンクDNAにも機能があるなんて話がでてきたら、「ほらみたことか!」とジャンクDNAも怒りますよ。
DNAの研究が進むにつれ、ジャンクDNAには生物進化の過程で重要な役割があったという説がでてきました。スコットランドはエディンバラ大学の生物学者Valerie Wilsonが、脊椎動物は体の大きさはまちまちなのに、種によって肋骨の本数が同じなのはなぜかと疑問を発しました。このテーマを研究するポルトガルのGulbenkian科学研究所チームが、マウスの実験である発見をしました。通常のマウスは肋骨が13ペアなのに対し、研究所で育てられたミュータントマウスは肋骨が24ペアあったのです。肋骨は背骨のほうまであり、股関節付近まで伸びていました。これは、まるでヘビのよう!
研究チームが目をつけたのはOCT4と呼ばれる遺伝子。脊椎の形成に一役買っているというOCT4ですが、これ自体には、ヘビでもマウスでもヒトでも大きな違いはないといいます。そこで、やっと目が付けられたのがOCT4の周辺にあるジャンクDNA。ヘビのOCT4周辺のジャンクDNAを、通常のマウスの胚のOCT4周辺につなぎ合わせたところ、このマウスは通常より多い脊髄を形成したのです。この実験から、ジャンクDNAには、体を形成する上で何らかの役目があるのではという新たな説を発表することになりました。
ジャンクDNAの役割に関しては、今回の研究をふまえ、これからまだまだ多くの実験や検証が必要になります。進化、変化は、1つのDNAだけで起こるのではなく、その周辺領域が引き起こすというのが、注目すべきところ。1人じゃできないことも、みんな集まればできるよ、的なね。動物はDNAレベルでも、みんなの力を合わせたいものなのかもしれません。そう考えると、この小難しい研究も、なんだか親しみが湧きますな。 -
ぜんそくなど重いアレルギー疾患を引き起こすたんぱく質を発見し、発症の仕組みを解明したと、千葉大の中山俊憲教授(免疫学)のチームが16日の米科学誌サイエンス・イムノロジーに発表した。このたんぱく質の働きを止める抗体を投与することで根本的な治療が期待できるという。
ぜんそくは気管支などが炎症を起こし、気道がふさがって呼吸困難を引き起こす。アレルギー反応を起こした病原性免疫細胞が血管の外に出て、炎症の原因となることが既に判明していた。
研究チームは、この免疫細胞が血管の外に出る仕組みに着目。アレルギー反応によって血小板から放出される「ミル9分子」というたんぱく質が血管内側に付着し、免疫細胞の通り道を作っていることを突き止めた。ミル9分子の働きを止める抗体を作ってぜんそくのマウスに投与したところ、免疫細胞が血管の外に出なかったという。
重度のぜんそくの治療は、免疫細胞の働きを弱めるステロイド注射など対症療法が主流だが、患者の免疫力が低下する恐れがあり、効果がない例も近年、多く報告されている。中山教授は「患者の不安が減る画期的な治療薬の開発につながる」と話している。 -
夫の父から精子、173人誕生…20年間で
夫婦以外の卵子や精子を使った体外受精の実施を国内で初めて公表した諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町、根津八紘(やひろ)院長)で、今年7月末までの約20年間に夫の実父から精子提供を受けた夫婦114組から、体外受精で計173人の子どもが誕生していたことが分かった。
17日午後に長野県松本市で開かれる信州産婦人科連合会学術講演会で発表される。
同クリニックは2014年7月、夫の実父から提供を受けた精子による体外受精で、13年末までに夫婦79組から計118人が誕生したと発表。それから2年半余りで誕生数は約1・5倍に増えた。同クリニックによると、1996年11月から今年7月末まで、夫に精子がない160組が、夫の実父(50歳代〜70歳代)の精子と妻の卵子で体外受精を行い、妻の子宮に移植。142組が妊娠し、114組が実際に出産した。 -
女性のバイアグラ? フリバンセリンを体験した
女性用媚薬として注目されていた抗うつ剤フリバンセリンが米国FDAの認可を受け、発売になった。その効果は本当なのか? 試用してみた。
女性用媚薬を個人輸入
媚薬
果たしてその効果はバイアグラを超えるのか…?
これがフリバンセリン。正規品は『アディ(addyi)』という名前で、アメリカでは2015年10月からスプラウト・ファーマシューティカルズが販売している。
「えぐい色ですね。でけえし」
女性用の媚薬である。バイアグラの驚異的な売り上げとその効果は、飲んだら誰でもわかる、強力なレベルだ。
当然、バイアグラのように効く女性用の媚薬はないのか? と考えるだろう。考えて探して出てきたのが、抗うつ剤のフリバンセリン。
『アディ(addyi)』はやたらに高い(4錠で5000円前後!)ので、ジェネリックの『フルバン』を購入。こちらは半額以下だ。
閉経前女性の性的欲求低下障害を改善する、つまり中年女性向けの薬である。若い娘さんには関係ない。さっそく編集部のセックスレスうん年の女性を実験台にする。
「飲めばいいんですか?」
そうそう。抗うつ剤だから、軽い吐き気があるかも。だから水を多めに飲んで、これ、胃薬。
「大丈夫なんですか?」
大丈夫だろう、たぶん。
「たぶん?」
胃から、吸収されるので効果が出るのは早くても30分後かな。常識的に考えれば2時間ぐらいかかると思うけど。
「したくなっちゃったらどうするんですか!」
そうなったら面白いけど、そんなに便利なものはないだろう。
「バイアグラは?」
飲んでもしたくなるわけじゃない。あれはホスホジエステラーゼ(PDE)-5という、血管が収縮する物質が出るのを阻害するの。
だから勃起したらそのまま血が送られ続けて、起ちっぱなしになる。問題は最初の勃起ができるかどうかで、そもそもが血管がダメになってる糖尿病やストレス性のEDには効かない。
「わかりました。飲んでみますね」
2時間経過。どうよ?
「眠い」
えーと副作用に、嘔吐や眠気、低血圧とあるね。
「あとは別に」
そうなの?
「まったく」
ゼロ?
「マイナス?」
ふーん、じゃあ本当なんだ。
「何がです?」
臨床試験で性的欲求が改善された人は46〜60%なんだけど、1日1錠を3週間以上継続しての結果なんだな。
つまり毎日飲んで、1カ月ぐらいしてようやく半数ぐらいの人に効く。
媚薬
2時間が経ち、「眠い」しか言わなくなった実験台
「何ですか、それ。ダメじゃねえですか」
ダメだねえ。飲んだたら、もうどうにでもして! なんて薬なら面白いけど、そういうのじゃないんだ。ビタミン剤みたいなもんだな。
「それにしちゃ高くないですか?」
高いんだよ。1カ月分で14〜18万円もする。それでバイアグラみたいに物理的に効果が出ればいいけど、効果が出るかどうかは丁半バクチなわけだ。
「なんでそんなものを売りますかね。眠いんで、私、帰りますね」
はい、お疲れ様。
女性をその気にさせる薬は男の夢だが、そんないいものはこの世にはないのだ。もしよからぬことを考えている男性がいたら、やめておけと言っておこう。無駄無駄無駄、だ。 -
猿人のルーシーの死因は木からの落下か。皮肉にも、木の上で生活していた証拠に
木で暮らしていたはずなのに、木から落ちるとは…。
私たち人間のご先祖様、猿人の中で最も有名な「ルーシー」。そんな彼女の死因が、木からの落下死ではないかという説がでました。事実であるなら、進化の過程のわりと最近まで木の上で生活していたことになりますが、研究者の中には疑う声もあります。
Natureに掲載された新たな研究によると、テキサス大学オースティン校の古人類学者のJohn Kappelmanと共同研究者たちは、ルーシーは木から落ちて亡くなったという仮説をたてました。
彼らはルーシーの1320万年前の骨についた、場所によってはかなり酷い骨折のあとを調べてこの結論に達しました。この研究により、丁度ヒトが登場し始めた頃、アウストラロピテクス・アファレンシスが木の上に棲息しており、まだ二足歩行のヒト科にそういった習性があった可能性が浮上しました。
ルーシーの現存している骨は全体の40%しかありませんが、発見された中ではヒト科で最も古く、完全な化石の一つなのです。彼女が属するアウストラロピテクス・アファレンシスは390万年前から290万年前までアフリカに生息していました。人間同様にこのヒト科も二足歩行であったようですが、木の上に住んでいたのかは分かっていませんでした。しかし、今回の新しい研究によればその習性は霊長類たちの中に比較的最近まであったということになります。
ルーシーの化石(image: Marsha Miller / UT Austin)
「人類の進化において木の上での定住に関する議論の元となる化石が、木から落ちて死んだ可能性があるというのは皮肉なことです」とKappelmanは公開の際にコメントしました。
研究者たちはルーシーの骨をスキャンし、3万5000箇所の断面のデジタル画像を作り出した上でこの結論に至りました。テキサス大学オースティン校、Jackson School of Geoscience内にある高解像度コンピュータ断層撮影施設(UTCT)を利用し、肉眼に見えない骨の細部の様子や構成を視覚化したのです。
スキャン中の骨(image: Marsha Miller / UT Austin)
最初に研究者たちが注目したのは、ルーシーの右上腕にあった、珍しく奇妙なほどハッキリとした骨折でした。「こういった圧迫骨折は、落下の際に手が地面に当たり、肩の各部がお互いに衝撃を与えることで起こり、上腕骨に特徴的な骨折の痕を残します」とKappelman。
整形外科医の協力を得て、研究者たちは骨折がかなりの高さ(約12m)から落下し、ルーシーが衝撃を和らげるために腕を伸ばした際に発生したと結論づけました。似たような骨折はルーシーの骨の他の部分や現代における骨折の症例にも見られます。骨折のパターンを解析した結果、ルーシーは足から先に落ちて、腕で身構えた後に前に倒れ、重傷を負ったせいで落下の後すぐに亡くなったと研究者たちは言います。
「ルーシーの複数の重傷に注目が集まった時、私の頭には彼女の姿が思い浮かび、時と空間を超えて彼女に共感を持っていました。死を知ったことで、彼女はただ箱に入った骨ではなく、小さく、怪我を負った体で木の下に力なく横たわる一人の個人となったのです。」とKappelmanは語りました。
そもそも、二足歩行のヒト科動物、体重は約60ポンド(約27kg)で背丈は3.5フィート(約1.07m)程のルーシーは木の上で何をしていたのでしょうか? 仮説では、彼女は食べ物を探していたか、木の上に寝床を探していたとのことです。
ルーシーの骨の3Dプリントを持つJohn Kappelman(image: Marsha Miller / UT Austin)
しかし、ルーシーが木から落ちたという説を誰もが信じているわけではありません。New York TimesにてCarl Zimmerが書いたように、生き物が骨折する時には曲がった部分が生じます。細かく検査をしたら、ルーシーの骨にも曲がった跡があるかもしれませんが、確認されていません。彼は南アフリカのプレトリア大学の考古学者であるEricka N. L’Abbeの言葉を引用しています。「一番の問題は、研究者たちが顕微鏡で骨を観察しなかったことです」また、別の可能性として、ルーシーが死後、砂に埋もれた後に骨が折れたということも考えられます。
確かに説得力がありますが、そこまで詳細な仮説をたてるには情報が少なく状況証拠でしかありません。また、既に存在する証拠とすり合わせを行わなければなりません。ところで、アウストラロピテクス・アファレンシスは足が平たく、歩くのに適していたという事実があります。ルーシーはより遠い彼女の先祖と違って木登りには適していなかったのです(実際に彼女が木から落ちたとすると、彼女が落ちた原因の説明にはなります)。それでも、Kappelmanはルーシーが地上と木の上どちらでも移動できる特徴を持っているため、両方で生活していたと信じています。
ルーシーの骨のデータは一般公開され、eLucy.orgで閲覧できるようになっています。なので、今回の説を疑うという人は自分でデータを確認できます。エチオピア国立博物館の許可のもと、誰もがダウンロードやプリントをし、仮説の証明を行うことができるのです。
source: Nature -