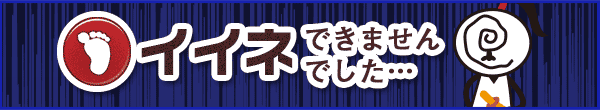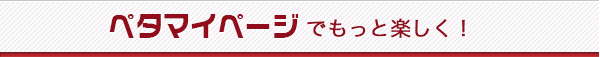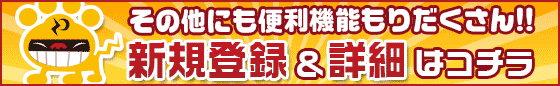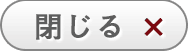カオス帝国〜リターンズ
-
スレッド一覧
- 雑談!! (241)
- たった一言!! (814)
- つぶやき!! (459)
- 生駒ちゃん (851)
- 画像!! (451)
- 芸能スレッド (1013)
- 名言!!!!!!!!!! (985)
- イマジン〜想像力育成講座〜 (256)
- 面白画像(≧▽≦) (884)
- MUSIC♪♪♪ (654)
- ヌコスレ(=^ェ^=) (688)
- 事件,事故!!( ; ゜Д゜) (471)
- 修造松岡!! (103)
- 俗にいうオカルト系(;゜∀゜) (299)
- (50)
- 豆知識 (677)
- つまるところこの人は美しい (307)
- 世 (112)
- JRA (1448)
- The パチ!!!!!!〜懐かしの〜 (457)
- 飲み食い市場(´・c_・`) (385)
- (140)
- サイエンス (202)
- 映画!!DVD!!ドラマ等々!! (157)
- AVタイトル‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- 復活!いい話スレ(ToT) (37)
- (80)
- つまるところこの人は美しい 本編 (33)
- (654)
- フラグ成立!!(^_^)/~~ (39)
- 笑 (392)
-
国連(UN)の世界保健機関(WHO)は11日、世界の多くの地域の同性愛者男性の間で、後天性免疫不全症候群(AIDS、エイズ)の原因となるヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染が増加していると警告し、感染を予防するために、同性同士で性交渉を持つすべての男性に抗レトロウイルス薬の使用を勧告した。
WHO本部があるスイス・ジュネーブ(Geneva)で会見したWHO・HIV対策局のゴットフリート・ヒルンシャル(Gottfried Hirnschall)局長は「爆発的な流行だ」と懸念している。同局長によれば、33年前にエイズの症例が初めて確認された際、HIVハイリスク群の一つとされた同性愛者男性の間で現在再び感染率が高まっているという。
ヒルンシャル氏は、1980年代に国際的な啓発活動が進んだ一方で、HIVとの共存を可能にする新たな治療法を目にしてきた若い世代では、エイズ自体への関心が薄れていると指摘する。そして現在、同性愛者男性が感染する確率は全体平均の約19倍になっているという。
そのためWHOは、11日に発表したHIV/エイズ対策に関する新たな提言で初めて「HIV感染を予防する追加的な方法として抗レトロウイルス薬の使用を考慮することを、男性と性交渉を持つ男性たちに強く推奨する」と述べた。米当局も5月に同様の勧告を行っている。 -
植物が環境の変化に反応していることは古くから知られている。光や気温に反応を返すほか、触られると反応するものもある。さらにこのほど、シロイヌナズナは音を“聞いて”いるとする研究結果が発表された。
シロイヌナズナは可憐な花を咲かせるアブラナ科の植物で、英語ではネズミの耳になぞらえてマウスイヤー・クレス(mouse-ear cress)とも呼ばれる。この植物はモンシロチョウの幼虫が葉を食べる際の振幅の大きな振動に対して、堅固な防御反応を示していることが、ミズーリ大学の2人の研究者によって明らかになった。
この研究は、音響分析と化学分析を組み合わせて、植物が周辺環境の音のうち、生態学的に重要なものに反応していることを初めて明らかにしたものであると、ミズーリ大学植物科学科の上級研究員を務めるヘイディ・アペル(Heidi Appel)氏は言う。
アペル氏は同大学生物科学科のレックス・コクロフト(Rex Cocroft)教授と共同で研究を行い、レーザーとひときれの反射素材を用いて、チョウの幼虫が葉を食べる際の振動を記録した。これはシロイヌナズナの葉を、1万分の1インチ程度上下させるにすぎないわずかな振動だ。その後、実験用のシロイヌナズナを2グループに分け、一方には2時間分の振動の記録を聞かせ、他方は静かな環境に置いた。
すると、咀嚼の振動の記録にさらされたシロイヌナズナでは、辛味成分を含む油の分泌量が増加した。これは虫の攻撃に対する防御反応と考えられる。
振動が「引き金となって、その後の攻撃に対する備えを促した。咀嚼の振動という情報をあらかじめ得ていれば、いち早く堅い守りを示せる」とアペル氏は言う。
またシロイヌナズナは、特定の振動にしか反応を返さない。最初の実験のすぐ後に、アペル氏らは似たような振動に植物をさらしている。風や、シロイヌナズナにとって害をもたらさない虫による振動では、特に反応は得られなかった。
「特定の周波数の音、つまり特定の高さの音にだけ効果があるといった単純な話だとは考えていない。(シロイヌナズナは)咀嚼の振動に反応する一方で、同じ周波数でも虫の鳴き声には反応しなかった。このことから、植物の音響受容は、特定の音高に反応するというような単純なものではないことが窺える」とコクロフト教授は言う。
◆小さな植物に大きな“耳”
今回の研究は、特定の植物とそれを食べる特定の虫の関係に焦点を当てたものだが、その結果は他の植物にも広く当てはまるのではないかとアペル氏らは予想している。研究の次の段階は、別の種類の植物とそれを食べる動物でも同じ現象が見られるかを確認することだ。今回の発見の農業分野への応用を検討するには時期尚早だと2人は言う。
植物にとって何が有益かを私たちは完全には理解していないということを裏づける興味深い情報は近年増えており、アペル氏らの研究結果もそれに連なるものだとウィスコンシン大学マディソン校のジョン・オロック(John Orrock)准教授(動物学)は言う。
オロック准教授は、植物とそれを食べる動物との間の「恐怖の生態学」を専門としており、カタツムリのぬめりが植物の防御系におよぼす影響について研究を発表している。オロック准教授は今回のミズーリ大学の研究が、植物行動学の分野において「興味深く多彩な一連の設問を新たに切り開く」ものと考えているとのことだ。
「植物が反応を示すと分かっている情報の形はたくさんある。光に注意を向けていることは分かっているし、周辺の土壌や大気に含まれるさまざまな化学物質に注意を向けていることも分かっている。(中略)植物はいかなる瞬間にも、さまざまな情報を考慮している。今回の研究によって、音による情報も、植物が考慮するもののひとつであると分かった」とオロック准教授は言う。
「つまり植物も、ある意味で音を“聞いて”いるのだ」。
咀嚼音へのシロイヌナズナの反応に関する今回の研究は、「Oecologia」誌オンライン版に7月2日付けで掲載された。 -