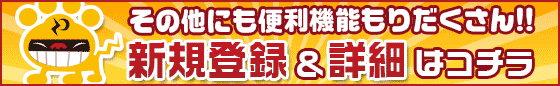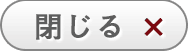�J�I�X�鍑�`���^�[���Y
-
�X���b�h�ꗗ
- �G�k!! (241)
- �������ꌾ!! (814)
- �Ԃ₫!! (459)
- ������ (851)
- �摜!! (451)
- �|�\�X���b�h (1013)
- ����!!!!!!!!!! (985)
- �C�}�W���`�z���͈琬�u���` (256)
- �ʔ��摜(������) (884)
- MUSIC���� (654)
- �k�R�X��(=^�F^=) (688)
- �����C����!!( ; �K�D�K) (471)
- �C������!! (103)
- ���ɂ����I�J���g�n(�G�K�́K) (299)
- (50)
- ���m�� (677)
- �܂�Ƃ��낱�̐l�͔����� (307)
- �� (112)
- JRA (1448)
- The �p�`!!!!!!�`�������́` (457)
- ���ݐH���s��(�L�Ec_�E`) (385)
- (140)
- �T�C�G���X (202)
- �f��!!DVD!!�h���}���X!! (157)
- AV�^�C�g��‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- �����I�����b�X��(ToT) (37)
- (80)
- �܂�Ƃ��낱�̐l�͔����� �{�� (33)
- (654)
- �t���O����!!(^_^)/~~ (39)
- �� (392)
...

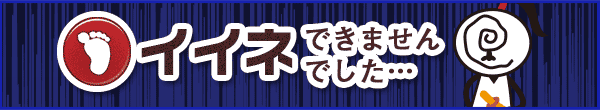
���C�C�l�I�͊e�J�L�R�~�ɑ��A1��̂ݎt���܂��B
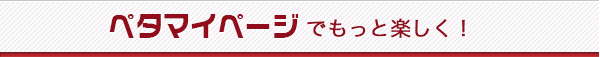
���}�C�y�[�W�ł́A�������u�C�C�l�I�v�������J�L�R�~��ۑ����A�����Ƃ��Č��鎖���ł��܂��B
-
�����̘r�A�Ί��̊W�A�嗝�Α��̔j�ЁA��̐����̉~�Մ��������́A���E�ōł��Â��Ƃ�������L���Ȓ��v�D���猩�������╨�̐��X���B
�@10��4���A�M���V�������Ȃ̐����╨���傪�A9��4������20���ɂ����čs��ꂽ���@�����̐��ʂ\�����B�����ΏۂƂȂ����̂́A�M���V���̃A���e�B�L�e�B�������A���[��55���[�g���̏ꏊ�ɂ���u�A���e�B�L�e�B���̒��v�D�v�B���������╨����́A�S�����̃��[�}�����̗l�q�������������Ƃ��ł���B
�@�������̋�����\�߂��A�Q���L�E�V���b�V���́A�u�i���̒��v�D����j�嗝�Α��⓺���ȂǁA�ƂĂ��M�d�ȍ��������Ă��܂��v�Ƙb���B
�@�V���b�V���ɂ��ƁA���̏��D�͋I���O1���I����Ƀ��[�}�Ɍ������r���Œ��v�������̂ƌ����Ă���A�S����40���[�g���Ɠ����ɂ��Ă͑傫���B���̍��̃��[�}�ł́A�T���Ȏs���������@����M���V���|�p�ŏ����Ă����̂ŁA�o�`�����Ƃ��ɂ͂�������̌|�p�i��ς�ł����ƍl������B
�@�����̗l�q���B�e��������ɂ́A�ʎ��I�Ȓ����̘r�̕������������l�q���L�^����Ă���B�`��w�̌�������A�N�w�҂����f���ɂ������̂�������Ȃ��Ƃ����B
�@�����̒����͓����̍����|�p�������ƍl������B����A���������Ȃ��ŁA�����炭�ł��D��S����������̂́A�����Ȑ����̉~�Ղ��낤�B���̉~�Ղɂ́A�������̌����J�����Ă���A�Y���̖͗l�����܂�Ă���B�V���b�V���́A�����������Ɏg���Ă������̂Ȃ̂��킩��Ȃ��ƌ����B
�u�܂����Ƃ������܂��A�Ƌ�p�̏��肩��́A���邢�͉��炩�̓��������܂���v
�@������Ďv���o���̂́A���́u�A���e�B�L�e�B���̋@�B�v���B100�N�ȏ�O�ɂ��̒��v�D���猩�����������̎��Ԏ��@�B�ŁA�����ׂ����x�œV�̂̉^�s���v�Z�ł����ƍl�����Ă���B���̐��m������A�����u�Ñ�̃R���s���[�^�[�v�Ƃ��Ă��B
�@����A�l�Êw�҂̃`�[���𗦂����̂́A�V���b�V���ƃX�E�F�[�f���̃����h��w�̍l�Êw�҃u�����_���E�t�H�[���[�����B���炭�͍��N��������╨�̌����𑱂��A2018�N5���ɂ͂ӂ����ђ��v�D�̒������s���\��ƂȂ��Ă���B
�u�A���e�B�L�e�B���̒��v�D�v�̗��j
�@�V���b�V���́A���N����ł����╨�͉ߋ��ő����x���ŁA�s���邱�Ƃ̂Ȃ����Â���̑�����̂��Ƙb���Ă���B���̒��v�D���ŏ��ɔ������ꂽ�̂�1900�N�B�C�ɐ����ĊC�Ȃ��W�߂Ă����l�����A�����̘r���������̂����������������B
�@����́u��̂Ȃ��r�v�ƌĂ�A����Ȃ�����ւ̊��҂����܂����B1976�N�ɂ́A�L���ȃt�����X�l�C�m�T���ƃW���b�N�E�N�X�g�[�����������s���A�����₢�����̏����Ȉ╨�������B
�@���̒��v�D��100�N�O����悭�m���Ă͂�����̂́A1970�N��ɃN�X�g�[�����K��Ă���́A�f���I�Ȓ��������s���Ȃ������B�������A2014�N�Ƀt�H�[���[�������̊C��ɒ��ڂ������ƂŁA�l�Êw�҂����̊Ԃŋ������ĔR���邱�ƂɂȂ����B�Ȃ��ł��ł��d��Ȕ����ƂȂ����̂́A�l���̈ꕔ�������������Ƃ��낤�B2000�N�O�̋M�d��DNA���ł���ق��A�������璾�v�D�̗��j�ɂ��Ă���Ȃ�肪���肪�����邩������Ȃ��BDNA�̕��͂͂܂������Ă��邪�A�����̒�������́A�Ⴂ�j���̍��ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B
�@�t�H�[���[����2016�N�́u�l�C�`���[�v���ŁA���̑D�����Ȃǂ̎��R���ۂ������ŁA�ˑR���v�����̂ł͂Ȃ����Ƙ_���Ă���B
�@�V���b�V���ɂ��ƁA���̒��v�D�̐ώׂA���������Ă���n���C�̒��v�D�̐ωׂ̑啔�����߂�Ƃ����B�c�[�������Ƃɂ͑���Ȏ��Ԃ���������̂́A����Ȃ锭�������҂����B -
�čq��F���ǁi�m�`�r�`�j�̌����`�[���͂T���i���{���ԂU���j�A��R�T���N�O�̌�����C�ɕ����Ă����A�Ƃ��镪�͂\�����B�ΎR�����ő�ʂ̐����C�Ȃǂ������o���A��V�疜�N�ɂ킽��\�ʂ����Ƃ݂���B���̌�K�X�̔��������܂�A���݂̂悤�ȕ\�ʂɂȂ����Ƃ����B
�@��厏�ɘ_�����f�ڂ��ꂽ�B�����`�[���́A�}�O�}���ł܂��Ăł������ʂ̍����ۂ��u�C�v�ƌĂ��̈�ɂ��āA�A�|���v��ō̎悵�������f�[�^��A���T���@�u���i�E���R�l�T���X�E�I�[�r�^�[�v�̍ŐV�̊ϑ����ʂȂǂ���A���o�����K�X�̑g����ʂȂǂ𐄌v�B�ΎR�������ł���������R�T���N�O�ɂ́A��_���Y�f�␅���C�Ȃǂ���Ȃ��C���A�ő�P�O�O�L���̌����ŕ\�ʂ��Ă����ƌ��_�Â����B��C�͌��݂̒n���̖�P�O�O���̂P�����A���݂̉ΐ����Z�������Ƃ����B
�@���ʂ̉ΎR�����ŕ��o���������C�̑��ʂ́A���i�̂P�O�{�߂��ɒB�����\��������B�����͉F����ԂɎ���ꂽ���A�ꕔ�͑��z�����͂��Ȃ��ɒn�ȂǂɎc���Ă���Ƃ݂��A�����̗L�l�T���Ŏ����Ƃ��Ċ��p�����҂���Ă���B
�@���͖�S�T���N�O�A�a������̒n���ɕʂ̓V�̂��Փ˂��Ăł����Ƃ�������L�͂Ƃ���Ă���B -
�@2015�N�ɔ������ꂽ�V��̋��u���r�[�V�[�h���S���v�B���̐����ĉj���p���I�[�X�g�����A�ɂāA���E�ŏ��߂Ċϑ�����܂����B�����Ɋ�^���Ă��鐼�I�[�X�g�����A�B�������ق�FaceBook�ŁA���悪���J����Ă��܂��B
�@���r�[�V�[�h���S���́A�g�Q�E�I�ڃ��E�W�E�I�Ȃɑ�����A�^�c�m�I�g�V�S�Ɏ������B�Â���1919�N�ɍ̏W���ꂽ���̂��͂��߂Ƃ���4�̂��A�W�{�Ƃ��đ��݂��Ă��܂����B���ꂪ�ߔN��DNA�Ӓ�Ȃǂ�p������������V��Ɣ����B�ߋ��̍̏W�ꏊ����A�I�[�X�g�����A�ߊC�̐[���̈�ɂ��������Ă���Ɛ�������Ă��܂����B
�@�����`�[���͐�������Ԃ̌̂�T���ׂ��A���x���_�C�r���O�����s�B50���[�g�����̐[�x�Ŕ������A�B�e�ɐ������܂����B���̂��Ƃ̓��r�[�V�[�h���S�������I�[�X�g�����A�ɕ��z���Ă��邱�Ƃ������Ƃ��A�ی�̏�����i�߂Ă��܂��B
�@�Ȃ��A����܂Ŋm�F����Ă����V�[�h���S���̒��Ԃ́A�E�B�[�f�B�[�V�[�h���S���ƃ��[�t�B�[�V�[�h���S����2��ނ̂݁B���r�[�V�[�h���S���͖�150�N�Ԃ�Ɋm�F���ꂽ3��ޖڂƂȂ�܂��B -
��Ŋ낤���V��u�X�J�C�E�H�[�J�[�E�t�[���b�N�e�i�K�U���v
�@�A�W�A�ŐV��̃e�i�K�U����������A1��10���A�w�p���w�č��쒷�ފw�W���[�i���x�ɔ��\���ꂽ�B�~�����}�[�������璆���쐼���ɂ����Ă̐X�тɐ�������t�[���b�N�e�i�K�U���̒��ԂŁA�u�X�J�C�E�H�[�J�[�E�t�[���b�N�e�i�K�U���i�w����Hoolock tianxing�j�v�Ɩ��t����ꂽ�B�u�X�J�C�E�H�[�J�[�v�Ƃ��������t�����̂́A���������Ȋw�҂������w�X�^�[�E�E�H�[�Y�x�t�@�����������߂ƁABBC�j���[�X�͓`���Ă���B���Ȃ݂ɁA�w���́utianxing�v�������ŏ����Ɓu�V�s�v�ɂȂ�B
�@�f��Ń��[�N�E�X�J�C�E�H�[�J�[���������o�D�}�[�N�E�n�~�������̃j���[�X��m��A�u���h���B���[�N�͂���܂ł��َq�≺���A�؎�ɂȂ��Ă������ǁA���x�͂���I�v�ƃc�C�[�g���Ă���B
�@�ăE�B�X�R���V�������쒷�ތ����Z���^�[�̏��ɂ��ƁA�t�[���b�N�e�i�K�U���͑̒���80cm�ŁA���͂Ȃ��A���ϑ̏d�̓��X��6kg�A�I�X��7kg���x�Ƃ����B�������ꂽ�X�J�C�E�H�[�J�[�E�t�[���b�N�e�i�K�U���i�ȉ��A�X�J�C�E�H�[�J�[�j�́A�ڂ̏�̖т�ҊԂ̖сA�j�̂܂��̖т̐F��`�����̃t�[���b�N�e�i�K�U���Ƃ͈قȂ��Ă���B
�@������A���Ȃ����ҊԂɔ����F�̖т��������e�i�K�U����ڌ����Ă��A����̓X�J�C�E�H�[�J�[�ł͂Ȃ��B�I�X�̃X�J�C�E�H�[�J�[�̖т͒��F�������B
�@����V��ƂȂ����e�i�K�U���́A����܂ő��ݎ��̂͒m���Ă������A�߉��̃q�K�V�t�[���b�N�e�i�K�U���iH. leuconedys�j���Ǝv���Ă����B�q�K�V�t�[���b�N�e�i�K�U����IUCN���b�h���X�g�Ŋ�}��Ɏw�肳��Ă��邪�A�X�J�C�E�H�[�J�[���V��L�ڂ��ꂽ���߁A�ۑS�����߂ĕ]������K�v������Ƃ����B�u�X�J�C�E�H�[�J�[�ɂ��Ă͂قƂ�lj����킩���Ă��܂���B�������肵�����Ȃ��ɕۑS��]�����邱�Ƃ͍���ł����A�����炭IUCN���b�h���X�g�̐�Ŋ뜜��ɂȂ�Ǝv���܂��v�ƌ����B
�@�Ȋw�҂��������̃T���ɉf��̐l�C�L�����N�^�[�̖��O��t�����̂́A�l�X�̖ڂ��Ђ��ĕی슈���ɖ𗧂Ă����ƍl�������������Ȃ��B�t�H�[�X�Ƌ��ɂ���Ƃ��B -
���̃X��196�̏ڍ�
�����������v���ŃT���ƃV�J�̌���s�����ώ@�����_�������\����܂����B�킪�傫�����ꂽ�����Ԃł̌���͒������A�Ȋw�����Ƃ��ċL�^���ꂽ�͍̂���2��ځB
�@�����`�[���̓j�z���U���̈���ɂ�����A���v���ɐ������Ă��郄�N�V�}�U�����ώ@�B2���̎��W�J�ɂ܂����������悤�Ƃ��Ă����Y�U���̎�����w�p���uPrimates�v�ŕ��܂����B
�@�V�J��1���͒�R�����A�T����10���Ԃɂ킽���Č���s���������Ă����Ƃ̂��ƁB�B�e���ꂽ�����ʐ^�ł́A�V�J�̂��K�̂�����ō������Ă���l�q���m�F�ł��܂��B�Ȃ��A�g�̂̂��肪�Ⴄ���߂��A�}���͍s�Ȃ��Ă��܂���B����1���͉�]�����葖�����肵�ăT����U�藎�Ƃ����Ƃ��usexual behaviour�i���I�ȍs���j�v������܂���ł����B
�@�_���łَ͈�Ԃł̌���s���������������R�Ƃ��āA�Y�U�����Q��ɑ����Ă��炸�A���Ƃ̐ڐG����������Ă������ƁA�ɐB�����}���Ă������Ƃ������Ă��܂��B�܂��A���̂����Ԃ����Ƃ��̂悤�ɃV�J�ɋߕt�����̃T��������ǂ������s���������Ă������ƂȂǂ���A�����`�[���̓T���ƃV�J�����a�I�ȊW��z���Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���悤�ł��B
-
�e�̃X�g���X����`�A�q���̐����͂������c���匤���O���[�v
�@���s��w�̌����O���[�v��1��11���A�e����ɃX�g���X��^���邱�ƂŃX�g���X�ϐ��̏㏸������̉������q���Ɏp����邱�Ƃ������B�s���ȕ��������������u�l���`���̈�`�v���ۂ̃��J�j�Y���ɂ��ĐV�K�̘g�g�݂������̂Ƃ��āA����̔��W�����҂����B
�@���������̂́A���s��w�����Ȋw�����Ȃ̐��c�h�����̌����O���[�v�B�����w�ł͌�V�I�Ɋl�������`���͈�`���Ȃ��ƍl�����Ă������A�ߔN�A�ʐ����悤�Ȏ��ۂ������悤�ɂȂ����B�����ŁA�����O���[�v�͐e����q�֎p����鐶���D�ʐ��ɒ��ځB������V�������ɗp����������uC. elegans�v�������ΏۂƂ��Ċl���`���̌p�����J�j�Y���𖾂�ڎw�����B
�@�����ł́A�e����Ő����ɂȂ�܂łɒ�e�ʂ̃X�g���X��^���Ĉ�Ă�Ƃ��܂��܂ȃX�g���X�ϐ����㏸���A���̑ϐ��㏸�̓X�g���X��^�����Ɉ�Ă��q�̐���⑷�̐���ɂ��p����Ă��邱�Ƃ��B
�@����ɁA�I�X�̐e�����ɃX�g���X��^�����ꍇ�ł��A�q�̐���̐����ɃX�g���X�ϐ��㏸������̉����Ƃ������ʂ��݂�ꂽ�B���̂��Ƃ���A�X�g���X�ϐ��̏㏸������̉����ł���u�z���~�V�X���ʁv���q���Ɍp�����邱�Ƃ����߂Ė��炩�ɂ����B���̃��J�j�Y�����𖾂��邱�ƂŁA�g�D�R�~���j�P�[�V����������u�G�s�W�F�l�e�B�b�N����v�Ƃ����V�K�̘g�g�݂�������ƂɂȂ�B�X�g���X�������̃V�O�i���`�B�o�H�́A�����ȊO�̐����ł��d�v�Ȓm���ƂȂ�Ɨ\�z�����B
�@����́A���X�g���X�łǂ̂悤�Ȉ�`�q�̈悪�u�G�s�W�F�l�e�B�b�N����v����̂��A�Q�m���S��ɂ킽���͂��s�����Ƃŏڍׂȕ��q���J�j�Y���̉𖾂�ڎw���Ă����B����̌������ʂ́A�C�M���X�̊w�p���uNature Communications�v��1��9���A�I�����C���f�ڂ��ꂽ�B -
�yAFP�������z�����������v���ŁA�Y�̃T�������̃V�J�ƌ�������݂�Ƃ����u�ɂ߂Ē������v��ʂ��B�e�����Ƃ���_����10���A�w�p���v���}�[�e�X�iPrimates�j�ɔ��\���ꂽ�B
�@�َ�Ԍ���͂����܂�Ȍ��ۂŁA�����`�[���ɂ��ƕ�͍��킸��2���ځB�����A��Ɏ��炳�ꂽ��ߊl���ꂽ�肵�������Ԃŗ�O�I�Ɋm�F����邱�Ƃ͂���Ƃ����B
�@�����`�[���́A1�C�̎Ⴂ�j�z���U�����A�������������Ƒ傫�Ȏ��V�J���Ȃ��Ƃ�2���̔w���ɏ���Ă���l�q���B�e�����B
�@�T���͎��ۂ̌���͂��Ă��Ȃ����̂́A�V�J�̔w���̏�Ő��I�Ȃ������������Ă���B�V�J�̓T���̂��邪�܂܂ɂ����Ă��邱�Ƃ�����A�����ē����o�����Ƃ��������Ƃ����B
�@�t�����X�̃X�g���X�u�[����w�iUniversity of Strasbourg�j�̃}���[�E�v���iMarie Pele�j����AFP�ɑ��A�u�B�����͈�Ȃ��A���炩�ɐ��s�ׂ��v�Ǝw�E���Ă���B
�@����ɂ��̃T���́A�܂�Ŏ����̎��W�J���u���v�悤�ɑ��̗Y�U����ǂ������l�q���������Ƃ����B
�@�����`�[���͂��̍s���ɂ��āA�����߂��鑈�����������Q��ł́u�������̕s���v�ƁA�ɐB���ɔ����z�������ʂ̑������v���ƂȂ����ƕ��͂��Ă���B
�@�_���ɂ��ƁA�َ�Ԍ���ɂ��Ă̏��̉Ȋw�_����2014�N�̂��̂ŁA��ɂŃy���M���Ƃ̌�������݂��I�b�g�Z�C�̎��Ⴊ����A�傫�Ȓ��ڂ��W�߂��B
�@���v���̃T���ƃV�J�̗l�q�����߂�����́A�ȉ��̃T�C�g�Ō��J����Ă���B
http://www.edge-cdn.net/video_1106810?playerskin=37016 -
�X�g���X�͂�͂��G�I�@�݂���̐i�s�����������邱�Ƃ��c
�@�N�����A�����ꏭ�Ȃ��ꉽ�炩�̃X�g���X�������Ȃ�����X���߂����Ă��邾�낤���A���N�̂��߂ɂ́A��͂�X�g���X���ŏ����ɂ������������B���̂��Ƃ��Ȋw�I�ɗ��t���錤�����ʂ��o���B
�@������w�́A�č��R�����r�A��w�ȂǂƋ����Ő_�o�X�g���X���݂���̐i�s�����������郁�J�j�Y�������������Ɣ��\�����B�l�Ԃ̐_�o�זE�́A�]�����ł͂Ȃ��S�g�ɕ��z���Ă��āA�ݒ��ɂ�1���ȏ�̂��܂��܂Ȑ_�o�זE�����݂��Ă���Ƃ����B�ȑO����A�_�o�X�g���X������₳�܂��܂ȕa�C�̌����ɂȂ�\���͎w�E����Ă������A���̗��R�͕������Ă��Ȃ������B�����ł́A�݂��i�s����ߒ��ŁA����זE���u�_�o�������q�v�ƌĂ��z���������Y�����A����ɔ��������_�o�זE������g�D�ɏW�܂�A��������̋����X�g���X�h�����邱�ƂŁA�݂���̐������������Ă������Ƃ����E�ŏ��߂Ė��炩�ɂȂ����B�܂��A���́u�_�o�������q�v��}������A�_�o�X�g���X����o����זE���������邱�ƂŁA�݂���̐i�s��}���邱�Ƃ��ł����Ƃ����B
�@���ÂƂ����ƁA����זE�̑��B�ڗ}����R����܂��ł���ʓI�����A����̌������ʂ��A�_�o�זE�Ƃ̑��ݍ�p��}�����܂ň݂���ɑ�����ʂ����߂鎡�Â��s����\�����o�Ă����B
�@����͂������A�ق��̕a�C�ɂ�������Ȃ����߂ɂ́A�Ȃ�ׂ��X�g���X�t���[�Ȗ������߂������`�B -
�u�����v�Ƃ������t�������m�ł����B�S���e�n�̂���Z���^�[���w�a�@�Ȃǂ̍��@�\�a�@�ŁA���Â��ł��Ȃ��Ȃ������҂��A��t���猩������Ă��܂��A�s������Ȃ����Ă��܂��Ƃ������ł��B
������Z���^�[�Łu�����v���������Ă���H�@�I�@
�@���@�\�a�@�ɂ́A��ʓI�ȕa�@�ɂ͂Ȃ��悤�ȍ��x�Ȏ��Ë@�킪����A���オ���܂��B�ꌩ���Â�����Ȋ��҂�����Ă��ꂻ���ȃC���[�W������̂ɂ��ւ�炸�A���҂��u��v�ɂȂ��Ă��܂��̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B���̗��R�𗝉�����ɂ́A����̎v�l�@��m�邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B
�@����̈�t�����҂�f�Â���Ƃ��A���̎v�l�@�ɂ����Ƃ��e����^���Ă���̂́A�����܂ł��Ȃ��u�Ȋw�v�ł��B����������A��t�͉Ȋw�҂Ƃ��ċ��炳��A�����Ă���̂ł��B
�@�Ȋw�҂Ƃ��Ă̈�t�Ɋ��҂����̂́A�@�_���I�ł���(�������ʂ�)�A�A���ؓI�ł���(�Ȋw�I��@�ɂ��m���E���v�I�ɏؖ��ł���)�A�B���ՓI�ł���(���E�̂ǂ��ł��A�N�ɂł����Ă͂܂�)�A�C�q�ϓI�ł���(��Âł���)���Ƃł��B�����āA���̂悤�Ȉ�t����Ă��w���炪�s���܂��B���̂��Ƃɂ���āA������ȏ�̈�Ð������ێ����邱�ƂɂȂ����Ă���ʂ�����܂��B�q�ϓI�ł���(��Âł���)���Ƃł���A���̂悤�Ɉ�w���炪�Ȃ���܂��B����ɂ���āA������̈�Ð������ێ����邱�Ƃɂ��Ȃ����Ă���ʂ�����܂��B
�@���������Ȋw����Ƃ��錻���ẤA�u��w���f���v�ƌĂ�܂��B��w���f���ł́A�a�C�ɂ�(1��)����������A���̌����̌��ʂƂ��ĕa�C�������Ă���ƍl���܂��B�����āA�a�C�̌����������o���āA�������菜�����Ƃ���Â̖ڕW�ƂȂ�܂��B�����ǂł���A�ۂ�E�C���X���ɂ�菜�����邱�ƁA����ł������̑g�D����p�Ő�������A���ː��ł���������A��łԂ��Ƃ�������ł��B�����āA���̃��f���ɂ����Ĉ�Â��s����̂́A���Ƃł����Î҂ƂȂ�܂��B
��Ấu��啪���v�̕��Q
�@���������Ȋw�I�Ȉ�w�ɂ����ẮA��啪�����i��ł��܂����B��w�̐i���ƂƂ��ɁA�m���ƋZ�p�͈̔͂��L���Ȃ�A�����[���Ȃ��Ă������߂̓��R�̂��Ƃł��B��w�S�ʂ�1�l�̈�t�őS�Ă��J�o�[���邱�ƂȂǁA�ƂĂ��ł��܂���B����Ƃ��āA��啪������߂ăJ�o�[����͈͂��������邱�ƂŁA���̐�啪��ɂ�����m���ƋZ�p�ɐ��ʂ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B
������͐�啪��ɑ��ĐӔC������
�@����́A��������啪��Ƃ���a�C�ɑ��ĐӔC���������܂����A���łȂ�����̕a�C�ɑ��ẮA�����ɂ͊W�Ȃ����A�ӔC���Ȃ��ƍl�������ɂȂ�܂��B�����āA��啪��̕a�C�ł����Ă��Ȋw�I�Ɏ��Ì��ʂȂǂ̃G�r�f���X(�Ȋw�I�؋�)���ςݏグ��ꂽ���͈͓̔��ŁA��Â����悤�Ƃ��܂��B���Ö@���m�����Ă��Ȃ��a�C�⎡�Â��]�߂Ȃ��i�s�x�ɂȂ�ƁA�ǂ����Ă����������������ɂȂ�܂��B
�@�Ⴆ�A�����ߋ��Ɍo����������ȃP�[�X������܂��B������~�}�O���ɗ������҂���́A��ɐS�s�S�̏Ǐ��Ď��܂����B�����ŁA���͏z����Ȃ̈�t�ɁA���̊��҂����f�Ă���Ȃ����ƈ˗����܂����B�������A���̈�t�́A��ʓ��ȂŐf�Ă��炦�悢�ƁA���̈˗���f��܂����B�ނ̔��z�͂����ł��B�S���J�e�[�e���Ȃǂɂ�鎡�Â��K�v�ȐS�؍[�ǂ⋷�S�ǂł���A���̐��ł��鎩���̏o�Ԃ�����ǂ��A�����łȂ��Ȃ�Ύ������f�Ȃ��Ă��ǂ��A�Ƃ����l����������̂ł��B
�@�b���������ƁA�����Ԃ��̋�����t�̂悤�Ɍ����܂����A����͐���ɂƂ��Ă������Ē������l�����ł͂���܂���B���҂��������f����ƁA����͂܂��A�����̐�啪��̑ΏۂƂȂ銳�҂��ǂ����f������̂ł��B�����āA�Ώۂ���O��Ă��܂��ƁA�S�������Ă��܂��܂��B���O�̂��Ƃ͂悭����Ȃ�����A�Ȃ�ׂ��ւ�肽���Ȃ��Ɠ������ɂȂ�̂ł��B
�@�����̐��͈͓̔��̊��҂ł��邱�Ƃ�����A���ɁA���Ɋւ��a�C���ǂ����f���܂��B�����āA���Ɋւ��Ȃ����̂ł���A�܂����u���Ă����ėǂ��̂ł͂Ȃ����ƍl�������ł��B����́A�����𖾂炩�ɂ��đΏ�����u�����Ö@�v����ƍl���܂�����A�Ǐ��}���Ă��������̎��Ấu�ΏǗÖ@�v�Ƃ��Čy���������ɂȂ�܂��B
�@���������āA���t������摜�����ňُ킪������Ȃ���A�Ƃ肠�����͖��Ɋւ��a�C�ł͂Ȃ��Ɣ��f���A�u��������������ǂ��A�ǂ��������Ƃ���͌�����Ȃ��v�Ɠ����Ă��܂��܂��B
�@�܂��A���͈͓̔��ł͂����Ă��A�����������Ȃ��A���邢�͎����Ȃ��Ȃ������҂Ƃ͊ւ�肽���Ȃ��Ƃ����C�����������Ă��s�v�c�ł͂���܂���B��t�ɂƂ��āA�����Ȃ����Ƃ́u�s�k�v�ƂȂ邩��ł��B
��t�ɂƂ��āu�����Ȃ��v���Ƃ͔s�k��
�@��t�Ƃ����E�Ƃ́A������������Âɂ���Ď������Ƃ̂ł��銳�҂�����ł���A���Â����������������ɂ͊��A���ӂ���܂��B�������A��t�s���̏�Ԃ������Ă��܂�����A���Ẩ\�Ȋ��҂�������R�҂��Ă����Ԃɂ���܂��B����ȏ̉��Őf�Â����Ă���ƁA�����Ȃ��A���邢�͎����Ȃ��Ȃ������҂Ƃ͊ւ�肽���Ȃ��Ƃ����C�������͂��炢�Ă��s�v�c�Ƃ͌����܂���B
�@�`���ŏЉ���悤�ɁA���ݑS���e�n�̂���Z���^�[���w�a�@�Ȃǂł́A���Â��ł��Ȃ��Ȃ��Ċ��҂���t���猩������Ă��܂��Ƃ����u�����v�̔��������ɂȂ��Ă��܂��B����́A��ɏq�ׂĂ����悤�Ɏ������Ƃ̂ł��Ȃ����҂���t�́u���Ȍ��͊��v��ł��̂߂����Ƃ�����悤�Ƃ���A��t���̐S���̖��ł�����̂ł��B
�������銳�҂�D�悵�Đf�ÁA�Ƃ����g�����̗��Ԃ�
�@�����A����͒P�Ɉ�t���s�k�����������ł͂Ȃ��A�����銳�҂�D�悵�Đf�Â��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����g�����̗��Ԃ��ł�����܂��B�d�����̈�Ë@���������}�����a�@�ł���قǂ����l����ł��傤�B�܂��A�d�����̕a�@�ł́A�d������K�v�Ƃ����Â��s��Ȃ���Ζ��ʂ��o�Ă��܂��A�Ƃ�����Ìo�ς�ی��f�Ï�̖�������̂ł��B�܂�A�u�����v�̔����͂�����x�d�����Ȃ��ʂ�����̂ł��B
�@�ł́A���������邽�߂ɂ͂ǂ�����Ηǂ��̂ł��傤���B���@�\�a�@�����̋K�͂�傫�����āA���Â��ł��Ȃ��i�s����������a�̐f�Â��s����������邱�Ƃ͉����@��1�ł��B�������A����͂����炭��Ìo�ϓI�ɂ������͓���Ǝv���܂��B�܂��A�i�s��������̊��҂��A�Ƒ��̂��鎩��痣�ꂽ�ꏊ�ň�Â��p�����ĎȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������܂��B���́A���̗l�ȕ����Ɉ�Â��i��ł������Ƃ͗��z�ł͂Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@����ɑ�������@�́A���҂�����Z���^�[���w�a�@�Ȃǂ̈�t�ɗ��肷�����A�u���������v���ق��Ɏ����Ƃł��B���@�\�a�@�͂����܂ŁA���̋@�\�����҂����p���邾���̏ꏊ�ł���Ɗ�����Ă��܂��A�������S���痊��ɂł���厡��͕ʂɎ��̂ł��B��������A���@�\�̕a�@�ł̈�Â̑ΏۂƂȂ�Ȃ��悤�ȕa��ɂȂ��Ă��A���̌�̈�Âɂ��đ��k�ł��邱�Ƃ��ł��܂��B
�悢�厡���������
�@�܂�A���@�\�a�@���痣��邱�ƂɂȂ��Ă��A�����́u�����v�Ƃ͊����Ȃ��悤�Ȏd�g�ݍ������邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B���x�Ȑ���́A���̋@�\�𗘗p���邾�����A�Ɗ��ґ��������邱�Ƃ�1�̉����@�ł��B
�@���āA�����܂Ő���ɗ��肷���Ȃ��悤�ɂƂ������ƂŘb�͐i�߂Ă��܂������A����������̒��ɂ��f���炵����t����R���邱�Ƃ͎����ł��B���Â̓���a�C�ł���Ȃ�����A����̒�����悢�l�������邱�Ƃ���ԑ�ɂȂ�܂��B
�@�w����Ƃ����O��ł���ɂȂ����x(���~��)�̒��ҁA���R�m�N����́A40�Α�O���Ɉ����]��ᇂƔ����a�Ƃ���2�̂���ǂ��܂������AIT�֘A��Ђ𗧂��グ�����̌o���Ɣ\�́A�����Đl�����t���Ɋ��p���āA���҂��������Ă����܂����B���Ҋw�����R�ɐg�ɂ��Ă��邨��{�ƂȂ���ł��B
�@���R����́A���Ö@�Ɋւ�����̎��W���s���A�ǂ̕a�@���ǂ�����I�m�ɔ��f���A�ǂ��厡��ɏ������Ă��܂��B�]��ᇂ����Â����]�O�Ȉ���A�����a�����Â������t���Ȉ���A����ł���Ȃ��獂���I�ȑԓx���Ƃ邱�Ƃ͂Ȃ��A���҂̎��������d�A���҂̋C�������ƂĂ���ɂ��Ă�����悤�ł��B
�@�����̂����������炱���A�u�����v�ɂȂ�Ȃ������ƌ������Ƃ��ł��܂����A�����炭���R����Ȃ獂�x�@�\�a�@�ł̎��Ö@���Ȃ��Ȃ����Ƃ��ł��A���̕a�@�ɂ����݂����ƂȂ��A�ʂ̓���T�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@����̈���(�{���͈������������Ƃ��Ă���̂ł͂���܂��A�����̂悤�ɕ�������l������ł��傤)�������Ă��Ȃ���A����ɂ�����Ȃɐl�ԓI�Ȉ�Â�����t�����邱�Ƃ�m�邱�ƂŁA�z�b�Ƌ����Ȃł��낷�C�����ɂȂ�܂����B
�����҂���҂������邱�Ƃ����
�@�����āA�킽�������C�ゾ����30�N�ȏ�O�ɂ͂���������O�ȑ��݂��������҂ɍ����I�Ȉ�t�́A���ł͏����h�ɂȂ��Ă��܂��B����ƂƂ��Ɉ�t�̑����ω����Ă��Ă��܂��B
�@���̂悤�ȕω��̎��������炱���A�����ɍ�������t���厡��Ƃ��đI�����邱�Ƃ��A�悢��Â����Ō���I�ɑ厖�ƂȂ�̂ł��B
�@��Î҂ɕω��𑣂��̂����҂̗͂ł��B�����I�Ȉ�t�͌������Ă�����Ύ���ɐ�ŋ@��ƂȂ��Ă����̂ł�����B -
�@�傽�鎩�o�Ǐ�Ȃ��B�������ꂽ���ɂ͂قƂ�ǂ������̃X�e�[�WIV�ŁA5�N�������͂킸��1�`2���B���������A���̓�a�̒��ł��ł��|�낵���u����̉��l�v�ƌĂ�鏊�ȁi�䂦��j���B�������A���̂���������̎��Ì���̌��i���ߔN�A���I�ɕω����Ă���Ƃ����B
�@***
�@���������X�����Ə\��w���A�݁E�_�ǁE���X�ǂ̈ꕔ�A�_�X���܂Ƃ߂Ď�菜���B�����ď������������������A�c�����݁A�_�ǁA���X�ǂƐڍ�������B�X���\��w���؏��p�͕��G�ŁA�����������p�̒��ł����ɓ���B��ᇂ��喬�ɐZ�����Ă���ꍇ�͂���ɍ���ɂȂ�A��p���Ԃ�6�`8���Ԃɋy�ԁB��ʂ̑����a�@�ł͔N��10�`20��s���Ă���Ε]������邱�̓��p���A100��߂������Ȃ��Ă����Ë@�ւ�����B�É������É�����Z���^�[���B�����ł��������Â��哱���閼����A�ƊE�̐l�Ԃ͂����ĂԁB
�u�_�̎�v�����B���@�����́E�_�E�X�O�ȕ����̏�⍎�F���ł���B
�u�_�̎�Ȃ�đ��݂��܂���B�������M�O�ƋZ�p�͕K�v�ł����A���ɂ����ł��Ȃ���p�Ȃǂ���܂����v
�@���̏���t�͂����������邪�A�ނ炪���̕���ʼn���I�Ȑ��ʂ������Ă���͕̂�����Ȃ��������B����t�̃`�[�����܂����ڂ����̂́A2007�N�A�h�C�c�Ŕ��\���ꂽ����Տ������̌��ʂ������B�����������p���s�������҂ɍR����܁u�Q���V�^�r���v�𓊗^�����Ƃ���A��p�����̊��҂�5�N��������10�E4���������̂ɑ��A20�E7���Ɣ{�̉������ʂ��������̂��B
�u�w��p��̍R����ܓ��^�x�����������グ�邱�Ƃ��ؖ����鏉�̃G�r�f���X�ł����B�����Ŏ��B��07�N����Q���V�^�r���ƍR����܁wS-1�x���r����Տ��������s�����B�S��33�J���̈�Ë@�ւ�385��̊��҂����ΏۂɎ��{���܂����v�i���j
�@���̌��ʂ͐��E��������������̂������Ƃ����B
�u�Q���V�^�r����5�N��������24�E4���ł������AS-1�𓊗^�����O���[�v��44�E1���Ƃ������ٓI��5�N���������L�^�����̂ł��v�i���j
�@���̌��ʂ��Љ���_�����A���N�A���E�I���Ђ̂����w�G���u�����Z�b�g�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�B
�u�Ȃ��Q���V�^�r�����S-1�̕������ʂ��������̂��B���������p��ɍĔ�����̂́A�̑��ւ̓]�ڂł���ꍇ�������B���̓_�AS-1�͂��̊̑��ւ̓]�ڂ����͂ɗ}���Ă���悤�Ȃ̂ł��B����̖ڕW�́A�w��p��̍R����ܓ��^�x���Â�5�N�������������50���܂ŏグ�邱�Ƃł��B��p���ł���A2�l��1�l�������鎞��ɂȂ�킯�ŁA10�N�O�܂łȂ�l�����Ȃ��i���ł��v�i���j
�@��]�̌��������Ă����B�����Ƃ��ŏ������p�s�\�̊��҂͂ǂ�����Ηǂ��̂��B�Ȃɂ��낷��������̏ꍇ�A�������Ɏ�p���\�Ȃ̂�30�`40���ɉ߂��Ȃ��B�����������҂̗Տ������ɐϋɓI�Ɏ��g�ވ�t������B���É���w�a�@������O�Ȃ̓���w�y�������B
�u�ȑO�́w�邩�ǂ����x�����Ȃ��������������Âł����A�ߔN�͎�p�E�R����܁E���ː������ɑg�ݍ��킹�A�헪�𗧂Ă�w�W�w�I���Áx�̏d�v�����F�m����n�߂܂����B�ڕW�́A�؏��ł��Ȃ��Ɛf�f���ꂽ���҂���ɑ��A�W�w�I���ÂŎ�p�܂ł����Ă������ƁB���@�ł�10�N����16�N�ɂ����A�喬�⓮���ւ̐Z��������A��p�s�\�Ȃ���������87��ɑ��A8�J�������AS-1��肳��ɋ��͂Ȍ��ʂ�����R����܁w�t�H���t�B���m�b�N�X�x�������́w�i�u�p�N���^�L�Z���x�̓��^�ƁA���ː����Ái1�J�����j���s���āA��p��ڎw���Տ����������{���܂����v
��3000�{���g�̍����d��
�V����u�i�m�i�C�t�v
�@���ʂ͂ǂ��Ȃ������B
�u��p���ł���悤�ɂȂ����̂�71���B������2�N�������͂���܂ł�7������66���Ɣ���I�ɐL�т܂����B�܂������I��5�N�������͏o���܂��A���݁A5�N���o�߂��Đ����Ă�������������܂��B�]���͎�p���ł��Ȃ���A�F�A2�`3�N�ȓ��ɖS���Ȃ��Ă��܂��̂��펯�������̂ŁA�傫�Ȑi���ł��B�a�@�Łg��p�͖������h�ƌ����Ă��A���߂��A�Z�J���h�I�s�j�I�����Ăق����v�i���j
�@���������������Â̐��E�ł́A����Ȃ�V������T���Ă���B���̈�Ë@��̖��̓i�m�i�C�t�B�č��ł͔F����Ă��邪�A���{�ł͂܂����F����Ă��Ȃ����߁A�Տ������Ƃ��Ď��{����Ă���B�ډ��A���̈�Ë@��������ŗB��A��g���A���Â��s���Ă���̂��A�R���a�@����Ǐ��Ö@�Z���^�[���̐X���j�T��t�ł���B
�u�����g�̉摜�ł���������̏ꏊ���`�F�b�N���Ȃ���A����15�Z���`�A���a1�E1�~���̐j��2�`6�{�A�̂̕\�ʂ������A��ᇂ����͂ނ悤�Ɏh���Ă����܂��B�����Đj�Ɛj�̊Ԃ�3000�{���g�̍��d���̃p���X�d���𗬂��A����זE��100������1�~���̏����Ȍ����J���A���ł�����̂ł��v
�@4�{�̐j���g���A�킸��15���ԂقǂŒ��a3�Z���`���x�̋���͈̔͂̂�������ł�������Ƃ����B
�u�i�m�i�C�t���Ẫ����b�g�́A���W�I�g�Ď܂ȂǂƈႢ�A�זE�݂̂����ł����A���ǂ�_�o�Ȃǂ̊Ԏ��������Ȃ����ƁB���B�͎�ɐ؏��s�\�Ǐ��i�s����������ɑ��ăi�m�i�C�t���Â��s���Ă��܂����A����ɂ��喬�A���o�����A�㒰�Ԗ������Ȃǂ̑������ǂ̍\�����c�����܂܁A�����ɐZ�����Ă����ᇍזE���������ł���������ʂ�����B�{���Ȃ��p�Ŏ��Ȃ�����זE��I�m�Ɏ��ł����A��ᇂƌ��ǂƂ�藣���A��p�\�ȏ�Ԃɂ����Ă����B���邢�͎�p�ł��Ȃ��Ă���ᇂ�����Ə��������āA�Ǐ�����A�����Ԃ̐�����̂��ړI�ł��v�i���j
�@���̎��ÂŐ�s����č��ł́A2015�N�A���C�r����w����p�s�\�ȋǏ��i�s����������Ƀi�m�i�C�t���Â��s�����f�[�^�\�����B���ʂ�200��̂���50�Ⴊ�A�㒰�Ԗ������ɐZ�����Ă�������������Ƃɐ������A��p�\�ɂȂ����B�܂��A��p�ł��Ȃ������Ǘ���R����܂����̎��Âɔ��2�{�̐������Ԃ�����ꂽ�Ƃ����B
�@�X����t�́A��N���炱�̃i�m�i�C�t�̗Տ��������n�߁A���N8���̎��_�܂ł�32��Ɏ��{���Ă���B
�u8�����_�ōł��o�߂��������҂��܂��p��15�J���ł�����A���v�����\�ł���i�K�ɂ͂���܂���B�ł��A���̕��͂���̉e�������A�O���ōR����܂̎��Â��Ȃ���A���C�ɕ��ʂ̐����𑗂��Ă��܂��v�i���j
�@���̃i�m�i�C�t���W�w�I���Â̈�ɑg�ݍ���ł����A5�N�������͂���ɐL�т�͂����B�u����̉��l�v�̐����ɂ܂�����߂Â����ƂɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B -
�����l�ԂƓ����悤�ɃX�g���X���d�Ȃ�Ǝᔒ����������炵���\�\�B�����w�҂Ŏ��ǂ̌[�������ł��L���ȃe���v���E�O�����f�B������̌����`�[�����A�����s���w��̍������ɂ���Ȍ������ʂ\�����B
���[�͐��N�O�A�R�����h�B�f���o�[�Ō��̌P���{�݂��^�c����J�~�[���E�L���O�����A����̋N�������������قǎႢ�������甒����т��������ۂɋC�t�������Ƃ������B���̘b�����R�����h�B����w�����̃O�����f�B�����̊��߂Ō������n�܂����B
�O�����f�B�������L���O���̘b���Đ^����Ɏv�������ׂ��̂́A�č��̗��哝�̂Ɏᔒ�����������ۂ������Ƃ����B
�����`�[���̓m�[�U���C���m�C��w�łS�Έȉ��̌��S�O�O�C�i�������������j��ΏۂɁu�ᔒ���v�̏������B���ʂ͂S�Έȉ��̌��Ɏᔒ���͌����Ȃ��Ƃ����B
�����Ώۂ̌��͂��ꂼ��Q���̎ʐ^���B��A������ɂ͒����̖ړI�������Ȃ��܂ܕ��i�̍s���ɂ��ĂQ�P���ڂ̃A���P�[�g�ɓ����Ă�����Č��̕s������Փ����̋����ׂ��B�l�Ԃ̏ꍇ�A������������̕s����ȏ�ԂƃX�g���X�Ƃ̊֘A���w�E����Ă���B
�A���P�[�g�̕��͂ł́A�P�l�ŗ���Ԃ�����ƃN���N��������i�����肷��s����A�吨�̐l������Ɛg�������߂�s���͕s�����̕\��Ɣ��f���A�l�ɏo��Ɣ�ѕt���s����A�U���̍ۂɃ��[�h���ߓx�Ɉ�������s���͏Փ��̋����̕\��Ɣ��f�B���̌��ʂ��ʐ^�Əƍ����āA�@�̎���̔����̑����Ƃ̊W�ׂ��B
�O�����f�B�����͕@�̎���̔����̑������S�i�K�ɕ����A�S���������Ȃ��u�O�v����A�S�̂������ɂȂ��Ă���u�R�v�ɕ��ށB�s������Փ����������Ɣ��肳�ꂽ���́A�����̑����O���[�v�ɕ��ނ����m�����S�O�`�U�T�������Ȃ邱�Ƃ����������B
���̃X�g���X�Ǝᔒ���̊W�ɂ��ē����͉��^�I�������Ƃ����m�[�U���C���m�C��w�̃g�[�}�X�E�X�~�X�����́A�u�f�[�^�͂���Ƌ����悤�Ȍ��ʂ��o���v�Ƙb���Ă���B
�O�����f�B�����ɂ��ƁA�X�g���X�Ǝᔒ���Ƃ̊W�͐l�ƌ��ȊO�̚M���ނł͊m�F�ł��Ă��Ȃ��Ƃ����A����Ɍ�����i�߂�K�v������Ƃ��Ă���B -
�V���M�����e�B�[�ɂ���
�u�������������Ă���Ԃɂ͋N����Ȃ��v�Ƃ����\��������܂��B�s���̕a�̎��Â�P���ԗ��s�A�����̉����ȂǁA�l�ނ̍ł���S�I�Ȋ�]�▲�Ɋւ���c�_�ł́A�������̕\�����p�����܂��B�������ŋ߁A�ꕔ�̉Ȋw�҂́A���ĂȂ��y�[�X�ŋZ�p���i�����邱�ƂŁA�߂������A�l�H�m�\�������I�ɐi���𐋂���悤�ɂȂ�u�V���M�������e�B�iSingularity�j�v�ɓ��B����\��������Əq�ׂĂ��܂��B
���������Ȋw�҂�1�l�ł���_�ˑ�w�̏��c��疼�_�����́A�V���M�������e�B�͋߂������ɋN���邾���łȂ��A�~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����l���������܂����B����ɁA�\���Ȏ���������Γ��{�͔F�m�������u���g���ĉ��ď������������V���M�������e�B�ɒB����\�����炠��Ƃ��Ă��܂��B�挎�̍u�`�ł́A�V���M�������e�B��̐l�ނ̓��퐶���ɂ��ČÑ㕶�������������ɏo���Đ������܂����B�Ñ�M���V����[�}�ł́A�L�x�ȓz��J���͂ɂ����1���l�̎s���������A�X�|�[�c�A��y�ȂǂɎ��R�Ɏ��Ԃ��g�����Ƃ��ł��܂����B���{�b�g��������J�����s�������Љ�ł��������Ƃ��N����A�ٗp���x��v�𗧂Ă�Ƃ����T�O�����������\��������Ƃ����̂ł��B
�l�H�m�\���l�ނ̐V�����ƍl���Ă���̂́A���c���_���������ł͂���܂���B����ŁA�x����炷�e���͂̂��鐺�����݂��܂��B �X�e�B�[�����E�z�[�L���O���ƃC�[�����E�}�X�N���́A�Z�p�̐i���͌��ݒn���̂��߂ɂȂ��Ă�����̂́A����s�\�Ȑl�H�m�\�������炷���Ђ͐l�ނ̗��j��ōő�̂��̂ɂȂ蓾��Əq�ׂĂ��܂��B�ŋ߂̃W���p���^�C���Y�̋L���ł́A���Ƃ̂Ȃ��Љ�Ƃ������z���̉��b����O�ɁA�l�Ԃ̎d����e�Ղɂ��Ȃ���m�����������@�B���������邱�Ƃő�ʂ̎��Ǝ҂����܂�A�a瀂��g����\��������ƌx�����Ă��܂��B���̃V�i���I�́A�H��ɂ����Đ��Y�H���̎���������ƈ��̐E��D���Ƃ������g�債���悤�Ȃ��̂ƌ�����ł��傤�B
����A�i���̃y�[�X���݉����Ă��邱�Ƃ��w�E������^�I�Ȑ�������܂��B���[�A�̖@���̓R���s���[�^�[�̐��\��2�N���Ƃɔ{������Ƃ��Ă��܂����A���̐��̓g�����W�X�^�̏��^���̌��E�ɂ�鋺�Ђɂ��炳��Ă��܂��B�ŋ�Nature�Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ł��A�l�ނ͍ŐV�̋Z�p�Ō��ݒB���ł�������̌��E�ɒB���悤�Ƃ��Ă���Ƃ���Ă��܂��B�������A�Z�p�̐i�����ǂɓ˂��������Ă���Ǝv���镪����������ŁA�l�H�m�\�Ɛ_�o�Ȋw�̕���ł͒������i���������Ă��܂��B���N�����ł��͌�Ə����ɂ�����l�Ԃ̉��҂��R���s���[�^�[�ɔs�k���i���܂����B�挎�ɂ́AFrontiers in Neuroscience�ɁA���G�Ȕ]�������ɕϊ����邱�Ƃ��ł���Ƃ��鑍�����f�ڂ���܂����B����́A�����ߏnj�Q�̊��҂ɂƂ��Ċ�]��^����i���ł��邾���łȂ��A�l�H�m�\�̔��W�ɂ����Ă��������Ȃ��O�i�ł��B
�l�H�m�\�̐i�������āA�e���{���ڕW���߂Ă��܂��BEU�̃q���[�}���E�u���C���E�v���W�F�N�g�́A2023�N�܂łɃR���s���[�^�[���g�p���Đl�Ԃ̔]�̓�����͕킷�邱�Ƃ�ڎw���A�o���1600���~�ȏ�ɏ��Ɨ\�z����Ă��܂��B�l�Ԃ̕��G�Ȕ]�@�\�̉𖾂�ڎw������1�̃v���W�F�N�g�ł���A�����J��BRAIN�C�j�V�A�e�B�u�́A2�N�Ԃő����̐_�o�Ȋw�̃u���C�N�X���[��B���������߁A10���ɓ����z��1��5000���h���ɔ{�����܂����B�����̃C�j�V�A�e�B�u�₻�̑��̍ŋ߂̐i�W���]�����̐��m�ȒǐՂ��\�ɂ��钆�A����20�N�ԂŐl�H�̐l�Ԃ̔]�����o���Ƃ����W�]����������ттĂ��܂����B���̏ꍇ�A�R���s���[�^�[���������g��v���n�߂�V���M�������e�B��2045�N�܂łɋN����Ɨ\�z����܂��B
���c���_������̎咣���������A�V���ɏo������l�H�m�\���l�ނ̏����ɂȂ�̂Ȃ�A�������������Ă���ԂɋN����V���Ȕ����ɂ��Ă���ȏ㌜�O����K�v�͂Ȃ��̂�������܂���B����ǂ��납�A���܂Ő����Ă�����̂��ɂ��Ă����A�����S�z���Ȃ��Ă��悭�Ȃ�̂�������܂���B -
���ȏ��ŏK���g���E�l�啶���h�ƌ������\�|�^�~�A�����ɃG�W�v�g�����A�C���_�X�����ɉ��͕����B���\�|�^�~�A�����̐����͋I���O35���I���A�G�W�v�g�����͋I���O31���I���Ƃ�������\�\�[���A�C�������Ȃ�قǑs��ȉߋ������A�k�邱�Ƃ����2000�N�A�I���O54���I�̈�\���G�W�v�g�Ŕ������ꂽ�B
�u�G�W�v�g�l�ÏȂ��t�F�C�X�u�b�N�Ŕ��\�����̂ł����A���n�A�r�h�X�ŁA�I���O5316�N�́g�Ñ�s�s�h���������ꂽ�Ƃ����̂ł��B�G�W�v�g�l�����őg�D���ꂽ���@�`�[�����Ƃ̈ꕔ��y��A�Ί�ɉ����A15�̕���������Ƌ����Ă��܂��B��̂����̂������̓A�r�h�X�ɂ��鉤���̕���傫�������ŁA�t�@���I�̉\���͒Ⴂ�悤�ł����A�G�W�v�g�l�ÏȂ́g���߂�ꂽ�l�������ɐg�����������������ؖ����Ă���h�ƃR�����g���Ă��܂��v�i��莆�L�ҁj
�@�A�r�h�X�̓J�C������i�C�����k�邱��500�L���A�Ñォ��M���W�߂��I�V���X�_�̕悪���邱�ƂŒm����B�_�Ȃ̂ɂȂ��悪���邩�ƌ����A�I�V���X�͌��X��n�Ɣ_�k�̐_�B�l�X���Q�삩��~���A�h���Ă����̂��_�Z�g�ɓi�܂�A�E����Ă��܂��̂��B���̌�A���ł���Ȃł�����C�V�X���_�̎�Ń~�C���ƂȂ蕜���A���{�̉��Ƃ��ČN�Ղ��邱�ƂɂȂ邩���͋�Ȃ̂����B
�u���̃I�V���X�̕�Ɋ��Y���悤�Ɍ��̂��G�W�v�g�ōł��������Ñ㌚�z�̂ЂƂA�Z�e�B1���̑��Փa�B����́g�Ñ�s�s�h��\�́A��������킸��400���[�g����������Ă��炸�A�A�r�h�X���Ȃ��Ñ�̐��n�ƂȂ��������A�������������ɂȂ邩������Ȃ��ƒ��ڂ��W�߂Ă���̂ł��v�i���j
���������t����������n��
�@�G�W�v�g�w�ƌ������̐l�A����c��w���_�����̋g���쎡���������B
�u�����ւ�Ӗ����锭�����Ǝv���܂���B��������Ă����̂��t�@���I�łȂ��͓̂�����O�B�����܂��A�t�@���I�ƌĂׂ�悤�ȁg���ׂ鉤�h�͓o�ꂵ�Ă��Ȃ��̂ł��B7000�N�O�̃G�W�v�g�́A��̏W��������_�k�����Ɉڍs������܂��ɂ��̎����B�����s�s�ɂȂ�A�����Ɓi�m���X�j�ɂȂ�A���ɂȂ�Ƃ����ߒ��Ō����A�܂��g���h�̒i�K�Ȃ̂ł��傤���A�G�W�v�g�ŌÂƌ����Ă悢�_�k�����̍��Ղ��������ꂽ���Ƃ̈Ӌ`�͔��ɑ傫���v
�@�~�g�R���h���ADNA�Ȃǂ̉�͂ɂ��l�ނ̗��j��ǂ��A�����Ȋw�����ق̐l�ތ��������A�c���ꎁ�������B
�u������7000�N�O�Ƃ����̂��s���|�C���g�ł��B�_�k�����̒n�ɓ`�d���Ă���A���ƌ`���ɓ��鎞���̏ɂ��Ă͂قƂ�Ǖ������Ă��܂���ł����B��ʂɔ_�Ƃ̎n�܂�͊K���Љ���o�������A�������t���������܂��B�܂��ɂ��̎����̈�\�͋M�d�ł��傤�v
�@���������ꍇ�̔N��͒Y�f14�Ƃ������ː����ʌ��f�̔䗦���v��A���肷�邱�Ƃ������B�g�p�����L�@���́g�F�Ձh�ƌĂ�镰���ΐՂȂǂŌ�����Y���B���܂��A�l�ނ̊����̏ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�c���͌����B
�u�����炨�悻20���N�O�ɁA�A�t���J�Œa�������Ƃ���錻���l�ނ́A6���N�قǑO�ɃA�t���J���o��ƑS���E�ɍL����A1��6000�N�قǑO�ɂ͓�Ă̓�[�܂œ��B���Ă��܂��B���̌�A��Z�����Ɉڍs���A���\�|�^�~�A�ł�9000�N�قǑO�ɂ͔_�k���n�܂����ƍl�����Ă��܂��B�A�r�h�X�̓G�W�v�g�ɂƂ��Ă̓A�t���J�ƃA�W�A�̃N���X���[�h�B���\�|�^�~�A����_�k���`���A�A�r�h�X����G�W�v�g�������n�܂����ƍl����Ƌ����[���ł��ˁv
�@�����̒a���܂ők��A�Ȃ�Ƃ��s��Șb�Ȃ̂��B -
�@�Q�s���ŊÂ��H�ו����~�����Ȃ�̂́A�]�́u�O���O�玿�v�ƌĂ�镔���̓����ɂ�邱�Ƃ��A�}�E�X�̎����ŕ��������B�}�g��̃~�n�G���E���U���X�y�����炪�P�O���܂łɉp�Ȋw���C�[���C�t�ɔ��\�����B�����s������얞�A�����K���a�Ɏ���d�g�݂��𖾂��A���N�I�ȐH�����𑣐i����̂ɖ𗧂Ɗ��҂����B
�@�����ɂ͐Q����ȂȂǂ̐[���m�����������ƁA�̂͋x��ł��Ă��]���������Ă��郌������������B����܂ł̌����ŁA�����������s������ƁA�H�߂��đ���₷���Ȃ�X�������邱�Ƃ��m���Ă����B
�@�}�E�X�̃���������W����������s�����Ƃ���A�����̎听���ł���V�����⎉���̐ێ�ʂ����������B�]�̑O���O�玿�̊�������`�q����Ȃǂŗ}������ƁA�����̐ێ�ʂ͑��������A�V�����͑������A�����ɑ���~����S���Ă��邱�Ƃ����������B�@ -
�u�Q�m���ҏW�v�Ƃ����V�Z�p���g���ĕs�D�ɂ����O�����E�u���[�M������i�Ȃǂɕ������A���Ԃ����₳����v���W�F�N�g���A���Y�����E����@�\��O�d��̃O���[�v���i�߂Ă���B�O�������쏜����V�������݂ŁA�R�N����߂ǂɐl�H�r�Ŏ������n�߂�v�悾�B
�@�u���[�M���͖k�Č��Y�B�P�X�U�O�N�ォ�獑���e�n�ɍL�������B���i�ɂ̓u���b�N�o�X�ƍ��킹�ĂP�Q�S�O�g���i�Q�O�P�T�N�j����Ɛ��肳��A�����Ȃǂ�H�ׂ邽�ߍݗ������ւ̈��e�������O����Ă���B�Ԃł̕ߊl��d�C�V���b�N�ŋ쏜�������Ă���A���ꌧ�ƍ����N��P���~�̑���S���Ă���B�����ߔN�͓V��Ȃǂ̉e���ŋ쏜�ʂ�����A���̂܂Ƃ߂ł́A�P�S�N���琶���ʂ͑����ɓ]���Ă���B
�@�����O���[�v���i�߂Ă���̂́A������邽�߂ɕK�v�Ȉ�`�q���Q�m���ҏW�ɂ���ĉA���X���s�D�������`�q�ψق����I�X���ʂɌJ��Ԃ�����������@�B���̃I�X�Ɩ쐶�̃��X����z���Đ��܂ꂽ���X�͗����Y�߂��A�Ō�̂P�C�܂ŋ쏜�ł���Ɗ��҂���Ă���B
�@�č��̌̃f�[�^�����ɂ������Z�ł́A�����̐������̂P�O����N�����A�ߊl�Ƒg�ݍ��킹��A���i�Ȃǂł����\�N�ō���ł���\��������Ƃ����B -
�@�ԕ��ǂ��܂߂��A�����M�[�́A���Ƃ��Ƒ̂ɐN�������ۂ�E�B���X�Ȃǂ���̂����Ɖu�V�X�e�����ߏ�ɔ������Ă�����B
�@�ԕ��ǂ���ς����A�����������Ă����ɂ͌������Ȃ��V�X�e���ł���B���̖Ɖu�Ɋւ�邢�����̈�`�q�̓l�A���f���^�[���l�ƃf�j�\���l����́u�v���[���g�v�������ƍ��N��1���ɖ��炩�ɂȂ����B
�@��`�w�̉Ȋw���uThe American Journal of Human Genetics�v�œƂ̌����`�[�������\�����B���{�l�̈�`�q�̒��Ƀl�A���f���^�[���l���u����Łv����B
�q�g�̓l�A���f���^�[���l��ł��č��̔ɉh��z�����B�ƁE�}�b�N�X�v�����N��������Janet Kelso�̃`�[���͌���l�̈�`�q�̒��ɁA�l���f���^�[���l��f�j�\���l�Ƃ̌�z�ɂ���Ďc�葱���Ă���u�ނ�v�̈�`�q���������Ă����B
�@�l�ނ̐i���ŃG�|�b�N���C�L���O�ȍŋ߂̔����Ƃ����A�q�g����ł������ƍl�����Ă���l�A���f���^�[���l�Ɛl�Ԃ���z���Ă������ƂƑ�3�̐l�ރf�j�\���l�̔������B
�@����3���50���N�O�ɋ��ʑc�悩�番���ꂽ�ƍl�����A�l�A���f���^�[���l�̓q�g��萔�\���N�O�ɃA�t���J���o�Ď�Ƀ��[���b�p�ɍL�������B
�@�����`�[�����ڂ������̂�TLR�̈�`�q�B����܂ł̌����f�[�^���ƂɃs�b�N�A�b�v�����BTLR(Toll Like Receptor)�͍זE�̕\�ʂɃj���L�j���L�Ɛ����Ă���^���p�N���B�Ɖu�Ŕ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����B
�@�̂��O�G������ɂ́A�܂��O�G�̐N�����֒m���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̖h�ƃZ���T�[�̖�����S���̂�TLR�Ƃ����^���p�N���Ȃ̂��B
�@�̓��ɐN�������ۂ�ۗށA���̈ꕔ������TLR�ɂ������ƃZ���T�[���쓮���A�O�G���������זE���W�܂�����ƁA���܂��܂ȖƉu�V�X�e���������d�g�݂��B
�l�A���f���^�[���l�̈�`�q���ł����������{�l
�@��������TLR�̂���TLR1��TLR6�ATLR10�͐��F�̏�ɗאڂ��Ă���B�l���f���^�[���l��f�j�\���l��3��TLR���܂ޗ̈������l�Ɣ�r����B
�@���[���b�p�l�Ɠ��A�W�A�l�A�A�t���J�l�Ȃnj���l��14�W�c�̂��̗̈�ׂ��7�̃^�C�v�ɕ��ނ��ꂽ�B���̂���2���l���f���^�[���l�R���A�ЂƂ��f�j�\���l�R�����Ɣ�������B
�@���_�I�ɂ̓q�g��萔�\���N��ɃA�t���J���o�āA�������o�R���ă��[���b�p�ɍL�������l�A���f���^�[���l�̈�`�q�́A�A�t���J�Ɏc�����c��R���̃A�t���J�l�ɂ͑��݂��Ȃ��B
�@���ׂ�ƁA�m���ɃA�t���J�l�ɂ̓l���f���^�[���l�R����TLR���܂ޗ̈悪�قƂ�ǂ݂��Ȃ������B
�@���̂悤�ɁA����l��TLR���܂ޗ̈�̃Q�m���z����ڍׂɒ��ה�r���ăl���f���^�[���l�ƃf�j�\���l�R�����Ɠ˂��~�߂��B
�@�����āA�@�\�����ɏd�v���Ȃ̂ŁA�����N�Ƃ������R�I�����Ă��قƂ�Ǖς�炸�ɍ��p�x�Ŏc���Ă����ƍl�����B
�@���͂��̃l�A���f���^�[���l�R����TLR1��TLR6�ATLR10��`�q���ł��������̂����{�l�B�ǂ̏W�c���������A��51���������Ă����B
�@�ԕ��ǂ̍ő�̗v����TLR1��TLR6�ATLR10�����ڊ֗^����킯�ł͂Ȃ����A�Ɖu�V�X�e����ʂ��Đl�ނ̑s��Ȑi����z�����A���Ȃ�l�A���f���^�[���l���v�����Ƃŏ����͏Ǐy���Ȃ邩������Ȃ��i����Ȃ��Ƃ͂���܂���j�B -
�n���ɂ���āA���ȋL�����]���ŋ��������\��������Ƃ̌������ʂ�29���A���\���ꂽ�B�{�����܂ܐQ�邱�Ƃ����߂�Â��i���ɁA�Ȋw�I�ȐM�҂傤����^���錋�ʂƂȂ��Ă���B
�@�����ƕč��̌����`�[�����p�Ȋw���l�C�`���[�E�R�~���j�P�[�V�����Y�iNature Communications�j�ɔ��\���������_���ɂ��ƁA�`�����ꂽ����̈����L����ێ������܂ܖ���ɏA���ƁA���ꂪ�]�ɐ[�����ݍ��܂�A��ɂ��̋L����@������̂���荢��ɂȂ�Ƃ����B
�@�����E�k���t�͑�w�iBeijing Normal University�j�ō���̌��������{�����_���̋����ҁA���ΓN�iYunzhe Liu�j���́AAFP�̎�ނɁu�̂���w�{�����܂ܐQ��ȁx�ƌ����Ă��邪�A���̒��������A���ɂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����̌����͎������Ă���B���ɏA���O�ɂ܂��A���̉��������߂����v�ƌ��B
�@������͐������L���ɋy�ڂ��e���ׂ邽�߂ɁA�j�q�w��73�l��팱�҂Ƃ��č̗p�B2���Ԃɂ킽��A����̉摜�ɍD�܂����Ȃ��L�����֘A�t����P�����s�����B
�@���̌�A�팱�҂ɂ��̉摜���Ăь����A�D�܂����Ȃ��A�z����݂����点�邩�A�܂��͂���ɋt����ċL�����ĂыN�����Ȃ��悤�ɂ��邩�A�ǂ��炩����̎w�����o�����B
�@������2��s���A1��͋L���̊֘A�t���̌P����30����ɁA����1��͔팱�҂���Ӗ�������ɂ��ꂼ����{�����B�������͂����Ɣ팱�҂̔]�������X�L�������ċL�^�����B
�@���̌��ʁA�팱�҂�́A������ɋL����}����������͂邩�ɓ���Ɗ����邱�Ƃ����������B�܂��]�X�L�����ł́A�D�܂����Ȃ��L���������L���Ɋ֘A����]�̕��ʂɕۑ�����Ă���\�����������Ƃ����������B
���L���̃R���g���[���Ő��_��w�ɉ��p��
�@�����́A�V���Ɋl�����ꂽ��]���ŕۑ��A��������A�Z���L�����璷���L���̃l�b�g���[�N�ւƈړ�����d�g�݂ɉe�����y�ڂ����Ƃ��m���Ă���B
�@�����`�[���ɂ��ƁA�D�܂����Ȃ��A�g���E�}�i�S�I�O���j�ƂȂ�悤�ȏo�����̋L���́A�D�܂����L����A�ǂ���ł��Ȃ��o���̋L�����������Ԏc��ꍇ�������Ƃ����B���������̋L���͂�����x�A�ӎ��I�ɐ��䂷�邱�Ƃ��\���B
�@�����L����}���ł��Ȃ����Ƃ́A�}����S�I�O����X�g���X��Q�iPTSD�j�ȂǑ����̐��_��w��̖��Ɗ֘A���Ă���B
�@����̍ŐV�������s����܂Łu�L���̗}���͐����̑O��ǂ��炪���₷���̂��A���邢�͂��ɂ����̂��A�������Ă��Ȃ������v�Ɩ����͎w�E�����B
�@���̂悤�ȃv���Z�X�Ɋւ��闝����[�߂邱�ƂŁAPTSD�Ȃǂ̎����ɑ��鎡�Â̌���ɂȂ���\��������B�u�Ⴆ�A�g���E�}�I�Ȍo������������̐������D�ɂ��A�g���E�}�ƂȂ�L���̋�����h���A���̌`����j�~����@���ł���\��������v�ƁA�_���̎��M�҂�͋L���Ă���B -
�X�E�F�[�f���E�����h��w�̌����`�[���ɂ���āA�X�E�F�[�f���쓌�̃o���g�C���݂ɒ��ޒ��Ί펞��̋��Z�n�Ղ��������ꂽ�B
�������ꂽ��Ղ͔��ɕۑ���Ԃ��悭�A�G���N�̊p�ł���ꂽ9000�N�O�̂��̂Ƃ݂���蕶����̂�͂��Ȃǂ̐����p�i�����������B�蕶�̈Ӗ��͍���𖾂��Ă����Ƃ̂��Ƃ��B�܂��A�����܂Ƃ߂ĕߊl����̂Ɏg���A�n�V�o�~�̖_��҂�ł��������Ɨp�̃g���b�v����������Ă���B��������]�ŕ�炵�Ă����l�X������Z���������Ă������Ƃ�����������B
����̈�Ղ̔����́A�l�Êw�݂̂Ȃ炸�n���w�ɂ����Ă��d�v���B���̏W���ɐl�X����炵�Ă�������͍Ō�̕X�͊��̂��ƂŁA���݂����C�ʂ��Ⴉ�����B���̌�A�C�ʂ̐��ʂ��オ�邱�ƂŐ��v�����Ƃ݂��Ă���B
�����h��w�̔��m�ے��ő�l�I�̒n���w����������A���g���E�n���\���́A�wSci-News�x�ɂ����āA���̂悤�ɃR�����g���Ă���B
�u�����͊��V���̂Ȃ��ł����g�Ȏ����������悤�ł��B���Ȃ��Ƃ��Ă̊Ԃ͒g�����A�H�ו����L�x�Ől�X�ɂƂ��ĉ߂����₷�����������Ǝv���܂��B�n���w�҂Ƃ��ẮA�����̂��̏ꏊ���ǂ̂悤�Ȍi�ς����������Č����Ă݂����ł��ˁB�����͒g���������̂����������̂��A�����Ă��̌�ǂ̂悤�ɋC�ϓ������̂��v�ƃR�����g���Ă���B
�����`�[���͏ڍׂȔN�����肷�邽�߂ɁA�ԕ��ƌ]���̒����ƕ��s���A���ː��Y�f�ɂ��N�㑪��ƊC��̌@�풲����i�߂Ă���B�܂��A�C��̐[�x���ǂ̂悤�ɕω��������𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�C��n�`�}�𐧍삵���B�u����܂ł͒f�ГI�ȏ������Ƃɂ����Ă����n�}�ł����A����͉ߋ��̗l�q���I�Ɍ�����̂ɂł���͂��ł��v�ƃn���\���͏q�ׂĂ���B
�A�t���J���N�����Ƃ����l�ނ�10���N�ȏ�ɓn���ĈڏZ���������A�n����̊e�n��ɋ��Z�n���L���Ă����B�����A�ǂ̂悤�Ɉړ������Đ��������Ă������ɂ��ẮA���܂������̃~�b�V���O�����N������B���̉𖾂ɂ́A�Ñ�̐l�ނ̑��Ղ����A�s�[�X������߂Ă��������Ȃ��B����̔������܂��A11700�`8000�N�O�̃o���g�C���݂̎��R���Ƃ����ɕ�炷�l�X�̕����ɑ��A���̗��ʂ���̌��������I�ɐi�߂�傫�Ȏ肪����ƂȂ邾�낤�B -
�i�b�m�m�j�@���̒��ʼn��x�����x���葱���Ď~�܂�Ȃ����̉��y�B�Ȗ����ڂɓ����������ł܂������J��Ԃ����n�܂�\�\�B����Ȍ��ۂ��N���闝�R�ɂ��ĉ�������_�����A�R���̕ĐS���w��Ɍf�ڂ��ꂽ�B
����̊y�Ȃ����ɂ��т���ė���Ȃ����ۂ́A����X�O�����T�ɂP��ȏ�̕p�x�Ōo������B�p�_������w�̉��y�S���w�҃P���[�E�W���N�{�E�X�L���̌����`�[���͂��̎�ȗ��R�Ƃ��āA�e���|�A�����̌`�ԁA�Ɠ��̉����̂R�̗v�������邱�Ƃ�˂��~�߂��B
�W���N�{�E�X�L���ɂ��ƁA�����ƂȂ�̂́u�P���������A���G�����Ȃ��v�y�Ȃł��邱�ƁB�܂��̓��Y���ɍ��킹�đ̂����Ă��܂��悤�ȁA�e���|�̑����ƌy���������߂���B
�Q�ڂƂ��āA�����痣��Ȃ����y�͐����̍\���͒P���ł����Y�~�J���ȃp�^�[���������Ă��āA�����̏㉺���J��Ԃ����B���w�̑����͎q�ǂ������Ɋo���Ă��炢�₷���悤�A���̃p�^�[���ō�Ȃ���Ă���Ƃ����B
�R�ڂ̏����́A�S�̓I�ɂ͒P���ŋψ�ȃp�^�[����ۂ��Ȃ���A�s�ӂɓƓ��̉��������邱�ƁA�u�܂�P���Ȃ���ς���Ă���v�i�W���N�{�E�X�L���j�y�Ȃ��Ƃ����B
�����`�[���͂Q�O�P�O�`�P�R�N�ɂ����Ď�ɉp���̂R�O�O�O�l��Ώۂɒ������s���A���ɂ��т���₷�����y�������Ă�������B���̌��ʁA���f�B�E�K�K�́u�o�b�h�E���}���X�v��M���Ƃ��āA���|�I�ɃK�K�̊y�Ȃ����������B
�u�������̒��Ńo�b�h�E���}���X�����ꑱ���Ă���v�Ƃ����W���N�{�E�X�L���́A�Ȗ������邽�тɓ��̒��ł��̋Ȃ��������Ă��܂��Ƃ��ڂ��Ă���B -
�A�i�^�����^����^�͂�����`�q�Ō��܂��Ă�H
���Ȃ��͒��^�H ��^�H
DNA��̓T�[�r�X�̉��23andme����9���l��Ώۂ�DNA�����������Ȃ����Ƃ���A���^����^���Ƃ����͈̂�`�q�Ō��܂��Ă���Ƃ������ʂ��o�������ł��B�܂����̒����ɂ��ƁA��^�̐l�͂��a�⌒�N��̖�����葽��������Ƃ̌��ʂ��B�ł��A���̌��ʂ͕K���������ʊW���Ӗ�����Ƃ͌���Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�������ł��B
�l�C�`���[�E�R�~���j�P�[�V�����Y�Ɍf�ڂ��ꂽ���̌����́A���^�l�Ԃ��ǂ����́A�i���R���v�V�[�i���C�̔���j�A�����Ԃ̃��������A���߂̑̓����v�Ȃǂɂ��e������15��ނ̈�`�q�I�Ȍ`���Ɗ֘A���Ă���Ƌ������Ă��܂��B���^�ɂ��ẮA���a�ɂȂ�ɂ����Ƃ��A�얞�x�w���iBMI�j����߂ł�茒�N�I�ł���Ƃ����X�����������A��^�͂��a��얞�̃��X�N����荂���Ƃ����X�����o�Ă��邻���ł����A�����`�[���͂���𗧏���؋�������킯�ł͂Ȃ��ƌ���Ă��܂��B
23andme�̌����҂����͈�`�q���̋��L�ɓ��ӂ���89�C283�l��DNA�́B�팱�҂����ɂ͐�����X���ɑ���A���P�[�g�ɓ����Ă��炢�܂����B����̒����́A�Q�m���W�ł�1�ԑ傫�Ȍ��������̂ЂƂƌ����Ă��āA���Ԃ̊�Ƃ����̂悤�ȈӖ��̂���Ȋw�I�Ȍ����������Ȃ����Ƃ��\���Ǝ�����������ɂȂ����悤�ł��B���̎�̌����́A�ʏ�ł͂��܂莑���邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ł��B
�u���̌��ʂɂ��A���܂��܂ȕa�C�Ȃǂ̗��ɂ����`�q�����o�����Ƃ��ł��܂��B�����ĉ�X�����݂��ɂǂ��Ⴄ�̂��Ƃ����̂𗝉�����̂ɂȂ���Ƃ����ȂƎv���Ă��܂��v�ƃ��f�B�A�Ɍ��̂�23andme�̎�C������David Hinds����B
WIRED�̋L���ɂ��ƁA23andme�͐����Ɋ֘A�������������ӂł��邽�߁A�̓����v�ɍ�p�������J�����Ă���Reset Pharmaceuticals�Ƃ�����Ђƍŋ߁A�_����������ł��B�Ƃ����킯�ŁA���̐����Ђ́A23andme�̎����[�U�[���Ɋ�Â��Č����J���������Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł��ˁB
����̌������ʂł́A���^�̐l�͔N���ʂɊւ�炸�A�얞�x�w���iBMI�j����߂̌X���������܂����B�܂��A�قƂ�ǂ̐l�i56%�ȏ�j�͎����́u��^�v���Ǝv���Ă���悤�ł��B������60�Έȏ�̐l�X�͒��^���������������ł��B���^�̐l�����͕s���ɔY�ތX�������Ȃ����ƂƁA����8���Ԉȏ�̐������K�v�Ȑl�������āA��^�̐l�����������a�ɋꂵ�ނƂ����X�����Ⴂ���Ƃ��킩���Ă��܂��B
�������e�����^�l�Ԃ������ꍇ�A���̖��́A���^�l�ԂɂȂ�\����2.4�{�����Ȃ�A���q��1.9�{�����Ȃ邻���ł��B�����Ă������낢���Ƃ́A���^�l�Ԃ͖�^�l�ԂƊW�������Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��B���N���̐l�����͕s���ǂ����Ȃ��A��^��5�l��2�l���s���ǂł���̂ɔ�ׂāA���^��5�l��1�l�����Ȃ����ł��B
���̌����ł́A���������ꂼ��̑̓����v�͐��܂ꎝ�������̂ŁA�g���N���_�E�����ʂłق��̐����w�I�E�S���I�v���Z�X�ɉe�����y�ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝ������Ă��܂��B����̍l�@�ŁA�������̐����ɑ��闝����[�߁A������Q�ɔY�ސl�����̂��߂ɖ𗧂悤�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB�����āA�Ȋw�҂��������̌������ʂł��a�Ɣ얞�ɂ��Ă���Ɍ�����i�߂邫�������ɂȂ邩������܂���ˁB
�����čŌ�ɁA���̌������ʂ̓��[�U�[�ɂ�鎩�Ȑ\���̃A���P�[�g�ɂ���ďo�������̂Ȃ̂ŁADNA�̕��͂����̌��ʂł͂Ȃ���ł��B��`�q�̂ق��ɂ��A����Љ�I�v���������̃T�C�N���ɉe�����Ă���Ƃ������Ƃł��ˁB
-