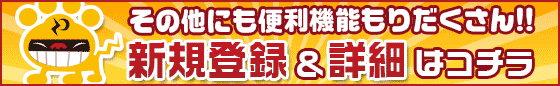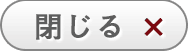�J�I�X�鍑�`���^�[���Y
-
�X���b�h�ꗗ
- �G�k!! (241)
- �������ꌾ!! (814)
- �Ԃ₫!! (459)
- ������ (851)
- �摜!! (451)
- �|�\�X���b�h (1013)
- ����!!!!!!!!!! (985)
- �C�}�W���`�z���͈琬�u���` (256)
- �ʔ��摜(������) (884)
- MUSIC���� (654)
- �k�R�X��(=^�F^=) (688)
- �����C����!!( ; �K�D�K) (471)
- �C������!! (103)
- ���ɂ����I�J���g�n(�G�K�́K) (299)
- (50)
- ���m�� (677)
- �܂�Ƃ��낱�̐l�͔����� (307)
- �� (112)
- JRA (1448)
- The �p�`!!!!!!�`�������́` (457)
- ���ݐH���s��(�L�Ec_�E`) (385)
- (140)
- �T�C�G���X (202)
- �f��!!DVD!!�h���}���X!! (157)
- AV�^�C�g��‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- �����I�����b�X��(ToT) (37)
- (80)
- �܂�Ƃ��낱�̐l�͔����� �{�� (33)
- (654)
- �t���O����!!(^_^)/~~ (39)
- �� (392)
...

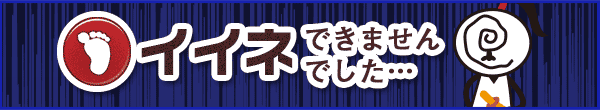
���C�C�l�I�͊e�J�L�R�~�ɑ��A1��̂ݎt���܂��B
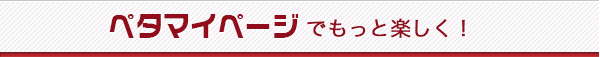
���}�C�y�[�W�ł́A�������u�C�C�l�I�v�������J�L�R�~��ۑ����A�����Ƃ��Č��鎖���ł��܂��B
-
�}�W���فI�@�u�����͂炢��v���邠��E7�I
�����݂̂Ȃ���Ȃ�A�u���o�����Ȃ���A�������肵�Ȃ����I�v�ȂǂƐe���猾��ꂽ�o���͂���܂��H�@�ʓ|���̂����L�����Ɍ���ꂪ���ŁA�����邱�Ƃ����������ł����A�{�l�́u�炢���ǁI�v�Ɣ��_�������Ȃ邱�Ƃ��B����́A����Ȓ����̑�ς����A�����݂̂Ȃ���ɂԂ����Ⴏ�Ă��炢�܂����I
���e�ɂ��������҂����
�E�u���������������A�e����̊��҂��������v�i29�^�@�B�E�����@��^�����n���E�j
���߂Ă̎q�ǂ��Ƃ������ƂŁA�e����̊��҂���g�ɔw���킳��邱�Ƃ��������ł��B
���Z��̖ʓ|���݂��
�E�u�N���̌Z��̖ʓ|�����Ȃ���Ȃ炸�A�䖝���邱�Ƃ���������v�i25�^���̑��^���E�j
��ɁA���̎q�̐S�z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂������̖��܂�肾�����肵�܂��B�e�̎�`�������邱�Ƃ��������ł���ˁB
�����ł��p�C�I�j�A�I
�E�u���ł����������߂ĂȂ̂ŁA�I������̂ɂ��낢��l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��C�����邩��B���̎q�͂��o�����Ɍo�����Ă��邱�ƂɏK���Ă�����������������A�y���Ǝv���v�i28�^��ÁE�����^���E�j
���߂Ă��炯�̒����́A�e���A�q�ǂ����o�����Ȃ����A�����ƔY��Ō��߂Ă������Ƃ������ł���ˁB�����Ŋw�K�������Ƃ����A���̌Z��͎��s�̂Ȃ�������݂₷���̂�������܂���B
���Â���̂�����
�E�u�l�ɊÂ����Ȃ��̎��Ȃ̂ŁA������d���ő���ɏ��ɊÂ����Ȃ��v�i29�^�\�t�g�E�F�A�^�Z�p�E�j
�������肵�Ă�q�̃|�W�V�������܂�肩�狁�߂��邱�Ƃ��������߁A�Â����Ȃ��^�C�v�ɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B
�����̎q�̂���{
�E�u�������̎q�̂���{�ɂȂ邱�Ƃ����߂��邩��v�i30�^�w�Z�E����֘A�^���E�j
�N�ゾ����Ƃ������R�ŁA������������҂̂��o�����ł���悤�A���͂ɋ��߂��邱�Ƃ��������ł��B
�������̃v���b�V���[���c�c
�E�u����ς�ӔC������Ǝv�����A�����̃v���b�V���[���������傫���v�i25�^���ہE���ہ^�����n���E�j
�e�Ƃ��ẮA�K����ɂȂ������̎q���珇�ԂɁA�������Ă����Ăق����Ǝv�����̂Ȃ̂�������܂���B
�����̃v���b�V���[���c�c
�E�u�F�l�́A�����e�Ɂw�����Ȃ���A������삵�Ăˁx�ƒ��w�����炢�̂��납�猾���Ă����B�������v���b�V���[���ȂƎv�����v�i33�^�H�i�E�����^�����n���E�j
�������A���e�̖ʓ|���݂�̂͑厖�Ȃ��Ƃł����A���������납��v���b�V���[����������Ƒ�ςȋC�����܂���ˁB
���܂Ƃ�
�����́A����������̃L�����ŗ����镪�A�u�炢��[�I�v�ƌ��������Ȃ邱�Ƃ��������ł��B�����l�����������Ă���ǂ��Ȃ�Ȃ��悤�A���������A�����炵����������悤�ɂ��������̂ł��ˁB���Ȃ��̒����ɑ���C���[�W�́A�ǂ�Ȃ��̂ł����H
���₢��A���j�̕��������Ƃł��� -
�������܂�ɒ����I�u���a���܂�̍l���Â��v�Ǝv���H
�u���a���܂�v�ɑ��鈫���Ƃ��āu�J���I�P�ʼn̂��̂������ł��Ȃ��v�i24�E�j���j�Ƃ����ӌ���
�M�����a���܂�̕M�ҁB����Q���������݉�ŁA��b�̗���Łu�����ȊO���S���������܂�v���Ƃ������Ƃ��킩���āA������ƏՌ������B�����O�܂ł́u�������܂�v���������Ƃ���āA�C�W��̑ΏۂɂȂ��Ă��悤�ȋC�����邯�ǁA���R�Ȃ��畽�����܂�̐l�������A����������l�Ȃ̂��B
�����ŁA�������܂��20��j���L�E��200�l�ɁA�u���a���܂�ɑ���ӎ��E����M���b�v�v�ɂ��āA�A���P�[�g�������Ă݂��iR25���ׁ^���́F�A�C���T�[�`�j�B
�q�u���a���܂�v�̐�y���i�A�m�荇���ȂǂɁA�u�l�����Â��v�Ǝv�������Ƃ͂���H�r�E�v�������Ƃ�����@50.0��
�E�v�������Ƃ͖����@50.0��
�������܂ꂽ���̈ӌ��́A���傤�ǔ��X�c�B�u�v�������Ƃ�����v�Ƃ����l�ɁA���̗��R�������Ă݂�Ɓu�d�����I����Ă��Ȃ��Ȃ��A��Ȃ��v�i23�E�����j�A�u�c�Ƃ��Ē����d�������Ă�p�������邱�Ƃ��A�w�͂��Ă���p���Ǝv���Ă���v�i25�E�����j�ƁA�J�����Ԃ̒����ɑ���R�����g��������ꂽ�B
�܂��A
�u�w�����̎q�͉����l���Ă��邩������Ȃ��x�Ƃ������������邩��v�i24�E�����j
�u��������Ƃ�ňꊇ��ɂ���Ƃ���v�i25�E�����j
�u�w��Ƃ萢���Ƃ萢��x�ƁA��Ƃ萢����₽��Ɣ������A�����t���Ă���B�����ł��N�z�̕��C�����Ȕ���������Ɠ˂����܂��B���̌������͂ȂɁH�@�Ɓv�i21�E�����j
�ȂǁA���܂ꂽ�N�⌳���𗝗R�Ƀo�b�V���O����邱�Ƃւ̔������������悤���B���Ȃ݂ɁA��Ƃ苳��ƌĂ��w�K�w���v�̂̉����̉e���́A1987�`2002�N���܂�̐l���邱�ƂɂȂ�B1987�N�A1988�N���܂�̐l�́u���a���܂ꂩ��Ƃ苳��v�Ƃ����g�o�b�V���O�̓�d��h��w�����Ă���̂��c�B
�ł́A�u���a���܂�v�������ň����������Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ�����̂��낤���H
�q�u���a���܂�v�̐�y���i�A�m�荇���ȂǂɁu�l�����Â��v�Ƃ��������e�̈������i�F�l�⓯���ȂǂƁj���������Ƃ͂���H�r�E���������Ƃ�����@18.0��
�E���������Ƃ͖����@82.0��
���ۂɈ������������̂́A5�l��1�l���x�̂悤�B����������e�������Ă݂�ƁA
�u�������m��Ȃ��悤�Ȑ̘̂b�����ꂽ�Ƃ��A��k�ŁA�������������܂�ł�����A�݂����Ȃ��Ƃ͌��������Ƃ�����v�i26�E�����j
�u�V�Q�ƌ������v�i24�E�j���j
�u�w�Ȃ�ł�Ƃ�ɓ`���Ȃ����Ƃ��茾���Ă�낤�x�ƌ��������Ƃ�����v�i27�E�����j
�u���������̐���ƍl������������肷��ƁA���a���ۂ���ˁ[�ƈ����̂悤�Ȃ��Ƃ�b�����肷��v�i25�E�����j
�Ȃǂ̐�����ꂽ�B
�V�c�É��̐��O�ވʂɂ��A�������ς��\��������Ă��邯�ǁA�u���avs.�����v�̂悤�Ȗ��v�ȑ�����Η����A����ȏ㐶�܂�Ȃ����Ƃ��F��܂��c�B
-
�g�����v���͖{���͑哝�̂ȂɂȂ肽���Ȃ�����
�u��ׂ��A���I����������c�I���B�ǂ����患�c�v���ĕ\��̃g�����v��
�܂����A�܂����̃g�����v�����哝�̑I�ɓ��I�B
�����o���F���A���Y�Ƃ̃g�����v�����哝�̂ɑI��܂����B
�A�����J�̍����́u���Ɂv�u�ǂ����������Ɓv���A�������Ĕނ�I�̂ł��傤���B
���܂ł�1�N�ԁA�ߌ��Ȍ����Łu���܂����v�I�|�W�V�����������g�����v�������A�哝�̂ɂȂ�Ȃ�āE�E�E
���������ăg�����v�����g�����I����Ƃ͎v���ĂȂ������̂ł́H
����ȕ��͋C�������o���Ă���ƁA�g�����v���̕\�������Ă���Ɛ��̉\�ł��B
�ʐ^���������̂͂��Ⴎ�l�q�Ƒł��ĕς���ĐÊς��Ă���悤���œ��I���Ċ��ł���l�q�ł͂Ȃ��悤�ł��B
�u�}�W�ŃI���Ȃ̂���E�E�E�v
�u���ł����Ȃ�āc�A�����J�l���Ă킩��˂��ȁc�v�Ɠ���Y�܂��Ă�H�H
���I�O���猾���Ă����\�����A���͂����N�����g���ƍ��̃I�o�}�����������Ō����������������������Ƃ̘b�������蕶��������̂��ړI�ō��̕č����̑�ق����������������̔ށB
���������Ȃ����ɂ����������͂��������בI���ɂł��B
�����錾�����ނƔނ̉Ƒ��̕\��͑O�㖢���̂��܂���������ł͂Ȃ������錾�ƂȂ����B
���Ƃ͂�����Ă����L��ԂɂȂ�͖̂ڂɌ����ĂȂ����H -
�v���|�[�Y�A���������c�ƂȂ�ƋC�ɂȂ�̂��A���Г��̌��ߕ��B�����������Ƌ��ɁA���������l�ɂƂ��ďd�v�ȈӖ������̂��u���Г��v�ł��B�ːЏ�ł��A����ē�l���v�w�ƂȂ���B���S��Y��Ȃ����߂ɂ��A���Ёu��ȋL�O���v�Ƃ��Ĉʒu�t�������ł���ˁB�ł����Г����āA���������ǂ�����Č��߂�̂��x�X�g�Ȃ́H�@��y�J�b�v�������ւ̃A���P�[�g���ʂ���A�I�X�X���̕��@���Љ�܂��B
�����Г��͂ǂ̂悤�Ɍ��߂܂������H��1�ʁu���ɂ������͂Ȃ��v�c�c41.0��
��2�ʁu���N�̂������v�c�c16.0��
��3�ʁu����܂��͎����̒a�����v�c�c11.0��
��4�ʁu���ۋL�O���A�o��������Ȃǂ̎v���o�̓��v�c�c9.0��
��5�ʁu��C���킹�A�]���ڂȂǁA�o���₷�����v�c�c7.0��
��6�ʁu�����v�w�̓��v�c�c3.0��
����6�ʁu�j���v�c�c3.0��
��8�ʈȉ��ȗ�
��ȓ������炱���A�F��������đI��ł���̂��Ǝv������A�Ȃ��1�ʂ́u���ɂ������͂Ȃ��v�Ƃ������ʂɁI�@�Ȃ��������Ȃ��́H�@������������́A�Ȃ������ɂ��悤�Ǝv�����́H�@��̓I�Ȉӌ����`�F�b�N���Ă݂܂��傤�B
����1�ʁu���ɂ������͂Ȃ��v�E�u�C�O�����������̂ŁA�������Ɉ�ԋ߂����i�o�����̒��O�j�ɓ��Ђ����v�i43�^�����^���̑��j
�E�u�V�����s�̓����ɍ��킹�āA��Ђ̋x�݂���邽�߂Ɂv�i29�^�����^�Ɠd�EAV�@��j
�E�u�d���ŋx�݂����邢�����͂��̓������Ȃ������v�i34�^�j���^�������j
�������ɐV�����s�A�����z����e��葱���ȂǂȂǁc�c�����ł����Z�����̂����������ӂ̎����I�@���ɋ������J�b�v���̏ꍇ�A�u���݂��̋x�݂����킹�邾���ň��J�v�Ȃ�ď�����̂�������܂���ˁB�u���t�v�ł͂Ȃ��A��Ȃ̂́u��l�ꏏ�Ɂv�Ƃ����_�B�����@�őI�ԂƁu���̓������Ȃ������I�v�Ȃ�ăJ�b�v���������悤�B�Ƃ͂����A��l�̓s�����������ŁA�u�ł��邾���������̂��������v�ƑI��ł���l������悤�ł��B
����2�ʁu���N�̂������v�E�u���N���������v�i49�^�j���^�����d�@�j
�E�u���p�Ȃnj��Ă������ɂ����v�i42�^�����^���̑��j
���ꂩ��扽�����邩�킩��Ȃ��������������炱���A�ł��邾�����N��S���ł��������I�@�Ƃ����C�����A�����ł�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������̓��Г��Ȃ̂ɁA�u���ł�����c�c�v�Ȃ�ă�����������͔̂��������Ƃ���B�e��e�����ŋC�ɂ���������邩������܂���ˁB���N�̂�������I�Ԃ��߂̃R�c�́A�R�����㔼�ŏڂ������`�����܂��B
����3�ʁu����܂��͎����̒a�����v
�E�u�Ȃ�2��14�����a�����ŁA���o�����^�C���Ȃ̂ŁA��ΖY��Ȃ�����v�i44�^�j���^�V�X�e���C���e�O���[�^�j
�E�u���Г��́A���݂��ɖY��Ȃ��悤�ɁA�ǂ��炩�̒a�����ɂ��悤�ƌ��߂Ă����B���̓��́A�s�����̍Ŋ��w�Ŏd���A��ɑ҂����킹�����āA���ԊO��t�œn�����v�i30�^�����^���̑��j
�ߔN�́u���N�v�����u��l�ɂƂ��Ă̓��ʊ��v���d��������������Ă��܂��B�ǂ��炩�̒a�����ɓ��Г����d�˂Ă��܂��A�����ɂ��j�����邱�Ƃ��\�I�@�Y���S�z������܂���B�u�ł�����������A�d�����c�c�v�Ȃ�ĕ��ł����v�B�����͂��́A365���A24���Ԓ�o�\�ł��B��ԑ����Œ�o����A��o������Г��Ƃ��Ď��Ă���܂���B
�������A��o�ꏊ���o�����Ȃǂ̏ꍇ�A��Ԏ�t�����Ă��Ȃ��P�[�X������̂ŁA���O�Ɋm�F���Ă����̂��I�X�X���ł��B�܂����ނɕs��������ƁA���Г�������Ă��܂��܂��B��o����O�ɁA�L�����@�ɂ��Ă�������ƃ`�F�b�N���Ă����܂��傤�I
����4�ʁu���ۋL�O���A�o��������Ȃǂ̎v���o�̓��v�E�u���߂ăf�[�g�������ł����v�i42�^�j���^�R���s���[�^�[�@��j
�E�u���ۂ��n�߂�����Y��Ȃ��悤�Ɂv�i40�^�j���^�v�j
�a�������u�v�w�ǂ��炩�̋L�O���v�Ȃ�A������́u�v�w��l�̋L�O���v�ƌ�����ł��傤�B���Г����}���邽�߂ɁA���߂Ď���Ȃ����u�Ԃ̃h�L�h�L������݂������Ă���̂����c�c!?�@���l����̎v���o���A��ɂ��܂��Ă��������ł��ˁB
����5�ʁu��C���킹�A�]���ڂȂǁA�o���₷�����v�E�u��C���킹�B10��29���ʼnł��v�i38�^�j���^���ʁE�`�F�[���X�g�A�j
�E�u������2���D���ŁA2��2���ɂ����v�i37�^�j���^�T�[�r�X�j
�����̎����ɂ���ẮA�a�������L�O�������Ԃ�Ȃ��I�Ȃ�Ă��Ƃ�����ł��傤�B����ȂƂ��ɂ́A��C���킹�ŖY��ɂ������Г����ӎ����Ă݂ẮH�@���̂ق��ɂ��u1��8���v�́u1�ԃn�b�s�[�v�A�u2��7���v�́u2�l�Ȃ��悭�v�A�u7��22���v�́u�Ȃ��悵�v�w�v�A�u10��2���v�́u�i�v�i�Ƃ�j�Ɂv�Ȃǁc�c�G�߂ɉ����Č�C���킹�͂�������܂��B��l�Œ��ǂ��b�������̂��I�X�X���ł���B
�����̑��A����Ȉӌ����c�c
�E�u��l�̒a�����̊Ԃɂ����B�Ȃ�2���B�l��4���B�����3���ɂ����B�l��20��Ō�̌��ł��������̂Łv�i66�^�j���^���̑��j
���݂��̒a�����ɂ�����肽������ǁA���t�̊W�Łc�c�Ƃ������́A���Ёu�^�o�[�X�f�[�v�ׂĂ݂ẮH�@��l�̒a��������͂���ƁA�����Łu�^�v����Ă����A�v��������܂��B���̓��ɓ��Ђ��s���A��苭���Ӗ���������ƂȂ肻���ł��B
�E�u�����L�O���Ɠ��Г����Ⴄ�ƍ������邽�߁A������I�����I���A��n�܂�O�ɍ����͂��o�����v�i56�^�j���^��ÁE�����j
�ǂ����Ă��Y��Ă��܂������c�c�Ƃ������ɂ́A����ȕ��@���I�X�X���B�����͂������ł���o�\�ƒm���Ă���A�����������ł������鎞�Ԃ͌�����͂��ł��B�ːЏ�ł��v�w�Ɂc�c�Ǝv���ƁA�C�������������܂�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����Ɂu���N�̂������v�������I�@���ЂɓK���������Ă���H���āA���Г������߂��ŁA�ǂ����Ă��C�ɂȂ�̂��u���N���������ǂ����v�Ƃ����_�ł��B���ƂŃ����������Ȃ����߂ɂ́A���БO�ɂ�����ƒm���Ă����ƈ��S�ł���B
���N�̂������t�I�тƂ����u�Z�j�i�Z�P�j�v���L���ł����A�u���������₩�ɐi�ދg���v�Ƃ����A��͂����B������A���N�̂������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�܂������֘A�̋V���ł́A�F�����I�X�X���B���͑���ɑ����ĉ��N���������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�揟�͌ߑO�A�敉���͌ߌ�Ȃ�OK�B�����ĐԌ��͌ߑO11������ߌ�1�����炢�܂ł͋g�Ƃ���Ă��܂��B���t���I�ׂȂ��ꍇ�́A�s�����鎞�Ԃ��C�ɂ��邾���ł��[���Ή��ł������ł��ˁB
�܂����́A�u����v��������ɉ��N�������u�V�͓��v�Ƃ����������݂��܂��B��N�ɂ�����������������܂��A2016�N��12��8��������ɓ�����܂��B���ɂ��̓��͂ЂƗ������{�ɂ��Ȃ�Ƃ����u�ꗱ���{���v�ł�����܂�����A��l�ŐV�������Ƃ��n�߂�u���Ёv�ɂ̓s�b�^���̈�����ƌ��������ł��ˁB
��y�J�b�v�������̓��Г��̑I�ѕ��͂������ł������H�@�����ɍl���A�ǂ̂悤�ɓ��t��I�Ԃ̂��́A��l����ł��I�@���ꂩ���������Ƒ�ɂł���悤�A�悭�b�������āu���ЋL�O���v�����肵�Ă݂Ă��������ˁB
-
�u�b�N�I�t�R�[�|���[�V�����A10.9���~�̉c�ƐԎ�
�@�u�b�N�I�t�R�[�|���[�V������11��4���ɔ��\����2017�N3������2�l�����i2016�N4��1���`9��30���j�̘A�����Z�́A���㍂��392��7000���~�i�O�N������8.2�����j�A�c�Ƒ�����10��9300���~�i�O�N�����͉c�Ƒ���3��5100���~�j�̐Ԏ��ɁB��N�ʊ��̉c�Ƒ����ł���5��3000���~�����啝�Ԏ��ƂȂ����B
�@�uBOOKOFF�v�Ȃǎ�͂̃����[�X�X���Ƃ̔��㍂��343��8100���~�ŁA�Z�O�����g������4600���~�i�O�N������8��3200���~�̗��v�j�B�p�[�g�E�A���o�C�g�X�^�b�t�̐l���g�[�ɂ��l����̑����A�V�K�o�X�ɂ��o�X��p�̑����ŐԎ��ƂȂ����B�O���[�v���c�X��7�X�ܐV�K�o�X��������ŁA���c�X8�X�܁EFC�����X8�X�܂�X�����B
�@�u�b�N�I�t�I�����C�����Ƃ̔��㍂��32��2800���~�i27.2�����j�A�Z�O�����g���v��1��3200���~�i62.2�����j�BEC�T�C�g�uBOOKOFF Online�v�̉����������AEC�T�C�g��̏��i�A�C�e���������ɂ���������̑����ő����ƂȂ����BYahoo!Japan���^�c����u���t�I�N�I�v�ŏ��i���o�i�����g���A�����R�X�g�͂����������̂̍D���������B
�@�X�܌^�̃r�W�l�X�Ɍ��肵�Ȃ������[�X�Ƃ̉^�c��������n�O�I�[�����Ƃ̔��㍂��9��5500���~�i163.4�����j�B23����𒆐S�ɂ����K�┃��T�[�r�X�A�S�ݓX���ł̑������摊�k�����̉^�c�ȂǂɎ��g�ނƂƂ��ɁAEC�T�C�g�̔��AB2B�̔��A�Î��̔����L�т����Ƃő����ƂȂ����B�Z�O�����g������1��1600���~�i�O�N������2��5800���~�̑����j�ŁA�O�N��ł����P�����B
�@�u�b�N�I�t�R�[�|���[�V�����́A2020�N3�����̉c�Ɨ��v40���~��ڕW�Ƃ��A�d�������Ɣ̔����������i�߂钆�����ƌv������肵�Ă���B�ʊ��̘A���Ɛї\�z�͏C�������A���㍂850���~�������ށB
-
�g�����v�哝�̒a���ŕč��o�ς͍D�i�C�ɁH�@���{���̉҂����͏I��鋰���
�@��ڐ�ƂȂ����đ哝�̑I���́A�y�d��Ńg�����v�����t�]��������Ƃ��������ׂ����ʂƂȂ�܂����B�s��͗\�z�O�̓W�J�ɑ卬���Ɋׂ��Ă��܂��B�g�����v�哝�̂��a������Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���{�o�ςɂ͂ǂ̂悤�ȉe�����o�Ă���̂ł��傤���B
TPP����̍s���́H
�@�g�����v���̑哝�̏A�C�ōŏ��Ɍ��O�����̂͂�͂�TPP�i�����m�p�[�g�i�[�V�b�v�j����̍s���ł��傤�B�g�����v���͓����A���L�V�R�Ƃ̍����ɕǂ����Ɛ錾�ANAFTA�i�k�Ď��R�f�Ջ���j��TPP�ɂ��Ĕے�I�Ȍ����������Ă��܂����B�}�̐����ȍj�̂ł́A�f�Ջ����P�p����Ƃ͐錾���Ă��܂���A�g�����v�����ǂ̂悤�ȑΉ�������Ă���̂��A�����_�ł͉��Ƃ������܂���B
�@�����ATPP����S�ʓP�ނɂ͂Ȃ�Ȃ������Ƃ��Ă��A�č��̘J���҂�ی삷��Ƃ������ڂŁA���{�����s���ɂȂ�����������o���A�Č����Ă���\���͏\���ɂ���ł��傤�B�����TPP�����̂܂ܔ�y�����Ƃ͍l���Ȃ������悳�����ł��B
�@��A�̎��R�f�Ռ����ڍ�����Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�A�o�����ł�����{�ɂƂ��Ă͑傫�ȑŌ��ƂȂ�܂��B���{�≢�B�ȂNJe���̊����s��ɂ������e����^����ł��傤�B�č��s����Z���I�ɂ͑傫�ȍ����������邩������܂���B
�g�����v����̕č��͍D�i�C�ɁH
�@�����g�����v���̑哝�̏A�C�ɂ���ĕč��o�ς������I�ɑŌ�����̂��Ƃ����Ƙb�͂܂��ʂł��B�g�����v���͏��Ȃ��Ƃ�5000���h���i��51���~�j�K�͂̃C���t�����������{����ƌ���Ɍf���Ă��܂��B�c��Ƃ̌�������܂�����A���̋��z�����̂܂ܒʂ邩�ǂ����͕�����܂��A���ȏ�̍����o�����s����\���͍����Ƃ݂Ă悢�ł��傤�B
�@���݂̕č��͂Ȃ��Ȃ����������E�p�ł��Ȃ���Ԃł�����A��K�͂ȍ����o���͕č��o�ς������������A�����𐳏�ɖ߂��������ʂ����\��������܂��B�����I�Ɍ��Ă��A�č��̓V�F�[���K�X�̊J���ɂ���Ă��ׂẴG�l���M�[�������ł���ɂ���A��i���ł͒������l�����������������݂ł��B�č��P�̂Ō����ꍇ�A�g�����v����͈ӊO�ƍD�i�C�ɂȂ邩������܂���B
�ی��`�����܂�Γ��{�̐����ƂɂƂ��ċt��
�@�����Ƃ����{���猩����̋t�ɂȂ�܂��B���ʂ͉~���̃��X�N������܂����A�������I�ɂ͕ی��`�����܂邱�ƂŁA�����ƂɂƂ��ċt���ƂȂ�\��������܂��B�A�o�卑��m���卑��W�Ԃ��A���ł�����Ă����č��Ƀ��m���đ傫�ȗ��v��Ƃ�������܂ł̓��{�l�̉҂����́A�g�����v���̑哝�̏A�C�ɂ���ďI�����}���邩������܂���B -
���ۂɎg��ꂽ�u���肦�Ȃ��v���Η��R�ꗗ
�uCall in Sick�v�B��`�ʂ�Εa���̈Ӗ��ŁA�č��ł͓K���ȗ��R�����������܂߂Ă����ĂԂ��A�Ȃ��ɂ͐��������܂�Ɂu���肦�Ȃ��v���e������B���l�T�C�gCareerBuilder.com�������Call in Sick�̗���܂Ƃ߂Č��J�����B
���̒�����Harris Poll�Ɉϑ����A8��11���`9��7���Ɏ��{�B�t���^�C���œ����Ă���]�ƈ�3,100�l�ȏ�ƁA�ٗp�E�l�ޕ���̊Ǘ��E2,500�l�ȏォ����W�߂��B
�ٗp���ɍ��܂ŏ]�ƈ����畷�����ꂽ�Ȃ��ň�Ԃ��₵����Call in Sick�̗��R�͂ǂ�ȓ��e����q�˂��Ƃ���A���̂悤�ȉ��������B
�E�u��C�Ɋ܂܂��I�]�����N���}�̃^�C��������ɂ��Ă��܂����v
�E�u���͓炪�������A�������т��Ă���̂ʼnƂɂƂǂ܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ������v
�E�u�Ȃ̂��Ƃ��̃y�b�g�̑��V�ɎQ�A�g�����h�Ƃ��āA���̕t�Y�l�Ƃ��Ė������ʂ����˂Ȃ�Ȃ������v
�E�u�Ƃɓ˓����Ă����x�@�ɑj�~���ꂽ�v
�E�u�����l�ɕs���ȏ،������˂Ȃ炸�A�����l�̒��Ԃ��P���Ă����v
�E�u���̐����ۂ̕������݂��Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ������v
�E�u�L���b�g�t�[�h���c�i�ƊԈႦ�ĐH�ׂĂ��܂��A���ʂقNj�����������v
�E�u�����Ă��郉�}�i�����}�j���a�C�ɂȂ����v
�E�u���L�ɒE�ъ���g���Ă����Ƃ����i�ł₯�ǂ����Ă��܂��A���r�����낹�Ȃ��Ȃ����v
�E�u�������̃{�[�����O�Q�[�������Ă��āA�d���ɂ����Ȃ������v
�E�u�Ƃ̒��ő�O���ɑ������A�S�I�O�����X�g���X���o�������B�N���ɑΏ����邽�߂ɉƂɂƂǂ܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ������v
�E�u�����Ƃ��ׂ����Ƃ��������v
�E�u�a�����P�[�L��H�ׂ������v
�E�u�A�q���Ɋ��܂ꂽ�v
���Ȃ݂ɏ]�ƈ����q�ׂ�Call in Sick�̖{���Ƃ��đ��������͎̂��̒ʂ�B
�E�u�����d���ɍs�������Ȃ������v�i28���j
�E�u��҂ɂ����邽�߁v�i27���j
�E�u���������b�N�X����K�v���������v�i24���j
�E�u�����s������������K�v���������v�i18���j
�E�u�����̂��߁v�i11���j
�ٗp����3����2�͂������������������Ă���B������3����1�͎������m�F����p�����B�u�f�f���̒�o�����߂�v�i68���j�Ƃ��A�u�]�ƈ��ɓd�b��������v�i43���j�Ƃ��A�u�]�ƈ��̉Ƃ�K�₷��v�i18���j�Ȃǂ��B
�܂��ٗp����3����1�͏]�ƈ��̃\�[�V�������f�B�A�����Ă��āA���e�ɂ����Call in Sick���R���Ƃ͂����肷��ƁA27���̓N�r�ɂ��A55���͂����������ւɒ������Ă��邻���B
�����̌��̌�����قNjC�ɓ������̂��A�č��̒����o�ώ�Forbes�����̌��ʂ����グ�Ď�̂��L���ɂ��Ă���B�č��̓N���X�}�X���܂ށu�z���f�[�V�[�Y���v���߂Â�����A���̎�����Call in Sick�������Ȃ�̂������B
-
�d�ԓ��ł̉��ς��e�[�}�ɂ������}�d�S�̃}�i�[�L�������c�����������Ƃ��A�C���^�[�l�b�g��ł́A�ԓ��ɂ�������f�s�ׂɂ��Ă̋c�_������オ���Ă���B
������J-CAST�j���[�X��2016�N10��30������31���ɂ����A�d�ԓ��̍s�ׂōł��s������������̂ɂ��Ẵ����N���b�N���[�����{�B�ǎ҂���͖�1200���̕[���W�܂�i31��18�����_�j�A�S10���ڒ�3���ڂ��h�R���錋�ʂƂȂ����B
����ς�C�ɂȂ�u���v�Ɓu�ו��v
3���ڂ�1�߂́u�吺�ł̂�����ׂ�v�i203�[�j�B�b�ɔM�����邠�܂�A���͂ɓ��e���������ɂȂ�قǂ̑�{�����[���ʼn��X�ƃy�`���N�`��...�B�ԓ��͎��ꌵ�ւł͂Ȃ��ɂ���A�x���z����������ׂ�ɃC���C�����点��l�͏��Ȃ��Ȃ��悤���B
�I�����ɂ͂Ȃ��������A�C���z����w�b�h�z������R���V���J�V���J���A�K���Ȃǂ�H�ׂĂ���N�`���N�`�����Ȃǂ������u���v�̖��Ƃ��ċ�������B�R�����g���ɂ́u�g�ѓd�b�ł̎B�e���v�Ƃ����ӌ������Ă����B
2�߂́u���G���Ƀ����b�N��w�������܂�Ԃ��邱�Ɓv(196�[)�B�o�������������b�N�͒ʍs�̎ז��ɂȂ邾���łȂ��A1�l���̗��X�y�[�X�����D���Ă��܂����A����ł���Ȃɔw����������l������̂����B
3�߂́u�ו��ō��Ȃ��L���邱�Ɓv(207�[)�B�ԓ����Ă���Ζ��Ȃ����A����ł��Ă�������������܂ʼnו����ǂ��Ȃ��͍̂�����̂ł���B
���̑��̍��ڂł��u���G���̋r�g�݁A�r�����o���v(161�[)��u�h�A�n���v�i135�[�j��4�A5�Ԗڂɑ����[�Ă����B�R�����g���ł́u�X�}�z�𑀍삷��X�y�[�X�����炷�邱�Ɓv�ւ̔ᔻ�������݂��A�����I�Ɏז����ƍl������s�ׂ͓��ɖ�莋����Ă��邱�Ƃ����������B
�I�����ȊO�ɂ��u�}�X�N�����ł̊P�v�u�A���R�[���L�v...
���}�̍L���Ŏ��グ��ꂽ�u�ԓ��ł̉��ρv��121�[�ŁA6�Ԗڂ������B���ς��ꎩ�̂��K���������ږ��f����������̂ł͂Ȃ����߁A����͒��ډe���̂��鉹����X�y�[�X���ɂ�葽���̕[�����ꂽ�悤���B
�����A�u�ԓ��ł̉��ρv���u�݂��Ƃ��Ȃ��v�Ɗ����Ă���l�͑���������悤�ŁAJ-CAST�j���[�X���ʂ̋@��Ɏ��{���������N���b�N���[�ł́u�݂��Ƃ��Ȃ��Ǝv���v��77�����߂Ă����B
����ŁA�ӊO�Ɠ��[�̏��Ȃ������̂��u�i�����Ă���אȋq�ɂ��j�����ꂩ����v�i31�[�j���B���x�����x����肩������A���ʂɍ����Ă��邾���ł����J�Ȃ͂������A���肪�Q�Ă��邱�Ƃ������āA������͑�ڂɌ��邱�Ƃ��ł���̂�������Ȃ��B
�ǎ҂���́A�I�����ɂ͂Ȃ��������f�s�ׂɂ��āA�u������A���R�[���L�v�u�}�X�N�����ł̊P�v�u�����q����u����e�v�ȂǁA���܂��܂Ȉӌ�����ꂽ�B -
�H�����̃X�}�[�g�t�H���g�p���߂���A�C���^�[�l�b�g��ŋc�_������オ���Ă���B
�@���������́A2016�N11��2�������́u�}�c�R���L�g�̓{��V�}�v�i�e���r�����n�j�ŏЉ�ꂽ�����ғ��e���B���̓��e�ҁ\�\28�̒j����Ј��́A�ꏏ�ɐH�����Ă���̂ɃX�}�z��������F�l�����ւ̓{����Ԃ��܂����B
���u �}�i�[�ᔽ����Ȃ��Ȃ��������̂�v
�@���e�҂̗F�l�ɂ́A�H�ׂĂ��鎞���b�����Ă��鎞���X�}�z��ʂ���ڂ𗣂��Ȃ��l�������Ƃ����A���������Ɂu��b���e�܂Ȃ��v�u�����𖡂���Ă���l�q���������Ȃ��v�ƃC���C�����点�Ă���̂��Ƃ����B
�@����ƃ}�c�R�E�f���b�N�X����(44)�́A���e�҂̌������ɗ�������������Łu���͂����ɂ͗���������Ȃ����Ƃɂ�����ł��B���������l�������ǂ�ǂ��Ă����i����j�v�Ƒł��������B���������̗���Ƃ��Ď~�߁A���łɒ��߂̋��n�ɒB���Ă���悤���B����ɁA
�@�@�u���Ԃ�}�i�[���ς��Ǝv���B���ѐH�ׂĂ�ԃX�}�z�����Ă���Ă��Ƃ��}�i�[�ᔽ����Ȃ��Ȃ��������̂�B����Ȃɔ��g�������X�}�z�������Ă鎞��ɂȂ�������v
�Ƃ��w�E�B�V����G����ǂ�A�e���r�������肵�Ȃ���H������P�[�X�ɂ��G��u(�X�}�z��)�V�������̂����狑�۔��������������ǁA�i�u�Ȃ���сv���̂́j�O����݂�Ȃ���Ă邱�Ɓv�Ƃ����B
�����w���́u�H�����̃��[���֎~�v�͑����X��
�@�ԑg���A�c�C�b�^�[���ɂ́u�q���ʓI�Ɍ��v�u�ˑ��ǂ�����v�Ƃ��������۔�������u�����t�c�[�ł���v�u�{��l�Ƃ͐H���ł��Ȃ��v�Ƃ������m��ӌ��܂ŁA���܂��܂Ȑ����オ�����B
�@�����A���̒��œ��ɖڗ����Ă����̂́u��l�̎��Ȃ�Z�[�t�����A�l�Ƃ��鎞�̓A�E�g�v�Ƃ����ӌ��������B�s�V�̈������̂��̂ł͂Ȃ��A�u�l�ɒ��ږ��f�������Ă��Ȃ����ǂ����v���|�C���g�ɂȂ��Ă���̂��낤�B
�@���Ȃ݂ɁA�_�ђ������ɂ������w���Ώۂɍs���Ă���A���P�[�g���������Ă݂�ƁA�u�H�����ɓd�b��[�������Ȃ��v�悤�������Ă���q�͑����X���ɂ���B05�N�ɂ�18.8����2���ɖ����Ȃ��������A11�N�ɂ�34.0���A16�N�ɂ�48.5���Ɩ��ɒB�����B�\�\�������A�}�c�R����̌����悤�Ɏ���̗���Ń}�i�[���̂��̂��ς��A�A���P�[�g���ʂɂ��ٕς������邩������Ȃ��B -
�u�ƒ�ɐZ��߂��Ȃ��v�j���͂�͂薣�͓I��
�����ł����̂͊������A�ł��Ɛg�����\�y���������킯�ŁE�E�E�i�C���X�g�F�x�]�Ďj�j
�@�u��{����A�������ŏ��Ă���j���͌��X�����点�j�q�������炵���ł���B35���炢�܂Ō������鎩�M���Ȃ��āA������ɉ����Ă�����Ă悤�₭�������������ł��B�Ӎ�������ɂ҂����肶��Ȃ��ł����H�v
�@�����͈��m�����S�s�ɂ���u�i���X���[�X�v�B�M�҂Ɠǎ҂Ƃ̌𗬉�ł���u�X�i�b�N��{�v�̈��m���ŁA�A���R�[���ނ����Ă�����Ă���B
�@����͒j�����킹��16�l�̂��q������}�����B���̂قƂ�ǂ͖{�A�ڂ̓ǎҁB���E���E�ŃC���^�r���[��ސ���Љ�Ă����̂��B�����̗ǂ��l�����Ƃ��܂݂��������A���ݐH���Ƃ�����ׂ���y���݂A��ސ�m�ۂƂ����d���̏d�v���������Ȃ���B��Ȃ��炠�肪�����C�x���g�ł���B
�������ɈӋ`�����������Ȃ�����2�̗��R
�@�����ނ����Ă����̂́A���m�����Ŏ��c�Ƃ��c�ޔ���N�F����(�����A41��)�B�_���Œb���Ă���Ƃ������ȑ̊i�̎�����Łu�����点�j�q�v�ɂ͌����Ȃ��B�����̋������ň����킵�Ȃ���A�ނ̔Ӎ��X�g�[���[����邱�Ƃɂ����B
�@�u�n���̗F�����̓��[�L���O�z���f�[�ɍs���Ȃǎ��R�ɗV�Ԃ̂��D���Ȑl�����������āA20��̂����Ɍ�������̂͏����h�ł����B���m���͐��l���Ă��e�Ɠ������Ă���̂���{�ł���ˁB�����������͉Ƃɓ����Ƃ��Ă��������ɂ͎������܂���B�l���F�B�ƗV�Ԃ̂��y�����āA�����ɂ͈Ӌ`�������������Ƃ��ł��܂���ł����v
�@���Z���ォ��8�N�Ԃ��t�������Ă������l���������A�����ɂ͋C�����������Ȃ��������R�����ɂ�����B�����Ɣ������B
���͎��R���I
�@�N�F����͑�w�𑲋Ƃ�����A���É��ɂ���L���֘A��ЂɏA�E�����B��8��������I�d�܂œ����āA�y�����o���邱�Ƃ����������B����ł��N����300���~�ɓ͂��Ȃ��B���ƕ�炵�Ȃ̂Ő����ɍ��邱�Ƃ͂Ȃ����A�N�F����̔��Əł�͕���Ă������B
�@�u���ƂɏA�E�����ޏ��̂ق�������������������Ă��܂����B���̔ޏ����l�ɋ�s�������A����肽��������������Ă���̂ɊÂ������Ƃ������Ȃ�A�Ɣ������Ă��܂��Ă�����ł��B�ق��ĕ����Ă�����ׂ��������̂Ɂc�c�B�҂��������ėD�������Ȃ��A�����ɂ��ς���Ȃ��B�t����ē��R�̒j�ł���ˁB�ޏ��̋C�������l���炾��Ă����̂������Ă��܂����v
�@���l���ł͂܂������Ȃ��B�M�҂��܂߂������̒j���́A�d���̏[���x�ƒj���Ƃ��Ă̎��M���������Ă���B�d���ʂł̓W�]�������Ȃ��Ɋׂ�ƁA���ׂĂɂ����Đ��ʂ������n�߁A�{����ۂ��Ȃ�����ڋ��ɂȂ����肷��̂��B���e�悤���Ȃ��B
���u�A�C�E�A���E�t���[�I�v�Ɛ⋩����u��
�@�u�ʂꂽ����͗������݂܂������A�����ɉ��܂����B����Ǝ��R�ɂȂꂽ�A�x�݂̓��͂��ׂĎ����̂��߂Ɏg����I�@�Ƃ����C�������t�c�t�c�ƗN���Ă�����ł��v
�@���̊��z�ɂ��������Ă��܂��B�M�҂�33�̂Ƃ��ɗ������o���������A�ʋ�����1�J���ギ�炢�ɗN���オ����������͍��ł��Y����Ȃ��B���ꂩ��͂��ׂĎ��R�Ȃ̂��B�v���Ԃ�̈�l��炵�B�����ȃA�p�[�g���肽�B�x�b�h�̏�ő�̎��ɂȂ�A�u�A�C�E�A���E�t���[�I�v�Ɛ⋩�������Ƃ��o���Ă���B
�@�l�͊F�A�u�C�܂܂Ɉ�l�Ő��������v�Ƃ����C�����Ɓu�N���Ə����������ߍ����Ȃ����炵�����v�Ƃ����C�����A2�̖��������v��������Ă���C������B�������ǂ��Ȃ��p�[�g�i�[�Ƃ̕ʂ���o������ƁA�ꖕ�̎₵����������Ɠ����ɑO�҂́u�A�C�E�A���E�t���[�v���ɕ�܂��̂ł���B
�@�N�F�����20��㔼�œ]�E�����A�J�����͑啝�ɉ��P�����B����ł������ɂ͖ڂ��������A�_�����ĊJ����ȂǏ[�������Ɛg�����𑗂��Ă����B���݂̍Ȃł��鈟�R������(�����A38��)�Ƃ̏o���8�N�O�A�u�l�����킹�̍��R���v�������ƐU��Ԃ�B
�@�u���b�D���̏��F�B�ɗU���Ă��炢�܂����B�ȂƂ͐��ʂɍ����Ęb�������Ƃ��o���Ă��邮�炢�ł��v
�@���݂��ɘA��������Ƃ��Ȃ������B�������A�l�Ɛl�͂ǂ̂悤�ɂȂ��邩�킩��Ȃ��B3�N��Ɋ����̗F�l����v���Ԃ�ɘA��������A�u���R���̂��ƁA�o���Ă�H�@�@����1�Ȃ��Ɖ���ĐH�����������炵���v�ƗU��ꂽ�B
�@�u�@�����l�b�g���[�N�r�W�l�X�̊��U���낤�Ƌ^���܂���(��)�B�ł��A�F��������w��ɂ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��x�Ƌ�������ꂽ�̂ŁA��x��������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����v
���R����������Ǝv�������R�Ƃ́H
�@���ǂ����������߉�Ԃ�ł���B�M�҂�3�N�قǑO����ӎ��I�Ɂu����������������v�����H���Ă���A��1�y�[�X�Ŗ���̒j�����������킹�Ă���B�������A9���͓k�J�ɏI���B���ӂ����ǂ��납�A�u�ǂ����Ă���Ȑl�����Ƃ����������Ǝv�����́H�v�Ƃ��������̎����������邱�Ƃ��炠��B
�@���̏����Ď咣���Ă��������B��������������������������Ȃ̂�����A���߂�1�炢�̓f�[�g���Ă݂Ăق����B�����I�Ɍ��łȂ���A��l�̊W�ɐi��łق����B���̂����Ō������邩�ۂ������݂��ɔ��f��������Ǝv���B���ʂƂ��āA�������菝����ꂽ�肷�邩������Ȃ��B�ł��A����ǂ��납���������ݍ��ދC�������Ȃ���A�Ԃ̑��l�ƉƑ��ɂȂ邱�Ƃ͓���Ǝv���B
�@�N�F����̘b�ɖ߂�B3�N�Ԃ�ɉ�������R������́A�u������v�ƘA�����������R�𐳒��ɖ������Ă��ꂽ�B
���R���r�j�A�C�X�Ŋ��ł����ޏ�
�@���R������͏����X�̔̔����Ƃ��ē����Ă���A20��̂������猋����]���������B���R���ɂ��Q�����Ă������A�T���߂Ȑ��i�̂����������ėǂ��j���Ƃ̉��ɂ͌b�܂�Ȃ������B����ŁA�E��ł͓X���ɂȂ邱�Ƃ�Őf�����B���R�����Ζ����鏬����`�F�[���ł͓X���̐ӔC�͏d���A�����ԘJ������{�ł���B�������܂��܂������Ȃ邱�Ƃ�\���������R������͂��錈�ӂ�����B�v�����Ď����̊k��j���Ă݂悤�\�\�B
�@�u���܂ł̍��R���Ȃǂŏo������j���ŁA�w������Ɨǂ������ȁx�ƋL�����Ă���l�Ɏ���������߂Đ��������Ă݂邱�Ƃɂ��������ł��B�l�͂��̂�����1�l�ɉ߂��܂���(��)�v
�@�N�F����ƈ��R������͗��s�D���Ȃǂ̋��ʓ_�������ĈӋC�����B������y�����Ă��y����ł���鈟�R������ɍN�F����͐S�䂩�ꂽ�B
�@�u��l�ɂȂ�ƃJ�b�R���ĕ]�_�ƂԂ肽���Ȃ�܂���ˁB�ł��A�Ȃ̓R���r�j�̃A�C�X�ł��w���������������ˁI�x�ƏΊ�ɂȂ��ł��B���̔������������āA�����������ł��d���A��ɂ��y�Y�������ċA��܂��B���v���A�Ȃƕt���������Ǝv�������������͂��̏Ί�ł��v
�@�������A�N�F����͌��ۊJ�n���甼�N���߂��Ă��v���|�[�Y����C�z���猩���Ȃ������B�Ȃ��Ȃ̂��B
�@�u����̏����ƕt�������Ă���Ƃ������o�͂���܂������A������������Ȃ炱�̐l���낤�Ƃ͎v���Ă�����ł��B�ł��A���łɃt���[�����X�ɂȂ��Ă������Ƃ������āA�Ƒ���{�����M������܂���ł����B���͉҂��ł��Ă��A10�N����d��������ۏ͊F���ł�����ˁB���傤�ǎd�����Z���������̂ŁA�����������z���Ƀp���[�����������Ȃ��Ƃ����C����������܂����v
���R�������҂��Ă�����
�@����̈��R������́A�N�F����Ƀf�B�Y�j�[�����h�⍁�`�ɘA��čs���Ă��炤���тɁu�T�v���C�Y�����v�����҂��Ă����B�F�l������u�N���N�n�ɍ��`���s�H�@�@�f�G���ˁB�����ƃv���|�[�Y������v�Ȃǂƌ���ꑱ���A�v���b�V���[�Ɋ����Ă����炵���B�������A�N�F����͉�������Ȃ��B���Ԃ肳�������Ȃ��B1�N��̂�����A���ς�炸�̂�C�ȍN�F����̖ڂ̑O�ň��R������͗܂𗬂����B
�@�u���̂ق�����Ñ�����̂͌��Ȃ���ǁc�c�B���Ƃ̌������ǂ��v���Ă���́H�v
�@�Q�ĂčN�F����̓v���|�[�Y�B�������A���S�ł͕s�������������Ă����B�N�F����͈��R������ɑł��������B�����͖{���ɉƑ���{����̂��낤���A�ƁB
�@�u�Ȃ̗��e�͎��c�Ƃł��B�w�����͂�����������Έ�����������B3�N���炢�Ȃ玄���撣���ĉ҂�������v����B3�N������A���Ȃ����V�����d������������ł��傤�x�ƌ����Ă���܂����B���������ɐS���X�b�ƌX�����u�Ԃł����ˁv
�@�N�F����́u�����点�j�q�v�Ƃ��������u�T�d�j�q�v�Ȃ̂��Ǝv���B�����āA�Ɛg�������y���߂鐫��������B
�@�u��������2�l�̎q�ǂ��ɂ��b�܂�܂����B�����ނ�̂��߂Ȃ�Α����̕s���R�͉}��Ȃ����A�����ƂȂ�����A���o�C�g�����Ăł��H�킵�Ă����o�������܂��B���ł��Ȃ�TV�ԑg�����Ă��A�ȂƂ������z�����L�ł��鑊�肪����̂͊������ł��v
���Ɛg�ɂ͓Ɛg�̊y����������
�@���̂悤�ɑO�u�������������ŁA�N�F����͕\���ς����Ɂu�Ɛg�ɂ͓Ɛg�̊y����������Ǝv���v�ƌ��̂��B
�@�u��l���Ȃ�Έ��S��q���ʂ̂��Ƃ����܂�l����K�v������܂���B�v�����łǂ��ɂł��s���܂��B�j���m��������Ԓ��������ĉ\�ł��B�����������Ƃ�����قǕK�v�͂���܂���B�l�͎Ԃ��������D���Ȃ̂ł����A�Ƃ̃��[����Ԃ��Ă��鍡�͍D���ȎԂ��]�T�Ȃ�Ă���܂���B�Ɛg�������炠��ȎԂɏ�ꂽ�̂ɂȁ`�A�Ǝv�����Ƃ͍��ł�����܂��v
�@������A���R������ƕʂ��悤�Ȃ��Ƃ���������A�N�F����͓�x�ƌ����͂��Ȃ����肾�B�M�҂̂悤�ɍč�����l�̋C�������悭�킩��Ȃ��ƌ�����B
�@�u����������ɓ��ꂽ�Ɛg�Ƃ������R���Ȃ��܂�������̂ł��傤���B�l�ɂ͗����ł��܂���v
�@�K���ȉƒ됶���𑗂鍡�ł��A�Ɛg�҂̐S������������N�F����B30�㔼�܂Ō������Ȃ��j���ɂ́A�N�F����Ɠ����悤�Ȑ��������l�������悤�Ɏv���B
�@�ނ�͌��������Ă��傫���͕ς��Ȃ��B�o�����X���o�ɕx�݁A�u�ƒ�̉������v�ɐZ��߂����A���܂��܂Ȃ��ƂɍD��S������������̂��B������A�ꏏ�Ɉ����킵�Ă��Ă��y�����B�N�F����̂悤�Ȑl�́A���Ƃ��Ɛg�ɖ߂����Ƃ��Ă����͂̏����������Ă͂����Ȃ����낤�B -
�yAFP�������z�f�B�Y�j�[�iDisney�j�Ȃǂ��`���u�v�����Z�X�i���P���܁j�v�Ɍ������������W�܂��Ă��鄟���B�j�����ꂼ��̌Œ�ϔO�����荞�ނ��Ƃ��A������ɂƂ��ĕs���v�ɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ������O�̍L�����w�i�ɁA�����ł́A�q�ǂ������e���r�ԑg�̐����Ђɑ��āA���`���S���ӂ�鏗���L�����N�^�[�ݏo���ׂ��Ƃ̗v�]�����܂����B
�@�f�B�Y�j�[�ɑ��ẮA�T�^�I�ȁu���P���ܑ��v�����X�i���悤�j�ɔ��荞�ނ��Ƃɂ��A�c��������̎�������߁A�u�̌`�R���v���b�N�X�v���ɔ��Ԃ��|����L�Q�ȁu���P���ܕ����v�������藧�ĂĂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����ᔻ������B
�@������ē��Ђ͍����A�v�����Z�X�ɂȂ邽�߂�10�������f�����|�X�^�[�𐧍삵�A������Ɂu���𐳂����v�A�u������M���悤�v�ƌĂъ|�����B
�@���������암�J���k�iCannes�j�Ő悲��J�Â��ꂽ���E�ő�K�͂̃G���^�[�e�C�������g���{�s�ł́A�W�܂����A�i���X�g��ԑg�����Ђ���A������e�炪���҂��Ă���̂́A��蔲�{�I�ȕω��ł���Ƃ̎w�E���Ȃ��ꂽ�B�܂��A���ǂ����[�����f���i�͔́j����Ȃ�����A���̎q��������͂����ۂ��������Ƃ��������オ�����B
�@�p�����h���iLondon�j�����_�Ƃ���R���T���e�B���O��Ёu�p�C�i�b�v���E���E���W�iPineapple Lounge�j�v�̃G�}�E�E�H�����iEmma Worrollo�j���́A�e���̎q�ǂ���������l��Ώۂɍs�����ڍׂȒ����ł́A���̎q�����̕s���������яオ�����Ƃ��Ă���B
�@�E�H�������́A�u������̃W�F���_�[�̑������́A�i����܂ł̐���ɔ�ׂāj�����Ƃ����Ə_��B��������̓��ʂȗv�f�ƔF�����邱�Ƃ�������ł���v�Ɛ��������B
���u�W�F���_�[�v�Ƃ����T�O���̂��̗̂�����
�@�ƊE�W�҂ɂ��ƁA�A�j���̃q�[���[�̖�4����3�͒j���L�����N�^�[�Ő�߂��Ă���Ƃ����B
�@�E�H�������́A�u�i����10�`16�́jZ����ƌĂ��q�ǂ������́A�j�̎q�ł����̎q�݂����ɁA���̎q�ł��j�̎q�݂����ɂȂ��̂ɁA�w�e���r�ł͂��ꂪ�����Ă��Ȃ��x�ƌ����Ă���v�ƌ�����B
�@����ŁA���v��f�s���悤�ƌ��ӂ��ł߂��`�����l��������B�t�����X�ł͋Ǒ��������Ђɑ��A�q���C�������Ƃ���V���[�Y�������ɗv�������B�u���̑����Ɠ��l�v�A�j���̃L�����N�^�[��ɒ������s�ύt�����݂���Ǝ���F���������߂��Ƃ��Ă���B
�@���ǂ̎q�ǂ������ԑg������e�B�t�F���k�E�h���O�l���iTiphaine de Raguenel�j����AFP�ɑ��A�u�v�����Z�X��d���A���Ă�ȏ��̎q�����������̂͂�߂悤�Ƃ����������v�ƌ�����B
�����ȑ��̖��
�@���Ƃɂ��A���ȑ��̖��͂����c����������n�܂�Ƃ����B�č��ō��N���\���ꂽ�A���A�w����Ώۂɂ��������ł́A���P���ܑ��̍��荞�݂��������3�Ύ��̍s���l���ɂ��e����^�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
�@�����Ɍg������T���E�l�E�R�C���iSarah M. Coyne�j�������́A�u�w�����͂�������ׂ��x�Ƃ����Œ�ϔO�ɂƂ���߂��鏗�̎q�����́A�����ɂ͓���̂��Ƃ��ł��Ȃ��Ɗ�����v�Ɗ뜜��\�������B
�@�q�ǂ������G���^�[�e�C�������g��ƃW���E�w���\���E�J���p�j�[�iJim Henson Company�j�̃��T�E�w���\���iLisa Henson�j�ō��o�c�ӔC�ҁiCEO�j�́A�����Ђ͂��̖��Ɏ��g�ޕK�v������Ƒi����B
�@���Ђ��V���ɐ��삵���C�̒��Ԃ������ނɂ����V�A�j���V���[�Y�u�X�v���b�V���E�A���h�E�o�u���Y�iSplash and Bubbles�j�v�́A�w���\��CEO�̕��e�W���E�w���\���iJim Henson�j������|�������E�I�ɗL���Ȏq�ǂ������ԑg�u�Z�T�~�X�g���[�g�iSesame Street�j�v��u�U�E�}�y�b�c�iThe Muppets�j�v�̑��l�����p���ł���Ƃ����B
�@�V�V���[�Y�ł́u�j�̎q�Ə��̎q�̃L�����N�^�[�̐������낦�A���ꂼ��ɐ����z���������^�����B����Ă��Ȃ蒆���I���v�ƁA��CEO�̓R�����g�����B
�@�q�ǂ������Ɋy����ł��炢�Ȃ���u�ǂ����l�ρv��`���Ă����Ƃ������Ђ̎g����^���i���j�Ɏ~�߂Ă���ƁA�w���\��CEO�͌����B
�@�V�A�j���V���[�Y�̕���ł���C�ɂ��ẮA�u�C��͐M�����Ȃ����炢���l���ɖ����Ă���c499�C�̎q�ǂ��e�����ň�Ă�^�c�m�I�g�V�S�����ēo�ꂷ��v�Ə�k������Ɍ��A�����āu���������̃^�c�m�I�g�V�S�̕��e�́A�o�Y�����Ď����ł��Ă��܂��B�C�ł͕s�v�c�Ȃ��Ƃ���������N����v�Ƒ������B�y�|��ҏW�z AFPBB News -
��҂��u�����l������炵�v�Ƀn�}�闝�R
�@���A�Ⴂ����ɋ��ʂ��銴�o�Ƃ��āA�u�E�Z��v�v�u��������܂��B�������̂悤�ɁA���ɂ͐E��ƏZ�܂�����u�E�Z�����v���i�݁A��s���x�O�ɂ́A�s�S�֒ʋ���l�̏Z��n�𒆐S�ɔ��B�����x�b�h�^�E�����L�����Ă����܂����B����ȑO�́A�T�����[�}���͂������A���X��H��œ����l���A����X�����˂Ă�����A�Z�ݍ��݂œ����Ă����̂ł����A����ɐE��Ɨ��ꂽ�Ƃ���ɏZ�ނ悤�ɂȂ����̂ł��B
���u���e�̂悤�ɒ������ʋ͂������Ȃ��c�v
�@�������A���̌��ʂƂ��ē����������������ʂ��邱�ƂɂȂ����̂́A�E��܂ł̒������ʋł��B�����āA�����������Ԃ������Ď���Ɖ�Ђ��s�������A���ʂĂ�e�̎p�����Ă������̎Ⴂ����̒��ɂ́A�u�����͂��������������̓C�����v�ƁA�ł��邾����Ђ̋߂��ɏZ�݂�����l���������̂ł��B
�@����Ȏ�҂�������̐l�C���W�߂Ă���A�ʔ����s���Y��Ђ�����܂��B�uEARLY AGE(�A�[���G�C�W)�v�Ƃ�����Ђł��B�����Ă���̂́A������7���āA������l�������x�̏����ȕ����B����c�①�O�A��O�����ȂǁA��s�S�߂��́A�w����߂����n�𒆐S�ɓW�J���Ă��܂��B�����ɂ́A�g�C���ƃV�����[�A���ʏ��Ɨ���������˂��V���N������A���ɐ���@���͂ߍ��܂�Ă��܂��B�����ɂ���ẮA�g�C���̎d�肪�Ȃ��ꍇ������B�ꌩ�A�т����肷��Ԏ��ł����A���o��Ƃ����ɖ��܂��Ă��܂������ł��B
�̂̎l������炵�Ƃ͉����Ⴄ�̂�
�@����ȋ��������ɕ�点��̂����āH�@���ꂪ�A��点��̂ł��B���̕����ɏZ�݂����Ǝv���l�����́A�X�}�z��������ΐ����Ă����邩��ł��B�①�ɂ��u���Ȃ��Ă��A�R���r�j�����̖������ʂ����Ă���܂��B��������A�Ƃɂ�����Ђ���ƂɋA��܂ł̎��Ԃ��ɂ����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�ʋΎ��Ԃ��ɗ͒Z�����āA�����Q�����A�ƁB
�@�傫�ȉ�Ђ�����悤�ȓs�S�̋߂��ŏZ�����Ƃ���ƁA���R�Ȃ���ƒ��̑���͍����B�������A���J�l������l�͂���ł�������x�̍L���̉ƂɏZ�ނ̂ł��傤���A�����łȂ���A�Z���̍L�����͉�Ђ���̋߂���I�ԂƂ����킯�ł��B�Ƃ͂����A���̕s���Y��Ђ������Ă��镨���̏ꍇ�́A�����Ă��f�U�C�i�[�Y�}���V�����Ȃ̂ŁA�����܂ň����͂���܂��c�B
�@����́A�̂̋�w�����������Ă����l������炵�Ƃ͂܂��قȂ�`�Ԃł��B���͂�����A�u�V�E�l������炵�v�ƌĂ�ł��܂��B1970�N��̎l������炵�́A�n������s��ɏo�Ă�����҂������A���J�l�̂Ȃ��w������Ȃǂ��߂����ꏊ�ł����B�������A�������L���ɂȂ�ɂ�āA�e���r���A�X�e���I���c�Ƃ��m�������Ă����A������L�������Ɉ����z���Ă����܂����B�����āA�ƒ�����ƁA�x�O�ɏo�ĉƂ����̂ł��B
���������̒j�����Z�݂����X�́A���!?�@
�@����A���݁u�V�E�l������炵�v�����Ă���̂́A�x�O�Ő��܂�āA�s�S�ŏA�E�����A�����̎�҂ł��B�����āA�ނ炪������x�O�֖߂��Ă������Ƃ����ƁA�K�����������ł͂���܂���B���݁A�s�S�̐l���͑��������Ă��܂����A����͗����������Ă���̂ł͂Ȃ��A���o�������Ă��邩��ł��B�s�S�ɁA�����ҁA�����ҁA�q�����ȂǁA���l�Ȑl�X�̂��߂̏Z���������Ă���̂ł��B
�@�܂��A50�キ�炢�ɂȂ��Ă��J�l������Ɛg�j���̒��ɂ́A�s�S�ʼn��\�������镔�������l�����Ȃ�����܂���B�����s�����u�Z�݂����X�v�Ɋւ��钲���̒��ł́A�u�N���̍����j�����Z�݂����X�v��5�ʂɋ���������N�C�����Ă��܂��B���ہA���̒m�荇���̖^����Ƃɋ߂�50��Ɛg�j���́A����ɏZ��ł��܂���B������ƊO�H���悤�Ƃ������ɁA�������X����Ȃ̂ō��邱�Ƃ͂���悤�ł���(��)�B
�@�܂��A�������ĉƑ�������A���Ɏq�ǂ���2�l�ȏア��ꍇ�́A�s�S����̋������߂����ɔ�r�I�����Z�߂�A�]�ː��A��t���̒Óc�����t�A��ʌ��̑�{�Ȃǂ��l�C�ł��B�x�O���g�債�Ă���������́A�v�������A�Ȃ͐�Ǝ�w�Ƃ����Ƒ����f���ƈقȂ�A���͋������������Đ��ю������オ���Ă��܂��B����ƁA�Ƒ������Ă��ł��邾���s�S�̋߂��ɏZ��ŁA�ʋΎ��Ԃ�Z���������ƍl����悤�ł��B
�����X�A�Z�ފX�̋�ʂ��Ȃ��Ȃ�H
�@���̌��ʁA����́u�������߂̊X�v�A�u�Z�ނ��߂̊X�v�Ƃ�����ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă����ł��傤�B���ɁA�A�����J�̃}���n�b�^���͂��̋�ʂ��Ȃ��X�ł��B
�@�s�S�ɏZ�ސl�������Ă������ꍇ�A�l���������Ă����x�O�ɖ����͂���̂ł��傤���B���́A�x�b�h�^�E���̈�ۂ������u�x�O�v�Ƃ����ď̂͂�����߂āA�����������u�n���v�Ƃ��Č��Ă����ׂ����Ǝv���܂��B
�������������́A�u�T�����]�[�g�v�Ɍ����Ă���
�@�x�O��������n���Ƃ��čĐ����邽�߂ɕK�v�ȏ����́A�ȉ���3�ł��B1�ڂ́A�u���[�J�u���v�ȊX�ɂȂ邱�Ƃł��B�y�V����q�ʐ�ɖ{�Ђ��ڂ����悤�ɁA�傫�Ȋ�Ƃ�U�v����B���邢�́A�ݑ�Ζ��Ɍ����Ă���X�ɂ��邱�Ƃł��B
�@2�ڂ́A�ސE��̐l�������Z�ށA�u���^�C�A�����g�E�T�o�[�u�v�����邱�Ƃł��B�����A���ꂩ��͑ސE���Ă����S�ɓ������Ƃ���߂�͓̂������A�ݑ�Ζ������₷�����ł��邱�Ƃ������ł��B�����āA�������Ȕ������X�|�b�g������Ȃ��ǂ��B�g�ˎ��̂悤�ɂˁB�K�v�Ȃ��̂̓A�}�]���Ŕ�����̂ŁA��^�X�͕K�v����܂��A�������Č��I�Ȃ��X������Ƃ悢�ł��傤�B�����āA�d���Ŏϋl�܂����Ƃ��ȂǂɎU�����Ċy�����������邱�Ƃł��B
�@������3�ڂ́A�u�T�����]�[�g�v�Ƃ��Ĕ���o�����Ƃł��B�����͓s�S�œ����āA��Ђ̋߂��̉ƂɋA��l�������A�T�������͂��̊X�ɏo�āA�ʑ�ł������߂����B�������A���ӂ�����A�Ȃǂ̗v�f���������X�́A����ɓK���Ă��܂��B�������̉����Ȃǂ͔�r�I����Ɍ����Ă���Ƃ����܂��B�������A���i�͍ݑ�Ζ��ŁA�T�ɐ���s�S�̉�Ђɏo������A�Ƃ����������̐l�̏ꍇ�́A�����ɖ{����\���Ă����͂���܂���B
�@�ސE��̐l��ݑ�Ζ�������Ⴂ���オ�����荇���ďZ��ł�����A��������͂��ނł��傤�B�����Ċy�����u�E�H�[�J�u���v�ƁA�����Ċy�����u���[�J�u���v�A����2���d�v�ȏ����ł��B
�@���́A2012�N�ɏo�����w��l�̏���x�Ƃ����{�̒��ŁA���[�}���E�V���b�N�ォ��́A�l�����m�̏��L�ɂ������Ȃ��A�V�F�A�̏���ł���u��l�̏���v�Ɉڂ�ς���Ă��邱�Ƃ������܂����B�����āA��l�̎��ɂ�����A��܂̏���Ƃ͉����Ƃ����ƁA����́u�ꏊ�v���ǂ�����̂��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB�ǂ�ȏZ�܂��ɁA�����Ăǂ�ȊX�ɏZ�ނ̂��́A������l�����ŁA�c���ꂽ�e�[�}�ł��B
�O��A���{�̃t�@�b�V������80�N��̌��̎�����o�āA���݂̓V���v�������Ă��邱�Ƃ������܂���(�u�����������͂������v�������S�ݓX�s���v)�B�����A�Z�܂��Ɋւ��Ă͂܂��x��Ă��āA�t�@�b�V�����ɒu���������80�N��O�̏A�܂���̎��オ�������Ă��Ȃ��̂ł��B�悤�₭�A�Â��Ƃ��Ď����D�݂Ƀ��m�x�[�V��������̂��������A�Ƃ��������͏o�Ă��܂������A����͂܂��N���G�C�e�B�u�Ȑl�Ɍ����������B���ꂩ��́A�ǂ�ȊX�̂ǂ�ȉƂɏZ�݁A�ǂ��ŗ]�ɂ��߂����̂��A�Ƃ������ƂŌ����o���čs������ɂȂ��Ă����ł��傤�B -
���s���H��ؔ[�z�u�`��������B���ŕ���Ȃ�����˂�I�v�ی�҂̒Ⴂ�������Ȃljۑ肳�܂��܁c�S�����[�z�Q�Q���~�A�ٌ�m�����̐�s�����̂Ō���
�@���H��ؔ[�ւ̑Ή��Ƃ��āA���s���ς��ٌ�m�ւ̈ꕔ�ϑ����n�߂邪�A���̖��ɂ��Ă͑S���̊w�Z�W�҂�����Y�܂��Ă���B�����Ȋw�Ȃ̒����ł͑S���̌��������̖��[�z���v�͖�Q�Q���~�i�����Q�S�N�x�j�ɂ̂ڂ�B�w�i�ɂ͕ی�҂̃������̒Ⴓ�ƂƂ��ɐ��x��̖��������яオ��B
�@�u�`��������B���ʼn��炪����Ȃ�����˂�v�B���s�����w�Z�ŋ��@�����Ă����T�O��̒j�����A���������������A���H��[�̕ی�҂��痁�т���ꂽ�̂͂P��ɂƂǂ܂�Ȃ��Ƃ����B
�@���������w�Z�ł́A�����ݔ��⒲�����̐l����Ȃǂ͎����̂ȂNJw�Z�̐ݒu�҂����S���Ă���B�ی�҂ɋ��H��Ƃ��ĕ��S�����߂Ă���̂͐H�ލw����Ȃǂ������B�������A���ꂷ�略�����Ƃ��Ȃ��ی�҂ւ̑Ή��ɁA���猻��͘J�͂���������Ȃ��̂����Ƃ����B
�@�u���ɔ������Ă���邾���ł��܂��Ȃ̂�������Ȃ��B���S�ɖ�������A�������Ȃ����Ƃ�����v�B�j���́A�������ߑ��������B
�@���ȏȂ̒����Ŗ��[�̌�����q�˂��Ƃ���A�u�ی�҂̐ӔC����K�͈ӎ��v�Ɖ����w�Z�͂U�P�E�R���ɏ��A�u�o�ϓI�Ȗ��v�̂R�R�E�X����傫���������B
�@����ŁA�Ǘ����x�̖�������ɂ���Ƃ݂���B
�@�S���̏����w�Z�̂V���߂����̗p���Ă���w�Z���Ƃ̓Ɨ���v�i����v�j�ł́A�ؔ[�̕ی�҂Ƃ̐Ղ͒S�C�⋳���A�Z����w�Z���ꂪ��́B�ʏ�Ɩ��ɉ����ĉƒ�K��œ����s���Ȃǂ̕��S���傫����A�@�I�[�u�ȂNj����Ή��ɏ��o���ɂ����B���̂��ߎ����̂Ƃ��ċ��H����ꊇ�Ǘ�����u����v�v�ɐ�ւ��铮�����o�Ă���B
�@���s���ς͂Q�U�N�x�Ɍ���v�ɕύX���A�����ǐE�����ؔ[�ւ̑Ή��Ɏ�̓I�ɂ�����悤�ɂȂ����B�u�w�Z����̕��S�����炷���Ƃ��ł��A�ؔ[�҂ւ̑Ή������m�ɍs����悤�ɂȂ����v�i�S���ҁj�B���������E���̕��S�͊F���ł͂Ȃ��A�E������̓��������ł������Ɍ��E�͂���B
�@���s�ɐ�s���āA��N�x����ٌ�m�ւ̈ϑ���{�i�������Ă��铌���s���n��ɂ��ƁA�����O�̂Q�T�N�x�P�N�ԂŖ�Q�U�O���~�ɏ�������H��[�z�́A�Q�V�N�x�ł͔����ȉ��̖�P�Q�O���~�Ɍ��������B�ٌ�m����̓��ŕ����[�t�ɉ�������A�Z���̖��[�ɂƂǂ܂�P�[�X�������Ă���Ƃ����B -
�@�l�b�g��Łu���E�ی��@�ցiWHO�j�����I�p�[�g�i�[�����Ȃ��l�͏Ⴊ���҂ɂ�����Ɣ��f�����v�i�����}�}�j�Ƃ������킳���L�܂�u���I�p�[�g�i�[�v���g�����h���肷��ȂǁA�g�䂪�L�܂��Ă��܂��B���̑����̔��[�͊C�O�������p���ĕ�ꂽ�u���I�p�[�g�i�[�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�͏�Q�҈����Ɂv�Ƃ���Sputnik�̌��L���ŁAWHO���������������\���s���������͂���܂���B
�@Sputnik�̋L���͊C�O���uThe Telegraph�v�̋L�������ƂɁA�g���E�ی��@�ցiWHO�j���s�D����Q�Ƃ݂Ȃ��A���I�p�[�g�i�[���������Ȃ��l���Ⴊ���҂Ɠ��ꎋ���邱�ƂɂȂ����h�Ƃ�����e�ƂȂ��Ă��܂����A���L���́udisability�v�����`�ł́u��Q�v�Ƃ��Ă���ȂǁA���m�Ȗ|��Ƃ͂����Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̌�Sputnik�̋L��������Ɉ��p����`�ł͂��܋N�e���u�w����͕a�C�ł��x WHO�i���E�ی��@�ցj���Ռ����\�����������v�Ƃ���L�������J�������A�����̂܂Ƃ߃T�C�g�ł����グ����ȂǍL���g�U�B�������A���L���͂������ASputnik�̋L���ɂ��u����͕a�C�v�u����͏Ⴊ���ҁv�Ƃ��閾�m�ȋL�q�͂Ȃ��A�������������Ӗ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���L���͂����܂Łg�D�P���Â炢�j�����Ώۂ������u�s�D�v�u�q���Ɍb�܂�Ȃ��l�v�̒�`���A���L�͈͂ɂȂ������Ɓh�����グ�����́B����̑����͌��L�����܂Ƃ߃T�C�g���g����߂��A�N���������̂ƌ��������ł��B
-
�@���{�����e���̃f�p�[�g���A�ꋫ�ɗ�������Ă���B9��30���A���{�Ŗk�[�̃f�p�[�g�A��������X�i�k�C���E����s�j���X�����B���X�Ō�ƂȂ镨�Y�C�x���g�u�S�����܂����̑��v�͑����̔������q�Ő���オ��A���ɂ܂��ė܂���l���B���������ł͂Ȃ��B���N�����ł��������X�A�����t�����X�Ȃ�4�X�܂��A���N�ɂ͎O�z��t�X���k�ԓc��}�ȂǁA5�X�܂��X��\�肵�Ă���B
�u�����͎O�z�A�����͒錀�v�B���Ă���ȁu�n���̓��v�̏ꂾ�����f�p�[�g���A�����炱��Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��H
�@�V���[�E�C���h�[��ʂɁA�u���{�Ɛ� ����O�z8F�v�Ƃ��������B�����ď��������ȕ����Łu�ǂȂ��ł������R�ɂ������������܂��v�Ɠ��{�ꂪ�Y�����Ă���B�`���Ă݂�ƁA500�������[�g���͂���L���t���A�ɁA�q��10�l�����Ȃ��B40�l�قǑҋ@���Ă����X���͉ɂ����Ă��܂��Ă����̂��A�L�҂�������Ɓu����Ƌq�������v�Ɗ���P�����A���X�Ɛ��������Ă����B�����X����1�l����Ό�����ɁA�u�c�̋q������[���͂���������Ƃɂ��키��ł����ǂˁc�v�ƌ����B�悭�����ƃC���g�l�[�V�������Ⴄ�B�ǂ����X���̑唼�������l�̂悤���B
�@�����́A���N1���A�蕨����ŃI�[�v����������O�z�̖ƐŃt���A�uJapan Duty Free GINZA�v�B��`�̖ƐœX�Ɠ����悤�ɁA�p�X�|�[�g�ƊC�O�ɍs�����挔������Ώ���ł݂̂łȂ��A�ł��ŁA�����ł܂ł����ƐłɂȂ�B���������{����o�Ȃ��l�ɂƂ��Ă͊W�̂Ȃ��t���A���B
�@���J�Ȑڋq������̋���̍����f�p�[�g���A�������N�A�����l�ό��q�́u�������v���ʂő傢�ɓ�����Ă����B���������͑O�q�̒ʂ�A�ՌÒ������Ă����ԁB�킸��2�`3�N�O�̑S�����ɂ́A�������Ƃ�����200���A300���~��������O�������̂��A���͂��������\�����~�������Ƃ���B
�@�����̓����哱��A�~���E�����ƂȂ������A���z�i�͔���Ȃ��Ȃ�A��ʂɎd���ꂽ�������v��u�����h�i�́A�ɂ��肪�c�錋�ʂƂȂ��Ă���B
�@1991�N�̃s�[�N����9��7130���~�������S�ݓX�s��K�͂́A2015�N�ɂ�6��1740���~�܂ŏk�����Ă���B�o�u�������A���q����A�f�t���ȂǓ��������̉e��������Ɏ��f�p�[�g�ƊE�B
�u����ɒ��߂̌����������o�����̂́A�S�ݓX�ɂ��ӔC�̈�[������v�Ƙb���̂́A�o�ϕ]�_�Ƃ̕���a�V���B
�u�������Ⴊ����ł��B����̓C���o�E���h����������ɍ��킹�Ăǂ�ǂ�ĊJ����i�߂܂����B�S�ݓX������ɏ�����킯�ł����ό��o�X�����ʌ��ւɂǁ[��Ɖ��Â����āA��ʂ̒����l���呛�����Ĕ����Ă����B�̂Ȃ���̋�u������X�ł͂Ȃ��A����т₩�����ǂ悭����g�A�W�A�̈�s�s�h�ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
�@�c����₲��c�l�̎��ォ��ʂ��ė����Ƃ��������̂��邨���ӂ���Ȃǂɂ�����A�������������X�ŁA�����Ќ��ꂪ��ь����ڋq����ɂȂ��Ă��܂����X�Ɂg�Ȃ�ł���ȂƂ���Ŕ���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��h�ƈ��z���s�����ł��傤�v�i���삳��j
�@�������̒܍��ƂƂ��ɁA�f�p�[�g���ꂵ�߂鑶�݂��u�w�r���v���B�f�p�[�g�̒����Ԃ�Ƃ͑ΏƓI�ɉE���オ��𑱂���̂́AJR�����{�O���[�v��Ђ��^�c����w���~�l�x�B���N3�����̓X�ܔ���z��3255���~�ƁA�ߋ��ō����L�^�����B
�u�����������ɏZ��ł���̂ŁA��ЋA��ɐV�h�̃��~�l�Ɋ�邱�Ƃ��قƂ�ǁB�Z���N�g�V���b�v�������Ă��邩�畞�������邵�A�b��̃X�C�[�c��������Ă��邩��A��y�Y���Ƃ����d�Ă��܂��B
�@�̂͋���̃f�p�[�g�ɒʂ��Ă��܂������ǁA�ŋ߂͑S�R�s���ĂȂ��ł��ˁB�f�p�[�g���w����k��5���ł��A�������͉w�����ł�����ˁB�Ȃ��ʓ|�ɂȂ�������āv�i�g�c�m�q����E�����E41�ˁj
�@�������V�h�̖����ƂȂ����̂��A���N3���ɃI�[�v�������A���~�l�̐V�{��NEWoMan�i�j���E�}���j�B��4���܂ʼnc�Ƃ��Ă�����H�X������g������̗ǂ��ɉ����A�p�����܂�̃V���[�N���[�����X�w�V���[�E�_���t�F�[�� �p���x��ALA���́w800���f�B�O���[�Y �i�|���^�� �s�b�c�F���A�x�ȂǁA���{���㗤�̓X�������l�C���W�߂Ă���B
�u�����Ƃ͗��n�����ł��B�f�p�[�g�Ɠ����v�f�����{�݂��A�����̂����w�ɂł��Ă��܂��A�ڋq���Ƃ��Ă��܂��܂��B�Ƃ��ɑ���X�C�[�c�Ƃ������g�H�i�h��g���ϕi�h�ȂǏ����̌l����͕s�����ł����肵���h��������ł������A�w�r���ŊȒP�Ɏ�ɓ���ƂȂ�A�S�ݓX�́g�h�����h���N�H����Ă��܂��v�i�O�o�E���삳��j
�u�Ɛш����͔��Ŋ����Ă���v�Ƙb���̂́A��w���ƌ�ɑ��f�p�[�g�ɏA�E���A���݂͊֓����̓X�܂ɋ߂�ѓމ��q����i�����E50�ˁj�B
�u�g�������Ƒ��Ɖ߂������߁h�Ƃ������ڂŁA���N����1��2���̏��������߂Đ�^����Ă��铯�Ƒ��Ђ�����̂ł����A����͈Ⴄ�����ł��B�c�Ƃ��Ă��l�������M������锄��グ���Ȃ�����A�߂��ق��������Ɣ��f��������ł��v�i�т���j
�@����ɐ��������ܕ��́A�������q������₵�Ă��āc�B
�u���C�ɓ���̌C������Ă����̂ŁA�v�X�ɐV�����C�����Ǝv���ăf�p�[�g�ɍs�����Ǝv��������ǁA�l���݂ɏo��̂��Ȃ������Łc����ȂƂ��Ɂw�l�b�g�V���b�s���O�ł������E�ԕi�\�x�Ƃ����T�[�r�X�����������炻�����ɂ����Ⴂ�܂����v�i�n�Ӌ��q����E�����E35�ˁj
�@���q����̂悤�ɁA�l�b�g�V���b�s���O�𗘗p����l�������Ă���B2015�N�̑����Ȓ����ɂ��ƁA�l�b�g�V���b�s���O�����Ă���l�̊�����2002�N�ɂ�5.3�����������A2015�N�ɂ�27.6���ƁA5.2�{�ɂȂ��Ă���B���Ȃ̕ʒ����ɂ���1�ʂ́u���X�܂ɏo�����Ȃ��Ă����������ł��邩��v�i73.7���j�Ƃ������R�������B
-
�����������̂��Ƃ��D���ɂȂ�u���Y�r�A���v�A�j���̂��Ƃ������̂��Ƃ��D���ɂȂ�u�o�C�Z�N�V�����v�A�S�Ƒ̂̐��ʂ���v���Ȃ��u�g�����X�W�F���_�[�v�ȂǁA���I�}�C�m���e�B�̐l�������A�p�[�g�i�[����͂̐l����������\�͂Ɋւ��钲�����ʂ��܂Ƃ܂����B���̌��ʁA�g�̓I�Ȗ\�͂�I�Ȗ\�͂��Ă���l�����Ȃ��Ȃ����Ƃ���������ɂȂ����B
���̒����́A���I�}�C�m���e�B�Ɋւ�����M���Ă���u�Q�C�W���p���j���[�X�v��NGO�Ƌ��͂��āA2010�N11������2012�N3���ɂ����č����Ŏ��{�B�v50�l�̃��Y�r�A���A�o�C�Z�N�V�����A�g�����X�W�F���_�[�̐l������ΏۂɃC���^�r���[�����ł����Ȃ��A�������ɂ܂Ƃ߂��B
�����ł́A�g�̓I�Ȗ\�͂Ɛ��I�Ȗ\�͂ɉ����A���_�I�Ȗ\�͂��A��Q�҂֑傫�ȃ_���[�W��^������̂Ƃ��ďd���B������܂߂��u�\�́v�����o���������˂��Ƃ���A�����S�������ʂ��߂����āA���炩�̖\�͂��o�����Ă������Ƃ��킩�����B50�l�̂����A�g�̓I�Ȗ\�͂��o�������l��14�l�A���I�Ȗ\�͂��o�������l��28�l�A���_�I�Ȗ\�͂��o�������l��31�l�������B
�����Y�r�A�����J�~���O�A�E�g���ď�i�ɖ������ꂽ
���Ƃ��A����g�����X�W�F���_�[�̏����i�j���̐g�̂Ő��܂ꂽ���A�����������ƔF���j�͍��Z���̂Ƃ��A�������̒j�q10�l�ȏォ�炢���߂ɂ������B���̍ۂɁA����ڐG�����Ƃ����u�W�c�\�s�v�����Ƃ����B�������ɂ́u�����̒��ł͂Ȃ��������Ƃɂ��܂����B�i�L�����j�}���������Ƃ������ǁA�Y��悤�ɂ��Y����Ȃ��v�Ƃ����������L�^����Ă���B
�܂��A���{�݂œ����Ă������Y�r�A���̏����́A�E��Ń��Y�r�A���ł��邱�Ƃ��J�~���O�A�E�g�������ʁA3�N�ȏ�ɂ킽���āA��i�⓯�����疳�������Ƃ������_�I�Ȗ\�͂����B�ŏI�I�ɂ͑̒�������A�ސE�ɒǂ����܂�Ă��܂����Ƃ����B�����̏�i����́A�u���Y�r�A���Ƃ����������l���Ə����̗��p�҂���̐g�͕̂s���R������R�ł��Ȃ��A�������炳�ꂽ�肷��Ƃ�����ƕs�����ȁv�ƌ����Ă����̂��������B
���҂̔����ȏオ�u���E���l�������Ƃ�����v
�ق��ɂ��A�C���^�r���[�ɉ�����50�l��27�l���u���E�v�ɂ��Ĉ�x�͍l�������Ƃ�����A���̂���5�l�͎��ۂɎ��E�����̌o��������Ɖ����B�u�����I�Ɏ����̐l�����悭�Ȃ�Ƃ��v���Ȃ��B�ς��Ȃ������Ǝv���Ă��ꂪ�h���Ă����_�����Ǝv�����v�B27�l�ɂ́A���̂悤�Ɂu������`�����Ɓv�ɍ����������X��������ꂽ�Ƃ����B
����g�����X�W�F���_�[�̒j���̓C���^�r���[���甼�N��Ɏ��E�����B�Q�C�W���p���j���[�X������\�̎R��������́A�u�d���̖ʐڂ�f��ꂽ��A�Ƒ��E�w�Z�Ɏ���Ă��炦�Ȃ��ȂǁA�l�K�e�B�u�Ȍo�����ςݏd�Ȃ邱�Ƃ��w�\�́x�ɂȂ肦��v�Ƙb���Ă���B -
�ߘJ���E�ߘJ���E�i�����܂ށj�����킹���J�ДF�茏���́A����10�N�ȏ�A200���O��Ő��ڂ��Ă���B�������A�d�ʓ���1�N�ڂ̍����܂肳��i����24�j���ߘJ���F�肳�ꂽ����̂悤�ɁA�j���[�X�Ƃ��Ď��グ���邱�Ƃ͂��܂葽���Ȃ��B��������[�N���ꂽ��A�⑰���L�҉���J�����肵�Ȃ�����A��Ɩ��͂Ȃ��Ȃ��\�ɏo�Ă��Ȃ����炾�B
�⑰����Ж������\����A�Љ�I�ɂ͑傫�ȃC���p�N�g������A�J�����̉��P�ȂǂɂȂ���\��������B�������A���f�B�A�̑O�Ɏp��\���⑰�͏������B�S���ߘJ�����l����Ƒ��̉�E��\�̎����Ύq����i67�j�����s�{���́A�u��排����ȂǂɎN�����̂ŁA�s�����N�����ɂ͗E�C������B�������������Q���肷��⑰�������v�ƉߘJ���⑰���u���ꂽ�ꋫ�����B
�����������ȐӔC�_
�u�Ȃ�Ŏ��ʑO�ɉƑ��̊炪�����������낤���c�v�B�������g��1996�N�ɕv�̏�����i����49�j���ߘJ���ŖS�����Ă���B���H�X�̓X�������Ă���������́A�����ԘJ����В����狭���v���b�V���[�𗁂т���ꑱ���A�����1�q�قǗ��ꂽ�s�c�c�n��4�K�����э~�肽�B
�u�w�����Ă������Ȃ������x�Ǝ�����ӂ߂܂����B����ŁA�v�����ދC����������܂����B�w���ő��k���Ă���Ȃ������x�w�q�ǂ�������̂Ɂx���āB�����͎��E�ɑ���Ό�������܂����B�Ƒ��ł��������Ȃ�ł��v
��������ɂ��ƁA�⑰�������o���Ȃ��w�i�Ɂu�ߘJ���͎��ȐӔC�v�Ƃ�������������Ƃ����B��排����ւ̋����Љ�̖������̂��߂ɁA�⑰���ӔC��������ɕ�������ł��܂������Ȃ̂��������B
�u�Z�������Ƃ͒m���Ă��Ă��A�Ƒ��͉�Ђʼn����N���Ă������͕�����܂���B�����������悭������Ȃ���ł��B�܂��A�ߘJ�����咣���Ă��A���肩��́w�Ȃ�Ŏ��߂Ȃ������́B�Ȃ�Ŏ��߂����Ȃ������́x�Ɣᔻ����܂��B���E���Ɠ��Ɍ����Ȃ��B�w���_���ア�x�w�l�̐ӔC���x�ŕЕt�����Ă��܂���ł��v
��ʂɉߘJ������l�͂܂��߂ŐӔC���������A�d����Y�݂���l�ŕ������݁A���͂ɘb���Ȃ��X��������ƌ�����B��������̏ꍇ�́A������̑��V�œy�������Ďӂ�В����������āA�u��ЂɐӔC������v�Ǝv�����������B��������͂��̌�A�J�Ђ�\���A�ٔ��ł͉�ЂɐӔC��F�߂������B�ٔ��̉ߒ��ŁA�v�̉ߏd�J�����������A��Ђ̒��ł����Ɋ撣���Ă����������������Ƃ����B
���Ԏӗ��ɑ��錙�����Ɠi��
�������A�������v�̘J�Ђ�\�������̂́A����1�N�ȏ�o���Ă��炾�����B���R�͎q�ǂ��ւ̔z�����B�����͉ߘJ���E�ɑ���F�����Ȃ��A�����킪�\�z���ꂽ�B�u��̎q�͑�w2�N���ł������A���͒��w2�N���ł����B���Z����������܂ł͓����Ȃ�������ł��v
�q�ǂ�������ꍇ�A�z��҂��S���Ȃ�A�c���ꂽ����͎q��Ă����Ȃ��瓭���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����Ȓ��A�J�Ђ�\��������A�ٔ��Ő�����肷��̂͑傫�ȕ��S�ɂȂ�B������⑰���\�ɏo�ė��Â炢���R��1���Ƃ����B
�������A�J�Ђ��F�肳�ꂽ��A�ٔ��ʼn�Ђւ̈Ԏӗ��⑹�Q�����������F�߂�ꂽ�肵�Ă��A�Y�݂͐s���Ȃ��B��������́u�F�肳��ăz�b�Ƃ������ʁA�⏞�̂��߂ɂ���ė����̂��Ǝv���āA�}�Ɍ��������o���܂����v�ƌ��B
����⑰�́A�ٔ��ɏ��i�������Ƃ��V���ɍڂ����Ƃ���A���͂���u�S���Ȃ������ǁA���ꂾ�����炦�ėǂ������ȁv�u���������Ȃ��Ă����ȁv�Ȃǂ̐S�Ȃ����t���������A�ЂƑO�ɏo��̂��|���Ȃ����Ƙb���Ă����������B
���u�q�ǂ����������e�������Q���肷��̂����x�����ė����v
���N���߂č��ꂽ�u�ߘJ�������v�̒��ɂ́A�⑰���x������ٌ�m��⑰�̃R�������f�ڂ���Ă���B��������͂��̒��ŁA�u��Ў҂͒����N���嗬�������̂��A�ߔN�͎�N�w�ɍL����A���⑧�q��S�������e�䂳���A�����̐q�ǂ���������Ȃ����k�ɗ����Ă��܂��v�ƋL�����B
�u�z��҂������Ă��q�ǂ�������ꍇ�́A�����Ǝq�ǂ��̂��߂ɁA�撣�낤�Ǝv����B�ł��A�ߘJ���Ŏq�ǂ����������e�䂳��́A�w�������]�x���₽��Ă��܂���ł��B�������Ă��q�ǂ��͐����Ԃ��ė��܂���B�i�S���Ȃ������ƂƋƖ��̈��ʊW�́j���ؐӔC�͈⑰���ɂ���̂ŁA�J�ДF��̃n�[�h���͂ƂĂ������B�s���ȕ]��������邭�炢�Ȃ�A�Ƌ����Q���肵�Ă��܂��l�����l�����ė��܂����v
�����������ŁA�u��o���v�Ő��������������܂肳��̕�E�K������ɑ��A��������́u�����������Ď�ނŘb����悤�ɂȂ�ɂ͉��N��������܂����B��ςȗE�C���������Ǝv���܂��v�Ǝ^����B
��������́u�d�ʂł�1991�N�ɂ��ߘJ���E���N���Ă��邾���ɍ߂��d���B�⑰�ɎӍ߂Ɛ��ӂ���Ή������Ăق����B�d�ʂ����łȂ��A���{�S�̂��������ւ̈ӎ���ς���K�v������܂��v�Ƙb���Ă����B -
�O���l�ό��q�����̂����ɑ�ʂ̂킳�т������Ă����A������u�킳�уe�������v�̗]�g�������Ă���B�؍��l�̃e���r�v���f���[�T�[�̈�s���A���ƂȂ��������`�F�[���̕����̓X�܂�ˑR�K��B�X���̗l�q���Ńl�b�g�����p���Ȃ���A�����ɂ��ČJ��Ԃ��Ӎ߂�v�������B
�@�������ɂ��������������ɂ́A�؍������ł��u���̎��i�������ĎӍߗv�������Ă���̂��v�ȂǂƔᔻ���鐺���オ���Ă���B
�����������▯���Ζ��o���̂���e���r�v���f���[�T�[���ˑR...
�@����̃l�b�g�ԑg�œX�܂���̐����p�����s�����̂́A�e���r�v���f���[�T�[�̗��i�ցi�C�E�����h���j���B����������KBS�▯����SBS�ɋΖ������o�������B������s��2016�N10��11���ɁA�������N�������u�s�ꂸ���v��g�X��K��B�X�̔O�́A�ˑR�̎B�e��
�@�@�u���̂��q����f�邩��I������l�����邩��v
�@�@�u���̂˂��A����������ނȂ�g���𖾂����ė���ł��ׂ��ł����āA�H�����ɂ����̂���ނɗ����̂��������傭���ɂȂ��Ă���B�s�����ł���v
�ȂǂƍR�c�������A�������͎B�e�s�B�o���ꂽ�����́A�M�̏�́u�K���v�̉��ɂ킳�т��������Ԃ��������A�����̓V��������l�^���͂����āu���є����v���Ƃ������Ƃ��m�F����ƁA�ׂ̓��{�l�Ǝv����q�ɒʖ����āu�����͂킳�т͓����Ă��Ȃ����A�ǂ��v�����v�ȂǂƘb�������Ȃ���A�O��
�@�@�u�Ȃ��؍��l�ɑ��Ă킳�є����Ŏ��i�����̂��v
�@�@�u�O�̂��Ɓi�u�킳�уe���v�����j�Ɋւ��Ċ؍��l�Ɏӂ����͂Ȃ��̂��v
�Ƌl�ߊ�����B�O�́A
�@�@�u�����̉�Ђ̕��j�₩��v
�@�@�u�l��͕�����܂���v
�Ɖ�����ɂƂǂ߂��B��s�͏o���ꂽ�����ɂقƂ�ǎ�����Ȃ��܂ܓ�g�X����ɂ��A�����Ƃ͊W�Ȃ��u�s�ꂸ���v�̕ʂ̓X�܂Ɉړ��B���̓X�̔O��
�@�@�u����i�����j�͌������̓X�B��������Ȃ���H�v
�@�@�u����Ɏ�ނ���Ă�...�B�����̎������ɗ����Ƃ��Ă����Ȃ���...�v
�ƍ��f���Ȃ�����A
�@�@�u���̈ꌏ�������Ă���́A�킳�т��āA�ォ����Ă��炤�悤�ɂȂ��Ă���v
�@�@�u�؍��̕��́A�قƂ�ǂ̕����w�킳�т����������x�Ƃ��������v
�ȂǂƁu���є����v�̗��R����������B
�u�ӂ�̈ꌾ�����肢���Ă������ł����v
�@����ł�������
�@�@�u�i�킳�т��j������x�����̂����R�B�R����œ���Ă����͓̂{����Ăv
�@�@�u�ӂ�̈ꌾ�����肢���Ă������ł����v
�ȂǂƃJ�����̑O�ł̎Ӎ߂�v�����A�O��
�@�@�u����̌��Ɋւ��ẮA����Ȃ��Đ\����Ȃ������Ǝv���Ă��܂��v
�Ɠ����������B
�@��A�̏o�����͊؍����f�B�A�ł���ꂽ���A�ނ��뗛���̍s�����^�⎋���鐺���������Ă���B�Ⴆ��YTN�e���r�́A
�@�@�u�l�b�g���p�҂́A�O��̖��ɂȂ����w�����ł킳�т����S�ɔ����Ă����x�Ƃ����c�_�ɂ��ĉ𖾂��ꂽ�Ƃ���܂ł͗ǂ��������A�������{������ŎӍߗv������̂͗ǂ��Ȃ��A�Ƃ��������o�Ă���v
�ƕĂ���B���̒��ɂ́A
�@�@�u���̃f�B���N�^�[�͉��̎��i�������āA���̎Ӎ߂�v�����Ă���̂��낤���v
�Ƃ�������������Ƃ����B
�؍��l������💢 -
�u��҂̕n���v�ɑ�l�͂��܂�ɖ�����������
���m�o�σI�����C�� 10��17�� 6��0���bYahoo!�j���[�X
Twitter
Facebook
LINE
��҂����������Ă��u����ǂ��v�́A��l�����ɂ���āu����ꂽ�v���̂������H�i�ʐ^�FAH86 / PIXTA�j
���������Ҏx�����s���\�[�V�������[�J�[�ł���M�҂́A��҂����̎x���������s���Ă���ƁA���܂��Č����邱�Ƃ�����B�u�ǂ����Ă܂��Ⴂ�̂ɓ����Ȃ��̂��H�v�u�Ȃ����̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��̂��H�v�u�ӂ��Ă��邾���ł͂Ȃ��̂��H�v�u�x�����s�����ƂŁA�{�l�̊Â����������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����H�v�Ȃǂł���B
�v����ɁA"��҂ւ̎x���͖{���ɕK�v�Ȃ̂��H�@"�Ƃ����^�O���B����͎�҂����̒u����Ă��錻��̌��������A���܂��ɑ����̐l�X�̊Ԃŋ��L����Ă��Ȃ����Ƃ�[�I�ɕ\���Ă���B����̘A�ڂ�ʂ��āA�u��҂Ȃ���A�w�͂���Ε����v�Ƃ����咣�ȂǁA�i���Z���X�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��������B
�����͂�ʗp���Ȃ��J�����\��
�@��҂͓����Ύ����ł���A������������܂Ƃ��Ȑ������ł���Ƃ����_�b(�J�����\��)�����������݂��Ă���B��������Ɍ��������������A���̒����ɂ���Ă܂��Ƃ��Ȑ������c�߂�Ƃ������̂��B
�@�����邽�߂ɁA��҂͂ǂ̂悤�ȐE��ɓ��邩�A�ǂ̂悤�ȃL�����A��ςނ��ŔY�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A���肵���d���ɏA���悤�ɗv������Љ�I�Ȉ��͂ɂ��Y�܂����B���̂��߁A�A�E�����Ől�C������̂́A��͂�ꕔ����Ƃł���A�������u�]�̊w���������Ă���B
�@���������R�Ȃ���A����Ƃ֓��Ђł�����A�������ɂȂ��l���͂��Ƃ��ƌ��܂��Ă���B���ׂĂ̐l���܂Ƃ��Ȓ�������E�Ƃ��m�ۂ��邱�Ƃ��A�����ł͕s�\�ł���B
�@�����A�����Ă��܂Ƃ��Ȓ�����������ۏ��Ȃ��E��������Ă���B�����āA���̎d���͂����Ă��K�ٗp�ŁA�I�g�ٗp�ł͂Ȃ����߁A�s����ȏA�J�`�Ԃ��Ƃ��Ă���B�ܗ^�╟���������Ȃ��E��������A����������Ƃ����āA�������L���ɂȂ�Ȃ����Ƃ����݂̘J���s��ŋN�����Ă���̂��B������u���[�L���O�v�A���v�����ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B�����Ă��n������������Ă��܂��̂ł���B
�@����͉����{�l����w���ł�������A�R�~���j�P�[�V�����\�͂��Ⴂ�Ƃ������ƂɗR�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B��w�𑲋Ƃ��Ă��A���ʂɓ����Đ��v���ێ����邱�Ƃ��}���ɍ���ɂȂ��Ă���̂��B
�d���͑I�Ȃ��������ł�����H
�@�J���Љ�w�҂̖؉����j���́A�����̎�҂̌ٗp�ɂ��āA�u�o�ϊE�E��Ƃ́A�����̎�҂���{�^�V�X�e������r�����邱�ƁA�܂�A��҂��]���ɂ��Ȃ���A���{�^�V�X�e�����������悤�Ƃ����̂ł��v(�w��҂̋t�P�@���[�L���O�v�A���烆�j�I���ցx�{���)�Əq�ׂĂ���B�܂�A�o�ϊE���Ƃ́A�Ӑ}�I�Ɏ�҂̌ٗp������Ă����o�܂����邱�Ƃ�I�m�Ɏw�E���Ă���̂��B��҂����������Ă��u����ǂ��v�́A�J���Љ�w�҂��w�E����悤�ɁA��l�����ɂ����"����ꂽ"�̂ł���B
�@�u���b�N��Ƃ̑䓪����҂̍���ɔ��Ԃ�������B���ʂɓ����������A���ʂɓ������Ƃ������Ă��炦���A�Z���ԂŎg���̂Ăɂ���Ă��܂��B����ɂ���āA���a��_�����ǂ��Ă��܂��A�����Ȃ���Ԃɒǂ�����邱�Ƃ��������Ȃ��B������A�u�����Ή��Ƃ��Ȃ�v�Ƃ����u�J�����\���v�͂��͂�ʗp���Ȃ��B
�����Ƃ��s�������悪�u���b�N��Ƃł��c
�@�܂����̘J�����\����_����l�X�́A�J�����Ă��Ȃ���҂�A�J����]�܂Ȃ���҂�ӑĂ��ƌ��Ȃ��X��������B���̂��߁A�ł��邾�������J������悤�ɁA�Ȃ��u�d���͑I�Ȃ���Ή��ł�����v�ƁA�J���Ɏ�҂���藧�Ă�B���Ƃ��A��藧�Ă�ꂽ��҂��s�������悪�u���b�N��Ƃł������Ƃ��Ă����\�B
�@��҂̈ꕔ�́A�]�܂Ȃ��K�ٗp��u���b�N��Ƃɒ��N�A�g�𓊂����g����A�u���ǂ͕���Ȃ��J���������v�Ƃ��łɑ̊����Ă�����A����������Ȃ肽���Ȃ��Ǝv���Ă���ꍇ�������B�����炱���A�������I�т����̂ł���B����͂��������ł����ł��Ȃ�������O�̗v�����낤�B���S���ē������Ƃ��ł��Ȃ��ٗp�����������Ă��钆�ŁA�J���ɑ���C���Z���e�B�u���N���Ă��Ȃ���҂������o�Ă���̂����R�ł���B�����āA�ނ�ɋ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����A���ł��������炷���Ɏd���ɔ�т����Ƃ́A�ɗ͂��Ȃ��łق����B
�@�ȘJ�����ł��l���W�܂��Ă��邱�Ƃ��킩��A���̘J���҂̏����͂��܂ł��ǂ��Ȃ�Ȃ��B���S���Ď��Ƃ���������Љ�ɂ́A�ȘJ�����������܂Ŋg�U���邱�Ƃ͂Ȃ��B���������Љ�ۏႪ�[�����Ă��鑼�̐�i���ł́A�����Ɉˑ����Ȃ��Ă��A������x��炵�Ă����邽�߁A�ߍ��ȘJ���ɂ͂���Ȃ�̑Ή����x�����邵�A�Ђǂ���Ƃ���������Ă����B�Љ�ۏ��Љ�����x��Ă��邩�炱���A���Ƃ����Ƃ��ɍ��邵�A���}�ɘJ����J���s���藧�Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���Ƃ��A�u���b�N��Ƃ����߂����A�����Ɏd�������Ȃ��Ɛ����ɍ����Ă��܂��̂ŁA�}���ōďA�E�������ʂ̊�Ƃ��A�܂��u���b�N��Ƃł������Ƃ����b�͂�����ł�����B��������Ǝd����I�сA���������ė]�T�������ďA�E�����Ăق������A���̊������������Ă����������̂ł���B
�@�����āA�J���s��̗́A��҂̘J���ӗ~��D���Ă����B�ǂ̂悤�ɓ����Ă����ׂ�����Y�݁A���i�����������l�X�A���Ȍ[���Ɋւ��鏑�Ђ�ǂ݂�����l�X�Ȃǂ��悭��������B�{���I�ɂ́A���̘J���s��̍\����ς����ɁA�ނ�̋�Y�͏����Ȃ��̂ɂ�������炸�A�ł���B
�@�܂��A���Ƃ������Ȃ��Ƃ��A��҂����ɂ͕����c���ꂪ����̂ŁA�������J�l�ɍ������Ƃ��Ă��A�Ƒ�����������L�ׂĂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�b(�Ƒ��}�{��)������B
���������̐��������Ő���t�Łc
�@�������A�������Ă̂悤�ɁA�Ƒ��͎�҂��~���Ȃ��B�Ƒ��̐��ш����k�����A���ݕ}���@�\�͑O�Ⴊ�Ȃ����x���܂Ŏ�܂��Ă��邩�炾�B���єN���������X���ɂ���A��҂̐e�����c���ꐢ��́A���������̐��������Ő���t�ł��낤�B
���Ƒ��ւ̈ˑ����A���͂⍢���
�@�킽���͐����ɍ������Ă��܂�����҂����̑��k���āA�N�ԉ��\���������ی�\���ɓ��s����BNPO�@�l�S�̂Ƃ��ẮA�Ȃ�ƔN��300����(�I�@)�ł���B�\���ɍs���ƁA�����������E���͕K���A�u�����Ƒ��͂��܂��H�v�ƕ����B
�@�������A�Ƒ����}�{�ł�������ɂ́A�c�O�Ȃ���ꌏ���o����Ă��Ȃ��B��҂������ɍ������Ă����Ƃ��Ă��A�Ƒ��͗���Ȃ��̂��B���������Ƒ��𗊂��W�ɂ���̂Ȃ�ANPO������ɂ͑��k���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@���w������đ�w�ɐi�w����w���̑������A�Ƒ��ɂ��w��S��d���肪�\���Ɋ��҂ł��Ȃ��ɂ���B�Ƒ����݂ɕ}�����\�Ȑ��т́A�����������̓��{�ɂǂꂭ�炢�c���Ă���̂��낤���ƒQ��������Ȃ��B�ٗp�̕s���艻������A�N���̌����A�����̍����ȂǂŎ������g�̐��v���ێ����邱�Ƃ�����Ƃ��Ƃ������т���ʓI�ł���悤�Ɏv���B
�@�܂��A�߂������Ƃ����A�Ƒ����̂�����̎q�ǂ����A���̑ΏۂƂ��鎖�������B
�@���N�A�����s�҂��Ă�����A�\���ȗ{��⋳����Ƒ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ�������҂̑��݂��B�Ƒ��̑��ݎ��̂����������̂ł͂Ȃ��A��Җ{�l�ɑ��āA�Q����^���鑶�݂Ƃ��ċ@�\����ꍇ������Ƃ������Ƃ��B�Љ�I�ɂ�"�Őe"�Ȃǂƕ]����_�������邭�炢�ł���B
�@�Ƒ������Ă����҂����@�\�������ł��Ȃ��B���邢�͉Ƒ��W���̂ɃX�g���X���₷���A������x�������߂邱�Ƃɂ���āA��肪�������邱�Ƃ�����B���Ƃ��A���_������L�����҂����ƂŐ������Ă���ꍇ�A�����ɑ��闝�����s�\���ȗ��e���A�A�J��������ɑ������Ƃɂ���āA�ߑ�ȃX�g���X����Ƃ��������k����͌��₽�Ȃ��B
�@�ނ�ɂ́A�u�Ƒ��̎x���������Ǝ��邩����v����v�ȂǂƂ͌����Ă������Ȃ��B���̂悤�ȉƑ��ƕʋ����ĕ�炵�������A���v���ێ��ł��Ȃ�����A���R�ȕ�炵��j�Q����Ă���B����ɑ��Ăǂ�������悢���Ƒ��k����B���Ȃ킿�A�u���Ƃ���o���Ȃ���ҁv�̔Y�݂ł���B
�@������ɂ��Ă��A��҂�������芪����������ۂɂ́A�Ƒ��ւ̈ˑ��͍���ɂȂ��Ă���Ƒz�肵�Ă����K�v�����邾�낤�B�����20�������l�ɑ��āA�Ƒ����ǂ��܂Ŗʓ|������ׂ��Ȃ̂��A�ɂ��Ă��c�_��i�߂�K�v������B���O���ł͓��R�ł��邪�A���l�����ꍇ�A���̂Ȃ���̂���ғ��m�ł��A���{�قǕ}�{�����邱�Ƃ͂Ȃ��B��ɕv�w�Ԃ▢���N�̎q�ǂ��ɑ���}�{�`�����炢�ŁA���l��͐�����A�J�𐭕{��Љ�V�X�e�����ۏႵ�Ă����B�u��������Ƒ��𗊂�v�Ƃ������Ƃ�������O�̎Љ�łȂ��Ȃ邱�Ƃ������Ă��������Ƃ��v���B
�@�܂�A��������Ƒ��������Ă������Ƃ����_���́A��������ƎЉ����Љ�ۏ�̋@�\���Ƒ��Ɋە��������邱�ƂɂȂ����Ă��܂��B����ł͉Ƒ������|��̏��������˂��A����ɎЉ����Љ�ۏ�̔��W���W����B���������_�ɂ����āA�Ƒ��}�{���͊댯�ȑO�ߑ�̎v�z�ł���ƌ����邾�낤�B -
�o�ϓI�ɑ�ρA���M���Ȃ��c�q��������Ȃ����R�̖{��
2016�N10��13��
�@�����J���Ȃ̍���������b�����ɂ��ƁA�v�w�݂̂̐��т́A1986�N����2015�N�܂ł�30�N��2�{�ȏ�ɑ��������B������w���w�������Łw�Ƒ���x�i�������Ɂj�̒����Œm����R�c���O����́A���̗��R���������͂���B
�u�̂ɔ�ׂČ�p�������邱�Ƃւ̈��͂���܂������Ƃ�����ɂ������܂��B����ɉ����A���{�̏�����ߊς��Ďq�����Y�݂����Ȃ��ƁA�T����l�������Ă��܂��ˁB�܂��A�o�ϓI�ȗ��R�⎩�R�Ȏ��Ԃ����ꂽ���Ȃ��Ƃ����j���ɁA�Ȃ��]�킴��Ȃ��P�[�X���悭�����܂��v
�@�����Z�u�����s�����A���P�[�g�����i��20�ォ��80��̒j��594����ΏۂɎ��{�j�ł��A�u�q�����~�����A�~���������ł����H�v�Ƃ��������18.5�����g�q���͗~�����Ȃ��h�Ɠ������B�u�e�ɂȂ鎩�M���Ȃ��v�i57.5���j�A�u�q�����D���ł͂Ȃ��v�i43.8���j�A�u�o�ϓI�ɕs���v�i37���j�Ƃ����̂���ȗ��R���B
�@����ŁA�~�����Ă�������Ȃ������v�w������B���߂������́A�u40�˂��߂��āA�N��I�Ɍ������Ɗ��������i67���j�v�����������A�����������ӌ�������B
�u�v�Ǝ�◷�s�i���邤���ɁA���̐������������炵�����������Ɗ������B�q����������Ɛ����̃��Y��������邵�A���낢��Ɖ䖝���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���̂܂܂������Ǝv�����v�i38�ˁE��Ǝ�w�j
�@���ԂƂ�����v�w�⎩���̂��߂Ɏg�������ƁA�����āg�q�Â���h����߂�l��A�u�q�������邽�߂Ɍ��������̂ł͂Ȃ��v�ƕv�Ɍ����A�z�b�Ƃ��ĕs�D���Â���߂��P�[�X���B����g�������q�Â���h�ł͂Ȃ�����Ȃ̂��B
�@81.5�����́u�q�����~�����A�~���������v�Ɠ������l�̒��ɂ��A�����������Ă݂�ƁA�u�o�ϓI�ɑ�ρv�u�����̎��Ԃ��Ȃ��Ȃ����v�u�d�������߂���Ȃ������v�u�}�}�F�Ƃ̐l�ԊW����Ɂv�Ƃ������A�q������䂦�̋�J���̂��������B
�@����ɑ��A�����ّ�w�Y�ƎЉ�w�������Łw�����ƉƑ��̂��ꂩ��x�i�����АV���j�����̓���~�炳��͂����b���B
�u�d���ƈ玙�̗����x�����x���������肵�Ă���m���E�F�[�ł́A�q�����������̍K���x�����������̂ɑ��A�A�����J�Ɠ��{�͒Ⴂ�Ƃ����f�[�^������܂��B�w�q�����Y�ނƎd���Ƃ̗�������ρ��q�����Y�ނƕs�K�ɂȂ�x�Ƃ����T�O�����{�̏����ɂ͋������߁A�o�Y�ɂ�鐶�������x���������ł��B���Ɏd�������߂��Ƃ��Ă��A���x�͉Ƃ̒��ɕ������肪���ɂȂ�̂ŁA�O���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������Ƃ�Ȃ��Ȃ��ăX�g���X�����܂�B�����������Ƃ��\�z����邩��q�����Y�݂�����Ȃ��Ƃ������܂��v
�@�����́A�q���Ƃ��������ɂ������ɁA�Ǝ��E�玙�E�d���E�v�̐��b�A�����ĉ��̗����𔗂��A�����̎��Ԃ�������B����ɉƑ��������邱�ƂŌo�ϓI�ɂ��N�����邽�߁A�K�������K���ɂȂ�Ȃ��̂��B -