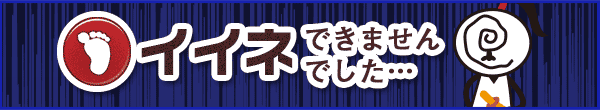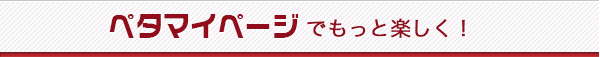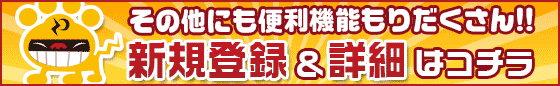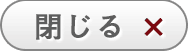カオス帝国〜リターンズ
-
スレッド一覧
- 雑談!! (241)
- たった一言!! (814)
- つぶやき!! (459)
- 生駒ちゃん (851)
- 画像!! (451)
- 芸能スレッド (1013)
- 名言!!!!!!!!!! (985)
- イマジン〜想像力育成講座〜 (256)
- 面白画像(≧▽≦) (884)
- MUSIC♪♪♪ (654)
- ヌコスレ(=^ェ^=) (688)
- 事件,事故!!( ; ゜Д゜) (471)
- 修造松岡!! (103)
- 俗にいうオカルト系(;゜∀゜) (299)
- (50)
- 豆知識 (677)
- つまるところこの人は美しい (307)
- 世 (112)
- JRA (1448)
- The パチ!!!!!!〜懐かしの〜 (457)
- 飲み食い市場(´・c_・`) (385)
- (140)
- サイエンス (202)
- 映画!!DVD!!ドラマ等々!! (157)
- AVタイトル‼ (26)
- 575m(__)m (245)
- 復活!いい話スレ(ToT) (37)
- (80)
- つまるところこの人は美しい 本編 (33)
- (654)
- フラグ成立!!(^_^)/~~ (39)
- 笑 (392)
-
20年ほど前から子供に「キラキラネーム」と呼ばれる読めない名前をつける親が増加した。「皇帝(かいざー)」「蒼流(そうる)」「今鹿(なうしか/注:男の子)」「士恵大(じぇだい)」「怜碧琉(れある)」「姫星(きてぃ)」「愛羅(てぃあら)」「音奏(めろでぃ)」「愛保(らぶほ)」などなど……キラキラネームは年々恐るべき進化を遂げている。
親にしてみれば「わが子にオンリーワンの名前を」という思いがあるのだろうが、当初から「学校でイジメられる」「名前を笑われて子供が傷つく」といったマイナスの影響が叫ばれていた。そして月日は流れ、現在はキラキラネームの第一世代、第二世代が大学生や社会人に成長。就職活動やビジネスにおいて、名前が深刻な弊害を生んでいると指摘されている。
都内にある大学の就職担当教員はこのように語る。
「キラキラネームは学生の性格によって就活の有利・不利に差が出る例もあります。子供のころから名前が原因で周囲に笑われたり、イジメに遭ったりしたために目立つことを避けるようになった結果、アピール下手になってしまったという学生も少なくない。一方で社交的に育った学生は『覚えてもらいやすい』といった理由で就活を有利にしているようですが、それは少数派のように感じられますね」
ネット上である医師が「子供が毎回、初対面の人に名前を笑われると心に深刻な傷を負う」と指摘したこともあり、場合によっては「小学生がキラキラネームのせいでうつ病になることもある」という。名前は人格形成に大きな影響を与える可能性があり、それが結果的に就活で不利に働いてしまうことも否定できないようだ。
また、都内の中小企業の人事担当者は「キラキラネームはできれば敬遠したい」と漏らす。どこかで「家庭環境に問題があるのでは」「親も子供も常識がないのでは」との疑念が湧いてしまうとのことだ。
もちろん、名前と家庭環境に因果関係があるのかどうかは担当者の思い込みにすぎない。だが、もし人気職種の狭き門を争っている時に担当者に余計な疑念を抱かせてしまったら、致命的なマイナス要素となりかねない。
何とか就活を成功させても、社会人になれば新たな試練が待ち受ける。今年1月に「俺もキラキラネームだが、人生は暗いぞ」などと題した投稿が、はてな匿名ダイアリーに寄せられてネット上で話題になった。
この男性は「想像してみろよ。取引先に名刺を渡した時の『あっ……』っていう空気を。さらに『キミくらいの歳で、もうこういう名前なんだねぇ』と言われるその場を。俺はなんて答えればいい?『親からもらった名前です!』って胸をはれると思うか?」などと悲痛な思いを綴っている。
受難続きの人生から逃れるために改名したといい、この男性は「すげえ安堵した。涙が出るほど嬉しかった。胸を張って自分の名前を言えるのがどんなに素晴らしいことか」と“普通の名前”の喜びを書き連ねている。
実際にキラキラネームを持つ人物に話を聞くことができた。「滝音」と書いて「たきおん」という名前を持つ30代の男性だ。
「僕の場合、名前でそこまで深刻に悩んだことはないし、不利益を被った記憶もないですね。初対面の人に毎回、名前の由来を説明するのが面倒だったり、病院や区役所など公共の場所でフルネームで呼ばれるのが恥ずかしいくらいです。妹も『美留季(みるき)』という名前ですが、普通に会社員をしていますし、兄妹みんな改名したいと思ったことはありません」
キラキラネームにネガティブなイメージがつきまとう一方、この男性のように普通の人生を歩んでいる人も少なくない。就活やビジネスも大事だが、人間にとって名前は長い人生を共にするもの。その人自身の生き方の問題であり、他人がとやかく言うべきではないのかもしれない。 -
子供たちの夏休みが始まった。夏休みといえば思い浮かべるのはラジオ体操、絵日記、アサガオの観察などなど。ところが、こういった風物詩と呼べるような光景も大きく変わりつつあるようだ。
教育面でいえば、ラジオ体操は夏の間の生活リズムを保ち、健康のためにも大切なものとされていた。ところが、福島県の小学校校長はこう明かす。
「いまはラジオ体操をやらない学校が増えている。地域によって子供の数が減っていて子供が集まらないという事情もありますが、親が夜勤の仕事などをしている家庭が増えたことも影響しています」
期間を7月中だけに短縮したり、「最終日に来てくれたら景品をあげる」という地域もあるようだ。
「公園でやると苦情が来るなど、場所とりも大変。正直、なくなってほっとしている」(神奈川県・40代女性保護者)
風物詩どころか、これでは“風前の灯火”である。
宿題の定番だった絵日記は、ほぼ姿を消している。旅行に行けない家庭があるなど、家庭環境に配慮した結果だという。
「うちの学校は絵日記を描かせるのは1〜4年生だけ。5〜6年生は代わりに読書感想文を書かせる。保護者に思い出づくりのプレッシャーをかけてはいけない」(京都府・小学校教諭)
1学期の終業式の日にアサガオの鉢植えを持ち帰り、毎日書き続けるアサガオの観察日記も、「いまは1週間に1回、学校に行って観察する」(千葉県・小学校教諭)というから驚きだ。
「家に鉢を置く場所がない家庭が増えている。近年の猛暑の影響で夏休み前に花が終わってしまうこともあり、夏休みの観察が難しくなっている」(同前)
昔は全教科の宿題が入った『夏休みの友』という冊子があり、「ずっとサボッていて、8月末に焦って全部をやろうとしたが、ダメだった」という人も少なくないのではないか。
「そんな冊子、いまはありませんよ。もともと、各教科の宿題が少しずつ幅広く入っている『夏休みの友』をこなしても学習効果が低かった。代わりに、漢字や算数のドリルなど各教科から宿題を出しています」(前出・福島県校長)
『夏休みの友』がなくなっても、始業式直前の「最後の追い込み」はなくなっていないようだ。「自由研究」は強制ではなく、児童の自主性に任せる。
「県や市などが主催する、科学観察などのコンクールを紹介し、興味を持った子だけがやる形式をとっています」(埼玉県・小学校教諭)
存在はしているものの、名前が変わったのが「プール開放日」である。
「いまは『プール指導日』です。以前、プール開放日に事故があったことから、開放して子供を遊ばせるのではなく、教師もプールの中に入って水泳の指導をしなければならない」(前出・福島県校長) -
年収1200万円から路上生活へ、介護離職で転落した男性
介護は高収入の人の生活をも一変させる可能性がある
貧困と介護が一つの家庭に重なった場合、その負担は想像を絶するものとなる。さらに、家族介護が貧困をもたらすこともある。高収入サラリーマンも例外ではない。
● 「介護心中のニュースは、あえて避ける」 介護離職から生活保護を経験した男性
前回は、2015年11月に埼玉県で起こった、高齢の両親と40代の娘の入水心中未遂事件について、「なぜ、一家は公的制度に助けを求められなかったのか? 」という側面から検証した。
この一家は、両親の介護・医療を含めて、「生き延びる」ために生活保護を必要とする状況にあり、しかも極めて差し迫った状況にあった。そのことは自治体も理解しており、迅速に対応した。ところが、生活保護の開始決定を迅速に行うために行われた調査が、皮肉にも心中の引き金となった。調査の4日後、遅くともその10日後には行われる保護開始を待たずして、一家は入水心中を実行。80代の母親・70代の父親が溺死した。死にきれなかった娘は逮捕され、2016年6月23日、懲役4年の実刑判決を受けた。
今回と次回は、「介護離職」と生活保護を経験した高野昭博さん(61歳)の、経験・思い・考えを紹介する予定だ。
高野さんは「介護離職」をきっかけとして、生活困窮状態に陥り、住まいを失い、路上生活者となった。その後、生活保護を経験し、現在は生活困窮者に対する相談業務で生計を立てている。週6日の勤務の様子を語る高野さんからは、「働かないと生きられないから働いている」という悲壮さは全く感じられない。相談業務は時に苦労も多いものだが、苦労について話しながらも、高野さんは「動いてないと、おかしくなっちゃう」と楽しそうである。自身については「根っから楽天的なんです」という。
まず、2015年11月の親子心中事件について、高野さんはどのような思いを抱いているだだろうか?
「正直なところ、『本人しか分からない』ことだと思います。実は、この事件の報道は、あまり読んでいないんです。『知っておくべきなのかもしれない』とは思うのですが、あえて、避けていました」(高野さん)
高野さんは、高校を卒業した後、流通大手に就職した。ステータスの象徴とされるその企業で、高野さんは販売に従事していたが、ほどなく企画など重要な職務を任されるようになった。高野さんの仕事ぶり・能力・実績は高く評価されており、昇進も順調だった。30歳で主任・33歳で係長・38歳で課長。その企業の平均的な大卒よりはやや遅い年齢ではあるが、高卒で入社した人が30代で課長になるということは、業種を問わず、大手企業では驚嘆されるべきことである。評価は報酬にも反映され、年収は最大で1200万円に達していた。しかし2000年、45歳のとき、高野さんは介護のための退職を余儀なくされることとなった。
高野さんは、どのように「介護離職」することになったのだろうか?
● 退職か? 過労死か? 介護との両立がありえない「企業戦士」生活
高野さんは1955年、東京で生まれ、8歳の時、家族とともに埼玉県に転居し、就職後も両親とともに埼玉県で生活していた。介護は「するつもりでいた」という。
職場で知り合った女性と、結婚を前提に付き合っていた時期もある。互いに裏も表も見て、「この人なら大丈夫」と確信していた。しかし、結婚には至らなかった。
「結婚したら、両親と別居することになります。当時は両親とも元気だったんですが、『老後、どうなってしまうんだろう? 』と考えました。まだ介護保険はなく、住んでいた地域には、高齢者の介護に関する制度が特にありませんでしたから」(高野さん)
結婚すれば、両親も、親しい関係の誰もかも、「嫁が介護を」と期待するだろう。
「両親は口には出しませんでしたが、『結婚したら、息子の妻が自分たちを介護するんだろう』という雰囲気でした。それもあって、結婚を断念しました」(高野さん)
そして、両親の介護は現実の問題となった。
「課長になって間もなかった38歳か39歳のとき、母親の介護が必要になってきたんです。もともと身体が弱くて、寝たり起きたりだったのですが、起きていられないことが増え、自分でできないことが増えてきた感じでした。でも、まだ認知症はなくて、頭はしっかりしていました」(高野さん)
介護保険制度は、まだ存在していなかった。既に退職していた父親と高野さんが、母親の介護を担うことになった。会社は、最初のころは「大変だね」と理解を示していたものの、長時間残業が難しい高野さんに対する職場の目は、徐々に冷たいものへと変わっていった。冷ややかな視線や態度を示され、「あなたの代わりはいくらでもいる」と言われ、さらに職場に自分の席がない状況になったという。
母親の介護が必要になる以前、高野さんの生活は、どのようなものだったのだろうか?
「管理職になると、8時より前に職場に入り、23時か24時に職場を出る生活でした。家に帰ったら、寝るだけでした」(高野さん)
計算してみると、1年あたりの労働時間は、約4000時間になる。休日や勤務時間が定まっている場合の過労死危険ラインは年間2880時間、変則勤務の場合は年間2400時間だ。オフィスと販売現場の両方にいた高野さんは、変則勤務と見るべきだろう。
「過労死、多かったですよ。食事中に倒れてそのまま死んだ同僚もいました。通勤の帰りがけ、ふらついていてホームから転落して電車に轢かれて死んだ人も、交通事故に遭って死んだ人も。もともと血圧が高かった人がストレスの高い仕事のために外出して、任務遂行直後に倒れて亡くなったこともあります」(高野さん)
ドリンク剤の「24時間戦えますか」というCMソングが流行していた時期、まさに「24時間戦っている」に近い状況にある企業戦士たちが実在していたわけである。
「精神的に追いつめられて、うつ状態になる人も多かったです。厳しい状況でした」(高野さん)
高野さん自身は?
「ストレスが溜まっていたとき、追いつめられた気持ちになり、オフィスで書類をぶん投げたことはありました。でも、私は開き直るのが速いんです。楽天的な性格が幸いしたのかもしれません」(高野さん)
● 公的介護支援もなく、職場の理解もなく 「介護離職」へ
出産・育児は、自分の意志で「やらない」という選択をすることも可能である。しかし親の介護は、実際にやるかやらないかは別として、存命の親がいれば必ず持ち上がる問題である。「育児・介護休業法」が成立し、介護のための有給休暇が一応は制度化されたのは、1995年であったが、雇用主の努力規定であった。義務化されたのは2010年(従業員100人以下の事業所に対しては2012年)であるが、何度かの大改正を経た現在も、事業主に対する罰則はない。被雇用者の苦情・あるいは紛争に発展した場合の調停等の仕組みが設けられ、勧告に従わなかった事業主に対する「これが処罰? 」と首を傾げたくなるほど軽い制裁措置が盛り込まれているだけだ。
高野さんが39歳で母親の介護に直面した1994年は、バブル崩壊直後。新卒の就職が「氷河期」と呼ばれ始めた時期でもある。もちろん、既に正社員としてキャリアを積んでいた社員に対しても、バブル崩壊の影響は大きなものだった。高野さんの当時の勤務先の企業体力を活かせば、バブル期なら「これを機会に、社として介護支援を充実させて、優秀な人材を採用しやすく」という配慮ができたかもしれない。しかし、安定経営が困難になっていた時期には、文字通り「無い袖は振れない」だっただろう。
それでも、ある程度は父親が母親の介護に当たれていた時期の高野さんは、自身も母親の介護を担いつつ、ギリギリの職業生活を、ギリギリの時間のやりくりとともに継続できていた。
「でも、介護と仕事の両立は、がんで父親が入院してから難しくなりました」(高野さん)
1999年5月、進行がんが発見された父親は東京の病院に入院し、8月に手術した。手術後も容体は良好でなく、同じ病院での療養生活が続いた。転院先が見つからなかったからである。
高野さんの勤務中、埼玉県の住まいでは、認知症の症状の現れていた母親が、一人で時間を過ごしていた。
「訪問販売に引っかかって、いろいろと高価なものを買ってしまい、クーリングオフもできず支払ったりしたこともあります。徘徊もありました。行方不明になって捜索願を出したこともあります。近所の方から『施設の方が良いのでは? 』というアドバイスもありましたが、母親が『ここから離れたくない』というので」(高野さん)
借家ではあったが、約40年にわたって暮らし続けていた「我が家」であった。
住まいにいる母親の介護、病院にいる父親への対応をしながらの職業生活に、高野さんが限界を感じていたころ、勤務先では早期退職者の募集が始まった。
「人件費削減のため、1万人を超えていた社員を2000人減らすことになり、早期退職者の募集が始まったんです。退職金の上積みもあったので、退職することにしました」(高野さん)
退職金は1200万円。
「『減らさずに働いていたら、なんとかなるだろう』と思いました。楽観的過ぎました。『世の中甘くない』と後で気づきました」(高野さん)
● 日々の介護に経済状況の悪化 ついに住宅喪失、そして路上生活へ
退職の翌月、父親は他界した。間もなく、母親は脳梗塞で倒れ、寝たきりになった。
「介護と両立できる仕事を探していました。でも、そうすると仕事の選択肢がないんです。なので、とりあえず、定時の仕事に入ることにしました」(高野さん)
2000年2月、高野さんはスポーツ店に再就職した。高野さんは、もともとスキーの指導員資格を持つスポーツマンで、スポーツの知識やスポーツ用品業界との人脈が豊富だった。流通大手に在職中は、スポーツ店の海外スキーツアーに同行したこともある。そういったことも評価されての再就職だった。年収は500万円。担当業務は、スキーウェアの仕入れだった。
「年齢的には、そこそこか、ちょっと良いか、というところでしょう。社長が介護に理解を示し、私は早めに帰れるように配慮されていました。助かりました」
「ほぼ定時の仕事でした。終わったら速攻で家に帰り、母親に食べさせて着替えさせて、でした。一番大変なのは入浴でしたね。自分は抵抗なかったですけど、母親は大いに抵抗あったようです」(高野さん)
しかし5年後、不況に襲われた会社は、人員削減をせざるを得なくなった。
「高年齢者から退職させられたわけですが、私は最後まで残してもらえました。前職の経験と蓄積があって、その会社でもずっと、スキーウェアの仕入れをしていたわけですが、若い人から見ると『なんであの人だけ残っているの』となるわけです。それで、辞めました」(高野さん)
その後も高野さんは、とにもかくにも「働く」を手放さなかった。年齢とともに厳しくなる求職状況の中、アルバイトなど不安定な雇用や、200万円以下までの年収激減も厭わず、高野さんは「働きながらの介護」を続けた。
「働くことは、ずっと続けていました。動いてないと、おかしくなっちゃうんです」(高野さん)
2008年、母親が86歳で亡くなった時、高野さんの経済状況は「どん底」(高野さん談)。約100万円の質素な葬式は辛うじて営めたが、納骨は費用が足りないためできなかった。
借家の家賃も払えなくなったことから住居を喪失した高野さんは、母親の遺骨と、母親とともに愛した茶トラのオス猫を抱いて、公園で生活する路上生活者となった。
次回は、高野さんが路上生活を脱却し、生活保護で暮らし始め、就労自立へと戻っていく過程を、高野さん自身の老後の見通しとともに紹介する予定である。
「ゼイタクではないけれど、心楽しく、不安少なく生きていける老後」が、もしも生活保護によらず実現できるのであれば、何によって実現できるのだろうか?
-
朝日新聞(7月10日付)の投書欄に寄せられたベトナムの留学生の投稿「日本人の幸福って何なの?」が話題だ。日本人の疲れた顔やあまり笑わない姿を見て、「経済的な豊かさは幸福につながるとは限らない」と感じたという内容が、ネット上でも注目を集め、議論となっているのだ。
【もっと大きな画像や図表を見る】
注目されたきっかけは、あるTwitterユーザーがこの記事を写した画像を添付し、「日本人は何のために頑張っているのだろう(哲学)」とツイートしたこと。この投稿は瞬く間に拡散し、同ツイートのリツイート数は13日時点で4万7000を突破。その数字から、いかにこの記事が衝撃的だったかがうかがえる。
記事によると、この留学生は来日当初まで、「日本は立派な偉大な国」であると思い、その発展ぶりや豊かさを見て、故郷であるベトナムとの間に大きな差を感じていた。そのため、当然のように「日本人は幸せだと感じている」と思っていた。だが、来日から10カ月後、そうではないと気づいたのだという。
彼女の目に映ったのは、電車内では睡眠不足で疲れ切った顔を見せ、それ以外のときでも、あまり笑わずに何かを心配している日本人。「日本人は何のために頑張っているのか。幸福とは何なのか。日本人自身で答えを探した方がいい」と締めくくられる。
Twitterでは、
「すっごいすっごい考えさせられる・・答えがないのだけれど」
「反論の言葉が何一つとして出てこない・・・」
「これ読むと、むなしくなってくるな。ほんのひと昔は笑いや、幸せあったのよ」
「最後の一文がとても深いね。いくらでも自由に生きる権利があるんだから、いい塩梅で少しだけでも手を抜けたら楽なんだろうなぁと思う」
と、的確な考察に衝撃を受けるユーザーの様子が伝わってくる。また、
「留学生の方が日本を解ってるよ、大丈夫かよ社畜のみんな、現実見てくれ」
「有給を取ろうものなら嫌な顔をされ、休日出勤だってある会社が多いだろうし。何のために生きてるんだろうね」
と、働く日本人の現状を憂いたり、日本特有の慣習に改めて疑問を投げかける声もあった
多くの日本人が共感した、ベトナム人留学生の投書。日本人それぞれが“心の豊かさ”を見つける必要があるのかもしれない。 -
面接官もびっくりする最近の人々
就職や転職活動では、何社も受けなくていけないので大変だが、採用担当者もいい人が見つかるまで何回も面接をしなければならず、色々思うところはあるようだ。
7月5日、女性向けコミュニティーサイト「ガールズちゃんねる」に「今まで印象に残っている方や、びっくりするような求職者の方っていらっしゃいましたか??」という内容のトピックが立ちがったので紹介する。
履歴書に手書きで顔文字「よろしくお願いしますm(_ _)m」
トピ主は現在転職活動中という女性。自身が求職中ということもあり、採用担当者が印象に残った求職者について知りたくなったようだ。
このトピックに300件以上のコメントが寄せられている。
「面接の際、この後予定があるので10分で終わらせて下さいと言われた。では帰って頂いて結構ですと3秒で終わらせてあげた」
「正社員の求人で、まずは書類審査だから履歴書送ってと言ったけど、すぐ面接してほしい、やる気は人一倍あります、とアピールしてきた。 いや、いや、最初のルールを守れない人は、入社してもルール守れないでしょ! 不採用にしました」
面接の時間を急げと言ったり、強すぎる熱意を伝えたりするのは採用担当者にとっては困りものだろう。筆者(編集部S)は過去に面接に携わったことがあり、求職者から「絶対に御社に入りたい。お願いします!」と繰り返し言われて対応に困った記憶がある。
履歴書関連でも、困った候補者はいるようだ。写真欄に「プリクラ貼ってきた馬鹿はいました」というケースのほか、
「履歴書と一緒に自分の取り扱い説明書を同封してきた人」
「写真が10年前くらいで別人」
「履歴書につけまつ毛がくっついてた」
といった話が出ていた。取扱説明書を送られた方もそんな候補者は面倒だと思うだけだろう。「よろしくお願いしますm(_ _)m」と手書きで顔文字を書いてきた人もいたという。
面接ドタキャンやすっぽかしは絶対にNG!
面接時の服装が気になることもあるようだ。バイトの面接ぐらいならジーンズも問題ないケースが多いが、「バリバリのロリータ衣装」というのは確かに困惑してしまう。
面接をすっぽかす求職者への不満も目立つ。
「面接のアポ取っておいて連絡もなくドタキャンする奴は以前はよくいたな。電話も出ない。こちらもその為に時間をとっているのだからふざけるなといいたい」
ヤフー知恵袋でも、連絡もなく面接に来ない求職者が困るという人がトピックを立てている。投稿者は「担当の人間はその面接の為に時間を空けて、その間来客のアポイントももちろん断ったり整理したり、当然ですがやっています」と不満を漏らす。会社側は面接の用意をしているのだから、行けなくなった場合は連絡を入れるのが当然だろう。
書き込みを見ると、面接の欠席の連絡を入れない、身だしなみや言葉遣いが悪いなど、仕事のスキルの前に相手を気遣った対応ができるかが重要であることを痛感した。面接で立派な志望動機を話すよりも、社会人としての最低限のマナーを見直すことが大切ではないだろうか。 -
写真8万人調査で見えた「幸せな人と不幸せな人」の決定的な違いとは
「幸せですか? それとも不幸せですか?」と聞かれたら、あなたはどう答えるだろうか。しらべぇ編集部では全国の男女88,321名を対象に調査し、「幸せな人の理由」について探ってみた。
■若者は男性より女性のほうが「幸せ」を感じている
すると、「自分は幸せなほうだ」と回答した割合は若い男女では女性が高いことが判明。20・30代では、それぞれ10ポイント以上も差がついたのだ。
男性だけに着目すると、年齢を重ねるにつれて「幸せだ」と感じる人が増えている。男女や年代での感じ方の違いもあるが、仕事の内容やその地位、職場環境による差も大きいだろう。
高度成長期やバルブ経済時代を過ごした世代と、それを知らない若者世代では、やはり結果は異なってくるのかもしれない。
■幸せな人も「収入」や「仕事」の満足度は高くない
幸せな人と不幸せな人の違いを「家族関係」や「収入」などの満足度の違いで比較したのが、次の結果だ。
それぞれの項目ごとの「非常に満足」「やや不満」などの回答を点数化し、満足度が高いとプラス、低いとマイナスの得点で表している。
すると、幸せな人は「家族関係」「趣味」などの満足度が高いという結果に。健康については、50代以上の人が平均値を下げてしまっているようだが、元気でいることを幸せを感じる人が比較的多いよう。
一方で、どの年代でも男女ともに「仕事」では満足度が低く、「収入」にいたってはマイナスである。その結果として、「将来の備え」も十分ではない様子がうかがえる。
不幸だと思っている人はすべての項目でマイナスであるが、幸せな人でも満足度が低かった「収入」や「将来の備え」については、より不満度が大きいことがわかる。
■幸せな人は「家族」「友人」との関係で満足度がより高い
幸せな人と不幸せな人を比較すると「収入」での差が大きいように見える。だが、その得点差を計算すると、じつは「家族関係」「友人関係」「仕事」などでの満足度の開きが大きいことがわかった。
これらは、自分の努力で改善できるかもしれない項目。幸せな人は、身近な「家族」「友人」「趣味」などで気持ちが満たされ、幸福度を高めているといえそうだ。 -
仕事をすれば少なからずストレスに晒されるものだが、中でもレジ打ちの仕事は多くの客と接する分、客の言葉や態度にイラッとすることもあるだろう。
7月3日、とある女性が「レジで地味に苛々するやつ」というタイトルでツイート。苛々させる客の行動をイラスト付きで説明し、約1万件リツイートされ、接客経験のある人から共感が集まっている。
「商品打ってるのにICカードかざして待ってる」「電話しながらレジ来る人もイラつく」
投稿者は小売店でレジのバイトをする女性で、地味に苛々する客として次の4つを挙げてツイートした。原文はイラストのため、様子について筆者が追記した。
1つめは「カードの上にお札を置く人」。カードはポイントカードのことだろうか。お札の下にあると取りにくい。2つめは、「子供を注意しない親」。店内で騒いだり、レジ台の上に載ったりする子供がいても、店員としては注意しにくい。親から注意してほしいものだ。
3つめが「イヤホン外さない奴」。耳を塞いでいたら会話が聞こえない。レジ袋が必要かなど質問しても聞き返されれば、イラッとするだろう。そして、4つめが「商品打ってるのにずっとカードをかざして待ってる」。レジ打ちの最中にSuicaなどの電子マネーをレジの読み取り機にかざして待たれると、急かされているようで気分はよくない。
このツイートに続々と共感の声が集まっている。
「元コンビニ店員ですが気持ちめっちゃわかります! イヤホンもですけど電話しながらレジ来る人も苛つきますよね…!」
「ICカードを読み取る機械は光ったらタッチしてくださいって言っても光る前にそこに置くお客さん、お?この人話聞けないのかな? ってなる」
「『会員カードありますか?』って聞いたら 『出しとんやけど』ってお札の下にカードがあるとき むっちゃ腹立ちますよね!!! こんなもん気付くかボケってなります(;ω;)w」
筆者(編集部S)は過去に飲食店でバイトをしたとき、電話をかけながらレジに来て、小銭を投げつけるように支払うお客さんが苦手だった記憶がある。急ぎの用事なのだろうが、店員としていい気はしないものだ。
レジで新札を要求する客に「ここは銀行じゃありません」
ネットでは、他にもレジで客にされて苛立ったことの書き込みが多く見られる。
「お金を投げるお客さんがいます。 神社かよ……と、つぶやいちゃったりします」
「商品をレジに通しているときにスマホをいじっていたり、連れとしゃべっていたり……そしていざお会計ってなったらバックをあさって財布捜し。いやー財布が必要ってわかってるんだからちゃんと準備してよ!!」
「お釣り5千円札の時に『新札ないの?人にあげるから綺麗なやつ欲しいんだけど』とか言ってくるババァいた。ここは銀行じゃありません」
そのほかにも、カゴへの商品の入れ方に注意してくる客、会計途中で商品を取りに行く客、レジで商品の袋詰めを要求する客など、困った客は結構いるようだ。
一方で、冒頭の投稿者の女性は自身のツイッターで、客の「神対応」も紹介している。クレジットカードの支払い回数を予め言ったり、レジ袋必要カードを店員が取りやすいように置いたり、店員に対して配慮ある対応をする客を快く思っているようだ。
あるネットユーザーは「会計後にお礼を言ってくれるとレジでの疲れとストレスが吹っ飛びます」と書いている。店員と客は本来上下関係はない。お互いに気持ちよく買い物ができるよう、ちょっとした気遣いをし合いたいものである。 -
かつて性風俗は借金や精神疾患など、何か「特別」な事情を抱えた一部の女性が稼ぐ最終手段の場であった。しかし現在は経済的に困窮した「普通」の女性が、生活費を確保するためにカラダを売っている。性風俗業界の動向から日本の格差と貧困を読み解く『図解 日本の性風俗』を著した中村淳彦氏の特別リポート。
*
カラダを売っても稼げない
「もう、風俗歴20年になるかな。10年くらい前までは稼げたけど、今は1日1本つけばいい方。持って帰れるお金は1万円にはならないわ」
鶯谷の熟女デリヘルで働く渡部美幸さん(仮名・50)はこう話した。埼玉県某市のベットタウンで夫と2人暮らし。ごく一般的な主婦だったという渡辺さんは、結婚11年目で夫が個人経営する喫茶店が廃業、住宅ローンが払えなくなった。諸々の事情から購入した一軒家を手放すことができず、首が回らなくなり悩んだ末に風俗で働くことにしたという。
風俗嬢として働き始めた最初の5年間は、月50万円以上は稼げたという。ところが1999年の風営法改正でその風向きが変わる。デリヘルが激増し、客が徐々に減ったのだ。風俗だけでは収入が足りず近所のスーパーマーケットでパートを始めた。今も週3日はデリヘル、他3日はスーパーで働いている。
*
この数年間、風俗業界は深刻な不況と、風俗嬢の収入の下落にあえいでいる。いまや風俗嬢の「超高収入でラクして稼いでいる、消費と遊び好きな女性」というイメージは、80〜90年代の全盛期を経て過去のものとなった。ブランド物で着飾った派手な風俗嬢はほんの一握り、大半はバーゲンやアウトレットで買った洋服を着て、格安居酒屋で割り勘で飲むという地味な生活を送っている。
その傾向は、風俗業界に大打撃を与えたリーマンショック以降から特に顕著で、現在の風俗嬢のほとんどは中小企業のサラリーマンと同レベルか、それ以下の賃金でカラダを売っている。カラダを売っても中小企業のサラリーマン以下の賃金とは夢も希望もない話だが、これが現実だ。
風俗の下落はなぜ起こったのか
風俗嬢のセカンドキャリアを応援する非営利法人「GrowAsPeople」やセックスワーカー自助団体「SWASH(Sex Work and Sexual Health)」などのアンケート調査によれば、風俗嬢の現在の平均賃金は月33万円〜38万円程度で、2000年ごろの月70万円程度といわれていた頃と比べると半減している。世間の世帯収入の下落を大きく上回り、風俗嬢たちの収入は激減しているのだ。
風俗嬢が稼げなくなった原因は、性風俗のデフレ化によるものだ。00年代から社会全体がデフレに悩まされているが、「女性のハダカ」の価格はその実質経済を上回る勢いで下がり続けている。デリヘルを中心に多くの風俗店が価格競争に巻き込まれ、サービスの単価を下げながら、集客も減らしている。社会と連動する形で、性風俗の世界でも格差が広がっているのだ。
性風俗のデフレ化の最大の要因は、従来であれば性風俗業とは無縁の一般の女性が続々とハダカになったこと、そしてデリヘルの激増によるものだ。
単身女性の3人に1人が相対的貧困に該当するという「女性の貧困」が深刻化したことで、一般女性の風俗志願者が増えた。さらに1999年の風営法でデリヘル(無店舗型)が実質合法化されたため、男性客が減り需要と供給のバランスが崩れたのだ。
それまでの店舗型性風俗は、違法か合法かわからないグレーゾーンの業種だったが、どんな業種でも合法化(規制緩和)されれば参入が増える。デリヘルも他に漏れず異業種参入が続き、現在警察への届出数は1万9000店舗超えた。
この数はセブン-イレブンの店舗数1万8572軒(平成28年2月現在)と同程度で明らかに供給過多といえる。限られた需要の中で店舗が増えれば、男性客が分散し稼動も下がる。その結果誰も稼げなくなってしまったのだ。
デフレが進んだ現在のデリヘルは、過半数以上が60分1万円以下という破格の価格帯で性的サービスを提供している。この価格帯は安すぎだ。そんな格安風俗店を支えるのは、若さでは勝負できない30歳以上の熟女たちである。
近年の人妻熟女の流行で風俗嬢の上限年齢はなくなったものの、労働者派遣法を代表とする格差に拍車をかける政策によって、現在、生活のために風俗を志願する一般の女性の増加が後を絶たない。風俗業界全体で需要と供給のバランスを完全に崩壊させたことで、単価は下落の一途を辿っている。
さらに、カラダを売っても貧困レベルの低賃金しか稼げないという女性も存在する。経済的な苦境に陥りハダカになった風俗嬢の中で、さらにその下層にいる稼げない女性たちの多くは40歳以上の熟女だ。
下層風俗嬢の多くは、未婚、バツイチ、シングルマザーなどの単身女性たちだ。彼女たちは自分の稼ぎで生活を支えなくてはならず、風俗店の増加による供給過多のため厳しい競争にさらされている。競争に負けた風俗嬢たちの収入は生活保護水準を下回り、「食べるのもやっと」といった危険な状態となっている。
ハダカの女性は社会を映す鏡
カラダを売って貧困レベルの低賃金しか稼げないという現実を信じられない読者のために、デフレの象徴である、激安デリヘルで働く女性を想定して収入を試算してみよう。
続々と競合店が増え続ける中、性的魅力が普通レベルの女性が働ける店は限られている。都市部デリヘルの値下げ競争の象徴とされている某老舗チェーンでは30分3900円、45分5900円という価格帯でサービスを提供しており、そのうち女性の取り分は2400円、3500円と異常なほどの低賃金だ。単価が安すぎるこの店には各種性風俗を断られた女性が集まってくる。
デリヘルはとにかく男性客が少なく、低価格の格安店でも女性1人あたりの客数は平均で3人、人気のある上位の女性でも多くて6人程度だ。3500円(1人あたりの単価)×3人で、日給は1万500円、週4日勤務でも16万8000円しか稼げない。東京都の最低賃金は900円なので、待機時間を含めれば、コンビニのアルバイト同等か、交通費なども入れればそれよりも低い賃金となる。
生活にお金のかかる東京で暮らすにはこの金額では最低限の生活もできないだろう。早朝に時給1000円程度の清掃のアルバイトをしてプラス月3万程度を確保し、なんとか凌いでいる女性もいるほどだ。
地方のピンクサロンも同様に厳しく、回転なしの30分5000円の店で時給は2000円、週4日勤務で日給1万2000円だ。雑費1000円と源泉徴収を引かれると、日給は9800円、月16日働いても15万6800円にしかならない。この収入は低賃金が社会問題となっている介護職と大して変わらない金額だ。
カラダを売ることは、性風俗が誕生した400年以上前から女性が稼ぐ最終手段であった。日本が貧しかった戦後や昭和期に風俗や売春を覚悟した女性たちの月収は大卒初任給の数倍と大きなリターンを受けていたが、90年代後半の新自由主義政策以降は一般女性の大量参入によって「簡単に価値が認められる」という大前提が崩れてしまった。
社会のマジョリティに属する一般女性が風俗や売春をする覚悟を決めても、貧困から逃れられない層を生む社会は異常としかいいようがない。多くの女性たちは月5〜6万円のお金が足りないがゆえに「ハダカの世界」に足を踏み入れている。これ以上「普通の女性」が風俗嬢にならないためには、最低賃金の上昇が不可欠だ。
現在と物価が変わらないことを前提として、その層の女性たちの収入が月5〜6万円アップすれば、おそらく風俗嬢志願者は激減する。時給に換算して最低賃金を約300円上げるだけで、カラダを売らなくても生活できる一般女性が大幅に増えるのだ。東京都では時給1200円、大阪は1150円、沖縄は1000円。しかしシングルマザーら常勤が難しい層を加味すれば、500円程度まで上げるのが妥当だろう。
格差が広がり女性の貧困が進むほど、風俗志願者が増え女性が生き延びるための最終手段が崩壊してゆく。格差社会の煽りを受けた女性たちが性風俗の世界に足を踏み入れても、立ちはだかる「貧困」からは逃れられないでいる。ハダカの女性は、今の日本の姿を映す鏡なのだ。 -
清原容疑者につづき、元俳優の高知東生容疑者も覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、テレビが再び覚せい剤のニュースで持ちきりです。
もし友人・家族が覚せい剤に手を染めたら、僕たちはどうすればいいんでしょう。
本日は、憧れだった人が覚せい剤に手を染めてしまったある男性の、体験記をご紹介します。
/////////////////////////////////////////////
コミュ症の僕は、女性不信を解消したくてメンズキャバクラの門を叩いた
20代前半、僕はコミュ症や女性不信を解消したくて六本木のメンズキャバクラの門を叩いていた。
ホストではないメンズキャバクラ。
ちょっとカジュアルな接客に料金体系がキャバクラスタイル、指名替えOK、場内指名有りと言う、日本で初めてのメンキャバで働いていた。
映画のプロモーションとコラボレーションしていたので、俳優志望が多かったというのもあり、ビジュアル的にイケてる人がそこそこいたし、六本木のきらびやかで今まで見たことがない世界に毎日が心躍っていた。
直前まで引きこもりをしていたし、女性とは過去に何人か付き合ってはいたけど、包丁沙汰(自分自身が元カレと浮気をしたショックで自分の首に刺そうとした女性がいた…)の恋愛で女性不信を引き起こしていたし、基本的に萎縮タイプのコミュ症なので、それらを解消するにはかなり毒をもって毒を制すような挑戦だった。
入って一ヶ月目、バックヤードで表に出たい新人がグラスをピカピカに磨いている。
もちろん僕も表に出たいけど出れないから磨いている。
先輩のゲロ掃除も僕達新人の仕事だったりもした。
そんなバックヤードの空気は表に出たいけど出れない憤りや、表に出られない理由が分からず不平不満が溜まりまくって暗く沈んだ表情をしているものだから、尚更表に出させてくれないという悪循環が続いていた。
その中で一人呼ばれ二人呼ばれ…僕だけ呼ばれないということも多々あった。
なので、何かを変えないといつまで経っても表に出れないし、顔を売ることも出来なければ指名も取ることも出来ない。
その店は、今考えるとダサいけど名札を付けることになっていて、ナンバーと源氏名が書いてあったので
「◯◯さん、おはようございます!」
「◇◇さん、お疲れ様です!!」
など、名前を呼んでから挨拶するというスタイルに切り替えた。
それからぽつりぽつりと呼んでくれるようになったし、場内指名もその挨拶が功を奏して頂けたりもした。
憧れだった一匹狼の竜先輩
そんなメンキャバ生活を半年ほど過ごしながら指名も徐々に取れ始めた頃、オープニングメンバーだったけど、途中でやめた竜先輩が出戻りしてきた。
このメンキャバは映画のプロモーションも兼ねていたので、ビジュアルがイケてる人は確かにいた。
でもカリスマ性やオーラがあるって思う人は誰もいなかった。
もしかしたら少しはオーラがあった人もいるのかもしれないけど、夜の欲、六本木の欲に負けて
役者で売れる<ホストが楽しい
になってしまう人も多かったと思う。
役者の夢を叶えるために人脈を広げよう、生活のために働こうって思いつつも、六本木の強烈な誘惑に負けてしまった人は本当に多い。
キャバクラやクラブ(女性が働く)でも同じように、お金の魔力に取り憑かれて本来の目的を忘れてしまって、そのままお金のためだけに働き続けて自分を見失っている夜の蝶も何人も見てきた。
とにかくVIPなお客さんが来る。だから自分も同じ位凄いと錯覚する。
そして遊びに行ってもお金を出さなくてもいい。
虚像である源氏名
金で口説かれ、金で口説く
落としもするし、落とされもする
全部が虚像だ。
とにかく、六本木という街で夜働くのは、非常に危ないことだと思う。
もちろん、スポンサーを見つけてお店を出したり、そこで出会った人に拾われてビジネスを立ち上げた人も多いからチャンスはあるけど、とにかくブレやすい街。
そんな、危険な街六本木で、一番勢いがあるメンズキャバクラで、ずば抜けてオーラがあったのが、その竜先輩だった。
180センチを超える身長に、日本人ばなれした股下、そして帰国子女の感性からくるファッションセンス
そして歌も歌手並みに上手く、話もずば抜けて面白かった。
顔は芸能人並で、今で言うと三浦春馬をワイルドにした感じだろうか。
そんな竜先輩は仕事が終わると、誰とも一緒に帰らず
「おつかれさんっ。」
と言ってそそくさと帰ってしまっていた。
同じテーブルに付く時は会話するけど、プライベートは全く分からない謎な先輩だった。
複雑な家庭事情、実は寂しがり屋だった竜先輩
そんなメンキャバ生活(=ホスト生活)を一年ほどこなしていくと、六本木が自分の街のように感じるようになって来た。
コミュ症だったのは完全に社交的になり、毎日女性と話したことで少しづつ女心が分かってきたり、指名の数や売上げが上がっていくにつれ自信がついたりした。女性不信も心の奥底にしまっておけるようになっていった。
そんな生活を続けながら土曜の仕事終わり(朝5時まで)はヴェルファーレのアフターアワーズと言う、当時流行っていたサイバートランスなどのイベントに行くようになっていた。
お店で飲みまくっているからそのままのノリで踊り狂うのが毎週末の楽しみだった。
そんな中、竜先輩がヴェルファーレで踊っている姿を見た。
何でこんなかっこ良く踊れるんだろう?
外国人と並んで踊ってても様になっている竜先輩は自分の憧れの先輩になっていた。
「お疲れ様です!」
『おぉ、お前か。』
「先輩も来てたんすね!」
『おう。結構来てるし、DJもやってんだよね。』
「えっ?そうなんですか!」
『じゃあ、家に来てみる?DJするよ。』
「行きます!」
と、こんな感じで竜先輩の家に遊びに行けるようになった。
元々の萎縮タイプコミュ症の僕は、憧れている先輩に気軽に話しかけることも出来なかったし、一匹狼タイプだと思っていたから、気を遣って話しかけれなかったと言うのもあったかもしれない。
それから僕は竜先輩の家に入り浸るようになり、週の3日から5日は一緒に過ごすようになっていった。
アフター以外のイベントにも一緒に行ったり、とにかく遊んだし、竜先輩の事が色々よく分かってきた。
家庭環境がとても複雑だということが、竜先輩の人格形成のほとんどを占めていると思う。
とにかく複雑過ぎる。
離婚して母子家庭とかそう言うのでもなく、とにかく複雑だった。
だから、本当は凄く寂しがり屋だったんだ。
彼女と付き合い、竜先輩と遊ぶ時間が少なくなった
僕はこのままこの店で働いていると役者の夢がブレてしまうと思ったので、思い切って辞めることにした。
そこそこの給料は貰っていたし、教育係のようなポジションや、毎日コンパしていてきらびやかな感じだったし、大御所の人達と非日常の遊びを共有させて貰っていたり、芸能人も時々来たり…
実像そうで、虚像で、その虚像に飲まれ始めている自分に危機感を覚えたからだ。
1年8ヶ月と言う期間できっぱり辞め、その後は何をしようかと色々考えていたが、その頃はギャンブルによる借金がかさんでいたので、データ入力と言う名の、当時ブームだった出会い系サイトのサクラの仕事につくことにした。
今は法律的にもモラル的にもやるべきではない仕事だけど、当時はサクラと言うビジネスモデルで大儲けしまくっているIT企業がとにかく多かった。
1サイトで月に数億円と言う売上げがざらだった。
そんなグレーな会社がその竜先輩の家から歩いて3分位の所だったので、やめても相変わらず遊ぶ頻度は変わらなかった。
でも、自分の中で変わったことがもう一つあった。
彼女が出来ていた。
その彼女と付き合うことになり、彼女と遊ぶ時間が多くなり竜先輩と遊ぶ時間が少なくなっていった。
「最近△△とアイスやってんだよ。」
久日ぶりに竜先輩の家に遊びに行くと、相変わらずの爆音の中でDJをしていた。
でも、決定的に違う事が一つだけあった。
それは、竜先輩が覚せい剤に手を出していたことだ。
アイス
隠語だったから最初は何のことか分からなかったけど、いつも見慣れていた小さなテーブルを見ると小さい透明のパケと呼ばれる袋に透明な結晶体が少しだけ入っているものと、吸引器のようなものが置いてあった。
「ほどほどにしておいて下さいね。」
僕はそれ位しか言うことは出来なかった。
竜先輩だったら変にハマったりしないだろうという気持ちもあったからだ。
憧れの先輩が覚せい剤に手を出したショックは大きかったけど、芯が強く、ブレた所は見たことがないから問題は無いだろうと勝手に思っていた。
その後、二週間に一回くらいが、月に一度会うか会わないかになり、3ヶ月くらい経った頃、久しぶりに竜先輩の家に遊びに行った。
竜先輩にも新しい彼女ができていた。そして僕と入れ替わり位で入ったお店の後輩もいた。
そして、竜先輩はアイスをやっていた。
会う度に言動がおかしくなっている。
行動もおかしい。
目は虚ろ。
そして、久々に有明のイベントホールでトランスのイベントがあるので、竜先輩を含めみんなで行くことになった。
だけど、会場に着くなり
「幽霊が多すぎるから、ここにいる。みんなが危ない!ウチラも危ないぞ!!」
と言ってきかないので、結局すぐに帰ることになった。
そして家に着くと
「幽霊が着いて来た。俺はアイスを吸ってから霊感が付いた。ドアの丸窓見てみろよ?いるだろ?」
すでに、、、、、
竜先輩は完全におかしくなっていた。
もしかしたら本当に見えているのかもしれない。
本当に霊感がある人なのかもしれない。
でも僕には見えないし、幻覚としか思えない。
いくら憧れている先輩とはいえ、どう考えても禁断症状としか思えない。
芯が強く、絶対にブレない人でさえも、覚せい剤の依存性には敵わないと思う。
だから僕は
「竜先輩、どう考えてもアイス吸ってるからだと思いますよ!マジで完全に覚せい剤が切れて、それでも見れるんだったら信じれますけど、今の先輩の状況だと何も信じれないです。
前と比べてどう考えても、話も行動もおかしいです。もうやめて貰えませんか?」
『俺は普通だよ!!!いつでも辞めれるし、辞めても見えることには変わりない。だから別に辞めても辞めなくても一緒だ。』
この会話を10回位繰り返した。
繰り返した理由は恐らく、竜先輩が覚せい剤によって頭がおかしくなったから、同じことを何回も繰り返すからだ。
もう、僕にはどうすることも出来なかった。
このまま覚せい剤を使い続けたら確実に死ぬだろうし、または警察に捕まると思う。
昔、何かのドラマで覚せい剤の常用者をベットにくくり付けているシーンを思い出した。
先輩のことを本気で思っているのであれば…
本当にベッドにくくり付けて、体内から薬が抜けるまで一緒にいるしか無い。
それでもダメなら諦めよう。
でも、その時の僕は仕事を休むわけには行かなかったし、返していない借金もまだあったし、ずっと見続ける覚悟がなかった。
今でもそんな自分が嫌になるが、話しが堂々巡りしていく中でもう埒が明かなくなって来たので
「じゃあ、辞めて薬が体内から亡くなっても見えるって言うなら、この薬が無くても大丈夫ですよね?それまで僕が預かっててもいいですか?それでも大丈夫ってことですよね??それを証明して欲しいです。」
『あぁ、大丈夫に決まってる。』
「これは僕が預かります。」
『あぁ、いいよ!持ってってくれて。俺は大丈夫だから。』
トゥルルルルルルルル…
トゥルルルルルルルル…
トゥルルルルルルルル…
<こちらは留守番電話サービスセンターです、、、、>
『なぁ、やっぱ帰ってきてくれないか?』
トゥルルルルルルルル…
トゥルルルルルルルル…
トゥルルルルルルルル…
<こちらは留守番電話サービスセンターです、、、、>
『おーぃ!!聞いてんだろ?戻ってきてくれよな!』
トゥルルルルルルルル…
トゥルルルルルルルル…
トゥルルルルルルルル…
<こちらは留守番電話サービスセンターです、、、、>
『ザっけんなよ!!!!戻ってこいよオラ!!!』
僕はその留守電を聞いた後、コンビニのゴミ箱に
シャブを捨てた。
覚せい剤一瞬所持。
僕は、本当の地獄を見た。
人間でなくなってしまった竜先輩と寂しい思い
今まで見てきた男性の中で圧倒的なオーラとカリスマ性があり、憧れの先輩で、いつの間にか毎日一緒にいれるようになれた竜先輩が
完全に人間で無くなってしまった。
人はいい方向にも悪い方向にも簡単に変われると思う。
でも、人はここまで落ちてしまうものなのか?
あんなに格好良くて、実はとても優しかったのに。
竜先輩がシャブをやり始めてすぐの時に、僕に話したことがずっと引っかかっていた。
『お前が彼女を作って遊べなくなったから寂しくなったぜ。』
もしかしたら僕が竜先輩に寂しい思いをさせてしまったのが原因だったのかもしれない。
彼女が出来たとしてももっと遊んであげれば、竜先輩はシャブをやらずにすんだのかもしれない。
再会、そして
そんな思いを感じながら疎遠になり数年後、竜先輩と僕は再会することになる。
誰に聞いても消息不明、死亡説、ブタ箱説、海外説、色々あったが
結局は捕まっていて数年刑務所に入っていたってことだった。
でも、それで完全にやめることが出来たのだから良かったなって思う。
もしあのまま捕まらずにいたら絶対に死んでるか廃人になっているかのどっちかだと思う。
「ダメ。ゼッタイ。」
ってキャッチフレーズがあるけど、それ以外の言葉は見つからない。
間近で変わっていく姿を見ていたから分かるけど
どんなに心が強いと思ってもシャブの力には叶わない。
お酒の依存もヤバいと聞くけど、シャブはとにかく人格すらも変えてしまう。
もしこれを読んでやっている人、やっている人が身近にいる人は
ダルクなり更生施設に行く、行かせてあげる、警察に出頭、出頭させて欲しい。
(*ダルク(DARC)とは、ドラッグ(DRUG=薬物)のD、アディクション(ADDICTION=嗜癖、病的依存)のA、リハビリテーション(Rihabilitation=回復)のR、センター(CENTER=施設、建物)のCを組み合わせた造語で、覚醒剤、有機溶剤(シンナー等)、市販薬、その他の薬物から解放されるためのプログラムを持つ民間の薬物依存症リハビリ施設。ー 全国薬物依存症者家族会連合会のHPより引用)
死ぬよりかはまだまし。
生きていれば必ずいいことはあるはずだ。
後日談
再会した時は、しっかりとクリーンな体になって帰ってきていたが
お金も仕事も服もないということだったから、
家に招待して当時付き合っていた彼女にご飯を作ってもらい三人で食べたり、
いらない洋服をあげたり、アルバイト先を紹介したりと、少し面倒を見ていた。
…あの頃、竜先輩がアイスに手を出す前、僕が当時付き合っていた彼女とばかり遊ばず、竜先輩とも遊んでいれば寂しさのあまりアイスに手を出さなかったのかもしれない。
そんな後悔の念に数年苛まれていたので、いつか再会した時には何かしてあげることで、この想いを払拭できれば…
と思っていたので再会できて本当に良かった。
逮捕はされてしまったけど、更生して返って来てくれて本当に良かった。
今後も自分を律して生きていって欲しい。
あの頃の六本木の夜で、僕が唯いつオーラを感じた、憧れの人なのだから。 -
「子なし夫婦」のなかなか理解されない実態
東洋経済オンライン 7月4日
子どもがいないと、貧乏くじを引く――。東京都内の私立大学で教員として働く山本健二さん(仮名・41)は、こんなふうに感じることが多い。同僚の教員が子どもの入学式や参観日、運動会などのイベントに出るため、休日の出勤を頼まれることが多いからだ。「子どもがすでに大きい男性の同僚もいるのですが、仕事を頼みやすいのは子どもがいない私。頼んだ本人に申し訳なさそうに謝られるのはもっとつらい」。
この記事の写真を見る
妻(36)とは大学のサークルで出会い、11年前に結婚した。その後、妻は子どもができにくい体であることが検査でわかる。これから子どもを持つのは自分も体力的にしんどいと思う。
■ フェイスブックの子育て日記にうんざり
週刊東洋経済7月9日号(4日発売)は『子なしの真実』を特集。結婚したら子どもを持つのが当然なのか。少子化が叫ばれる中、国を挙げて子どもを持つことを奨励する動きが活発になっている。だが、子どもがいない夫婦にとっては心の負担となって重くのしかかっている。 山本さんは10年ほど前のある記憶が鮮明に残っている。まだ独身だったときに指導教授から「子どもを育ててこそ、いい教育者になれる」「自分の子どもを観察できると、論文の内容が変わる」と諭された。今もこうした考えが教育現場に根強くあると感じる。面と向かって言われることはなくなった。それでもあらゆる方向から「子どもがいないこと」を認識させられ、言いようのない不安に見舞われることがある。
ネットニュースで子育てに積極的な男性の「イクメン」礼賛のニュースをたびたび目にしては鼻白む。この傾向が強まれば強まるほど、子どもがいない人に対して仕事のしわ寄せが出てくるような気がしてならないからだ。
フェイスブックで連日のように目にする、出産報告や子育て日記のたぐいの記事。喜ばしいことだし、自分も素直によかったと思って「いいね!」ボタンを押す。そのうち「子育て日記」が頻繁に目に留まるようになった。
「以前だったら、直接会ったときに子どもの話をするか、年賀状で成長記録を見る程度だったのに、フェイスブックで毎日目にしてしまう。正直うんざりするときもある」。ツイッターでは積極的に発信するほうだ。しかし年金や憲法改正論議で、「子どもの親としてこう思う」という意見が多いと共感が薄れる。
子なしハラスメント――。子どものいない人を不快な思いにさせる行為だ。少子化が進む中、世間には子を持つことを奨励する空気で満ちている。だが子どものいない人にとっては、「子どもはいないの?」と聞かれることすら苦痛に感じるときがある。
「集団的いじめの構造を説明した社会学の理論がありますが、A君はからかっている、B君は遊んでいる、C君はふざけているというふうに、それぞれはいじめているつもりがなくても、ターゲットのD君はそれが度重なることでいじめられていると苦痛になることがある。だからいじめかどうかは『受け手』の気持ちで定義されるようになりました。もしかすると、子なしハラスメントも、同じ構造だと思う」
山本さんにとって、見えない「子なしハラスメント」が軽減される一番の解決法は「子どもがいようがいまいが、気兼ねなく休みの取れる環境をつくる」こと。職場で子どもがいない人にしわ寄せが来ないような社会の余裕ができれば、個々の心の持ちようが大きく変わるのではないか。そうすることで子なしハラスメントの受け止め方が違ってくるのではと考えている。
■ 夫婦で納得できなければ、子はいらない
2010年の国勢調査によると夫婦のみの世帯数は1024万に上る。そのうち子育て世代とみられる妻の年齢が20〜54歳の世帯は289万と決して少なくない。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」に初婚同士の夫婦の妻を対象にしたアンケートがある。それによると「結婚したら子どもを持つべきだ」という考え方に対し、「反対」と答えた人は2010年で24.3%。約4人に1人は子どもを持つという考え方に執着していない。しかも1992年の9.6%から大幅に増えた。夫婦の意識は確実に変わってきている。
養護教員の佐藤加代さん(仮名・32)は結婚して8年。医師の夫(34)とは子どもを持たない考えを共にしている。学校で生徒たちと接していると、親の期待を背負いすぎてしまったり、親との関係がうまくいかなかったり難しいケースにも遭遇する。自分自身は子どもに愛情を注ぎながら、見返りを求めずに育てることができるのか。
子どもをもうけることには、大きな責任が伴う。30歳を目の前にして子どもを持ちたいと心が揺れたこともあった。今は「子育ての経験が人生にとって必要」と心から納得できなければ、持たなくてもよいと思っている。毎晩一緒に食事をしながら、日本国内や海外旅行にもふたりで出かける夫婦の生活は充実している。ふたりの時間は大切にしたい。
子どもを持たない選択はなかなか理解されない。職場では「よほど子どもができにくいのか」と心配され、上司には飲み会の席で「悩みがあったら打ち明けてもいいんだよ」と気遣われた。
学生時代の友人に「子どもが欲しくない」と話したら、汚らわしいものを見るかのようなまなざしを送られた。彼女は独身だったが、家族との結びつきが強く、「子どもは幸せの象徴」と信じて疑わなかったのだ。子どもがいる友人には出産を強く勧められた。「子どもが持てる環境なのにその考えはない。持てる者と持たざる者でいえば、持たざる者になってしまうよ」。その友人とは次第に疎遠になってしまった。
■ 人生は自分で決めるもの
何よりも苦しいのは「親不孝ではないか」という罪悪感だ。自分は親に大切に育ててもらったのに、それを仇にして返すつもりなのか? 夫は自分の両親や親戚に、毅然とした態度で「子どもを持たない選択」を主張するけれど、もしかしたら冷たい人なのではないか?
そんな気持ちを英会話学校で話したら、米国人の男性教師に「人生は自分で決めるもの。なぜ親が関わるの?」と言われ、はっとした。夫とはこうした心情も、包み隠さず打ち明けてきた。「自分の人生は自分で責任を取る」という、根っこの考えは夫婦で一致している。
もちろん今後子どもを持ちたいと考えが変わる可能性はある。3カ月に一度、避妊用のピルを取りに行くときに「いいよね」とお互いの意志を確認するようにしている。
子どもがいない家庭の事情はさまざまだ。価値観が多様化する中、少子化対策という大義名分を振りかざすだけでなく、子どもを持てない、持たない夫婦が肩身の狭い思いをしなくてすむ社会にしていくことも必要なのではないだろうか。 -
結婚、出産、母になることこそ、女の幸せ。日本では神話のごとく、いつからか語り継がれてきた。けれど、それは本当なのか――。
今年、女優の山口智子が、雑誌「FRaU」(講談社)のインタビューで、「私は、子供のいる人生じゃない人生がいい」「今でも、一片の後悔もないです」とキッパリと答え、世間はざわついた。とりわけ、未婚・既婚問わず、子どもを望んでいなかった女たちは、身を乗り出して興奮したのではないか。
「よくぞ、堂々と言ってくれた!」
時を同じくして発売された『子の無い人生』(KADOKAWA)。著者は2003年に『負け犬の遠吠え』(講談社)で30代以上・未婚・子なしの女性を“負け犬”と呼び、一世を風靡した、負け犬界のレジェンド・酒井順子さん。あれから10年以上がたち、酒井さんは、負け犬の定義を改めるようになった。負け犬を分けるものとは、結婚しているか、していないかよりも、子どもを産んでいるか、いないか、ではないかと。
本書は、この時代に、子を持たずに生きることについて問うエッセイ集。1人で死ぬということ、出産を諦めるまでの心境、結婚と出産で心が離れた既婚子アリの友との歩み寄り、子ナシ男性に聞く、子ナシであることへの罪悪感、結婚して子どもを産んでこそ一人前という世の中についてなど、さまざまな角度から“子無し”という人生に切り込んでいる。
現在、32歳独身、王道の“負け犬”の筆者は、結婚への大きな憧れもなければ、切実に子どもがほしい、と思ったこともない。とはいえ、出産にはタイムリミットがある。あと3年もすれば、高齢出産に足を突っ込む。タイムリミットがあると知ると、なんとなく落ち着かなくなるのが、人間というもの。ついつい、子どもがほしいのか、ほしくないのか、どうなんだ!? などと自問してしまうが、結局のところ、悩んだところで、相手ありきの話なので、結論の出しようがない。すると、自然と日々の仕事に精を出し、現状維持の方向へ。それは、何も独身のみならず、仕事が好きな既婚女性も、そうなのではあるまいか。
個人的には、この本が、出産したいかどうかがわからない、現代の迷える“負け犬”たちに、何かしらヒントを与えてくれるのでは、と期待していた。けれど、結果として正直にいえば、ますますわからなくなってしまった。最後まで読んで、やっぱり「子の無い人生」の選択は、個人の自由で認められていいものだし、とりあえず産むことが良いことで当たり前、という世間の声にのっかる必要もないのではないかと思った。そうなると、より自分の意思を固めなければ、という気がしてくる。
<おわりに>という章で、酒井さんは、こんなことを書いている。
「最近、しみじみと『子どもがいなくて、よかった』と思うのです。子アリの方々からすると、痛々しく聞こえるかもしれません。しかし年をとるにつれて、自己を冷静に見られるようになるもので、『今まで私は、本当に子どもを望んでいたわけではなかった』、そして『子育てには明らかに、向いていない』ということがわかってくるのです」
この後に続く文に、子どもがいなくてよかった、という境地へ至るまでの心境がカラッとつづられ、そういうものなんだな、と納得してしまった。
それにしても、出産の自由を手に入れることは、なんと難しいのだろうか。両親から、友人、ご近所さん、政府のエライ人まで、世間様があちこちで介入してくる。少子化が絡んでくるので、しょうがないのかもしれないが、自らの意思で「産まない」と決断することへの風当たりの強さよ。
だからこそ、辛口で知られる酒井さんをもってしても、今回の本に関しては、語り口調に慎重さが見られる。これまでに、世間という名の竜巻に幾度も吹き飛ばされそうになったり、内側から湧き上がる罪悪感という名のボディーブローにも耐え、決死の思いで踏ん張ってきてくれたに違いない。そのおかげで、今、わたしたちの前に「子の無い人生」の扉が開こうとしている。今後、それが世の中でどう受け入れられていくのかは、わからない。女の幸せは結婚&出産と考える保守派からは、おそらく大バッシングを受けるであろう。けれど、数が増えていくことで、少しずつでも受け入れが進み、女たちが選択できる、新しい幸せな未来のカタチのひとつになると、信じたい。 -
自分や多数の人と少し考え方が違うだけで『叩く』今の世の中について
鴻上:“分かり合えないこと”を憎むんじゃなくて、“分かり合えないこと”を“分かり合う”って思わないといけないですね。つまり分かり合えないとつい僕たちは憎みあってしまったり対立したりするんだけど、“分かり合えないこと”を“分かり合う”ってことを前提に始まらないといけないと思う。
出典:『NHKスペシャル』「#不寛容社会」
鴻上と同様のことを、同じく劇作家の平田オリザも別の番組の江川紹子との対談の中で語っている。
平田: だから違うことを前提にして、“いや、なかなか分かり合えないよね、でもここだけは共有できるよね”っていうふうにちょっと緩めたほうがいいんじゃないかなって思いますね。日本人はマジメだから「心から分かり合えないとコミュニケーションじゃない」って教え育てられてきちゃってるんで、これを“分からないけどがんばろう”みたいな感じにできるといい。
江川: 違うけどいいんだと。
平田: そうなんです。そのほうがたぶん楽だと思うんです。
出典:『週刊フジテレビ批評』16年5月7日放送
心の思春期は、生きてる限り続く
ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロトは、2010年に行われたインタビューで「人間、生きていればみんなイライラする」と語っている。しかも、そのイライラには本質的には実は理由がないと。
(怒りや苛立ちは)今も僕の中にある。自分の中にそういう感情があるっていうのは、いつも知ってる。だけどみんなね、そんな自分のわけのわからない苛立ちに理由をつけたいから、そういう気持ちを正当化したいがために、「戦争反対!」とか言うんだよ、若者とかはさ。違うんだよ。「お前はただイライラしているだけなんだよ。それに早く気付けよ」って。確かに自分が正しいことを述べることの興奮もあるしさ、ヒロイズムもあるしさ、それに繋げていくために、「社会に物申す」とかさ。でも、それって怒りを肯定化したいだけなんだよ。違うんだよ。何にもなくったって怒ってんだよ。だから僕は“人間らしい”って言葉が嫌いでさ、「人間らしくやっていいのかよ? じゃあ、ぶっ殺してやる!」ってなる。(略)だから、人間として生きるためにはさ、人間らしさを去勢しなきゃいけないんだよね。いかに本性を表さないで去勢をしていくか。
出典:『Gスピリッツ SPECIAL EDITION Vol.1 アントニオ猪木』
先日まで放送されていた「ゆとり世代」をテーマに描いた宮藤官九郎・脚本ドラマ『ゆとりですがなにか』(日本テレビ)の最終回(6月19日放送)。「ゆとり世代」の小学校教師・山路(松坂桃李)が性教育を行う場面がある。そこで彼は子供たちに向かってこう語りかけた。
「身体と違って、心の思春期は、生きてる限り続きます。
だから、大人も間違える。怠ける。逃げる。道に迷う。言い訳する。泣く。他人のせいにする。好きになっちゃいけない人を好きになる。
全て思春期のせいです。
大人も間違える。間違えちゃうんだよ。だから、他人の間違えを許せる大人になって下さい」
出典:『ゆとりですがなにか』 -